「奇妙な味」ってどんな味? 小説用語を徹底解説

読後に不気味な割り切れなさを残す推理小説・怪奇小説を表す用語、「奇妙な味」。今回は、この言葉の由来を解説しつつ、実際に「奇妙な味」に分類される小説3編をご紹介します。
驚くようなトリックを持った本格的な推理小説ではないし、幽霊や妖怪がはっきりと登場するホラー小説でもない。けれど、読み終えたあとに独特の後味が残る……。みなさんは、そんな作品を読んだことはありませんか?
実はそんな作品のことを、“奇妙な味”と呼びます。今回は、小説用語である“奇妙な味”を解説するとともに、実際に奇妙な味わいを持った国内外の作品のあらすじをご紹介していきます!
「奇妙な味」という言葉の由来と、その定義
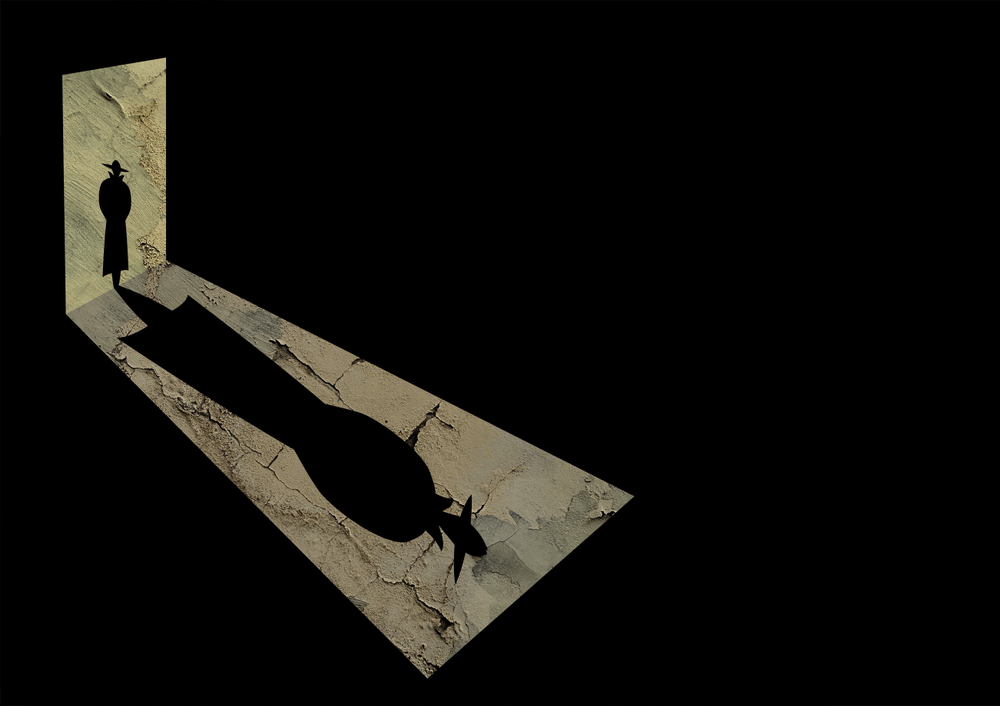
“奇妙な味”という言葉の名付け親は、日本の推理小説の大家・江戸川乱歩です。
今から二十年ぐらい前までは、西洋では、推理小説といえば、いわゆる本格推理小説ばかりであった。本格推理小説では、どうしてもトリックの創意が重要なので、作者はトリックの考察に骨身をけずった。
しかし、二十年ほど前から、英米推理小説界の様子が変わってきた。(中略)ハード・ボイルド、心理スリラー、サスペンス小説などが主流に浮きあがってきたのである。
江戸川乱歩『トリックの話』より
乱歩が1959年に書かれた『トリックの話』という随筆の中でこう語っているとおり、かつて本格推理小説ばかりであった推理小説界に、1930年頃からはトリックがストーリーの肝にならない心理スリラーやサスペンスが現れ始めていました。そして、戦前の日本では多くの場合、そういった作品は“変格”と呼ばれて本格推理小説と区別されていました。
そのような流れがあった中、変格推理小説の中でも特に読後に不気味な“割り切れなさ”を残す作品のことを、乱歩は“奇妙な味”と名付けたのです。
「奇妙な味」の要素は謎と論理の要素と殆ど肩を並べるほどに、探偵小説の重大な特徴となりつつあるのではないかとすら思われるのである。
かかる「奇妙な味」が探偵小説界に於て特別に歓迎せられる理由は何かと考えて見ると、すぐ思い浮かぶのは、本来の探偵小説の重大な条件である「意外性」の一つの変形ではないかということである。
『英米短篇ベスト集と「奇妙な味」』より
謎(トリック)とその整合性と同じくらい、“奇妙な味”は探偵小説(推理小説)において重要な要素となりつつある──。乱歩は随筆の中でそう語っていますが、実は、“奇妙な味”というものの明確な定義づけはしていません。乱歩は定義を述べる代わりに、奇妙な味に相当する作品を複数挙げることで、読者にその持ち味を伝えようとしています。
ここで挙げられたのは、ロード・ダンセイニの『二瓶のソース』、コナン・ドイルの『赤毛連盟』、ノックスの『密室の行者』……といった作品。これらの作品のあらすじは、「ノックスの十戒」という推理小説用語の解説記事でも詳しく紹介しています。
1965年に乱歩が亡くなってからも、乱歩に紹介された“奇妙な味”のブームは英米文学界を中心にしばらく続きました。しかし、1970年代頃からは徐々に静まっていき、現在は
読後に論理では割り切れない余韻を残す、ミステリともSFとも幻想怪奇小説ともつかない作品
中村融・編『街角の書店 (18の奇妙な物語)』より
といったニュアンスで“奇妙な味”を捉えるようになったようです。
ここからは、乱歩にならい、“奇妙な味”的要素の強い推理小説・怪奇小説の代表作をあらすじ付きでご紹介していきましょう。
(※以下の作品の紹介には、作品のトリックや結末に関わるネタバレが含まれます)
乱歩も“奇妙な味”の傑作と評した、妻の機転が光るサスペンス『夜鶯荘』

『夜鶯荘』収録/出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4488100090/
“奇妙な味”の名付け親である乱歩自身が「奇妙な味の傑作のひとつ」と随筆『英米短篇ベスト集と「奇妙な味」』の中で紹介しているのが、ミステリの女王、アガサ・クリスティによる短編『夜鶯荘』です。
このサスペンス小説は、アリクスという新婚の女性が、優しい夫・ジェラルドの裏の顔にふとしたことをきっかけに気づいてしまう……というストーリーです。
ある日、アリクスはジェラルドの机の中に、古びた新聞の切り抜きが入っていることに気づきます。
それはほとんどアメリカじゅうの新聞があつめてあって、およそ七年前のものだった。内容は、チャールズ・ルメートルという、悪名高い詐欺師で二重結婚者の裁判の報道であった。自分の女を殺害したという容疑である。ルメートルが借りていた家の床下から白骨が発見されたし、彼が『結婚』した女のほとんどが、その後、行方不明になっているのであった。
アリクスは、この新聞記事をきっかけに、ジェラルド自身がチャールズ・ルメートルであることに気づいてしまうのです。そして、ジェラルドはあろうことか、近所の人間に「明日からロンドンに行く」と、実際はない予定を言いふらし、アリクスに今晩は空けておいてくれと伝えるなど、アリクスを殺すためとしか思えない周到な準備をしているのでした。
アリクスは、かつての恋人、ディックに助けを求めることを思いつきます。アリクスが夜遅く、肉屋に電話をかけると偽ってディックに電話をかけようとすると、その部屋にジェラルドが入ってきてしまうのです。アリクスは、電話機のボタンを離しているときにはこちらの声が相手に聞こえないというしくみを活かして、機転を利かせてディックに助けを求めることに成功します。
「こちらはマーティンの家内ですの──『夜鶯荘』の。(ここでボタンをはなして)明日の朝、仔牛のカツレツの上等を、六人まえ持って(ここでボタンを押して)どうぞ来て下さいな。大事なことですから聞きのがさないでね」
アリクスは、ディックが来るまでの30分ほどの時間を、「自分はかつて前の夫を毒殺したことがある」という大胆な作り話をジェラルドにすることで乗り切ろうとします。そして、ジェラルドはアリクスの淹れたコーヒーに混ぜられた毒が回って、アリクスに暴言を吐きながらも死んでしまうのです。
自分を殺そうとしている夫から逃げる方法を妻が必死に考えるハラハラ感もさることながら、本作の最大の持ち味は、妻の疑念がだんだんと確信に変わっていくまでの心理描写の細かさと、ラスト、ついには夫を殺すことに成功したアリクスが最後につぶやく台詞の奇妙さにあります。その台詞がどんなものであったかは、実際に本作を読んで確かめてみてください。
短編の名手・サキによる、ブラックユーモアが光る1編『開いた窓』
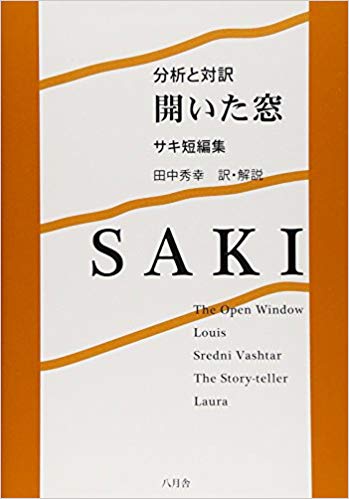
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4939058107/
オー・ヘンリーと並んで“短編の名手”と呼ばれるイギリスの小説家、サキ。サキの遺した作品にも、“奇妙な味”を楽しむことができるものが多く存在します。
代表的な作品は、『開いた窓』という超短編。フラムトン・ナトルという神経衰弱を患っている男が、姉の紹介で、田舎に住むサプルトン夫人という女性の屋敷を訪ねているシーンから物語は始まります。
夫人の屋敷には15歳の姪がおり、サプルトン夫人が下りてくるまでの間、彼女は3年前に夫人を襲ったという“悲劇”について話し出します。
「どうして十月の午後だというのに、あそこの窓を開けっぱなしにしているんだろう、って、おそらく不思議に思ってらっしゃるのでしょうね」姪は、芝生に向かって開いている大きなフランス窓を示した。
「ちょうど三年前の今日、あの窓を通って、伯父と、伯母の弟ふたりが狩に出かけたのです。そのまま三人は戻ってきませんでした。荒れ地を横切って、お気に入りだったタシギの猟場へ向かっている途中、沼地の柔らかくなっていたところに呑み込まれてしまったのです。あの年の夏は、雨ばかりだったでしょう、だからいつもの年ならなんともなかったところが、前触れもなしに崩れてしまったんです。三人の亡骸は、とうとう出てきませんでした。そのためにこまったことになったんです」
姪である少女は、サプルトン夫人がそれから精神を患い、「いつか3人と、3人が一緒に連れて行ったスパニエル犬が、あの窓を通って家に帰ってくる」と信じ込んでいるのだ、と、窓が開きっぱなしになっている不気味な理由を語ります。
同情を込めてその話を聞いていたフラムトンのところに、サプルトン夫人が下りてきます。そして、サプルトン夫人とフラムトンが談笑している最中、急にサプルトン夫人が窓のほうを見て顔を輝かせたのです。
フラムトンが気の毒なことだ、と思いながら姪のほうに目をやると、姪は“恐怖を浮かべた目”を見開いて、窓をほうを見ているのでした。
フラムトンは背筋の凍るような、なんとも名状しがたい怖ろしさを感じ、椅子にすわったまま振り返ってそちらに目をやった。
徐々に暮れていく薄闇のなかを、三つの影が、芝生を横切って窓のほうに近づいてきた。みな、小脇に銃を抱え、なかのひとりは白い雨合羽を肩にかけている。そのあとについてくるのは、疲れたようすのスパニエル犬だ。
なんと、夫人の話どおり、3人の男とスパニエル犬が窓を通って屋敷に帰ってこようとしている様子が見えたのです。フラムトンは恐怖におののき、挨拶もせずにその屋敷を飛び出しました。
最後、屋敷の中で、帰ってきた男たちとサプルトン夫人、そして姪がこんな会話を交わすシーンで物語は幕を閉じます。
「なんだかおかしなかたでしたわ、ナトルさんとかおっしゃるの」サプルトン夫人は説明した。「ご自分の病気のことしかお話しにならないの。あなたが帰ってらしたっていうのに、挨拶もしない、失礼します、とも言わないまま飛び出していくなんて。なんだか幽霊にでも遭ったみたい」
「たぶんそのスパニエルのせいよ」と、そしらぬ顔で姪は言った。「犬がおっかないんですって。先にガンジス河の河岸にあるどこかの墓地で、野犬の群れに襲われたらしいわ。(中略)」
とっさに物語を思いつくのが、この娘の特技だった。
“多重人格者”をめぐるゾッとするショートショート『多重人格』
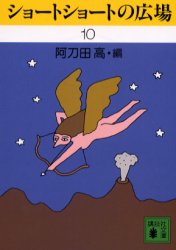
『多重人格』収録/出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4062647540/
ここまでは、古典と呼ぶにふさわしい“奇妙な味”の傑作を紹介してきましたが、国内で発表された現代小説の中からも1作をご紹介しましょう。
『ショートショートの広場』は、『ナポレオン狂』など国内でもっとも“奇妙な味”の雰囲気の強い作品を数多く発表している小説家・阿刀田高が編者を務めるショートショートのオムニバス作品集です。この作品集の中に収録されているショートショート『多重人格』(湯川聖司)は、多重人格者をめぐる、ゾッとするような1作。
ストーリーは、室内で熱心にワープロを打っている白衣の男に、コートの男が話をしに行くシーンから始まります。
「先生」コートの男が言った。「また、先生のお力を借りたいんです。ちょっとよろしいですか?」
「ええ、構いませんよ」白衣の男が答えた。
「先生は、多重人格についてお詳しいですか?」と尋ねるコートの男。コートの男は刑事であり、取り調べの最中、妙なことを言い出す男に出会ったと話します。ある事件の犯人である会社員の男が、突如「自分は会社員ではなく、精神科医だ」と言い出したというのです。
「ほう、わたしと同じ職業ですか。それはますます話をしてみたくなりましたな。ぜひ一度、連れてきて下さい」
「……なにか思い出しませんか?」
「えっ?」という顔をする、白衣の男。おそらく読者のみなさんも予想しているとおり、この白衣の男こそが、自分を精神科医だと思い込んでいる会社員なのです。コートの男が部屋を出てくると、男に本作の語り手である“私”が「どうでしたか?」と話しかけます。
白衣の男はすっかり自分自身のことを精神科医だと思い込んでいて重症だ、これで逮捕することができなかったらたまったものではない──と、“私”に訴えるコートの男。一方、コートの男と別れた“私”が白衣の男の部屋に入っていくと、「彼は完全に自分のことを刑事だと思い込んでいるんですよ」と白衣の男が言います。
なんと、白衣の男もコートの男も、どちらも多重人格者。病院の中で、患者の自殺防止のため、ふたりの男の部屋での様子をモニター越しに見ていた“私”は、ため息をつきます。すると、“私”の部屋に温厚な笑みをたたえた病院の院長が入ってくるのです。
「どうですか、患者の様子は」
「いま、『医者』と『刑事』のやりとりを見たんですが、二人とも相変わらずですね」
「そうですか、まあ、頑張ってください。あなたがしっかり監視してくれているので、私も助かります」
院長が部屋を出ていき、物語はこんな一文で締めくくられます。
私はふたたび仕事に戻った。
なぜか、外から鍵をかける音がした。
おわりに
今回は、実際の短編作品のあらすじを中心に、“奇妙な味”と呼ばれる作品の特徴をご紹介しました。ゾッとするような話やブラックユーモアの利いた話など、それぞれの作品の持ち味は違えど、どれも読み終えたあとに苦い薬を飲み込んだあとのような気味の悪さが残る作品である、ということがおわかりいただけたのではないでしょうか。
“奇妙な味”はまるでスパイスのように、作品の印象を一新し、読後に長い余韻を残す推理小説・怪奇小説の大切な要素です。推理小説の執筆に取り組んでいる方や短編小説のストーリーにひねりを加えたいという方は、ぜひこの“奇妙な味”のスパイスを活用してみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2019/04/02)

