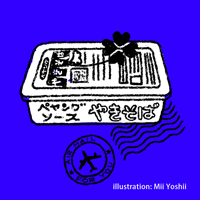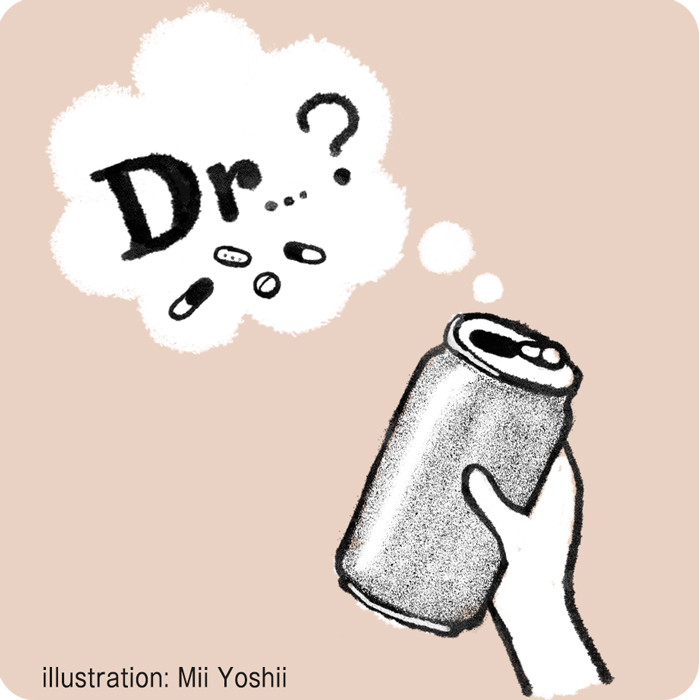思い出の味 ◈ 鈴峯紅也

私の父は昔、都内の大手サイン制作会社に勤めていた。主に飲料メーカーの屋外広告が多かったように思う。とある日、父が三箱もの段ボール箱を持って帰ってきた。試供品の炭酸飲料だという。なんのラベルも商品名もない、銀色のスチール缶だった。父はおもむろにプルタブを開け、持ち帰った者の責任としてまず自分で飲んだ。飲んでから少しばかり変な顔をした。それから美味いでも不味いでもなく、飲み掛けの缶を私に差し出した。
「クスリだと思って飲めば、飲めるな」
私は恐る恐る手を出した、と思う。たしか小学校の低学年だったと思う。クスリはイコール苦いもので注射は痛いもので、どちらも苦手な年頃だった。商品名もわからない、ただ銀色のスチール缶という得体の知れなさも、あるいはクスリっぽさを補完したかもしれない。
だが、初めて口にする炭酸飲料は意外なことに、たしかにそれまで飲んだことのない味がしたが、私にはわりと美味く感じられた。けれど、まだ私は幼く、「どうだ? 変な味だろ」と聞く父に逆らうようなことは言えなかった。「そうだね。クスリっぽいね」と言えば、「そうだろ」と言って父は笑った。
あとで思えばこの炭酸飲料は、間違いなく〈ドクター○ッパー〉だった。
私はこの試供品を、一人でずいぶん飲んだ。母は炭酸があまり得意ではなかったし、私の妹はまだ哺乳瓶をくわえていた。必然的にこの、せっかくもらってきた炭酸飲料を消費するのは私と父の役目になり、父は出勤で平日はほぼいないから、大半は私が飲む、ということになった。一日一本として、二カ月近くは飲んでいたはずだ。結果としてこのクスリで健康になったかどうかは知らないが、以来、ときおり無性に飲みたくなるようにはなった。私にその味を教えた父は他界してこの世にはいないが、元気だったなら胸を張り、こう言って飲み掛けを差し出したい衝動に駆られる。
「クスリだと思わなくても、俺は飲めるけどな」
はて、これは〈ドクター○ッパー〉の効用、いや、副作用だろうか。