【直木賞】第157回候補作を徹底解説!
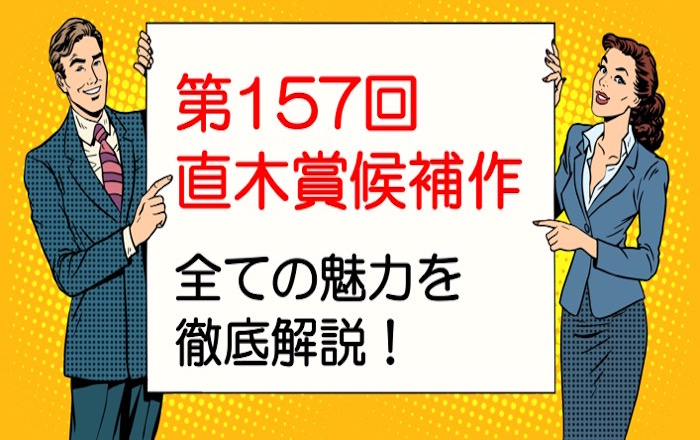
2017年7月19日に発表された、第157回直木賞。前回、見事に受賞作を恩田陸の『蜜蜂と遠雷』だとピタリと当てた、文芸評論家の末國善己氏が、なんと今回も2回連続の予想的中!佐藤正午の『月の満ち欠け』が受賞しました!候補作5作品のあらすじと、その評価ポイントをじっくり解説した記事を振り返ってみてください。
前回の直木賞を振り返り!
直木賞の予想は2回目となるが、まずは前回の答え合わせから。
第156回直木賞は、恩田陸『蜜蜂と遠雷』を本命、須賀しのぶ『また、桜の国で』を対抗、森見登美彦『夜行』を穴と予想した。選考委員の浅田次郎による選考経過によると、最初の投票で高得点だった『蜜蜂と遠雷』が受賞決定、その後『また、桜の国で』垣根涼介『室町無頼』とのダブル受賞の可能性を探ったが賛否がわかれ、結果的に『蜜蜂と遠雷』の単独受賞に落ち着いたという。
ということで、受賞作『蜜蜂と遠雷』、対抗『また、桜の国で』は的中したが、穴にした『夜行』は外れたことになる(作品を低く評価してしまった垣根さん、申し訳ありませんでした)。ちなみに『蜜蜂と遠雷』は本屋大賞とのダブル受賞となり、『また、桜の国で』は高校生直木賞を受賞した。
直木賞の歴史、芥川賞との違い、受賞作の傾向などは前回の原稿を参照していただくこととして、ここからは2017年7月19日に決まる第157回直木賞の候補作を作家名の50音順で紹介していきたい。ちなみに選考委員は前回と変わらず、浅田次郎、伊集院静、北方謙三、桐野夏生、高村薫、林真理子、東野圭吾、宮城谷昌光、宮部みゆきの9名である。
候補作品別・「ココが読みどころ!」「ココがもう少し!」
木下昌輝『敵の名は、宮本武蔵』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4041050804
木下は、デビュー作『宇喜多の捨て嫁』が舟橋聖一文学賞と高校生直木賞を受賞、第152回直木賞の候補作にもなる鮮烈なデビューを飾った。2年半ぶり2回目の直木賞候補作に選ばれた本書は、吉川英治、司馬遼太郎、柴田錬三郎、笹沢左保ら錚々たる作家が挑んだ宮本武蔵を描いている。ただ武蔵を主人公にするのではなく、決闘に敗れた武芸者の視点で武蔵をとらえた異色作となっている。
木下は、武蔵に厳しく剣を教えた父の無二が、美作の戦国大名・後藤勝基に仕える新免家の微禄の侍だったとしている。新免家は下克上で成り上がった宇喜多家を新たな主君に選ぶが、裏切りを拒み後藤家に残った一派もいた。後藤家の滅亡後、裏切り者十数人を惨殺したのが、「美作の忠犬」と呼ばれる無二だったのである。
連作集『宇喜多の捨て嫁』の表題作は、宇喜多直家が、後藤勝基に娘を嫁がせるところから始まるので、実は本書と関係が深い。残念ながら直木賞受賞に至らなかった『宇喜多の捨て嫁』のリベンジを、姉妹編ともいえる本書で果たせるかも見逃せないところだ。
収録作は、剣でなく染物で身を立てる吉岡憲法が、武蔵と刀を交える前に絵で勝負をしていたとする「吉岡憲法の色」、人買いに売られるも売れ残り、同じ境遇の千春に救われたシシドが、生きるためにクサリ鎌の腕を磨いていく「クサリ鎌のシシド」、小次郎が、武蔵と決闘する動機が意外な「巌流の剣」など全7作。本書に出てくる武芸者たちは、主君に忠誠心を利用され、命令に逆らわない殺人機械になっていくブラック企業の従業員のような無二、社会構造の変化で積み重ねたキャリアが使えなくなった吉岡憲法、社会の最下層で生きてきたがゆえに、危険で不安定な仕事にしか就くことができないシシドのように、現代と共通する“闇”を抱えているので、必ず共感できる人物が見つかるように思える。
木下はダークな物語を得意としているが、ひたすら武芸者と武蔵の戦いを描く本書も暗く陰惨だ。だが修羅の道を歩んでいた武蔵が、新たな境地を見つける終盤には救いもあるので読後感は悪くない。
本書は、武蔵と武芸者たちが繰り広げる迫力の決闘の中に、シシドと千春のせつない恋、無二と武蔵の複雑な親子関係、小次郎と無二・武蔵親子との因縁など多彩なエピソードを織り込んでいる。物語が進むと、複雑にからんだ因果の糸がまとまり思わぬ事実が浮かび上がるミステリータッチの展開もあるので、時代小説のあらゆるエッセンスが楽しめるといっても過言ではない。
木下は、『沼田家記』『兵法太祖武州玄信公伝来』などの史料を駆使し、小次郎の姓を有名な「佐々木」ではなく「津田」とし、小次郎の愛刀が「物干し竿」と呼ばれた理由も、物干し竿のように長かったとする従来の説ではなく、まっすぐな直刀だったからとするなど、独自の解釈で武蔵の世界を描いている。こうした歴史観は、吉川英治から始まる〈武蔵もの〉の系譜を知っている選考委員と、知らない選考委員ではインパクトが違うだろうし、史料の読み方も、斬新と好意的に取る委員もいれば、牽強付会と否定的に見る委員もいるだろう。このあたりが、受賞するか否かの分かれ目になる可能性が高い。
佐藤巖太郎『会津執権の栄誉』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4163906355
佐藤は、2011年に「夢幻の扉」でオール讀物新人賞を受賞。2016年には「啄木鳥」で決戦!小説大賞を受賞、同作がアンソロジー『決戦! 川中島』に収録された期待の新人である。単独の著書は本書が初で、それが直木賞の初ノミネート作となった。
佐藤と木下昌輝は、共にオール讀物新人賞の出身。同賞を先に受賞したのは佐藤だが、単行本の刊行は木下が先になったので、先輩・後輩の関係が複雑である。しかも本書は、木下の候補作『敵の名は、宮本武蔵』と同じく連作短編集なのだ。佐藤と木下の同門対決の行方も、今回の直木賞の見どころといえる。
鎌倉時代から東北の要衝の地・会津を治める名門の芦名家だが、戦国時代になると盛隆が家臣に殺され、家督を継いだ息子の亀王丸も3歳で病死し嫡流が絶えた。芦名家は、佐竹義重の次男・義広を養子にするが、伊達政宗の弟・小次郎を推した一派もいて家内に確執が残った。さらに義広を補佐するため佐竹家から来た大縄讃岐らと、芦名家譜代の家臣との対立も深刻化していた。物語は、この時点から始まる。
芦名家の血族・猪苗代家の当主・盛国の息子が、伊達に内通しているらしい。富田将監がその真偽を追う「湖の武将」は、緻密な伏線が意外な真相を導き出していていく。大縄讃岐の家臣が斬殺され、容疑者として芦名家の猛者の名が上がる。調査を進める桑原新二郎の前に、事件を目撃した牢人が現れる「復讐の仕来り」は、証言者が善意の第三者か、敵の手先か分からず、それが先を読み難くしている。芦名家が、伊達がこもる大平城を攻めることになった。「芦名の陣立て」は、偵察をめぐって芦名と佐竹の巧妙争いが起こり、さらに名誉の先陣をどちらが務めるかでも壮絶な駆け引きが行われていく。このように、本書の収録作はトリッキーなものが多く、ミステリーが好きな読者も満足できるはずだ。
養子を迎えた蘆名家は、佐竹のやり方を受け入れるのか、芦名の伝統を守るのかの選択を迫られる。芦名家の家臣の中には、味方の佐竹どころか、敵ながら破竹の勢いの伊達にすり寄る者もいて、混乱に拍車をかけていた。この状況は、企業の合併、買収が進み、企業文化が違う上司の下で働くのも当たり前になった現代の勤め人の戸惑いを先取りしているようなものなので、生々しく感じる読者も多いのではないだろうか。
本書は、各短編の完成度も高いし、連作を読み進めると長編としての骨格も浮かび上がるので、短編の切れ味と長編のダイナミズムの両方が楽しめるようになっている。ただ手堅くまとめているものの、本書ならではの“ウリ”も見当たらない。木下の『宇喜多の捨て嫁』は、第1話で娘を捨て駒にしてまで敵を滅ぼす宇喜多直家の梟雄ぶりを描いたが、第2話からは過去に遡り、子供の頃に城を追われ極貧生活を経験し、お家再興のため奮闘していた純粋な直家が、なぜ目的のためなら手段を選ばない武将になったのかを追う緻密かつ先を読ませる構成になっていた。また貧困と過酷な競争が、直家という“怪物”を生んだとしたところは、格差の解消に消極的な現代への批判になっているなどメッセージ性も高かった。本書は、連作を使った仕掛けも、テーマも、選考会で絶対に比較されるであろう木下の『宇喜多の捨て嫁』より弱く、今回の候補作『敵の名は、宮本武蔵』と比べるとさらに弱い。そのため、受賞は難しいように思える。
佐藤正午『月の満ち欠け』
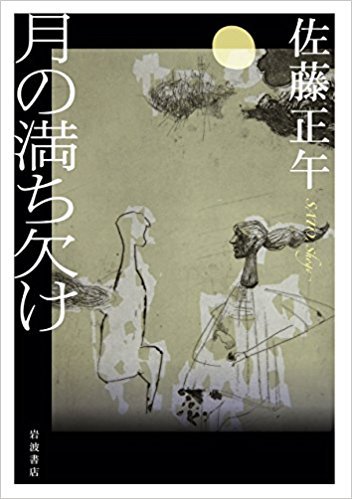
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4000014080
直木賞の候補作の発表が近づくと、何が選ばれるかの予想が始まる。今回の候補作でいえば、『敵の名は、宮本武蔵』『あとは野となれ大和撫子』は予想通りだったが、『月の満ち欠け』だけはまったくのノーマークだった(佐藤正午さん、申し訳ありませんでした)。佐藤は作家生活30年を超える大ベテラン(今回の直木賞の選考委員9人の中でも、佐藤よりキャリアの長い作家は少ないほど)だが、なぜか直木賞とは縁がなく、今回が初のノミネートである。
不明を恥じるばかりだが、候補作の発表後に読んだ本書は、本当に面白かった。直木賞の候補になったのも納得である。
物語は、東京ステーションホテルのカフェで、上京した初老の小山内と、女優の母親に連れられた7歳の少女るりが会う場面から始まる。2人は初対面なのに、るりは小山内のことをよく知っていて、親しげに話し掛けてくる。この謎めいた冒頭部だけで、物語に引き込まれてしまうのではないだろうか。
すぐに物語は、小山内の回想へと移る。小山内の娘・瑠璃が7歳の時、高熱を出した。小山内の妻によると、回復した瑠璃は、時折大人びた表情を見せ、知っているはずのない黛ジュンの歌を歌い、なぜかデュポンのライターを見分けたというのだ。だが小山内が心配したのは、瑠璃よりも、妻の精神状態だった。やがて瑠璃が家出する。どうやら瑠璃には、会いたい人物がいるらしい。小山内に諭された瑠璃は、大人になるまで勝手に出歩かないことを約束する。時は流れ高校を卒業した瑠璃は、妻の運転する車に乗っていた時に事故に遭い、2人とも即死した。小山内は、瑠璃と妻が何をしようとしていたのかも、2人がどこに向かっていたのかも分からないまま取り残されてしまう。
それから15年後、小山内の前に現れたのが、娘の瑠璃のことも、家族の思い出も小山内より把握しているるりだったのである。
本書は決して大きな事件が起こる訳ではない。ただ全体がミステリアスで、ページをめくらずにはいられない圧倒的なドライブ感があるのだ。本書は何の予備知識も持たずに読んで欲しいのだが、ネタバレを承知で内容に踏み込むと、るりは死んだ瑠璃の生まれ変れり、もしくは瑠璃だった前世の記憶を持っていて、さらに瑠璃が古い流行歌やデュポンのライターの使い方を知っていたのも、前世の記憶を持っていたからだと分かってくる。
中盤以降は、時間軸が錯綜し、何人もの登場人物の視点を使ってポリフォニックな物語が紡がれていく。それだけに、生まれ変わりを題材にしたファンタジーとしても、死が分かった恋人を輪廻転生しながら探すせつない恋愛小説としても、娘に何が起こったことを理解すようとする親子の情愛の物語としても秀逸で、どのジャンルが好きでも満足できるはずだ。
本書を読み進めると、輪廻転生を繰り返す少女は、死者の強い想いを受け継いでいることが明らかになってくる。死者の記憶をそのまま引き継ぐことはできないが、生きている者は、親、兄弟、友人らが先に逝けば、その人たちに恥ずかしくないよう懸命に生きようとする。本書の輪廻転生はその象徴のように思え、生きている者は、死者の無念を前に何ができるのかを問うラストは、胸に響いてくる。
“小説巧者”の異名を持つ佐藤だけに、美しく完璧な小説に仕上げてきた。あえて欠点を挙げるなら、生まれ変わった少女の近くに必ず前世の関係がいるのがややご都合主義に思えるのと、生まれ変わると少女になるので、想い人との年齢差が開き、少女愛的な世界になるので、そこが嫌いな人は嫌いかもしれない。
宮内悠介『あとは野となれ大和撫子』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4041033799
宮内は、デビュー作『盤上の夜』が直木賞候補になり、日本SF大賞を受賞。2作目の『ヨハネスブルグの天使たち』も直木賞候補になり、日本SF大賞の特別賞を受賞した。エンターテインメント小説界の驚異の新人として登場した宮内だが、2017年には、『彼女がエスパーだったころ』で吉川英治文学新人賞を受賞する一方で、短編「カブールの園」が芥川賞の候補作になり、同作を含む短編集『カブールの園』が三島由紀夫賞を受賞するなど、今や純文学作家としても注目を集めている。芥川賞と直木賞で綱引きをしている状態の宮内が、直木賞作家になるのか、受賞を逃し芥川賞作家になる可能性を残すのかも注目ポイントである。
直木賞候補になった宮内の2作品については、“難解”“読みにくい”との選評もあった。だが、女性の高等教育機関に生まれ変わった後宮(ハレム)で学ぶ少女たちが、大統領が暗殺され混乱する中央アジアの国アラルスタンを救うために立ち上がる本書は、女子校に通う少女たちが生徒会役員を務める青春小説のようなノリで、国家の運営に乗り出す明るくユーモラスな物語となっている。宮内作品の中でも分かりやすく、リーダビリティが高い本書は、直木賞の選考委員も直球のエンターテインメント小説と認めてくれるだろう。
アラルスタンは架空の国で、中央アジアに実在する塩湖アラル海に建国されたとの設定になっている。アラル海は、ソ連が大規模な灌漑を行ったことで面積が激減し、塩分と有害物質を含む広大な砂漠になってしまった。ここまでは事実だが、宮内は、ソ連を逃れた7人の科学者が、水蒸気をとらえる点滴灌漑、塩の大地でも育つように遺伝子改良した牧草などを使って環境を変え、人間が暮らせる国にしたのがアラルスタンとしている。
実際の歴史と矛盾なくアラルスタンを作った宮内は、イスラム原理主義組織による反政府闘争、利権を狙う隣国カザフスタン、ウズベキスタンの動き、介入をほのめかしながらも事態を静観する大国や国連など、中央アジアの小国に政変が起こった時、国際社会がどのような反応をするかも、リアルに再現してみせたのである。
それだけに、アラルスタンの中枢に座った少女たちが、政治、民族、宗教、人権、環境、移民など、大国のエリートさえも頭を抱えるアクチュアルな課題に、軽やかに取り組み解決のヒントを提示していく展開は痛快に思える。現在進行形の危機に対処しながら、長期的な国家運営のビジョンも考えているナツキたちは、宗教、人権、環境などの問題に取り組むには他国との連携、協力が必要との結論に至る。ここには、世界的な格差の広がりを背景に、自国第一主義やレイシズムの嵐が吹き荒れている現状への批判が感じられる。何より、中央アジアのイスラム教国で日本人の少女を活躍させた本書は、宮内がデビュー作から一貫して追求している“日本人とは何か”にも繋がっているので、考えさせられる。
エンターテインメント性と重厚なテーマが両立した本書だが、ネックになりそうなのは、ハラハラ、ドキドキは盛り込まれているものの、少女たちの国家運営があまりに巧く行きすぎること。これをエンタメのお約束と見るか、ご都合主義と見るかで評価が分かれるように思えた。
柚木麻子『BUTTER』
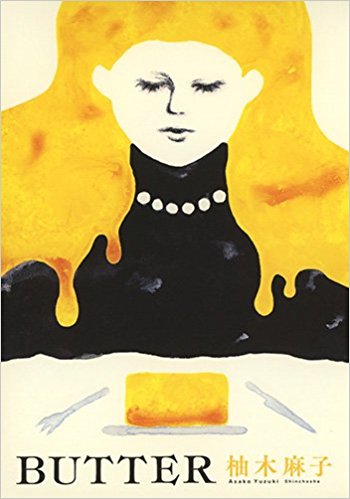
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4103355328
柚木は、『伊藤くんA to E』『本屋さんのダイアナ』『ナイルパーチの女子会』が直木賞の候補になっているので、今回が4回目となる。これは佐藤正午を除けば若手が多い今回の候補者の中では、最大のノミネート回数となっている。
本書は、2007年から2009年にかけて3人の男性が連続して不審な死を遂げ、犯人として木嶋佳苗が逮捕された事件をモデルにしている。
大手出版社(モデルは本書の版元の新潮社)の週刊誌で正社員の記者をしている30代の町田里佳は、連続不審死事件の被告として拘置所に収監されている梶井真奈子にインタビューをしたいと考えていたが、面会を拒否される。ある日、里佳は、料理が得意な親友の伶子に、料理や食べ歩きが好きだった梶井には、料理からアプローチした方がよいとアドバイスされる。その方法を使った里佳は、梶井との面会に成功する。
里佳は、細身の体型を維持するために暴飲暴食を避け、男性中心の社会でキャリアアップするため努力を重ねていた。梶井は、そんな里佳を見下し、美味しいものを食べ、セックスで男に悦びを与えることが女の幸せだと嘯く。
梶井が語る料理のレシピ、高級レストランの食事や高級食材の味は本当に美味しそうで、否応なく食欲をかきたてられる。そのためダイエット中の人や、健康志向な人は絶対に読んではいけない秀逸な“飯テロ”小説となっている。
欲望のままに生きてきた梶井は、圧倒的なカリスマ性で里佳のストイックな価値観を打ち砕いていく。梶井に操られるかのように、バターたっぷりの食事を続けた里佳が太っていくところは、トマス・ハリス『羊たちの沈黙』に出てきた天才的な猟奇殺人鬼レクター博士が、FBI捜査官クラリスを翻弄する展開を思わせる不気味さがある。
中盤以降は、「ブランド志向、保守的な価値観、選民意識」に凝り固まった梶井が必ずしも正しくないと気付いた里佳が、その影響下から脱しようと足掻き始める。やがて物語は、里佳を手元に置いておきたい梶井と、梶井の弱点を見つけて反撃に出る里佳の壮絶な頭脳戦、心理戦に発展するので、最後まで先の読めないスリリングな展開が楽しめるだろう。
本書には、仕事中心の生活で恋人はいるが結婚は視野に入っていない里佳、キャリアを捨て専業主婦になったが、妊活をめぐって夫と対立している伶子、そして男に貢がせ贅沢三昧の生活を送ってきた梶井など、男性中心の社会で自分なりの生き方を模索している女性たちが登場するので、里佳たちの言動は、同じ30代の女性読者には説得力があるのかもしれない。その一方で、中高年の独身男性は、料理ができず生活が破綻しがちなので婚活に熱心とか、若い男性は痩せている女性が好みだが口ではぽっちゃりが好きだというなど、あまりにステレオタイプな男性の性格・思考が気になった。男性作家は“女性が描けていない”と批判されることがあるが、これに倣えば本書は“男性が描けていない”。
柚木は、努力しない、我慢しない、自由奔放に生きる梶井を描くことで、組織に忠誠を誓い、空気を読み、心身を壊すまで働くケースが多い日本人に、まったく違う人生の選択肢があることを示そうとしたように思えた。そうなると世代も、性別も超えた普遍的なテーマになるのだが、“男社会で女性はこんなに苦労しているのよ”との主張が前面に出すぎていて、ターゲットを狭めていた。また木嶋佳苗の事件は、真梨幸子『5人のジュンコ』、花房観音『黄泉醜女』などもモデルにしているので、新しい事件の割に新鮮さがないし、モデル小説を書いている選考委員もいるので、実際の事件をモチーフにした本書はより厳しい評価にさらされる危険もあるのではないか。
ズバリ予想!本命は?対抗は?
以上を踏まえて、第157回の直木賞を予想してみたい。
本命は、佐藤正午『月の満ち欠け』。これは前回の『蜜蜂と遠雷』と同じく、功労賞的な性格を強めている直木賞で、ベテランがレベルの違う作品を発表したのだから、受賞の確率は高いだろう。
対抗は、宮内悠介『あとは野となれ大和撫子』。SF、国際謀略小説、ミステリーなどの要素をミックスさせ、それぞれのジャンルでしか描けない問題提起をさりげなく行った手腕は鮮やか。現代社会が直面している喫緊の課題を取り上げているところも、評価が高そうだ。
穴は、木下昌輝『敵の名は、宮本武蔵』。歴史時代小説の系譜に脈々と流れている〈武蔵もの〉の伝統を受け継ぎつつも、まったく新しく、現代人が共感できる物語に仕上げていた。ただ木下が得意とする陰惨でダークな物語は、好き嫌いがはっきり分かれそうな気もしている。
ということで、結果を待ちたい。
筆者・末國善己 プロフィール

●すえくによしみ・1968年広島県生まれ。歴史時代小説とミステリーを中心に活動している文芸評論家。著書に『時代小説で読む日本史』『夜の日本史』『時代小説マストリード100』、編著に『山本周五郎探偵小説全集』『岡本綺堂探偵小説全集』『龍馬の生きざま』『花嫁首 眠狂四郎ミステリ傑作選』などがある。
初出:P+D MAGAZINE(2017/07/16)





