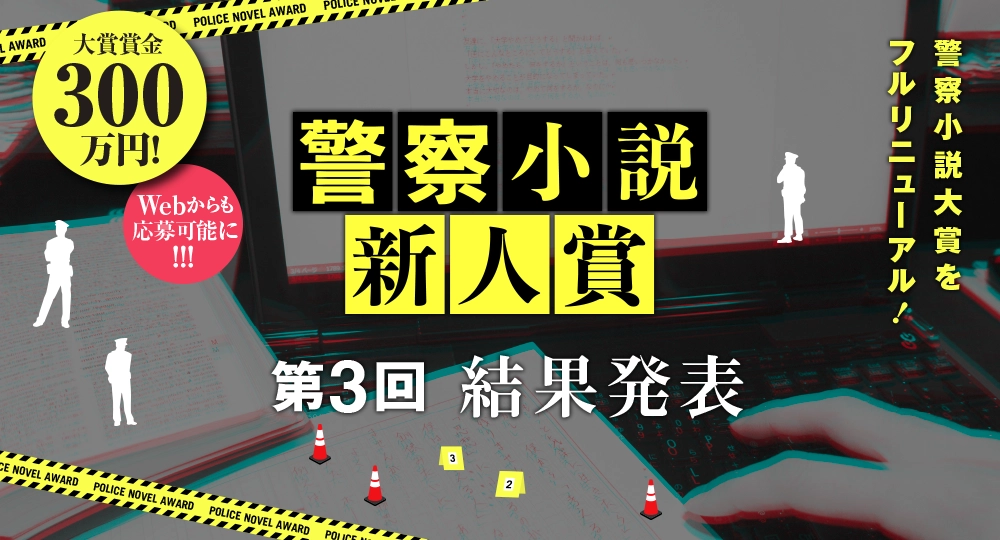
第3回警察小説新人賞は、2024年6月27日(木)に行われてた選考会にて、選考委員の今野敏氏、相場英雄氏、月村了衛氏、長岡弘樹氏、東山彰良氏による厳正な選考の結果、下記のように決定いたしました。

受賞作なし
「三人の密室破り」
竹中篤通
「リアルライセンスヒーロー」
烏丸舟
「背理の壁」
こち みちひさ
「総評/残念ながら未達」
三名の書き手の熱意、努力は感じられたものの、残念ながら新人賞のレベル、換言すれば、プロのレベルには未達ということで、今回は受賞作なしという結果になった。
「着想」、「ディテールへのこだわり」、「ストーリー回し」という基本を押さえた書き手ばかりだったが、「視点」という小説として一番大切な部分が三作品とも疎かになっていた。「視点」がブレてしまうことにより、読者は一気に作品への興味をなくし、注意力が散漫になってしまう。
過去のヒット作、あるいは熟練の書き手が記した作品を読み込み、「視点」がどのように描かれているか、小説を創造する基本中の基本を得るよう一層の努力を促したい。
また「推敲」の大切さを理解している書き手が少なかったとの印象も強い。自分の書いた文を読み返し、ブラッシュアップし、最終的な作品に仕上げようとする努力が足りなかったことも三作品に共通していた。
今一度小説執筆の基本に立ち返り、さらなるチャレンジを期待したい。
「背理の壁」
冒頭から読み手が事件の捜査本部に放り込まれたかのようなディテール、精緻な描写に圧倒された。警察組織の仕組みを熟知し、上下関係の機微もよく心得ている。桜井のとぼけたキャラと実際の鋭い観察眼のギャップ、吉川の強気一辺倒に見えて心優しい姿のギャップが凄惨な事件の真相を和らげる効果をもたせていた。
複雑な人間関係、トリックの暴き方、主要キャラ二人の背景と本筋との絡ませ方、回収の仕方が巧み。
マイナス点は、しばしば視点がブレてしまうこと。また主要キャラクターたちの会話が大袈裟で、乱暴。二つの点を改めることで、作品の完成度が一段と高まるはず。
「三人の密室破り」
タイトルから〈トリックを披露するための小説〉を予想していたが、良い意味で裏切られた。容疑者候補たちの背景もしっかり書き込まれ、人物像をきちんとトレースし、最先端医療の情報を加味してストーリーに仕立てた手法は見事。京都という特殊な都市の背景、人間模様も丹念に描かれていて、一京都ファンとして興味深く読んだ。怪盗フジノモリのキャラ造形も秀逸。
マイナス点は、もう少し構成を練った方がすんなりと物語が読み手に受け入れられるのではないか、ということ。人物造形がしっかりしているだけに残念に思った。個人的にはフジノモリを主人公にした犯罪小説とし、警察が振り回されるような作品に仕上げた方が良かったのではないかと考える。
「リアルライセンスヒーロー」
劇場型犯罪の風呂敷が大きく広げられ、どこでどう着地するかハラハラして読み始めた。着想自体は非常に斬新で三作品の中で一番オリジナリティーが高かった。
一方、キャラの立て方が大袈裟で、安直に感じた。三作品の中でも視点がブレる箇所が多く、読みにくかった。ラスト近く、大イベントでゼクスマキアがのこのこと現れるあたりも要検証。プロットの練り方、ストーリーの回し方についてもう少し訓練が必要と感じた。
大変残念なことに、今回の選考は受賞作なしという結果になりました。最終候補作はいずれも商業出版のレベルに達しておらず、これで受賞させデビューさせることは、かえって作者のためにならないのではないか、というのが選考委員の一致した見解でした。またそれは、旧警察小説大賞、および警察小説新人賞における過去の受賞者の権威を守り、未来の受賞者の栄誉を担保することにほかなりません。私たち選考委員は、気概と向上心、そして何より小説に対する情熱と愛情に満ちた才能を常に歓迎するものであります。
今回受賞に至らなかった方々も、臆することなく、新たな作品に取り組んで下さい。苦しいこともあるでしょうが、「自分は全力で小説を書いているのだ」という思いは、すべての小説家と小説家志望者にとって何よりの喜びであるはずで、それはきっと結果に結びつくことと信じています。
「三人の密室破り」は、趣向はよいと思ったのですが、それが活かされていないのが残念でした。本作が全候補作中最も短い作品であったのは、捜査の過程を詳細に描くことを避け、すべて捜査会議や取調室での説明にしてしまっているせいであろうと感じました。
「リアルライセンスヒーロー」の作者は、まず小説の文体というものに対する考察から始められるのがよいと思います。またいじめ問題を扱っているのですが、この深刻な問題に対して、魂から取り組んでいるようには感じられませんでした。
「背理の壁」は、「ー」(音引き)の異様なまでの多用により、とても読みにくい作品でした。そうした独特の記述法のせいかメリハリが失われ、劇的な設定であるはずなのに全く劇的に感じられないものになっています。日本刀の切羽に指紋が残るというのはよいアイデアだったのですが、わざわざ日本刀を使った理由が今一つ釈然としないこともあり、効果的とは言い難い印象になったのは残念でした。また真相が延々と続くセリフで説明されるのは小説として大きな欠点となりますので、気をつけるようにして下さい。
最終候補作のすべてに共通して言えることですが、ストーリーが進んでいるようで、実は説明に終始しています。小説の「描写」と「説明」の違いを今一度考え直すことは、決して無駄にはなりません。
また、セリフ、地の文を問わず、擬態語、擬声語の多用は厳に慎むべきです。主題や内容によってはそうした語を積極的に使うべき作品もあり得るのですが、少なくとも新人のうちはやるべきではありません。そうした点を疎かにすると、受賞はまずないものと思って下さい。
皆さんの新たなる挑戦を今から心待ちにしております。
「三人の密室破り」
警察小説を本格ミステリと融合させようとする志には、大いに賛同したい。しかし本作の場合は、物語の各要素がうまく融合されているとは言い難かった。ピッキングや再生医療といった興味深い題材がバラバラに存在し、最後には使い捨てにされてしまっているのが惜しい。作品に統一感を持たせるには、いっそ密室の謎は従にして、ほかに作品を貫く中心テーマを用意し、そちらを主としてもよかったかもしれない。せっかく被害者をパワハラ常習者に設定したのなら、ここをクローズアップする手もあっただろう。密室の謎が解けるにつれて被害者の本性が明らかになり、同時に警察のパワハラ体質までもが炙り出される、など警察小説として一本筋の通った展開になっていれば、もっと評価できたように思う。
「リアルライセンスヒーロー」
作者がご自分の作り出した物語に深く入り込み、楽しんで筆を進めている感じがよく伝わってきた。そのせいか、いろいろ盛り込みすぎて、作り話感が強くなってしまったのが悔やまれる。エピローグあたりは逆に説明が不足しているため、全体のバランスをもう少し調整する必要があったのではないか。もう一つ気になったのは犯人像である。いじめ自殺者が遺した復讐のシナリオがあり、それを犯人は代行したわけだが、殺されたのは何の落ち度もない無関係の人物たちだ。この部分に何らかのエクスキューズがないと、読まされる方としては不快な思いが先に立ってしまい、犯人に共感するのが難しい。警察官たちのキャラクターが際立つためには、敵も魅力的でなければならない。この独善的な犯人では、せっかくのヒーローたちが活きてこないだろう。
「背理の壁」
場面をきっちりと描写せず、簡単な擬音語だけで済ませてしまうなど、文章にはかなり粗っぽい部分が見受けられた。しかし、万年巡査部長の主人公やその周辺キャラクターたちには妙な可愛げがあり、なんとも憎めない作品になっている。こうなると文章上の欠点も、ヘタウマとでもいうべき独特の味わいに感じられてくるから不思議だ。内容について言えば、犯人が元警察官で、しかも他県警のそれであるという点が面白かった。ただ、この人物が犯人グループの一人でしかないのはもったいない。単独犯にするか、トリック上それが無理なら、いっそ犯人全員をそのような人物に設定したらどうだったろうか。そうして、他県の警察官と闘わなければならない苦悩や苦労を現状よりも膨らませて描いていれば、警察小説としての読みどころがもっと増えていたように思われる。今回も、できるだけ長所を評価しようと努めた。全体的に低調だったため、なおさらそうしなければならなかった。結果として『背理の壁』の愛嬌を最も買ったが、それでも残念ながら、受賞のレベルには達していないと判断せざるをえなかった。
「三人の密室破り」は、密室殺人の謎を追う刑事の物語です。警察小説と本格ミステリを融合させるという試みはいいのですが、小説というより、その準備段階のプロットを読まされたような感覚でした。
物語の作り込みが甘く、この程度の緩い密室であれば、誰が犯人であっても不思議はありません。主人公の思考回路は単純というよりも幼稚で、全編にわたって彼の不愉快な偏見や決めつけが散見され、それがこの作品に対して共感を寄せにくくしていました。ラストで、主人公は父親に対して偏見を持っていた事実を突きつけられ、物語は彼の内面の崩壊を予感させて終息します。もし作者が偏見の恐ろしさ、愚かしさを描きたいのだとしたら、主人公の偏見に対して何らかの総括をする必要があるのではないでしょうか。しかし作者自身が主人公の偏見に対して無自覚なのか、残念ながらそのような展開は見られませんでした。
「背理の壁」は、人情派老巡査部長とエリート女性警部のバディものです。のっけから酸鼻な殺人の場面で一気に興味を惹かれましたが、その興味を最後まで持続できませんでした。登場人物の造形に新味がなく、それを打破するために主人公たちのキャラクターをデコボコ漫才コンビのような設定にしたと思うのですが、事件をとおして登場人物の人間性を炙り出すことよりも、このふたりのやりとりに重点が置かれすぎていました。ようするに、物語における緩急のバランスが悪いと感じました。コミカルであるはずの彼らの台詞回しは陳腐で説明臭く、笑いを取りにいって失敗してしまった感が否めませんでした。ユーモアというものが笑いという手段を使って真実を伝える技術だとすれば、笑いだけを目的とする意味のないギャグだけが悪目立ちしていたように思います。
「リアルライセンスヒーロー」 は、いじめを苦に自殺した少年が書き残した復讐計画を実行する犯人一党と警察の攻防が描かれています。これから始まるデスゲームの予感にわくわくしましたが、やっと明らかになったそのデスゲームの全貌は魅力にとぼしく、そのせいで頭脳明晰であるはずの犯人像が浅薄なものになっていました。ほかのキャラたちについても設定と描写に齟齬があり、本来癖があって魅力的であるはずの登場人物たちにさほど魅力を感じることができませんでした。加えて、互いに相容れない価値観を持つ刑事がひとりもおらず、仲間を甘やかすような描写やセリフが多く見受けられ、それがこの作品を皮相的なものにしていたように思います。なによりも推敲が足りておらず、言葉遣いの誤用や誤記、視点のブレが目立ち、それが本文を読みとおす妨げになりました。
残念ながら今回は受賞作なしということになりましたが、最終候補の三作に共通して言えるのはどれも推敲が足りておらず、展開が強引で、作者の都合で物語をねじ曲げていたことです。もっと物語の要請に寄り添って書いていただけたら、当面の壁を乗り越えることができるのではないかと思います。









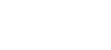
「小説を書く
ということ」
今回、候補作のいずれも受賞には値しなかった。厳しい言い方になるが、プロのレベルどころか、小説として成り立っていない。
「三人の密室破り」 竹中篤通
アイディアが生煮えのままで、まだ小説になっていない。そもそもなぜ密室を作ろうなどと思ったのか。ミステリ史上おびただしい数の密室が扱われてきた。今、密室ものの新作を書く意味はどこにあるのだろうか。
警察小説は、かつての本格探偵小説へのアンチテーゼとして誕生した。浮世離れした名探偵の謎解きに飽き足らない作家たちが行動派探偵小説を書き、その延長線上に警察小説が生まれた。一九四五年、ローレンス・トリートが「被害者のV」を発表して、新たなミステリである警察小説の歴史が始まったのだ。警察小説を志す人は、そうした矜恃を持ってほしい。
「リアルライセンスヒーロー」 烏丸舟
キャラクターがまったく活きていないので、誰が誰だか混乱してしまう。
この作者は、「視点」を理解できていない。視点を意識しないと、小説は成立しない。小説が他の表現と違うのは、視点があるからだ。誰が見て、誰が感じ、誰が考えているのか。それをちゃんと意識して書かなければならない。同じ場面で、複数の人物の視点が混在しては小説が成立しない。小説は視点の芸術だからだ。
これが映像や漫画と小説が決定的に違う点だ。一般に映像には視点の概念はないし、カット割りによって視点の混在が可能だ。漫画も多くの場合、作者の視点、つまり「神の視点」で描かれている。だから、映像を前提としている脚本にも視点の概念はない。
視点を理解しない限り、シナリオや漫画のネームは書けても小説は書けない。
「背理の壁」 こちみちひさ
文章がプロのレベルには程遠い。この作者も「視点」が理解できていない。描写に繰り返しが多く、また台詞の多くが説明でしかない。トリックも大雑把で、読んでいて納得のいくものではない。
ただ、まったくつまらないかと問われると、そうでもない。エピソードとしては面白い部分もあり、最後まで読めてしまう。
全体に殴り書きをしたのではないかと思うくらい雑な印象がある。丁寧に推敲を重ね、文章を整理すれば読み応えのある物語になったかもしれない。惜しい。
蛇足だが、機動捜査隊のコールサインが出てくるので一言。310、320というコールサインはあり得ない。一桁目は所属の隊を、二桁目は担当の方面を表している。第三機動捜査隊は第八方面や第九方面が担当だから、一桁目が3なら、二桁目は8か9だ。この物語の舞台は立川だから、コールサインは38○でなければならない。