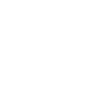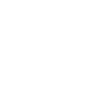火星開拓地にやってきた精神科医
カズキ・クロネンバーグ、29歳、精神科医。出生地は火星開拓地だがその後地球に移住し、今またやむにやまれぬ事情によって火星に戻ってきた。新しい勤務先は医療法人ゾネンシュタイン病院。火星唯一の精神病院である。
宮内悠介さんの第3作にして初の書き下ろし長編『エクソダス症候群』は精神医療史、そして家族をめぐる物語だ。
「実ははるか14年前から構想はありました。私は当時23歳で、小説家志望で就職活動もせず、ゲームセンターに勤めていました(笑)。カウンターの中でアイデアを書き留めていたものがこの話の原型です。とにかく無根拠な自信だけはある時期ですから……私が尊敬する小説家の竹本健治さんが23歳で『匣の中の失楽』という大長編を書いていて、私も同じ歳になったのでそれに匹敵するものを書かなければという野心があったのですが、アイデアを広げるだけ広げて結局まとめることができませんでした」
その頃から火星の精神病院という舞台や、エクソダスというキーワードはあったという。
「第1作の『盤上の夜』をまとめた頃に、今ならあの話も書けるかもしれないと考えたのです。抽象的に考えていたエクソダスを病名にし、キャラクターも半分くらい減らして書き進めていきました」
開拓地で増え始めた精神疾患、エクソダス症候群。妄想や幻覚が生じ、患者の多くが地球へ帰還したいという想念にとりつかれるこの病とカズキは向き合うことになる。彼はもともと地球ではISI=突発性希死念慮という、自殺願望を抱く病の研究をしていた医師だ。
「テクノロジーや薬によって精神疾患がコントロール下に置かれながらも、閉塞感があり、ISIという病によって人々が理由なく自死してしまう、というのが作中の地球の状況です」
一方、火星ではスタッフも薬もベッドも不足しており、カズキは激務に追われていく。やがて彼は、25年前、自分の父親もこの病院に勤務していた当時、何か重大な出来事がここであったと知る……。
これまでの2作もSFとして高く評価されているが、そもそも宮内さんは早稲田大学のミス研出身。しかし23歳の頃にはすでにミステリーではなくSFを構想していたということか。
「私は80年代のアメリカで育ったのですが、当時はスターウォーズ計画真っ盛りでした。これから人類は火星に出ていくかもしれない、と当たり前に考えていました。ですから自分にとって火星移住はSFというより、もっと普遍的な目的地だったと思います」
カズキを移住者にしたのも、自身もかつて米国と日本を行き来して、拠点が確定しなかった体験が作用したのかもしれない。
「確かに自分には謎の“故郷不在”感がありました。主人公が行ったり来たりしているのは自分と重ね合わせている面もあります。文化を跨ぐ者、文化の境界にある者が好きなんです。小説の書きだしでいちばん好きなのもバラードの『コカイン・ナイト』の〈私の仕事は国境を越えることだ〉ですから。今回も、境界を越えて両側を見る視点人物が欲しかったんです」
本作で描かれる火星は、露天商が並び辻馬車が主な交通手段であるような、西部開拓時代のアメリカのような世界。テラフォーミング(地球化)は進められているものの、大気を逃さないための天幕なしに人が住めるようになるのはまだ先のこと。そのため現在は山師や起業家たち、そして行き場のない人間たちが集まる場となっている。こうした火星の設定については「大変苦労しました」と宮内さん。
「テラフォーミングものは昔から多くの人がさまざまなアイデアを試みてきたジャンル。ですが今回、既存の手法に頼らず、フルスクラッチでゼロからテラフォーミングを試みることにしたんです。水を電気分解するところから考えていこうとしましたが、やはりそれは個人の手にあまるものでした。そこらじゅうで小さなバグが生まれてしまい、それを潰すのに大変時間がかかりました」
意外に苦労したのは、
「製鉄です。鉄はすべての産業の母ですよね。火星の表面が赤いのは酸化鉄ですから、鉄は無尽蔵にあると安心していたんです。しかしちょっと考えれば分かるのですが、製鉄というと大量の水と電力を消費する。火星では非常に難しいのです。火星には水が埋蔵されているという説に基づくのが無難なのですが、自分はワーストケースに対応していきたいタイプなので、水が少ないという想定のもとで考えていきました。無駄にゼロから考えたために、案外、これまでのテラフォーミングもので見落とされた点を奇跡的に拾えた箇所はあるかもしれません。そうであればよいのですが」

精神医療の歴史とは
この地でカズキはエクソダス症候群やISI、患者たちのさまざまな症状と向き合いつつ、病や病院の謎を探っていく。患者には聡明なエンジニアの青年もいれば、チャーリーという、病棟の主で、この病院の過去の事件も何か知っているとおぼしき謎めいた男もいる。
「チャーリーは精神医学の不都合な真実を一身に背負ったような人物です。そういうキャラクターを出すのが大好きなのです(笑)」
不思議な魅力を持つのは、言葉を話せない女性、ハルカ。また、病院のスタッフたちも個性的だ。彼らと接する日々のなか、カズキは自分の中の異状を認識していく。やがて、院内で深刻な事態が発生──。
本書の大きなテーマは精神医療であるが、
「小さい頃から精神医学に興味があったんです。高1か高2の頃にはじめて書いた小説は、意識とは何かをテーマにした『虚数世界』という、中二病感満載の恥ずかしいものでした(笑)。14年前に今回の話の原型を考えていた時も、コンピューターのバグに着目することで解析したりするように、精神疾患に着目することで人間の意識、認識をとらえようとしていました。ですからテーマが大きすぎ、抽象的すぎてまとまらなかったといえます」
この14年の間本書のための創作ノートも増え、考え方も変化していった。
「最初は人の精神や認識のことばかり考えていて、ある意味、個々の人間にはまったく興味がなかったんです。しかしそれから精神医学の本を読みあさり、就職して自分が鬱病にかかった時期もあったりして、だんだん個々の人間の病に興味が移っていきました。それでようやく、当初からあった大きな問いと、個人を引き結べるようになってきました」
その過程で心にあったのは、
「かねてから〈後期クイーン問題〉を真似して〈後期バラード問題〉と呼んでいるものがありまして(笑)。SF作家のJ・G・バラードの後期の3部作、『コカイン・ナイト』『スーパー・カンヌ』、『千年紀の民』は乱暴に言ってしまうと、高度な文明の中産階級から革命が起きる、ということが提示されています。たとえば『コカイン・ナイト』では、海辺の高級リゾートで、人々がみな精神安定剤によって浅い眠りに陥っているような状態が描かれます。これに対してバラードは一つの解を示すのですが、つづく二作では、また別の解が示されます。今回はそれに連なるもの、あわよくば新たな解を提示するものを書く、という壮大かつ無謀な野心がありました。バラードと自分を比べるなんてとんでもないとは思っていますが」
また、本書は現実の精神医療の歴史とそれに対する主人公たちの考えでも読ませるが、
「精神疾患に対する考え方は二転三転してきました。たとえば昔は旅行療法というものがあって、旅すれば精神疾患は治るといわれていた。これは、疾患は脳ではなく精神に由来するという考え方ですね。小説はある意味、人の心の変化を描くものですから、このほうが都合はいい。でもその後、統合失調症の原因遺伝子が見つかりはじめ、さらにその後、脳科学の発展の結果、やはり心理的な作用が大きいのではないかといわれている。最近は、このままずっと答えが出ないのでは、とすら思えてきました」
そんななか、興味を惹かれた説がある。
「作中でも引用していますが、中井久夫という精神科医が個人症候群という概念を提唱しているんです。統合失調症といった普遍性の高い疾患に対し、文化ごとの症状もあって、たとえば韓国の火病や日本の対人恐怖症は、その文化固有のものだそうです。であるならば当然、個人特有の症候群もあるはずだ、というなかなか目から鱗の見解です」
それらを踏まえて書かれたのが本作であるわけだが、
「精神疾患はあくまでも社会が規定するのだというのが私の出発点でした。社会にとって都合の悪いものを疾患と呼んでいるのだ、と。つまり世界の状況が変われば疾患の有り様も変わり、正常とされていたことが異常とされることもあるはずだという、受け入れやすい視点です」
つまりは患者こそが正常で、医師が異常だという世界だって成り立つかもしれない。さらにもう一歩踏み込んでみると、
「60年代のヒッピームーブメントなどでは、胡蝶の夢的な発想が流行ります。たとえばマジックマッシュルームを摂取すると、脳内のセロトニン受容体にセロトニンではなくシロシビンという物質が結合して幻覚や幻聴が起きる。逆から言うと、今私たちが見ている現実はセロトニンが見せている幻覚にすぎない、セロトニンが見せる現実もシロシビンが見せる現実も相対的なもので、どちらが正しいとは言えないんじゃないかという考え方です。これもまた耳触りのよい意見ですが、今回はそれも疑ってみようと思いました」
作中には、チャーリーが「反精神医学」なる視点に立った意見を言う場面もある。
「実際、狂気などは社会の都合で規定されるもので実際には存在せず、医者のほうがおかしいのではないか、という人たちもおられますし、私もそういった視点が好きです。でも文献を当たってみると、それらの意見の対立は単なる大学病院内の権力闘争が発端であったということもありまして(笑)」

父親探しというテーマ
カズキは精神科医として、病院内の事件、そして精神医療そのものと対峙していく。また彼はやがて、父親が関わった過去とも向き合うことになる。「これは故郷探しの物語であり、父親探しの物語でもあるんです」というように、読み終えた時、読者はこれは家族の物語であったのだとしみじみ思うはずだ。
多様な人種や民族が共存し混合している未来像は、多くのSF作品でも書かれてきた。しかしその一方で人は未来も、自分の血縁に対するこだわりを持ち続けるのか、とふと思う。
「未来において、すべての血は混ざっているのか、それとも多様化しているのか。それは私もSFを読むたびに思います。この先実際に血も結合し、ルーツも結合し、歴史も結合していくのでしょうけれど、それでも私たちは相変わらず自分たちのフィクショナルなルーツや歴史を求めていくのだと思います」
実は、この秋に刊行予定の新作も、こうした家族のテーマに触れているという。
「『yom yom』で連載していた『アメリカ最後の実験』を出す予定なのですが、これも父親探しの話です。ピアニスト志望の20代の青年が、失踪したジャズピアニストの父親が入学したというグレッグ音楽院を受験する。父親探しの話でもあり、音楽版『グラップラー刃牙』みたいな話でもあります(笑)」
つまり、次回作はミステリー色のある青春小説。今後、ジャンルにとらわれずに書いていくのだろうか。
「デビューまでに10年かかりまして、ようやく拾い上げてくれたのがSFの方たちでした。ですから今後もSFを軸にしながら、幅広く書かせていただければと思っています」
(文・取材/瀧井朝世) |