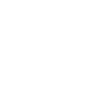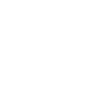オフビートな小説3選
『血の弔旗』(藤田宜永)での冷酷になり切れない根津の甘さ、弱さ、どうしようもなさ。これこそが暗黒小説の醍醐味だ。
正文館書店知立八ツ田店(愛知) 清水和子さん

アウトローやオフビートな小説は、えげつない描写や目を背けたくなる場面が多々ある。しかしそれは紛れもなくこの世界で起きている出来事であり事実であり、実は日常なのだと思う。そのような描写でしか表すことの出来ない人間の造形や世界の在り方、そのオフビート感覚が顔を出した瞬間、それを目撃した瞬間を読書の歓びと言うのだと思う。エンターテインメントとして成り立っているならば尚更素晴らしい!
『血の弔旗』藤田宜永(講談社)。根津は自分の雇い主の屋敷に忍び込み仲間と共に11億円を盗む。繋がりを持たぬよう別々の人生を歩み4年後に山分けするが……。高度成長期にともない目覚ましく発展していく戦後の日本と、例え人を殺してでものし上がっていこうとする根津が重なる。戦中、戦後、高度成長期、バブル期と、日本の風俗を肌に感じられる描写も良い。利己的な根津はだが情に流される弱い部分もある。冷酷になり切れない根津の甘さ、弱さ、どうしようもなさ。これこそが暗黒小説の醍醐味である。
『悪果』黒川博行(角川文庫)。密かにビール小説だと思っている。朝っぱらからビールをガブ飲みし、捜査に行く。または行かずに金儲けになるものを探しに行く。大阪府警マル暴担当刑事・堀内。高い捜査能力を持ちながらも、シノギを見付けどう甘い汁を啜るのか啜れるのかしか考えていない悪徳警官だ。金、女、享楽……そちらにどうしても目が向いてしまうふがいなさ。光と闇の間のボーダーライン。光とまでいかなくても灰色と黒の境目。その境目を描いている本作に慰撫されるのである。ラストシーンの余韻も素晴らしい。ビールを浴びるように飲んでしまう夏の暑さと相俟って、焦りやもどかしさを自分のことのように感じる。そして、ただただ物悲しく切なく心に沁み渡るのだ、堀内の全てが。
『デブを捨てに』平山夢明(文藝春秋)。表紙からして尋常ではない。4作の短編集。どれも素晴らしいが表題作を。平山夢明の文章は国境がない。安易な共感を断固拒否、乾き切っているが故のきらめきが存在しているところがとても好きだ。正と悪は常に反転する。「うでとでぶどっちがいい」。借金のカタにデブを捨てに行く羽目になるというかなりシュールな設定だが、何故かロードムービーのような風通しの良さを感じる。デブ(27歳女性)の男気に惚れてしまう!

〈新本格ミステリ〉三十周年を機に振り返る極私的三大傑作
綾辻行人『時計館の殺人』のため息が出るほどの完成度は、本格ミステリとして間違いなく十角館を凌駕する。
ときわ書房本店(千葉) 宇田川拓也さん

二〇一七年は、いわゆる〈新本格ミステリ〉の嚆矢である、綾辻行人『十角館の殺人』が刊行されてから、ちょうど三十年。中学・高校時代に、続々とデビューする若手新人作家を中心とした〈新本格〉ブームの直撃を受けた私から、いまなおとくに印象深い三作をご紹介したい。
名作『十角館の殺人』が、のちの国内ミステリシーンに与えた影響は計り知れない。しかし、〈館〉シリーズのベストなら『時計館の殺人』を挙げる。百八個もの時計が並ぶ、“時計”を模した異形の建築物でしか成立し得ない、巧緻にして鮮烈無比な大仕掛け。最後に発動する時計仕掛けの壮麗なカタストロフィの美。このため息が出るほどの完成度は、本格ミステリとして間違いなく十角館を凌駕する。ちなみに、ノベルス版の伝説のキャッチコピー「神か悪魔か綾辻行人か!」は、現在も文庫〈新装改訂版〉下巻の帯に用いられているのでお見逃しなく。
『翼ある闇 メルカトル鮎最後の事件』は、いまならミステリに疎い方でも、テレビドラマ『貴族探偵』の原作者──といえばピンとくるかもしれない麻耶雄嵩のデビュー作。京都近郊に蒼鴉城なるヨーロッパの古城のごとき館が建ち、そこで起こる惨劇にふたりの名探偵が挑むも、ひとりは推理がハズレるやショックで山に籠ってしまい、もうひとりのメルカトル鮎も“最後の事件”というサブタイトルどおりの結末を迎えてしまう展開に唖然茫然。こんなにも型破りな本格ミステリは初めてだったが、だからこそ、その異彩にたちまち目を奪われてしまった。単行本に添えられた、島田荘司、綾辻行人、法月綸太郎の強烈な賛辞も忘れがたい。
“型破り”といえば、九つものバラバラ事件を推理する、西澤保彦『解体諸因』も素晴らしい。エレベーターが降下する十六秒の間に解体されたOL。三十四個に解体された主婦。七つの首をスライドさせる連続殺人などなど、そのいずれもが、犯人はなぜ解体したのか?──をめぐるホワイダニットになっているのだ。なかには、わっはっは、こんなことのために解体したのか! と手を叩きたくなるような真相もあるが、それもまたチャーミングな魅力になっている(と個人的には信じている)。
このメモリアルイヤーを機に、ぜひ〈新本格ミステリ〉の名作に触れてみていただきたい。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
Shogakukan Inc. All rights reserved.
No reproduction or republication without written permission. |