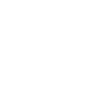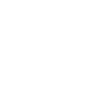天才ギタリストと女性ジャーナリスト
愛し合っている男女が幾度もすれ違うのは、恋愛小説の王道のパターン。それを平野啓一郎さんが書いたのだから意外といえば意外だ。新聞の朝刊連載だった『マチネの終わりに』は、天才ギタリストの男とジャーナリストの女が互いに強烈に惹かれあいながらも、人生を寄り添わせることができない様子を、現代社会のさまざまな事象を盛り込みながら描く。
「今の世の中は対立ばかりで、殺伐としている。それで、せめて小説を読んでいる間だけでも現実を忘れられるような、人と人とが結ばれあうことの美しさを書きたくなりました」
2006年、38歳の天才クラシック・ギタリストの蒔野聡史はコンサートの後、仕事関係者が楽屋に連れてきた女性に目を奪われる。2歳年上の彼女の名は小峰洋子。フランスの通信社の記者であり、母親は日本人、父親はクロアチア出身の映画監督で、なんと蒔野が大好きな作品を撮った人物の娘だった。打ち上げの席で話がはずむ二人だが、洋子にはすでにアメリカ人のフィアンセがいる。その後メールなどで交流を続ける二人だが、やがて洋子はイラクへ赴任、蒔野には少しずつスランプの波が押し寄せる。彼らが再会するのは、もう少し後のこと──。
40代にさしかかる男女を主人公にしたのは、
「若い人の恋愛というと、仕事がなくてもお金がなくても思いあう二人の気持ちの強さや、どちらかが死ぬ話になりがち。自分はいい年齢なので、あまりそういう恋愛には関心がないんです(笑)。もっと仕事や結婚、子どもといった現実と齟齬が生じる時に生まれる感情の起伏に興味がありました。それに40代くらいの人間を書きたい気持ちもありましたね。自分も37歳くらいから周囲にやたらと“アラフォー”と言われるようになったので(笑)、実際にアーティストや文学者など創作に携った人たちを振り返ったら、40代で迷走したり停滞している人が多かった。自分も小説家として20代、30代のうちにやりたかったことをやってしまった感があったので、もっと上のレベルを目指したいけれど、停滞する時期がくるのではないかと思ったりもしました。女性の場合、恋愛するにしても結婚するにしても子どもを産むか産まないかを考える年代。僕は周囲を見ていても、産んでも産まなくてもいいとは思いますが、でもやっぱり考えさせられることではありますよね」
ギタリストという設定にしたのは、
「以前、ショパンとドラクロワについて書いた『葬送』という小説を出しましたが、文庫で四分冊という長さの小説なのに、あれが好きだという方が結構多いんです。僕も、憧れの人たちについて書いているという幸福感がありました。それで、また音楽をテーマにして書きたいなと思っていた頃、クラシック・ギタリストの福田進一さんのCDを聴いて感動したんです。福田さんは数年前からバッハの曲に取り組まれている。バッハはプロテスタントだしヨーロッパ社会は凄惨な三十年戦争も経験しているし、どこか現代の日本人には理解しきれない部分がある気がしていました。でも福田さんのギターで無伴奏チェロ組曲を聴いて、すごく近くに感じたんです。それで、遠いところにいたバッハを自分に近づけてくれたクラシックギターのことを書いてみたくなりました。僕はずっとエレキギターをやっていましたが、これを書くためにクラシックギターを買って、ここに出てくる曲を練習しました」
あえて“天才”にしたのにも理由がある。
「単純な話、ぱっとした話にしたいなと思って(笑)。中くらいの実力の人がスランプに陥るより天才が陥ったほうが落差が大きいですよね。今回は等身大の話よりも、もうちょっとふわっとした世界にしたかった。それに、『葬送』でドラクロワが、今日は仕事をしなければいけないのにどうしてもできなかったなどと日記に書いている話を入れたら、その場面のことを言う読者が多くて。自分は大画家ではないけれど、気持ちが分かる、と言うんです。みんな、憧れるような素晴らしい人に共感できる面があると気持ちがいいんだなと気づきました。天才というのは、とにかく魅力的ですし」

洋子の背後に広がる現代社会の諸問題
だから少年時代から注目を浴びてきた蒔野が、40代を迎えアーティストとして壁にぶつかる苦悩も細やかに描かれていく。一方の洋子の抱える事情もなかなか複雑だ。数か国語を話し聡明で美しい彼女は、クロアチア出身の映画監督を父に持ち、長崎で被爆してからヨーロッパに渡り、父の二番目の妻となった日本人女性を母に持つ。また、イラクに赴任することになるが、これらはみな、どうやら昨今の世界状況が反映されたもののようだ。
「洋子はモデルがいるので書きやすかったです。もちろん、アレンジはしてあります。実際、ヨーロッパでは難民同士が結婚して生まれた子どもなど、複雑なルーツを持つ人は少なくない。昨今の“日本って素晴らしい”という風潮にうんざりしていたので、ルーツの複雑さとその人の個人としての魅力は関係ないんじゃないか、ということを書きたい気持ちがありました。彼女を精力的に働く女性にしたのも、今の“保育園に入れられないなら母親が家で育てろ”という反動的な女性観に対するアンチテーゼの意味合いもありました」
洋子の母親は長崎からヨーロッパに逃れ、洋子の父となる男性と出会ったわけだが、
「これは福島の事故のことが頭にありました。被曝の恐怖とともに生き続けている人たちは今の日本にもいる。福島に残り続けている人たちの声も社会のなかではマイノリティですが、避難した人たちの声はさらにマイナー。原爆の時にだって、もう長崎にいたくないといって他所の土地に行き、被爆した事実を隠して生きた人もいます」
洋子の父親をクロアチア出身にしたのは、
「今、昨日まで仲良く暮らしていた人たちが、民族対立や宗教対立によって壮絶な殺し合いをするようになっている。ユーゴスラヴィアを含むバルカン半島はヨーロッパのなかで一番矛盾がある。いろんな民族が共存していたのに、90年代に民族浄化という、絶望的な状況が生まれてしまった場所です」
洋子はイラクに赴任するが、のちにその時に一緒に働いた女性をパリで難民として迎えいれることになる。
「僕がこれを書いた頃は、ここまで難民問題は大きくなっていなかった。ただ、巻末にも書きましたが、亡くなったジャーナリストの後藤健二さんに取材した時に、パリで難民の女性の面倒を見たというエピソードを聞いたんです。そのことが大きなヒントとなっています」
洋子はイラクで、あと数分同じ場所にとどまっていれば爆死していたという体験もする。それは、以降の洋子の精神を揺るがす。
「これは東日本大震災のことが頭にありました。あの日、あと1時間津波が遅ければ、高台の用事を済ませて家に戻って流されていたかも、というような人はたくさんいる。地震や津波の可能性は知っていたとしても、それがいつ起きるのかはみんな分からない。努力してもどうにもならないということに、ある種の運命的なものがあるなとは感じます。戦争でも、そうしたタイミングの話は多いですね。僕の祖父は戦時にビルマに行っていたんですが、塹壕で嫌な予感がして飛び出した瞬間、そこに爆弾が落ちたんだそうです。危ないから出ようと言っても一緒に来なかった人はそれで死んでしまった。そういうふうに運命を決する人たちがいるというのが、戦場の感覚なんでしょうね」
しかし洋子は、生き延びたことをラッキーとは受け止められず、PTSDを抱えてしまう。
「9・11の時も震災の時も、イラクからの帰還兵などの例でも、生き残ったことに苦しみ続けている人は多い。今思えば、僕の祖父も突然激高して家族の中にはそれが消せない記憶として残っていますが、あれはPTSDだったのではないかと思う。長引く人は本当に大変ですが、洋子の場合は1年ちょっとで和らいでいます」
洋子のPTSDの症状もまた、二人の愛の方向を左右する要因のひとつ。そう、彼らがすれ違うのは、そうした内的な要因のほかに、外的な要因もある。
「今回は、会わないという決断をして会わないことと、偶然に左右されて会えないことと、その両方が起きた時に二人はどうなるのか、ということをテーマにしたかった」
読者からすれば愛し合っている二人のすれ違いは、どうしたって歯がゆくなるのだが、
「読んだ方はこの二人がすごく愛し合っていると思うし、結ばれてほしいという気持ちを抱きますよね。でも僕が書いたことといえば、この二人は話がすごく合うのだ、ということくらい。つまりはそれが、多くの人が恋愛で求めていることなんじゃないかなと感じました」
そう、実はこの二人、プラトニックである。
「それは最初から決めていました。二人の間の精神的な高揚感を描きたかったし、肉体的に満たされないからこそ、お互いに相手への気持ちが残り続けたともいえますから。それに、多くの人のなかに、肉体関係になってもよかったのにそうならないまま会わなくなった相手というのがいるんじゃないかと思うんです。そういう記憶と響き合う物語にしたかった」

過去というものは変わっていく
時は過ぎ、それぞれの人生模様も変化していく。そのなかで、たびたび思い起こされるのは、出会った日に蒔野が言った言葉。
〈人は、変えられるのは未来だけだと思い込んでる。だけど、実際は、未来は常に過去を変えてるんです。変えられるともいえるし、変わってしまうともいえる。過去は、それくらい繊細で、感じやすいものじゃないですか?〉
「科学的に根拠があるそうなんですが、人は過去を振り返る時、その思い出し方によって記憶を上書きしているらしい。あの出来事は実はこういうことだったのかな、もしかしてああいうことだったのかな、などと思うことで、過去は変わってしまう。逆に言えば、過去は変えることができるんですよね。そうしないと人生が続いていかないとも感じます」
そうやって思い直すことで、人は自分の人生と折り合いをつけているのだろうか。
「洋子の父親が娘に、未来を考える時は自分の意志で何かができると信じないとやっていけないけれど、過去を振り返る時に全部自分の意志の結果だと考えると苦しいから、自分ではどうしようもなかったことだと思いたい、と語る場面があります。自由と運命というもののなかで人は生きていて、そのなかで恋愛も起きている。そういうことを書きたかったんです」
読み終えてタイトルの意味をしみじみ噛みしめた時、彼らの人生も昼の公演を終えたくらいの時間で、今後も続いていくのだと気づく。
「マチネはもともとフランス語では朝という意味。それがずれて今は昼公演のことになっているんですが、そこが今の世代の状況にも近い気がしました。昔の20代、30代にくらべるとみんな若くて、恋をする時期も長くなって、後ろにずれこんでいる。その時期もそろそろ終わって、人生の後半に入っていくという意味合いもありますね」
運命と自由意志の導きに読者も翻弄されながら、マチネの後にたどり着く男女。いつまでも余韻に浸っていたくなるラストシーンが待っている。
「僕の小説を読んだことのない人に何から読めばいいかと訊かれたらこの本を挙げるくらい、手ごたえを感じています」
という平野さん。『日蝕』や『葬送』など第1期、短篇集などが中心の第2期、『空白を満たしなさい』や『ドーン』といった分人主義を描いた第3期を経た今、
「今は自然災害のこともあって、運命論的なことを考えざるをえませんね。分人主義という、個人のアイデンティティを追究したものを書いた後なので、今度はどうしても巻き込まれてしまう、外部環境について考えていくつもりです」
作家としての第4期に入った今、どうやら40代の停滞期はなさそうだ。
(文・取材/瀧井朝世) |