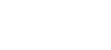ミステリ、ハードボイルド、組織論、はたまた公安や女性刑事ものまで。深さと多様さを得ていきながら、現在、警察小説は出版界の王道を歩んでいる。
しかし、その歴史を振り返ってみたとき、ジャンルとして確立したのは、そう昔の話ではないことがわかる。警察小説はどこからきたのか。いかに進化していったのか。販売の現場からその歩みを眺め続けてきたミステリ偏愛書店員が紐解く。
現在ではジャンルとして確立している日本の警察小説も、当然ながら黎明期があり、発展期を経て今日のような隆盛を誇るまでには、長い道程が存在する。相場英雄『震える牛』や長岡弘樹『教場』といったベストセラーを刊行した小学館により立ち上げられた新たな登竜門「警察小説大賞」が誕生し、 佐野晶『ゴースト アンド ポリス GAP』が第1回受賞作として世に放たれたこのタイミングに、改めて日本警察小説の辿ってきた変遷を振り返ってみようと思う。
かつてミステリにおける警察官は、探偵役のバリエーションのひとつか単なる脇役に過ぎなかった。しかし、米国人作家ローレンス・トリート『被害者のV』(1945年)において、轢き逃げ事件を追う警察捜査の実態がリアルに描かれ、〝世界で最初の警察小説″という評価を獲得する。
そして1950年代に入ると、英国人作家J・J・マリック〈ギデオン警視〉シリーズや米国人作家エド・マクベイン〈87分署〉シリーズがスタートし、いわゆる「警察小説」の基礎がここで形作られた。

いっぽう日本では、一見ぐうたらな警察署長が人情味あふれる手法で難事件をつぎつぎと解決する、山本周五郎『寝ぼけ署長』(1948年)や、刑事ふたりが情死事件に仕組まれたアリバイトリックに挑む、松本清張『点と線』(1958年)が刊行された。
そして1959年、藤原審爾の短編「若い刑事」が雑誌に掲載される。この一編こそ、戦後の新宿を舞台に刑事たちの群像を描き、〈87分署〉シリーズにも伍する日本警察小説の最高峰〈新宿警察〉シリーズの原型となる記念すべき作品である。
続いて60年代、まず1963年に刊行された結城昌治『夜の終る時』(日本推理作家協会賞受賞)は、ヤクザとの癒着が疑われていた刑事の死の真相を、乾いた筆致と倒叙形式を活かした二部構成で浮き彫りにした。
同年に刊行されたのが、水上勉『飢餓海峡』だ。沈没した青函連絡船から、なぜか名簿に記載のない人物の遺体が見つかった謎を発端とした、刑事たちの執念の捜査を描く。
ポン引きが「自分の部屋で女が殺されている」と派出所に駆け込み、なぜかその遺体の下腹部にはマジックで〝V″と書かれていた「赤きVの悲劇」をはじめ、捜査一課の面々が活躍する痛快な作品集が島田一男『紅の捜査線』(1968年)だ。
70年代も見ていこう。
明治6年、草創期の警視庁と旧南町奉行所一派との対決を軸に、実在の人物や歴史的出来事が絡む事件の数々を虚実取り混ぜて描いた、山田風太郎『警視庁草紙』(1975年)。ホテルのエレベーターで何者かに刺し殺された黒人青年が死の直前にタクシーに残した西條八十の詩集と謎の言葉「ストウハ」を手掛かりに、麹町署の刑事──棟居弘一良が戦後日本の欺瞞を背景とする事件を追う、森村誠一『人間の証明』(1976年)……といった作品がこの時代を代表している。
また、1978年刊行の矢作俊彦『リンゴォ・キッドの休日』も特筆したい。非番だった神奈川県警の刑事──二村永爾が署長の命を受け、射殺事件の鍵を握る女を公安よりも先に突き止めるべく横須賀の街へ踏み込む、チャンドラー直系のハードボイルド作品といっていい。
週刊誌の記者が寝台特急はやぶさで〝薄茶のコートの女″をカメラで撮るも何者かにフィルムを抜き取られ、さらに個室寝台から消えたその女が多摩川で遺体となって発見された。時刻表トリックを駆使した難事件をご存知、警視庁捜査一課の警部──十津川省三と亀井刑事が追うトラベルミステリーの嚆矢、西村京太郎『寝台特急殺人事件』(1978年)などがある。
 エド・マクベイン 〈87分署〉シリーズ
エド・マクベイン 〈87分署〉シリーズ
物語の主人公はスティーヴ・キャレラ二級刑事だが、筆者の偏愛キャラはキャレラの同僚でユダヤ人のマイヤー・マイヤー。珍しい名前のせいで苦労するも、忍耐強く、人間味あふれる彼にご注目あれ!