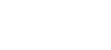1980年代になると、現在ベテランの域にある作家の初期作品が徐々に登場し始める。
逢坂剛『裏切りの日日』(1981年)は、『百舌の叫ぶ夜』(1986年)から始まる〈百舌〉シリーズの前日譚的な作品だ。極左テロ組織「東方の赤き獅子」メンバーを名乗る男が商社ビルの社長室に人質を取って立て籠るも、身代金を持って逃走する際、エレベーターから忽然と消えてしまう。さらに同テロ組織から脅迫文を受け取っていた右翼の大物が近くのマンションで射殺された。このふたつの事件を公安刑事の桂田が捜査していく。主人公に公安刑事を配した先駆け的な作品であり、鮮やかな人間消失トリックが光る。
黒川博行『二度のお別れ』(1984年)は、デビュー作にしてすでに著者の持ち味である「大阪」「コンビ」「テンポのよさ」が発揮された快作だ。人質をともない現金400万円を奪って逃げた銀行強盗を追い掛ける大阪府警捜査一課だったが、さらに犯人から1億円を要求する脅迫文が切断された指とともに届く。刑事の黒田と相棒のマメちゃん、通称〝黒マメ″コンビと知能犯の対決やいかに。
今野敏『東京ベイエリア分署』(文庫化に際し『二重標的 東京ベイエリア分署』と改題/1988年)は、現在も〈東京湾臨海署安積班〉として続いている人気シリーズの記念すべき第1弾だ。品川からほど近い若者ばかりが集まるライブハウスで30過ぎの女が殺される事件が発生する。安積警部補率いる安積班は捜査の過程で別の事件とのつながりに気づく。個性が光る捜査員たちがチームとなって事件を手掛けていく面白さは、まさに〈87分署〉や〈新宿警察〉の直系といえよう。
北方謙三『傷痕 老犬シリーズⅠ』(1989年)から始まり『風葬』『望郷』と続く〈老犬〉三部作は、『眠りなき夜』(1982年)で初登場したのち複数の作品に顔を覗かせる一匹狼の刑事〝老いぼれ犬〟こと高樹良文の生い立ちを少年期から振り返る大作だ。
スティーブン・フォスター「老犬トレー」のメロディーを口ずさみ、火つきの悪い旧式のオイルライターでゴロワーズをくゆらせるあのキャラクターが歩んできた壮絶な人生、そして刑事としての終着が胸に迫る。
 北方謙三 〈老犬〉三部作
北方謙三 〈老犬〉三部作
数々の好漢を生み出してきた北方作品のなかでも指折りのカッコよさを誇る〝老いぼれ犬″。一読心を撃ち抜かれた若い時分、どうしてもゴロワーズが喫ってみたくなり、ほうぼうを探し歩いたのは、いい思い出である。喫ってみた感想は……。
1990年代は、日本警察小説の歴史のなかでもとくに重要といえる作品が複数登場するのだが、なかでも大沢在昌『新宿鮫』(1990年)は、今日の警察小説ジャンルの人気を大きく押し進めた立役者といえる。
主人公である新宿署防犯課(のちの生活安全課)に所属する警部──鮫島は、単独で音もなく近づき犯人を噛む(逮捕する)ことから「新宿鮫」の異名で犯罪者たちに恐れられる存在だ。

国家公務員上級試験をパスしたエリート〝キャリア″でありながら、本庁在職時に公安絡みの暗闘に巻き込まれ、警察組織にとって〝爆弾″というべき手紙を預かったことから新宿署に左遷され、以来出世の道から外れたまま在るべき刑事を貫いて犯罪者を噛み続けている。この設定によって屹立する鮫島の孤高の人物像は、これまでのアウトローになかった斬新さを獲得した。
物語は、過去に逮捕した拳銃密造犯の木津が刑期を終えて出所し、鮫島はその足取りを追う。いっぽう、新宿署管内で警官ばかりを狙った連続射殺事件が発生。鮫島は顔馴染みの鑑識員である藪から、犯行に使われた銃が特殊な改造を施したものだと教えられ、木津の関連を睨む。
ちなみに大沢在昌作品ではもうひとつ、毎回異なる主人公の脇を新宿署の冴えない中年刑事──佐江が固める、『北の狩人』(1996年)から始まる〈狩人〉シリーズも強くオススメしたい。先の読めない展開では『新宿鮫』を凌駕する。
これもまた日本警察小説史において最重要級の作品といえるのが、髙村薫の『マークスの山』(1993年)である。平成4年、東京で〝マークス″を名乗る謎の殺人犯が現れ凶行を重ねる。
警視庁捜査一課の警部補──合田雄一郎は、16年前に南アルプスで起きた撲殺事件に起因するこの連続殺人事件の真相に地道な捜査で迫っていく。物語の密度とスケール、臨場感と熱量、そして人間の闇を描き出す文学的な筆致等、当時の年末ミステリランキングを制し、直木賞にも輝いたことが頷ける不朽の名作だ。
 大沢在昌『新宿鮫』
大沢在昌『新宿鮫』
筆者が発売まもないカッパ・ノベルス版『新宿鮫』を手に取ったのは中学生の頃。まだ「警察小説」という名称も今ほど使われてはおらず、背表紙には「書き下ろし長編ハード刑事小説」と記されていた。
2001年以降、女性刑事を主人公にしたシリーズが続々と立ち上がるが、その先駆けとなる二作品がここで登場する。
柴田よしき『RIKO女神の永遠』(1995年)の主人公──村上緑子は、上司との不倫が関係した傷害事件により本庁から新宿署に異動となった刑事だ。ある日、緑子はビデオ店から裏ビデオを押収する。
そこには誘拐した少年たちが輪姦される無惨な様子が録画されており、卑劣な犯人はこのビデオをネタに被害者家族から身代金を要求していた。男性優位の巨大な警察組織のなかで戦いながら、上司や同僚、果ては婦警とも性的関係を結んでいく緑子の躍動を描き出す、異色かつハードな警察小説である。
乃南アサ『凍える牙』(1996年)もまた、男性ばかりの捜査本部のなかで紅一点の存在である音道貴子が主人公。レストランで突如として客のひとりの上半身が燃え上がる不可解な事件が発生する。ベルトに仕掛けられた発火装置に加え、この被害者の脚には大型犬のような獣に咬まれたと思しき傷があった。さらに増え続ける何かに咬み殺された死体。貴子は、捜査線上に浮かんだ狼と犬をかけ合わせたオオカミ犬を追う。一心に獲物を追い掛ける貴子が、圧力や縛りから解き放たれるクライマックスの情景が忘れがたい。
そしていよいよ真打ちの登場である。横山秀夫『陰の季節』(1998年)は、刑事ではなく県警の警務部──つまり裏方の警察官を主役にすることで警察小説ジャンルに新風を吹き込んだ作品集だ。
大物OBが天下り先を辞めようとしない理由に隠されたある未解決事件、昇任を控えた生活安全課長の不倫の密告、はたまた県議が用意しているらしい県警の不祥事に関する質問内容の調査など、それぞれの短編に練度の高い謎解きを組み込み、警察小説の新たな面白さを見事に達成してみせた一冊である。
かつてミステリの傍流に過ぎなかった「警察小説」は、米英の始祖によって基礎が形作られたのち、日本でも優れた作家たちの手によって社会や世相と切り結びながら次第にジャンルとして確立していった。そして『新宿鮫』や『マークスの山』といった金字塔的な作品がベストセラーとなり、横山秀夫がデビューした90年代を経て、2000年代に入るとさらなる進化を見せ、より多彩な作品が登場することになる。
 横山秀夫『陰の季節』
横山秀夫『陰の季節』
捜査畑ではない警察官にスポットを当てた『陰の季節』には、この手があったか! と大いに感服した。ちなみに後年、同じくらい強くひざを打ったのが警察学校を舞台にした長岡弘樹『教場』である。