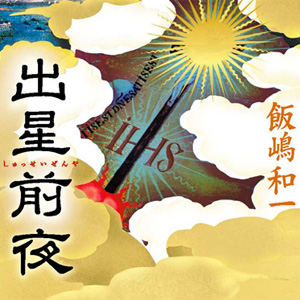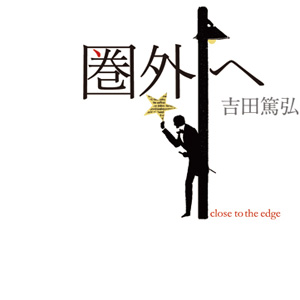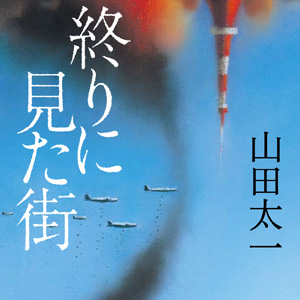| ホーム > きらら通信 > 2006年 |

|
|||||||
2006年12月号 【31】テレビで書評家がいわゆる「ケータイ小説」について、「小説の読者の裾野が広がるから」とやや肯定的にコメントしていました。不特定多数を相手に するテレビという媒体なので、きっと書評家も多少の配慮をもってそう答えたにちがいないとは思うのですが、実はこの考えには最近かなり疑問を抱いていま す。 「ケータイ小説」というのはいわゆる携帯電話のサイトで発表された作品で、特徴としてはまず文章のセンテンスが短い。これは携帯電話のサ イトが限られたスペースで成り立っているからとも思われるのですが、実は書く側の問題でもあると考えています。つまり長い文章で表現するものを書かない。 たとえばこれまでの小説がやってきたアンビバレントな人間のややこしい感情や複雑な心理などはあまり書かない。そこで展開されるのは描写が極端に少ない筋 だけの(場合によってはそれさえも希薄な)文章の一群なのです。 実際にいくつかを読んではみたのですが、どうしても自分の感情をフィットさせることができない。横書きであるとか、登場人物が若い人たち なので年齢が離れている自分には理解できないせいかとも考えたのですが、どうもそうではない。これを認めることができないのは、書き手の企みの稚拙さと感 情の幼稚さに、とても違和感を覚えるからなのです。さっき筋だけと書きましたが、実は感情吐露の部分もあります。とてもステレオタイプなむきだしのまま の、読んでいて恥ずかしくなるような。 さて、果たして「ケータイ小説」は「小説の読者の裾野を広げる」ことに繋がるのでしょうか。正直言えば「ノー」と答えたい。いまのところ これは小説とは似て非なるものとして認識しておきたい。少なくとも小説と呼ばれるものは、もっと人間の奥深い部分に降りていこうとするものではなかったの か。これを小説と認めてしまうことは、小説に携わってきた先達に失礼な気もするし、自分たちがやってきたことも無に帰するような気がするのです。もちろん これから画期的進化を遂げるのかもしれませんが、いまのままでは「裾野」は広がらないと思うのです。 ときどき「きらら」の「携帯メール小説」を「ケータイ小説」と同一視して、取材が舞い込むことがあります。もちろんその場で違いを説明することになるのですが、最近ではこう答えることにしています。あれは別の惑星で起きていることなんです、すみませんが。 ( I ) 2006年11月号 【30】小説家というのはとてもタフな職業だと思う。たぶん、ものを書いてそれを生業とするのは印刷というものが発明されて以降のことだと思うが、それにしても不特定多数の人に向かって物語を発していくということは、どうにもたいへんな仕事に思えて仕方ない。 たとえばいまネットの中で無数に発信されているメールやブログ。これは無限の広がりの中で展開されているという錯覚に陥りやすいが、印刷 メディアに比べればきわめてパーソナルに、送信者と受信者をダイレクトにつないでいる。つまり書き手は読み手のことを具体的にイメージしながらそれを書い ている。 翻って小説家は誰に向かって物語を発しているのか。もちろん自分なりの読者を意識しながら書いているのだろうが、それはとてつもなく漠然 として頼りないもののような気がする。否、最近の小説の中にはその意識さえ希薄なものが少なくない。つまり誰に向かって発信しているのか正直そのことさえ 掴みかねる作品に出くわすことも多いのである。 歴史的に小説家の前身は、物語を口承で伝える語り部のような人たちだと考えている。たとえば『平家物語』をかたちづくった琵琶法師や古代 ギリシャのホメロスあたりが源流となるヨーロッパの吟遊詩人のような人たち。彼らが物語を語るとき、それを享受する人たちは必ず目の前にいた。物語の発信 者にとってこれはたいへん幸せな環境にちがいない。受け手に向かって、音楽的パフォーマンスに乗せ、時には彼らがわかりやすいような身振り手振りも交え、 厭きさせることなく、いともたやすく物語を伝えることができたのである。 グーテンベルク以降、彼らは職を失することになるのだが、近代の琵琶法師や吟遊詩人たちはかわりにペンを執り、それを言葉と文章の芸で成 し遂げてきた。しかし、今度はその培ってきた至芸をあまりに熱心に磨くあまり、かつては目の前にいた物語の受け手の存在が頭の中からすっぽり抜け落ちて いった。 やがて現代、映像の登場で物語伝承のトップバッターの位置を脅かされつづけている小説。いまこそ原点に戻って、物語に目を輝かせる人たち の顔を自分の前に思い浮かべるのも悪くはないのではないだろうか。映像や音楽を駆使する琵琶法師や吟遊詩人たちと渡り合っていかなければいけない21世紀 の小説家はやっぱりタフな職業だと思う。 ( I ) 2006年10月号 【29】編集者という職業に就いてずいぶんたちますが、最近思うのはどうもこの仕事からは一生離れられないのではないかということです。実は家にいても仕 事に関係した原稿を読むことが多いので、なかなか自分の読書ができないでいるのですが、たまさか時間が空いて前から読みたかった小説などを手にとっても、 この書き出しは魅力的なのだろうかとか、この表現は当を得ているのだろうかとか、ここは人称が乱れていないか、時制はきちんと認識されているのかとか、そ んなことばかりが気になり、なかなか作品を楽しむことができないのです。一種の職業病といえなくもないのですが、小説を読むことを心から楽しむことができ ないのは自分にはひどく不幸なことのような気がして、ときおりこの仕事からすっぱり足を洗ってしまおうかと考えることもあります。 さて、自分にとって小説を楽しむとはどういうことなのかと、先日夜明けの薄暮の中で、校正が終わったばかりのゲラを前にして考えたのです が、どうも自分としては、小説を読むなかで時間を忘れさせてくれる何かに出遭う、そのことがいちばん重要な気がするのです。「何か」というのは、もちろん ストーリー展開から始まり、文章のスタイル、言い回し、そして作者の考え方、登場人物の魅力、それらをひっくるめてのことなのですが、いまいる世界からも うひとつ別の世界へ連れて行ってくれる、そんな作品にめぐりあったときに「読む楽しさ」をいちばん感じることができるのです。そういう意味では1行ごと1 ページごとに現実に引き戻されるゲラ読みではなかなかそういう愉楽に出遭うことは少ないようです。 では、なぜまだこの因果な商売から足を洗わずにいるのか。それは小説を読む楽しさとは別種の楽しさがそこに存在するからです。何かという と、いうまでもなく作者の作品世界に直接関わることができるということです。未発表であるなら何らかの影響を作品に及ぼすこともできる。書き手と同じ場所 から小説に対峙することができるからなのです。もちろんそういう関わり方を許さない作家の方もいらっしゃるし、こちらの実力が伴わないこともあります。と はいえこの仕事をやっていてのいちばんの楽しみは、自分たちもつくる側の一翼を担うことができるということなのです。だから明日もまた朝の匂いのなかで、 小説を楽しめない楽しさを味わっています、きっと。 ( I ) 2006年9月号 【28】音楽家なら聴覚、写真家なら視覚、料理人なら味覚、調香師なら嗅覚、さてわれらが小説家はどんな能力に優れているのか。 たとえば文章を綴る能力は小説家だけのものではない。世の中にはいろいろなところにいろいろな文章を書く人たちが存在する。新聞記者、法 律の専門家、取調べ調書をとる警察官、パソコンの長い長いマニュアルをつくる人、それこそそれぞれの場所にそれぞれの能力に長けた文章を書く達人がいる。 では書くことよりも話すことなのか。物語を淀みなく語っていくことも小説家の能力のひとつなのではないか。しかし、これなどはいつも皆の前で何かを語っている政治家あたりのほうがよほど上のような気がする。 では小説家の能力でいちばん重要なものは何か。それは嘘をつく能力のような気がする。 自らの経験に即して語れば、すぐれた小説家はいずれもかなりの「嘘つき」であった。 或る小説家と取材旅行に出かけて、後日原稿をもらうことになった。できあがった原稿には取材に出かけた場所のことはいっさい書かれていな かった(違う場所の違う時間の物語が展開されていた)。しかしそこで表現されていたものは、明らかに取材旅行の成果でしか生まれ得ないものでもあった。見 たもの聞いたものをそのまま表現するのではなく、それらを自らの心の宇宙に映して、あらたに再構築していく。「事実」から「真実」を抽出し、より「真実」 が強化された「嘘」をつくる。その過程をそのとき垣間見たような気がした。 別の作家に自分のことについて書かれたときには、明らかに現実には魅力的ではない男が、何故か八面六臂の活躍をしていた。そういえば彼が語る話はいつも五割がた誇張されていた(というより誇張するのが上手かった)。 たぶん「嘘つき」を職業に生かせるのは、小説家と詐欺師くらいかもしれない。小説家の方にはたいへん失礼な言い方になってしまうが、これは僕のささやかな経験則から引き出された個人的感想である。どうかお許しを。 このところ気持ちのいい「嘘をつく」小説が多くなってきたように思う。ただ時にはあまりにそれが気宇壮大すぎて、簡単に底が割れてしまう芸のない「嘘」も少なくはない。 ということで、実はいまいちばん僕が読みたいと思うものは、法律の専門家が書いた偽の六法全書かもしれない。 ( I ) 2006年8月号 【27】まずは宣伝から。「きらら」携帯メール小説大賞が本になります。(詳細は71ページに) 本のタイトルはずばり『携帯メール小説』。創刊以来この2年間に応募いただいた作品の中から、月間賞に輝いた40作品、佳作の中から39作品、そして選考委員である佐藤正午氏と盛田隆二氏の小説をそれぞれ12篇ずつ、計103篇の作品を収録する予定です。 「きらら」も創刊からようやく3年目に入りましたが、この間「携帯メール小説大賞」には1万篇を超える作品の応募をいただきました。あり がとうございます。今回の本はその中から選りすぐった作品ばかりですが、これら以外にも素晴らしい作品をたくさん読ませていただきました。限られたページ 数のため、すべて載せられなかったのがたいへん残念です。 さて、この「携帯メール小説大賞」を始めたきっかけというものを少しお話ししましょう。「きらら」は小説をもっと親しみやすいものに、い ままであまり小説を読まなかった新しい読者の方々にも小説の楽しさというものを積極的に発信していこうという考えから生まれました。書店員さんによる小説 の本のレビューである「from BOOK SHOPS」と並び、いわばこの「携帯メール小説大賞」は「きらら」の「きらら」たるゆえんの企画でもありま す。いまや生活必需品ともなった携帯電話を通して小説を書いて応募していただく。そのことで小説を読むだけではなく書くことにも楽しさを見出していただけ ればという思いでスタートしたのです。 おかげさまで当初から各メディアで取りあげられ注目を集め、毎月たくさんのご応募もいただきました。そして何よりも、これをきっかけに長 いものを書き始め一般の小説賞の候補になったり、応募者の方が文学賞を受賞されたりという嬉しい知らせも編集部には届きました。携帯電話を入り口に小説の 世界が少し広がったと僕たちもひと安心です。 さて、このところ携帯電話で読書するという人たちが毎年倍々ゲームで増加していると聞きます。まだ絶対数が少ないので、今後どうなってい くかは予測できませんが、その中でも僕たちは小説がたくさん読まれることを願っています。小説を楽しんでくれる人たちが増えてくれることを静かに祈りなが ら、「携帯メール小説」という本を世の中に送り出したいと思います。どうかよろしくお願いします。 ( I ) 2006年7月号 【26】ライトノベルの編集者が小説との違いを説明するときにとてもうまいことを言っていました。小説とライトノベルを分けるのは画がついているかいない かだと。確かにライトノベルと呼ばれる作品にはとても魅力的なイラストレーションがついている場合が多く、そのイメージに助けられ、読者は物語世界を広げ ていくことができます。そして書き手にも、そのような画の力を借り、文字による描写を軽減化している傾向は多々見られます。 しかしこの定義で困るのは、画を取り去り文字だけの物語として作品を読んだときでも充分に小説として楽しめる作品にしばしば出合うことです。 言語による表現である小説にとって、文字による描写は命です。その描写に関して画の助けを借りているライトノベルはやはりライトノベルと呼んだほうがいいのかもしれませんが、どうもそういう境界線をやすやすと乗り越えてしまう作品が最近は多いのです。 先月号の「きらら」の書店員さんインタビューに登場していただいた辻村深月さんの作品などはライトノベルの読者にも広く支持されていますが、やはり文字による表現がとてもきらめいていて、そういう意味でとても困惑させられる作品のひとつなのです。 「きらら」は、とくに小説とライトノベルを峻別して線引きするつもりもありませんし、ヴィジュアルとのコラボレーションにしても、どしどしやっていきたいと考えています。 (今月号から巻頭のカラーで若手イラストレーター福嶋舞さんの連載も始まりましたのでよろしくお願いします) ただ、言語による表現というものにはとことんこだわっていきたいと考えています。文字と画なら、やはり文字の陣営の一員として、物語の世 界を切り拓いていきたいと考えています。言葉の連なりの中でしか表現しえない重層的な感情、文章の流れの中にこそ広がる豊穣なストーリー、ヴィジュアルの 助けを借りずそれ以上に鮮烈なイメージを文字で構築すること、それらを小説というジャンルで試みていければと考えています。 文字を追う作業というのは、映像や音楽やアートなどに比べてかなり忍耐を要求されるものです。しかしそれだけに、そこから浮かび上がってくる世界は心に深く刻まれうるものになると僕たちは確信しています。 ( I ) 2006年6月号 【25】おかげさまで今号から「きらら」も3年目のスタートを切ることができました。読者の皆さまとご執筆いただいた作家の方々、そしてもちろん応援いただいた書店員の皆さまの力添えでここまで来ることができました。あらためてありがとうございます。 さて、いつも小説に関して少しややこしいことばかり書いているので、今回はシンプルに「きらら」の現在について触れてみます。 まず今号から石田衣良さんの新連載小説が始まりました。石田さんは「いま」を書かせたらこれほどアクチュアルに描ける人は他にいない、時 代の息吹をいつも作品中にみなぎらせている稀有な作家です。「きらら」では以前から執筆を依頼しており、創刊3年目にしてようやくそれがかないました。そ の間、作品に関する打ち合わせを何度も繰り返し、「きらら」という雑誌についても充分理解していただいたつもりです。いまは素晴らしい小説が生まれる予感 がひしひしとします。 1月号で発表した「第一回きらら文学賞」の受賞作、黒野伸一さんの「ア・ハッピーファミリー」が単行本として発刊されました。黒野さんは 賞の募集開始当初から作品をお寄せいただいており、僕たちが何よりも驚いたのは、応募されるたびに(計5本)その作品が深化していったことです。今回、単 行本化にあたっても編集部との緊密なやりとりの中で、見事にヴァージョンアップを果たしています。「サザエさん」の磯野家と同じ七人家族に起こる春の嵐の ような、心がいきづく物語をお楽しみいただければさいわいです。 いまや「きらら」名物となった「携帯メール小説大賞」も創刊3周年に合わせ単行本となります。すでに延べで1万を超える作品が賞には寄せ られました。応募の常連となった書き手の方もいらっしゃいます。選考委員の佐藤正午さんと盛田隆二さんの毎号の的確な選評でこのところ応募作品の水準もか なり上がっています。単行本では過去の応募作、受賞作の中から厳選して作品を収録する予定です。 「きらら」は創刊当初から小説における読者と書き手の架け橋とならんことをめざしています。書店員さんも含めた一方的ではない小説をめぐる 環境の整備と革新。なによりもコミュニケーションを大切に、これからも小説を楽しむために努力していきたいと考えています。どうかよろしくお願いします。 ( I ) 2006年5月号 【24】実は僕たちの仕事は微妙な場所にある。 小説はいまでこそ少し読者を増やしているが(いくつかベストセラーも生まれている昨今、とりあえずそう思いたい)、それこそしばらく前までは絶滅寸前の古代生物のごとき存在だったのである。 コミックや映画や音楽や美術や写真や、その他諸々の表現というフィールドに生息する新生物たちに比して、小説はやや機能不全に陥ってい た。新生物たちが続々と環境の変化に即応してこれまでにない清新な表現を生んでいたのに、一時代前の恐竜である小説だけが、かくあらねばならないという狭 量なドグマの中に閉じこもり、自縄自縛の状況にあっていた、そんな感じがしてならないのである。 さて、環境の変化とは、無論いまのネットコミュニケーションのことである。ネットの中で日々言葉をツールとした表現が誕生しているのに、 それを従来の小説と結びつける試みはあまりにも少なかった。両者は相容れないものとして(まるで『ロミオとジュリエット』のモンタギュー家とキャピュロッ ト家のように)、夜明け前の朝日の中で、不倶戴天の敵として対峙していたように思う。 このところ両者は少しずつ歩み寄ってはいる。ネットの中から新しい小説の書き手を発掘しようとする「ヤフー・ジャパン文学賞」のようなプロジェクトも、ネット・サイドのほうから登場してきている。 とはいえ依然として両者の親和の可能性を危惧する声も少なくない。主に小説サイドからの発言ではあるが、いわく、ネット空間からあらわれた言葉には「もののあわれ」がない、その表現もオリジナリティにかけるステレオタイプのものばかりである、と。 一面ではこの発言は当を得ている。どちらかというと古い世代の小説読みに属する僕も時々その嫌な感じは確かにするのである。 しかし翻って小説の発信者たる編集に携わる者としては、そうも悲観主義的になってはいられない。絶滅寸前の爬虫類を前に、何とか哺乳類た ちとの共存をはかり、さらに新たな進化を遂げられるよう両者の交配をはからなければいけない、そう考えているのである。「もののあわれ」もオリジナリティ もやがてその中から立ち上がってくることに期待したい。 生息環境そのものが崩壊に瀕しているときだけに、その延命の試みには少し余裕を持ってご覧になっていただけませんでしょうか、文学界の獰猛なティラノザウルス様。 ( I ) 2006年4月号 【23】「きらら」の表紙についてよく訊ねられることがある。〈どうして毎号椅子やソファを使っているのですか?〉これはとても嬉しい質問だ。実は創刊号 から本号までで通巻23号になるが、表紙には首尾一貫(こんなことでシュビイッカンしていてもしょうがないが)椅子やソファを配してある。そして目を凝ら さなければよく読めない大きさで〈please sit and read〉と英文字を添えている。もちろんこれは私たちのメッセージでもある。つまり椅子やソファの置かれた日々の暮らしの中でもっとカジュアルに小説を 読んで欲しいというささやかな願いなのである。 このところ椅子やソファがつくる私たちの生活の中の「特等席」は、映像や音楽に奪われがちであった。とくに安価なDVD(980円で楽し めるのだ!)が出回り始め、いままで小説でしか味わえなかったリピートしたり反復したりして物語を楽しむということがいとも簡単に映像でも可能になった。 そしてDVDにとっていちばん重要なのは、この何回も楽しめるということなのだと思う。劇場でたくさんの観客を集めた作品がもちろんそのままDVD化され ても売れるということは自明のことらしいが、それほど観客動員が思わしくなかった作品でもDVDでは売れるという作品も多いと聞く。むしろ反復して見られ ない劇場よりも、何回も心ゆくまで楽しめるDVDのほうが媒体として適した作品もあるように思える。小説家のポール・オースターが脚本を書き下ろした映画 「スモーク」などは、それこそ家のソファで何回も繰り返し観た。 いま強敵DVDを射程に置いて小説のことを考えると、この反復性やリピート度というものが重要になってくるような気がする。確かにその場 で読んで面白く、楽しい時間が過ごせたという気にさせる作品も成立する余地はあると思うが、本来、小説だけが持っていたこれらの特性を充分に保持した作品 がこれからのソファや椅子をめぐる熾烈な争奪戦を有利に運べるのではないかと考えてしまう。 ちなみにわがリビングのソファの脇には、すっかり表紙がセピア色に変わっている吉行淳之介さんの『砂の上の植物群』と倉橋由美子さんの『暗い旅』が置かれている。いくらDVDが嵩にかかってやってきても、当分その場所から退くことは無いように思う。 小説を送り出す側に従事する者として、そのことだけはしっかりといつも頭に焼きつけておきたいと思うのである。 ( I ) 2006年3月号 【22】先月号の本誌でも発表した「ヤフー・ジャパン文学賞」の授賞式に出席してきました。 当日は「ヤフー・ジャパン賞」の藤堂絆さん、「選考委員特別賞」のそらときょうさんも式に出席されましたが、偶然にもおふたりとも今回の作品が初めて書いた小説だったとおっしゃっていたのが印象的でした。 「ヤフー・ジャパン文学賞」は日本でも有数のポータルサイトであるヤフー・ジャパンがWEB上で初めて募集した小説の賞で、各方面からその 推移が注目されていましたが、2か月半の募集期間で4517篇もの作品が集まり、あらためてネットの持つメディアの広がりを再認識させられる結果をもたら しました。 もちろん原稿枚数が400字詰め換算で15枚から20枚という、比較的応募しやすい長さだったということもありますが、それにしても4000を超える応募作品数は小説の賞としては異例のことです。 パソコンやネット環境の進化で小説を書く人はかなり増えたのではないかと考えられます。かつてならペンと原稿用紙を用意して机に向かうと いうスタイルだったのが、いまならカフェのテーブルに颯爽とノートパソコンを広げてという若い人たちも多いのではないかと思います。事実、先日お会いした 20代の女性作家の方は待ち合わせの場所で一心不乱にキーボードを叩いていました。 カラオケの普及が自らマイクを握る人を飛躍的に増加させたように、パソコンやネット環境の進化はものを書く人を確実に増やしたことは間違 いありません。今回の「ヤフー文学賞」に4000をも超える応募があったのもその証左であると思いますし、その受賞者がおふたりとも初めて小説を書いた方 であったということも何か象徴的なできごとのような気がします。 受賞者の方は今回の事をきっかけにこれからも小説を書いていきたいとおっしゃっていました。カラオケが日本の音楽界に果たした役割には侮 れないものがあるような気がします。プロ並みの歌唱力を持った一般の方がどんどん増えるに連れ、プロはよりいっそうの才能と精進を求められてきたからで す。ネット上で展開される小説の賞は今後よりいっそう増えると思いますが、それが小説というものをより鍛える方向に向かえばと、授賞式に出席しながらずっ と考えていました。 ( I ) 2006年2月号 【21】自分のイメージでは、物語が生まれたのは洞穴の中。人類が初めて火を使うようになり、その明るい炎を囲んで、座のひとりがこの温もりと灯りの由来 を話し出すところから始まります。それはたぶんに火を手に入れたときの手柄話だったかもしれませんが、まだ森を出たばかりの人間たちにとって暗く長い夜を 過ごすには格好の愉しみだったはずです。 文字や、もちろんまだ印刷物など夢のまた夢だった頃、物語はいつも聞き手とともにありました。物語を話す人間の、すぐ目の前に聞く人間が いて、物語空間は成立していました。そして物語の「保存」は、話し手から聞き手へ、今度はその聞き手が話し手となり次の聞き手へとなされていったのだと考 えられます。 当然、その過程で物語は取捨選択されます。聞き手に感銘を与えられない物語は人々の記憶に残らず、支配者にでもそれを強要されぬ限り、次の世代には受け渡されはしなかった。言い換えれば聞く人間たちの心を動かした物語だけが、生き残っていったということです。 そののち文字が発明され、本が登場し、印刷が開発されるにつれ、物語の保存はいともたやすくなり、この取捨選択のメカニズムもきちんとは働きにくくなったと思われます。 最近いくつかの小説の賞の選考にかかわって思うことは、この物語の原始のかたちを忘れている作品が多いということです。いったい目の前の 誰に語っているのか皆目わからない物語が多い。もちろんいまは印刷物だけではなく、ネットでも小説を発表できる時代です。目の前に聞き手もいらないし、聞 く人がいなくてもワンクリックで物語は保存されていくことでしょう。しかしだからこそいつも物語の最初のありかたが気になっているのです。 人間はなぜ物語を欲するのか。ある人は娯楽と言い、ある人は生きる指針と答えるかもしれません。長い人類の歴史の中では物語が支配の道具 として使われたこともありました。しかし、ギリシャ神話や聖書の中の物語が生き残ってきたのは、ひとえにそれを欲する人間がいたからです。いくら印刷物や ネットなどの伝達手段が発達しようとも、物語が伝わっていくのは、結局、人間の心のなかなのです。 山のように詰まれた小説の応募原稿を前にしていつも思うのは、人間がいちばん初めに物語を語りだしたときのことです。暗く長い夜に洞穴の中で燃える火を囲みながら。 ( I ) 2006年1月号 【20】むかし話をひとつ、させてください。 初めて小説らしきものを読んだのは小学生の頃。題名も著者もとっくに忘れてしまったのですが、いま思えば原稿用紙100枚くらいの作品 で、学校の図書室で帰宅の時間を気にしながらも、ストーリーの行き着く先を知りたくて、夢中でページを繰った思い出があります。それは翻訳ものの推理小説 で、表紙に掲げられていた時計台の絵がいたく気になり、昼休みに読み始めたものでした。もちろん小説というものはそれまでも学校の教科書で目にしていて、 実際に読んでもいるのですが、自分の楽しみでページを繰ったという意味で、初めての小説体験はその放課後の小学校の図書室だったように思います。 次に不思議な小説体験をしたのは、数ヵ月後、町にオープンしたばかりの図書館をのぞいたときのことでした。警察署の庁舎に続く小さなプレ ハブの建物につくられた図書館は、やたらにペンキのにおいがして息が詰まりそうだったのですが、並べられた本が小学校の図書室に置かれている本とはまった く違ったもので、大人の世界を盗み見しているような甘美な感覚を呼び起こさせてくれました。その中の一冊(白い表紙の文学全集です)、ただ入り口に近い少 年の背にぴたりと合う場所に置いてあったという偶然から手に取った一冊ですが、何げなく開いたページから始まっていた一編の小説が、その後の小説観に決定 的影響を及ぼしたと、いまとなっては思います。 ある高名な賞を受賞した世界的な作家のその作品は、これまで読んできた小説(らしきもの)の文章とはまったく異なったリズムで綴られてお り、言葉の選択にもとても斬新なものを感じました。たちまちその文章と言葉が織りなす世界にひきこまれ、これといって確たるストーリーのある小説ではな かったのですが、一風変わった名前を持つ主人公がただただ女性を眺めるだけのその作品に夢中になりました。そして、明らかにそこには、小学校の図書室で体 験した小説を読む楽しさとは別種のものが、芽生えていたように思います。 以後、小説の楽しさというと、ペンキのにおいに包まれた町の図書館の体験のほうを優先するようになりました。それがいいのか悪いのかはよくわかりませんが、いまこういう仕事をしていると、逆にそのことはひどく大切なことのように思えてくるのです。 ( I ) |
|||||||