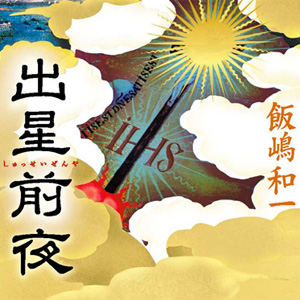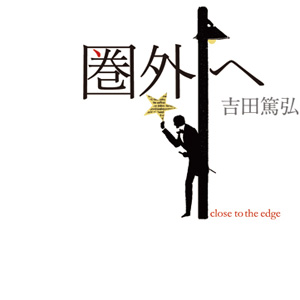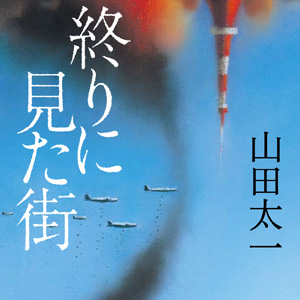| ホーム > きらら通信 > 2008年 |

|
|||||||
2008年12月号 【55】「アラビアンナイト」の語り部であるシェヘラザードは、ペルシャのシャーリアール王のもとに出向いて毎夜毎夜「物語」を語り始める。シャーリアール 王は最初に娶った妻の不貞を知ったことから女性不信に陥り、処女に夜伽をさせては翌朝処刑するという粗暴な行為を繰り返し ていた。大臣の娘でもあった聡明なシェヘラザードはその王に次から次へと奇想奇談を語り継ぎ、夜明け前きまって物語が佳境に入ったところで「明日はもっと 面白い話を聞かせましょう」と言って処刑から逃れる。 これが千と一夜続いたことから、「アラビアンナイト」は「千夜一夜物語」とも呼ばれるが、シェヘラザードが王の気持ちをそらさずどのよう にしてその興味をつなぎながら物語を語っていったかに、僕はとても興味がある。おそらくある場面では王の耳元で甘く囁きながら、また物語が盛り上がるクラ イマックスでは身振り手振りを交えながら詩でも吟ずるかのように朗々と語り続けられたに違いない。もちろんアリババやアラジンやシンドバッドたちが活躍す る破天荒な物語、それ自体に王が心を奪われたこともあるだろうが、シェヘラザードの巧みな「語り方」がなかったら千と一夜も「物語の夜」は続かなかったよ うに思う。 残念ながらタイムマシンにでも乗らない限りこのシェヘラザードの命がけのパフォーマンスに立ち会うことはできないが、死を賭して「物語」 を語るというこのエピソードから僕はとても重要な示唆を感じたりもする。「面白い物語」に対する希求はいつの時代でもあるものだが、それを面白く語ること に対し「アラビアンナイト」のシェヘラザードほどシリアスな場面に僕たちは迫られていない。これは幸せな状態ではあるのだが、それだけに寂しくもあるの だ。 大昔のアラビアに「面白い物語」が最初からあったわけではないと思う。何人ものシェヘラザードがそれを面白く語るうちに「ひとつのお話」 が「面白い物語」へと進化していったに違いない。音楽にサンプリングという手法があるが、小説にこれがあってもおかしくはないと思う。ひとつの作品を面白 く解体し再構築していく、こんな柔軟な作業ができるようになれば、僕たちが関わる小説にももう少し異なった局面が拓けてくるのかもしれない。 それにしてもいまの時代に命を懸けたシェヘラザードがはたして何人いるのか。「物語」を求める王の姿さえ定かではないのに。 ( I ) 2008年11月号 【54】むかし、まだ自分が世間知らずで素朴な少年だった頃、素晴らしい小説や映画を読んだり観たりすると必ず影響を受けてしまい、あるときは東北出身の作 家が著した処女短編集の一編を読んで、その舞台となった北の地に立つため夜行列車に飛び乗ったり、美しいバイクで北アメリカ大陸の南部を横断する映画を観 て、まだとりたての免許ではるか日本の最南端をめざしてツーリングに出かけたりもした。 小説でも映画でもすぐれた作品は人をして何がしかの行動に駆り立てる。自分以外の他人が創造した作品世界に触れて、いままでの自分と違う 自分に気づき、その新しい自分に向かって近づいていこうと試みる。ある意味、そのことがとても楽しくて今日まで小説を読んだり映画を観たりしてきたような 気がする。 かねてからその執筆活動がとても気になっていた小説家の方に先日初めてお会いした。その席で小説家の方はきっぱりこう言い切った。「自分 は作品を書くことで、それを読む人の中に変化を与えたいと思っている。そのために書いている」と。確かにその小説家の方の作品を最初に読んだとき、自分の 中で何かが変わったような気がした。それにこうして少なくとも作者に話を訊きに来ている。すぐれた小説は人をきわめて能動的にするのだ。 前号の本欄で「サプリ小説」というものについて書いた。泣ける小説、笑える小説、心が癒される小説などを称して別な小説家の方がそうカテ ゴライズされたものを、補足するかたちで論じてみたのだが(さいわい命名者の方からはこちらの定義が間違ってはいないというありがたい連絡をいただい た)、そのことと考え合わせるととても興味深いものを感じる。 泣けて笑えて心が癒されて日々の健康体を維持するだけのサプリメントのような小説を否定するものではないが、やはり小説はそれを摂取した人間に決定的な変化をもたらし、自己変革のきっかけになる、そんな劇薬や毒薬のような存在であって欲しいと願うのだ。 先日お会いした小説家の方の最新作はとても分厚い。すでにその存在自体から洗面台の棚にはとうてい収まらない。もちろんページを開くと、 いい意味での困惑と驚愕。そこには読む者を徹底的に扇動しようとする強烈な意志がみなぎっている。およそサプリメントには適さない小説。そして僕は少年の 頃以来の北の地への衝動的な旅に出ようとしている。
( I ) 2008年10月号 【53】最近はメールが普及していて、いつも仕事をお願いしている小説家の方ともなかなか直接会って話をする機会が少なくなってきている。とくに東京および その近郊に住んでいる方だとすぐに会えるという気持ちも手伝ってか、地方に住んでいる方より逆に顔を合わせることがまれであったりもする。昔から打ち合わ せはフェイス・トゥ・フェイスを心がけているので、できるだけ相手のところへ出かけていくようにしているのだが、最近は先方から打ち合わせはメールでと面 談を断られることも多い。編集者などという煩わしい人間に会うのは気が重いという気持ちもわからないでもないが、会って話をすると意外な会話に発展し、思 いもかけぬ発想へと行きつくこともあるので、この流儀はとうぶん守りたいと思っているのだが。 さて先日も無理矢理(?)ある小説家の方とお会いしたのだが、話をしているうち「サプリ小説」という概念に行き当たった。いわゆる泣ける 小説とか心が癒される小説とか笑える小説などのことをひと括りにして、小説家の方がそうカテゴライズされたのだが、これには思わず膝を叩いた。小説がビタ ミン剤と同じように実用に供されている現実をまさに言い当てるうってつけの言葉だったからである。常に商業的な側面に付き纏われる編集者としては、小説の 実用性については大いに考慮し訴えていかなければならないことなのだが、長年小説を愛読してきた一読者としては果たしてそんなお手軽なものでいいのかとい う思いがある。 もちろん東京近郊に住むその小説家の方ともこのことでディープな会話に発展したのだが、昔で言えば人生論や処世術のようなものが小説とし て仕立てられたり、映画のストーリー書きに過ぎないものを小説と称したり、文章や表現にまったく工夫のないものが小説として流通していたり、というような 小説の現状を憂えた談論風発の一夜となった。これだから会って話をするのは面白いというものだ。 そして最後には、サプリメント程度のことしか小説に期待しなくなったらこの表現手段はもう終わりではないかという結論にも達した。 泣ける、心が癒される、笑えるなどはもちろんそれはそれで重要なことなのだが、僕は小説にはもっと激しくダイナミックなものを期待している。日々の健康体をただ維持するようなサプリメントなどではなく、人間存在の根本を揺るがすような劇薬、毒薬のようなものを。 ( I ) 2008年9月号 【52】ある小説愛好者の集まりで、ちょっと違和感を覚えたことがあったので少し書き留めておきたい。座のなかに小説家の方もいらっしゃったので話はずいぶ んと盛り上がったのだが、最後に最近はどんな小説を読みたいかという話題になった。そこで出席者の大多数が(女性が多かったのだが)、幸せな結末の、心が ほっとする小説を読みたいと答えたのだ。 たぶんこのところ隆盛をきわめる「癒し系小説」を指すのだとは思うが、僕はどうも昔からそういうものがいっさい駄目なのである。とくにラ ストがハッピーエンドの小説はどうも嘘くさく感じてしまい(根っからの疑り深く暗い性格なのかもしれない)、どうもそういうものを書く小説家にもなじめな いのである。 さて、小説は何のために書くのかという宿命的命題がある。もちろん職業作家として生活の糧を得るために書く人もいると思う。人を面白がら せることが無類に好きで、小説を書くことでそれを実践している人もいると思う。でも、なぜそれが映像でも芝居でも音楽でもなくて、文章あるいは言葉なの か。僕の考えはそこらあたりでうろうろしてしまう。 もちろん小説でほっとさせたり、癒したり、はたまた幸せな気持ちにさせたり、そういうふうに読者を満足させることは必要であると思う。しかしこれだけ小説というものが世の中にあふれているなか、僕はあえてなぜ書くのかという問いにこだわってみたいと思う。 かろうじて首都圏に入る小さな町の中学生だった頃、僕は小説のなかに、確かに自分の内部に存在するのだが得体が知れなくてかたちのないも の、それらの像を必死で結ぼうとしていた。当時、読んでいた小説のなかにはその解答となるようなものがそこかしこにちりばめられていたように思う。そして そこで書かれていたのは幸せや満足ではなく、悪や欠落であることのほうが多かった。幸せに至る結末などより、自分の心情を汲みとってくれる小説の過程に魅 せられていたのだと思う。 冒頭の違和感は実はこんな僕の小説体験を呼び覚ましてくれた。そしてなぜ小説を書くのかという問いに戻るわけだが、僕はやはり自分のため に書くのだとしか言えない。それが個人的作業であればあるほど、小説という表現は力を持つ。もちろん読むほうも同じだ。小説は実はひどく危険で取り扱いが 難しい爆弾のような存在だと思っている。 ( I ) 2008年8月号 【51】いわゆる「夢落ち」の物語が苦手である。「夢落ち」とは、物語のラストで、いままで語られてきたことはすべて夢の中で起きたできごとです、とにわか に明らかにされて幕を閉じる手法で、たとえば宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』やルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』などは、この「夢落ち」で終わる代表 的な作品とみなされている(そういえばいまより純真であった少年時代でさえ、どちらの作品にも心を動かされたことはなかった)。 最近もいくつか読んだ原稿の中に、この「夢落ち」で終わる作品があって、いかにも安易な、書き手の物語に対する企みの無さに鼻白む思いを したことがある。こちらとしては、現実離れした破天荒な展開にいったいどんな結末が用意されているのだろうと期待しながら読み進めているのに、最後にきて これは主人公の頭の中で起きたできごとです、と一方的に宣言されてしまうと、これは読んできたほうとしてはまことにやりきれない気持ちが残る。 もちろんそれまでに作品中に気のきいた表現や言いまわし、卓越したフィロソフィーやユニークなものの見方などがちりばめられていれば別だが、それも見当たらないとなると読み終えた後もはや徒労感しか残らなくなる。 さて「夢落ち」に似たようなものとして「どんでん返し」という手法もある。物語の最後にきていままでの展開をがらりとひっくり返し、意外 な結末に導くというやり方で、映画などによく見られる。英語では「サプライズ・エンディング」と呼ぶらしいが、物語の発信者によって、まさにサプライズが 用意されているという意味では、「夢落ち」と同じである。 最近、見た映画の中でもその「どんでん返し」が炸裂する作品があったのだが、実は見終わったときはその意外な結末に感心したのだが、いま はどんな映画だったかさえよく思い出せない。物語を楽しむという観点から言えば、それはそれで真っ当なやり方なのだろうが、古い小説読みの人間としては、 果たしてそれだけでいいのかという疑問が強く残る。 はっきりいって私は「夢落ち」も「どんでん返し」も好きではない。そんなことに身をやつすくらいなら、もう少し表現を磨いたり、物事に対 する思索を深めたりして欲しいと思う。小説にサプライズは必要だと思うが、それがすべてだということになると、へそ曲がりの人間としては、否の声をあげた くなるのだ。 ( I ) 2008年7月号 【50】先日、「きらら」に連載小説を執筆していただいていた作家の方に会った。その方はいまもこの欄を読んでいると言ってくださったが、たとえ社交辞令としても僕は結構嬉しかった。 商売柄、作家の方に会うことはしょっちゅうだが、一度も仕事をご一緒したことがない方からも、思いがけなくこの欄のことに触れられたりすると、あらためて毎回毎回呻吟しながらもきちんと自分が小説について考えていること文章にしてきたことを妙に納得したりする。 実はこの欄は今回で区切りのいい第50回にあたるのだが、振り返り思うと自分としてはいつも同じことを書いてきたような気がする。それは つまり小説とは何かということである。 試しに過去のものを読み返してみると、圧倒的に小説がいま置かれている状況に対しての危機感を反映したものが多 い。物語を楽しむ表現物の中で、小説が特権的地位を持っていたのは少し前の時代のことであり、ネット社会という新しい環境の中で果たして小説はいままでの ような力を持てるのか、はたまた表現として生き残っていくことができるのか、どうもそのあたりをうろうろと、松明ひとつかかげて暗い地下の洞窟を行くかの ごとく、たどたどしく書いてきたような気がする。 さて最初の問いに戻るのだが、小説とは何かということである。ある人はそれを娯楽と断定するだろうし、またある人はそれを表現だと主張す るかもしれない。実は僕はどっちでもいいと思っている(どうしてもというのであれば後者にささやかな1票を投じるかもしれないが)。むしろ、最近は小説の 向こうに存在する物語のことのほうが気になっている。 おそらく知に目覚めた頃から人間は物語を必要としてきた。暗い夜をやり過ごすための享楽か、他から自分を峻別するための自己表現か、その 目的は種々あったと思うが、とにかく人間は物語を友としてこれまで親しくつきあってきた。そしてそれを主に取り結んでいたのが小説だったのだが、正直言え ばその地位はかなり怪しくなってきている、と思う(もちろんそうは思いたくないのだが)。 小説自体の衰退なのか、すでにアウト・オブ・デートなものとなっているのか、それを送り出す側としてはいつもシリアスに考えているのだが、もしかしたら人間は物語との親交に別れを告げようとしているのかもしれない、このところそのあたりまで疑り始めている。 ( I ) 2008年6月号 【49】文学というと僕などはすぐに「=小説」と考えてしまうのだが、実は文学といってもその中には詩や短歌も含まれるし、戯曲やエッセイ、さらに範囲を 広げていけば書評や日記なども文学に含まれる。そもそも文学というのは、言語で表現された芸術作品ということになるらしいのだが、それならばたとえばネッ トの世界で展開されるブログやチャットなども、それが芸術であれば立派に文学ということになる。 さて言語で表現された芸術作品である文学は、原初は口伝や口承で表現者から鑑賞者へと受け渡されていった。それは語り部が伝える叙事詩や 抒情詩であったり、あるいは舞台で上演される演劇という形式であったりした。つまり始原に遡れば文学の主流は詩や演劇に担われていたということになる。や がてそれらが文字という「メディア」に乗ることとなり、より複雑な情報を扱いうる小説という形式が文学の最前線へ押し出されてくるようになるのである。そ して、さらに小説は印刷技術の誕生および発展とともに、文学というものの中で領土を拡張しながら、ついには今日までその主役として君臨することになったの である。 文字や印刷技術など「メディア」の変遷とともに、文学の主役も詩や演劇から小説へと交替してきたわけだが、十五世紀の活版印刷技術の発明 に次ぐ革命的な言語環境の変化であるネット世界の出現が、果たして文学の世界にふたたび大きな変化をもたらすのか、これはなかなか興味のあることだと考え ている。 さて冒頭で述べたように文学が言語で表現された芸術作品であるとするなら、その作品が芸術であるか否かという判断はどのような基準をもっ てなされるのか。これはなかなか難しい問題だ。表現しようとする人間から発せられたすべてのものが芸術であるとする説もあれば、それを鑑賞する側が認めた ものだけが芸術であるとする人たちもいる。とはいえ今日の多くの芸術に関する記述を読むと、芸術とは表現する側の意志に大きく関わってくるものらしい。つ まりかなり簡略化していえば、表現者が鑑賞者たちに向かって「これは芸術だ」と宣言するだけで、それはとりあえず今日では「芸術」として成立することにな る。 寡聞にして自分のブログを「芸術だ」と宣言している人の声はまだ聞かないが、もしそういう革新的な表現者が現れたなら、僕はまず真剣に耳を傾けていきたいと考えている。 ( I ) 2008年5月号 【48】最近、小説を読んでいてとても気になることがある。ここで語られている物語はいったい誰が誰に向かって発信しているのか。作品を本にして世に送り出すという職業に就いているせいか、どんなものを読んでいても常にそのことが頭をよぎる。 最近調べものの際に重宝しているウィキペディアによれば、物語というのは「語り手が語られる主体に語るさまざまな出来事」とある。「語ら れる主体」という表現は少々いかめしいが、要するにその物語が活字の中に存在するのなら「読者」ということであり、口承で伝えられる物語なら「聞き手」と いうことになると思う。 さて人類史的に物語の発生を考えると、それは口伝えという形で始まった。「語られる主体」は常に「語る主体」の目の前に存在し、互いの 「主体」が誰であるかは明確に認識されていたと考えられる。つまり誰が誰に向かってその物語を発信しているかは自明の事実として存在していたに違いないの だ。そしてそれゆえ物語の輪郭は常に鮮明であり、そこで語られる時系列に沿ったストーリーはかなり強固であったと思われる。つねに「語られる主体」の前に さらされる物語は、急流でもまれる石塊のように「角」が取れスマートなものになっていった。古今東西に生き延びている物語はすべてそのような強度とある種 の洗練を備えているような気がする。 僕が最近気になっている疑問というのは、実はこの「語られる主体」についてのことである。このところ応募原稿やネットで個人が発表してい る作品などを読んでいて感じるのは、「語られる主体」に対する意識がひじょうに希薄だということである。人間が文字を所有し、印刷技術を開発し、ついには ネットという空間を獲得した、この物語を取り巻く環境の大変化は、一方では物語が有する本来の力を弱めることになってはいないかと危惧している。「語られ る主体」が「語る主体」の眼前から遠のき、結果、物語は不確かな空間を浮遊しているのではないかとさ え思っている。 いまこそ物語の原初に立ちかえって、小説というものを考えていくことは、まんざら意味のないことでもないと考えている。 ゲット・バック・トゥ・モノガタリ。 ( I ) 2008年4月号 【47】ポエトリー・リーディングの会に出かけてきた。学生時代に現代詩のようなものを齧っていたこともあり、当時の友人たちからときどき声がかかる。彼 らはいまでも殊勝に難解な詩を書き続けているが、商業主義の世界に身を投じた僕にとっては、その作品たちは地球の裏側で語られている言葉のようにも思え、 自らの詩人の魂が完全に死に絶えていることに気づかされる。 とはいえ僕がその会にのこのこ出かけて行くのは、現実の身体から発せられる言葉の強靭さに毎回驚かされるからだ。会では基本的に個々が自 作を朗読することになっているのだが、声と身振りをともなった言語の試みは、まるで目の前で繰り広げられる3D映画のように僕の脳髄を刺激してくる。もち ろん声の大小や高低、身振りの派手さ地味さはで違いはあるのだが、いずれも書かれたものを読むときとはまったく異なった鮮烈な言語空間を提示してくれるの だ。文字という「収容所」から解放された言葉のなんと立体的なこと(現代詩のような表現になってしまった)。 かつて「物語」も印刷技術の進歩によって文字の中に押し込められる前には、必ず声と身振りを有していた。それは人から人へ口伝というかた ちで生命を与えられていたのだと思うが、声と身振りで増幅しながら眼前で供せられる「物語」に、聞く者たちは欣喜雀躍反応していたに違いない。 やがて「物語」が書物という神殿に鎮座し始めると、それはいつでもどこでも享受できるありがたきものとなり、「小説」と呼ばれるようになっていった。そういう意味で言えば、小説は演劇などに比べきわめて新しい「物語のかたち」ではあるのだ。 ポエトリー・リーディングの会でいつも思うのは、小説にこの声と身振りのようなものがあったら、もっと多彩にもっと豊かに「物語」の世界 を楽しめるのではないかということである。そして小説における「声と身振り」というのはたぶん「文体と語り口」という言葉に置き換えられるにちがいない。 小説を書く人たちがこぞってこれを競うようなことになれば、この遅れてきた「物語のかたち」もまだまだ生命力を維持できるのではないか。気づけば詩の会に 出席しながら小説のことを考えていた。 ( I ) 2008年3月号 【46】香港島の小高い場所からビクトリア湾を眺めると、南シナ海へと続く湾の入り口が自分の立っている場所より高い位置にあるように見える。もちろん目の錯覚なのだろうが、彼方に広がる風景がまるで中空に浮かんでいるかのように映るのだ。 親しくしていただいていた作家の方が去年突然他界された。自分より少し年長であったが、まだまだこれから素晴らしい作品をいくらでも執筆することができたはずで、とても残念でならない。 先日偲ぶ会が開かれたが、何の前兆もない思いがけない死だったため、参会した人たちも口々にこれから読むことができたであろう未成の作品について語った。過去より未来について熱く語られた不思議な会でもあった。 冒頭の香港の風景は、その作家の方の作品集をつくったときカバーに用いたものだった。架空の空間でありながらその描写は精緻を極め、あり えない展開でありながらも登場人物の行動に妙な肩入れをしてしまう。作家の描く世界はいつも仮想の場所に存在していたが、僕はそれに強烈なリアリティを覚 えていて、ときには自分のいる場所さえ危ういものにする不思議な力を感じていた。収録作品のひとつに香港を舞台にしたものがあったということもあるが、そ の風景をカバーに使用したのは、自分なりの作家の作品に対する考え方をヴィジュアルとして表現したかったからである。 小説は虚構を描くものである。これは明々白々の事実なのだが、ときに僕たちはその中に鮮烈な真実を見出す。そして心に強くやきついたそれは、自らの生き方や存在をも激しく揺さぶる。対岸の空中楼閣は実は自分の足元を揺るがす存在なのである。 「飢えて死ぬ子の前で文学は有効か」と問いかけた哲学者がいたが、確かに死に直面する子供たちの前で小説は非力かもしれない。しかし彼らのことを考えさせる真実を対岸の虚構から引き出すことはできる。 作家の方とはタフな恋愛小説を書いていただくという約束をしていたが、いまとなってはそれを読むこともかなわない。香港を舞台にした小説 というのは「一九七二年のレイニー・ラウ」という小説だが、あらためてその作品が収録された作品集のカバーを眺めていて、僕はまたもその風景からいいよう もない強い磁力を感じていた。 ( I ) 2008年2月号 【45】ニューヨークに住む作家であるポール・オースターが、ヨーロッパで賞を受けたときに書いた「I want to tell you a story」という一文がある。素直に訳せば「私はあなたに物語を語りたい」。そんな題名となる文章だが、なかで彼は本を読む人間が少なくなってきている という読書界の現況に対して、その事実を半ば肯定しながらも、とはいえそれは「物語」に対する根本的欲求が減ったということではないと持論を展開してい る。いわく、現代の人間にとってもはや小説は物語の唯一の供給源ではないが、人々は映画やテレビ、コミックなどからも多くの物語を摂取しており、物語はい まだ人間にとって不可欠のものであると。 そのうえでオースターは小説の未来に対してきわめて楽観的な考えを示している。小説はあくまで作者と読者の一対一の関係の中で成立するものであって、作品の前にいるのは常に一人の読者がいるだけで、それゆえこのジャンルは生き残るであろうと託宣している。 たとえば映像やコミックが登場する前、小説は物語の勧進元としての特権的地位を得ていた。物語を貪るため人々は小説の本を手に取り文字を 追った。しかし映像やコミックなどのジャンルの発達とともに、小説はその地位を剥奪され、このところ少し元気がない(そういう気がする)。もう一度、旺盛 な「物語供給力」を発揮するためには、小説はよりパーソナルな部分に降りていくべきであると、オースターは言っているのだと僕には読めた。そして書き手は いつも作品を読むことになるであろう一人一人の個と向き合うべきだと。 思えばいまの時代ほど小説において「個」が重要な役割を果たすときはないように思う。書き手がインディヴィデュアルなものを作品に盛り込 むことで、小説は物語に新たな命を吹き込むことができる。かつて人伝に語られてきた神話や聖書や叙事詩などとは異なり、個からの声により耳を傾けながら注 意深くそれをすくいとっていくものであると考えられる。 いまケータイで流通する物語に対して危惧を抱いているのは、この「個」についての部分である。ケータイ空間の中で僕がいちばん嫌悪するの は物語への薄っぺらい共有と安易な共感だ。それは小説がこれまでやってきた書き手と読み手の一対一の真剣勝負をゲームオーバーにしてしまうのではないか、 そんな漠然とした不安を僕に感じさせるのである。 ( I ) 2008年1月号 【44】世界の文学史を紐解いてみると、小説というジャンルが確立されてきたのは、どうもグーテンベルクが活版印刷技術を実用化してからのことと思われ る。グーテンベルクはこの自らが開発した新技術を駆使して、1445年にいわゆる「グーテンベルク聖書」といわれる書物を印刷し、販売を試みようとしてい る。これが現在の印刷業及び出版業と呼ばれているビジネスの始まりではないかと考えられているが、この時代のグーテンベルク聖書は当時の人々の平均的年収 の倍にあたる価格がつけられていたという。その後、この活版印刷技術は急速に普及することとなり、書物の流通に圧倒的な寄与をもたらすことになる。 さて革命的ともいえる活版印刷技術が普及しつつあったヨーロッパで、いわゆる「個」から発する「物語叙述」である近代小説が誕生したの は、セルバンテスの「ドン・キホーテ」あたりではないかといわれている。それまでの物語が共同体の共通認識に基づき登場人物たちはある種の記号として語ら れていたのに比べ、この作品では「個」に主眼が置かれ、そこから発した描写や心理の葛藤が物語の主軸となっていた。つまり小説は初めて「ドン・キホーテ」 という魅力的な物語の主人公を獲得したともいえる。17世紀初頭に成立した「ドン・キホーテ」を嚆矢として、小説は次々に新しい個性的なヒーローを生み出 していくが、それもすべて活版印刷技術の発展によって、小説が同時に大量複製されるようになったおかげといえなくもない。 さてネット環境の進歩で小説はグーテンベルク以来の革新期に突入しているのではないかといわれている。もしそうであるのならわたしたちは ネットの中で誕生した小説の中に、「ドン・キホーテ」のような新しい時代を象徴する人物が出現していないか、細心の注意を払いながら見つめていかなければ ならないのだと思う。そこに存在するのがこれまでの小説には登場することのなかったまったく新鮮なヒーローたちなら、わたしたちは襟を正して彼らを迎えな ければならない。そして、もしかしたらそれはもう「小説」とは呼べない物語空間を闊歩する人物たちかもしれないのだ。 しかし幸か不幸かまだそのような刮目すべき出会いに遭遇してはいない。「ドン・キホーテ」はあいかわらず小説というジャンルの輝かしきヒーローとして君臨し続けている。 ( I ) |
|||||||