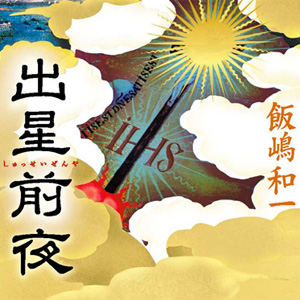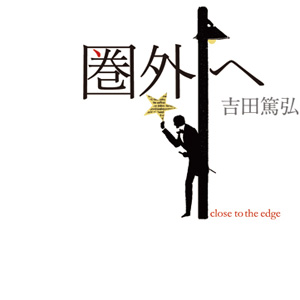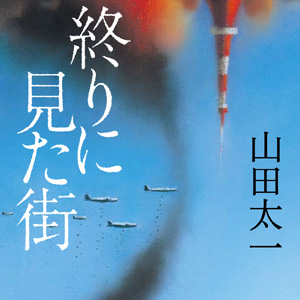| ホーム > きらら通信 > 2013年 |

|
|||||||
2013年9月号 【112】この前、ある人から、何様のつもりか、とお叱りを受けた。そのときのお話は、ここで書くと長くなるし、“向き”なお話ではないので、触れないことにするが、確かに自分の仕事について、よくよく考えてみると、何様のつもりなんだろう、と思ってしまう節がある。以下は、あくまで私個人が感じたり、思ったりしている小説編集の仕事観なので、その点、ご留意の上、お読みいただきたい。 作家さんと編集者は、基本、一対一の感じになる。かなりガチだ。そこでは、場合によっては、部分的に改稿や一部削除を相談するような場面も、少なからず出てくる。冷静に考えてみると、これは、なかなか太いというか、鈍い神経が必要な作業なのではないだろうか。なぜなら、小説を書くのは作家であり、編集は基本、小説を書くのが仕事ではない。書ける人は自分の名前で書けばいいのであって、あくまで、作家が書いた原稿に感想を述べたり、アシストをする立場でしかないように思う。 かといって、妙にへりくだりすぎてしまうと、場合によっては書き手も手応えがないというか、本当に自分の原稿を読んでくれたんだろうか、と逆にいぶかしがられてしまう可能性もなくはない。一方で、対等、場合によっては上から目線なスタンスでのぞむのも、書くという重要なパートを端っから作家に託しているのであるから、なかなか難しい気もしてくる。 野球の譬えで恐縮だが、書き手がピッチャーとすると、自分の感覚では、編集者は、キャッチャーというよりも、グラウンドにすらいなくて(なぜなら基本、プレーヤーではないのだから)、観客席、せいぜい外野のスタンドの最前列で熱心に応援している人、くらいな感じが適切な気がする。無論、この距離感は、個々の作家さんや編集者によって、様々にバリエーションがあるように思うし、仮に編集者がグラウンドで一緒に試合に出ている感覚がある場合でも、それでも、その試合のピッチャーは間違いなく作家なのだ。 一対一だけど、純粋な一対一ではないという状況下で、作家さんが懸命に書いたものに対して、こちらも真に打ち返していく。これは、ある意味での図太さがなければやっていけないのではないだろうか。そんなわけで、編集者には、ある種の何様根性のようなものが必要とされているように、個人的にだが、思う。 ( II ) 2013年8月号 【111】ある本を読んでいて、「文字に書かれている内容は、はじめから書き手のなかにあるものなのだが、書いてみないことには書き手すら考えも及ばなかった事項がそこに含まれていることがある」という内容のフレーズに行き当たった。 一見、なんのことやら、という感じの話だが、確かに、ある本を読んだ直後にメモをとったり、作家さんに感想の手紙を書いていたりすると、同じような感覚に捉われることがある。自分が考えたり、感じたりしたことを言語化することで、「あ、俺はこんなことを考えていたのか」と思ったりするのだが、書くという行為によって、それが、芋掘りをするように、つるつると地面から掘り起こされていく感覚に近い。 なので、書くという行為がなければ、そのままどこかに埋もれたまま出てこない類のものがそこに含まれていることになる。本を読んでも、読み終わった→なんか考えたり、感じたりした、と思って満足するだけだと半分くらいしか「読んだ」ことにならないのではないだろうか。感想などを紙に認めておかなければ霧消してしまう類のものを取り込んでこそ、の読書といえるのかもしれない。 考えてみたら、この項で書いている文章も、多分にそういうものを含んでいて、書きながらだんだん形を整えていこうとしている自分がいたりもする。かように自分レベルでこんな感じなのだから、作家さんは、どんなことになっているんだろうと思う。 先日、長編書きおろし小説の、書き出しの一行が書けたことを、ものすごくホッとしたような顔で報告してくれた作家さんがいたが、考えてみたら、最初の一行が次の一行を生み、さらにその次……という具合にどんどん続いていって、それが次第に全体を形作っていくように思えなくもない。 極端なことをいうと、最初の書き出しの一行が、際限ない選択肢のお話のその後の展開をかなりのところまで規定してしまうことになり、何かを書くという、一連の運動というか、連続性のなかで、作者も思いも寄らぬような場面や登場人物や細部の描写とかも出てきたりするのではないだろうか。 「書く」という行為が、さまざまなことを決めてしまう、ある種のプライオリティのようなものを持っていることに、自分も、もう少し自覚的になっていこうかと思う。 ( II ) 2013年7月号 【110】小説を書く際に、ある外的要因が働き、結果的にそのことが作品に影響を与えてしまうことについて、十九世紀のロシア文学を再読しながらなんとなく考えた。検閲と闘うなかで生まれる比喩表現。懐に潜ませた匕首のようにして周到に配された含意的な作品意図。省略やあえて書かないことで可能になる、多重な読み。時代情勢と表裏の原稿改変というか推敲作業を行うなかで生じる、作品生成のダイナミズムの妙味を感じざるを得なかった。 そんな話を先日、また知った風な顔をしてある作家さんにしたところ、そんな大きな社会的抑圧装置のようなものだけに、小説が影響を受けている訳ではないでしょ、と簡単に返されてしまった。 たしかに、現代でも、例えば、「3・11」以前と以降で、書くべき主題が変わってしまったというような書き手の方も少なくない。でも、もっと日常の些細な風景だったり、ふとした感情のぶれみたいなもの、あるいは、運命という言葉を用いると大仰になってしまいそうな、小さな偶発的事項の積み重ねで生まれる結節のようなもの、そんな類のことでも、小説を書く際に十分な影響を受けてしまうというのだ。 「作家脳」を持っている訳でもないので、いつものごとく、拙い推測をするしかないのだが、そのくらい書き手の方々は、大きなものから小さなものまで、日々、というか、時々刻々、様々なことに影響を受けながら小説を書き進めているような気がしてしまう。 そんなことを考えていて、ふと思い出してしまったのが、ワード・プロセッサーを使い始めた頃に作家さんがやらかしたある失敗談だ。使っていた機種のものが故障してしまい、そこまで書き進めていた原稿のバックアップも不幸にして取っておらず、かなりの枚数分が吹っ飛んでしまったという。泣く泣く、同じように一から書き直しをしたのだが、当然、一字一句同じ、というようなことにはなるはずもない。だけど、今では、その書き直しをせざるを得なくなった箇所がたいへん気に入っていて、むしろ、天の配剤の妙のようにも感じているのだという。「My Ever Changing Moods」という昔の洋楽のタイトルを思い出してしまうくらい、生々しい手触りのなかで、おそらくたくさんの小説は生まれ、これからもつくられていくのだろう。 ( II ) 2013年6月号 【109】少し気持ちの悪い感じの書き出しになってしまうが、先日、ある作家さんが目の前で原稿をノートパソコンに打っている姿を見て、思わず見惚れてしまった。文字通り、惚けるようにしばらく見入っていたので、相手の方には、かなり複雑な表情をされてしまった。 打ち合わせ先でのことで、作家さんは締切の時間に追われていたのか、少しの空き時間にパチパチとキーを叩いていたのだ。ちなみに、その方は男性作家の方で、私にはそうした性的嗜好はない(と思う)。 考えてみれば、子どもの頃から、手練れの職人さんが懸命に自分の仕事に打ち込んでいる姿をじっと凝視してしまう傾向があった。テレビ番組で鍛冶職人の姿を追ったドキュメンタリー然り、工事現場の鳶職人から、バスの運転手、靴磨きの女性まで、恐らく、プロフェッショナルに洗練された動きを見せる彼らの姿に心を奪われていたのだと思う。 この途方もない反復の末に辿り着いたと思われる一連の動作は、流れるような美しさを生み、淀みない安定感に繋がっているように思える。 当の本人には、そういった意識はなくても、いざ、自分の縁とする仕事にとりかかった途端、スイッチが入るように、彼らの目つきはキリリと引き締まり、纏っている空気に心地よい緊張が漲る。 恐らく、ある種、普段の仕事に取りかかるときのその人の所作というのは、全身でそれをするのに最適な形になり、誤解を恐れずにいえば、あまり何も考えていないような心境に近づいていくのではないだろうか。ある種の「無」の状態とでもいうべき、己からマシーンへと移行していくがごとき滅私ぶり。大の大人がそこまで打ち込んでしまう、このプロフェッショナル感に、エクスタシーに似たものを感じてしまっているのかもしれない、と書きながら、今、ふと思ってしまった。 本誌「きらら」のアート・ディレクションは、創刊号よりお世話になった羽良多平吉さんから、今号より、吉田篤弘さん・浩美さんのお二人からなるクラフト・エヴィング商會に襷が渡される。双方のデザイナーさんともに、当然、ここに書いてきたような「職人芸」の域に達していらっしゃる方たちだ。もし、仕事場にお邪魔したら、恍惚とした表情を浮かべた気持ちの悪い自分が容易に想像できる。迷惑な話だが。 ( II ) 2013年5月号 【108】いろんな方の話を聞いたり、読んだりしていると、エッセイを書くときの書き手のスタンスとして「本当のことをきちんと書く派」と、「フィクションをさらりと入れて書く派」の二手に分かれるようだ。ここでは、前者のパターンのみの話として、少し書いてみたいと思う。 エッセイを書くことは、我が身やその周辺に起こった出来事を書いていく作業でもあるので、だんだん書き続けていくと、ネタに困るようになってしまう。そんななか、向こうの方からどんどん書いてくれといわんばかりに引きの強い体験をしてしまう人もいるようだ。 ある作家Aさんと浅草で晩ご飯を食べて、少し通りから外れたところをブラブラ歩いていたら、Aさんが、急に小走りになってある方向に歩き始めた。 彼が向かう方向に目を転じると、暗闇のなかで、バイクを熱心に物色している風の中年男性の後ろ姿が目に入った。人通りもないし、なんとなく物騒な雰囲気が 漂っている。さりげなく近づいていくと、どうやら、バイクの荷台をビリヤード台に見立てて、ショットを打つ入念なフォーム・チェックを繰り返し行っている ことが分かった。バットの素振りを何度もするように、ストイックに、エア状態で。 この人は、なんでこんなところで、こんなことを繰り返してるんだろう。半笑いになりながら、そんな疑問が沸々とわいてきて、自然、興味を抱いてし まった。でもAさんは、同じようににやけた笑みを浮かべながらも、このレベルのことはよくあるようで、5段階で3くらいの感じのインパクトらしい。 正直、Aさんのリアクションも印象に残ったが、別の日に、会社のそばの神保町駅の交差点のあたりで待ち合わせていると、ホームレスらしき人と将棋 を指しているAさんの姿が目に飛び込んできた。聞けば、少し前に待ち合わせ場所に着いてしまったので、ぼーっとしていたら、横で寝っ転がっていたその人か ら誘われたらしい。ふだん、その場所は、通勤の関係上よく通り過ぎる場所だが、今まで一度もホームレスの人を見たこともなければ、ましてやそんなところで 将棋を指している人も見たことがなかった。 Aさん自身、少し変わった感じのする方なのだが、変わった人は、変わった人を引きつけてしまうという言葉だけではすまない何かを感じてしまった。こういうのも、やはり、作家の実力のうちに入るんだろうか。 ( II ) 2013年4月号 【107】この前、居酒屋的なところで打ち合わせをしていたら、隣の席のグループの人たちの話がなんとなく聞こえてきた。そのなかのひとりが、最近、知人か 誰かのために腎臓をひとつあげたという。まわりの人たちは、なかなかできることじゃないといった話をしきりにしている。誠実な印象を与える四十前後の男性 だ。驚いたのは、彼らのグループが席をたってしばらくしてからだった。レジのあたりで、大声で店員に怒鳴り込んでいる男の声が聞こえてきた。見れば、さき ほどの人物だった。お店に傘を忘れてしまったが、見当たらないようなので、かなり立腹している。一緒にいた客はすでにみな帰り、ひとりのようだ。すごい高 い傘で、まだ新品だ、店に弁償しろとがなり立てている。 こういう瞬間に出くわすと、なんだか、小説で読みたくなったり、自分でスケッチ的に書いてみたくなる。相反する感情、気分のようなものが 同じ人間のなかに矛盾することなく共存している。このひとは、こういう人、あの人は……という具合に簡単にカテゴライズできないのが、人間の不可思議で奥 深いところだ。 しかしながら、これも毎度のことであるが、では書いてみようかとなると、怖気がたってしまう。「小説は、贋札作りをするようなもの」という吉村昭 氏の言葉にもあるように、小説的な本当らしさというか、読者を首肯せしめるものがそこでは要求され、そうしたことのために日々苦しんでいる作家さんの姿を 曲がりなりにも目にしていると、自分が首を突っこむことはどこかおこがましい気持ちになってしまう。 よく読者の方から、どうしたら作家になれるのですか? といった問い合わせが作家の方に質問として投げかけられることがあるが、答えは「気がつい たら、書いていた」が正解のように思う。書きたいという欲求が衝動のようにして起こり、それからは、小説を書くことを抜きに自分の人生は成立しなくなって しまう。でも、書き続けることはしんどくて、いっこうに楽にならないし、ある種の地獄がそのあとは延々続いていく。昔は、それでも、漱石のように三十後半 になったら自分でも書いてみようと考えたこともあったが、そんな年齢もとうに過ぎ、いまは、たとえていうなら、ものを書くという縄跳びのなかに入ろうとし て逡巡してしまう、愚かしい自分がいるだけだ。まるで、輪の中に入ることに失敗したら、輪切りにされてしまうかのような恐怖に怯えながら。 ( II ) 2013年3月号 【106】一時、担当する作家さんに、自分の人生相談のようなことばかり聞いてもらっていた時期があった。気がついたら新幹線のホームに立っていて、こだま に乗って名古屋まで行ってしまったこと。新宿駅西口ロータリーに当時まだあった喫煙所コーナーから、狼煙のような大量の煙が夕刻の寒空を汚していたのを見 た瞬間、なぜかいろんなことにやる気をなくし、甲州街道を延々歩き続けてしまったこと。世田谷通りを三軒茶屋方面に向かうバスに乗っていたとき、信号待ち で停車中のバスの車窓を過ぎった、ペダルのない自転車をエア状態で漕ぎ続けていたおじさんのこれ以上にない笑顔が頭を離れず、それが神に見えて仕方なかっ たこと。 いま考えると、だからなんなんだ、と突っこみたくなる微妙なプチ病気自慢の話を、作家さんの貴重な時間を割いて聞いていただいていたよう に思う。しかし、ひとつ言い訳めいたことを言わせてもらうと、こういう話を聞いて欲しくなるような空気を皆、漂わせていたように記憶しているし、なかに は、私の話を面白がって、小説のなかに様々なかたちで取り込んでくれた方もいた。 こんな具合に色んな意味でどうかしている時というのは、小説を読むときも、なにか自分に必要不可欠なものを取り込むようにして貪り読んでいたよう に思うし、作家さんに仕事をお願いするときも自ずと触覚を働かせて、そうした作品を依頼しているところがどこかにあったように思う。 まったくひどい話である。会社から給料をもらい、仕事と称して自己救済に当たりそうなことをしばらくのあいだ繰り返していたのだから、公私混同も 甚だしい。でも、そんな風にして作家さんに携わったことで生まれた作品は、いま振り返ってみても、なにやら妙な存在感というか、迫力に満ちていて、話の中 身はもとより、タイトル、帯のネーム、カバーデザイン、翻って自分が社内に向けて出した企画書に至るまで、あきらかに纏っている気配が違っているように思 えた。こうした、一見、というか多分間違った方向に熱量が注がれたディレクションの本は、これはこれでやはり必要なものを含んでいるのかなと改めて思いも する。ある作家の方の文庫の解説を書いていた見知らぬ他社の若手編集者の文章に触れ、自己満足ギリギリの際どいところで成立していた本を、自分も確かにか つて作っていたことに改めて気付かされた。 ( II ) 2013年2月号 【105】先日、ある理由からMRIの検査を受けた。MRI、すなわち、核磁気共鳴画像法、英語で記すとmagnetic resonance imagingの略称である。MRIを受けた方は、共有していただけるかと思うが、これが、かなりしんどい。細長い台に仰向けに寝かされた上、体をベルト 状のもので拘束された後、頭部をトンネル状にくりぬかれた機械のなかに突っ込まれたまま、30分程度身動きがとれなくなってしまう。これに加えて、あえて 表現するなら80年代ノイズミュージックのような、硬質な金属音が間断なく大音量で流れ続ける。一応、この金属音をあまり聞かせないように、ヘッドフォン でリラクゼーション系の音楽が耳元で流されるが、私が受けたときは、生憎その音量が小さすぎたことと、音楽が、よくセレモニーホールの告別式などで流れる 出棺時の無色無臭の安っぽいものだったため、自分が棺桶に入ってしまったような感覚まで受け、いやな汗を相当にかいてしまった。そんなリアルMRI体験以 上に不可思議な印象を持ったのが、検査室に貼ってあったMRIについての説明文だった。記憶が曖昧ではあるが、およそ次のような文言が書かれていた。 人間の細胞は、ふだん、まったくバラバラな方向を向いて自由な感じでいるが、そこに、強力な磁力を与えることで、すべての細胞を一定方向 に向かせ、しかる後に、あるパワーをもったサムシングを加えることでその状態をさらに強化したのち、それらのスイッチを切ると、細胞は、またもとの状態に 戻ろうとする。その瞬間を撮影することで、かなりクリアな画像を入手することができる──。 おそらく、MRIについてまるで知らない私のような人間に、わかりやすく噛み砕いて説明した内容だったのだろうが、逆に、なにか本質的なものが剥 き出しになってしまい、得も言われぬ恐怖心を煽られた。実際、その後調べてみたが、さきのようなMRIについての説明文には、ついぞ出合わなかったし、私 の意訳した部分も入っているので、そこは差し引いてお読みいただければ幸いである。かように、言葉が、へんな風に化けてくるような感じは、様々な取扱説明 書を読んでいても時々感じることだ。要は、言葉で説明するしかないが、その言葉がきちんと当を得ていないというか、テクニカル・タームの、そのまた説明の ようなことをしているうちに、急に剥き出しの表現が現れ、読み手に向かってくることがあるように思った。 ( II ) 2013年1月号 【104】先日、活動20年を迎えたあるミュージシャンが、自分のデビュー当時にヒットした曲を歌っている番組をテレビで見た。 通常、こうしたケースでは、ある種の違和感が付きまとう。歌い方が変わっていたり、当人のいまの状況に比して、歌が若すぎるため、歌う側 も、見ている側も、なんだか半笑いな感じになってしまうことが多いのだ。まあ、考えてみれば、20年前の自分、とくにそれが若い頃の自分であればあるほ ど、「他人感」は強くなるのは否定できない。我が身をふりかえってみても、20歳すぎの自分が何を考えていたのか思い出す機会に触れると、大変恥ずかしい 気持ちになるとともに、なにを考えているんだ、と理解に苦しんだり、説教のひとつでもしてやりたくなる。 ところが、冒頭にあげたミュージシャンには、そうした妙にぎこちない空気感は見当たらなかった。なぜなんだろう、と理由を考えてみる。彼がいつま でも、若い頃のキャラを保ち続けているなんとも希有な人だといわれれば当てはまる気もする。だけど、それだけでは答えとして不十分な気がする。要は、歌詞 が二十歳くらいの頃の自身に繋がっていることはもちろん、いまの彼にも違和感なく響いているようにも聞こえてしまうところが肝要なのだ。 こんなふうに、己のその後をどこか予見するというか、規定してしまうような凄味のようなものが、初期作品に限って宿ってしまうことは、小説の世界でも、往々にしてあることのように思える。 ともすれば、かようなケースは、デビュー作を仮想敵にせざるを得ないほどに書き手を追い込んでしまうこともある。いつまでも一つの作品のイメージ が書き手に付きまとうような枷をはめてしまう危険性を孕んでいるからだ。だけど一方で、「間違いなく、あの時の自分にしか書けなかったはずのものだった」 と肯定的に振り返る書き手の方も少なくない。 こうした、何かが降りてくるようにして出来上がってしまう、まるでライブ一発録りのような、ある種の一筆書きのような勢いに満ちた作品が生まれて いく小説の生成過程自体に興味を持ってしまう。だからこそ、その作家にとっての一生に一度しか書けないだろう、こうした作品に、自分は惹かれてしまうのか もしれない、と改めて思ってしまった。 ( II ) |
|||||||