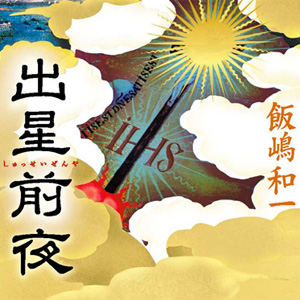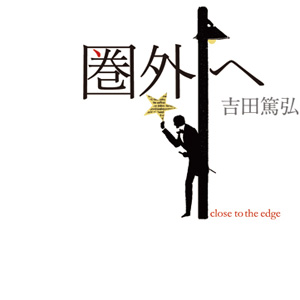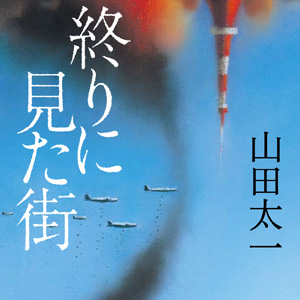| ホーム > きらら通信 > 2009年 |

|
|||||||
2009年12月号 【67】知り合いの小説家がこんなことを言っていた。どうしたらいい小説が書けますかとよく質問されることがあるのだが、そんなときにはひとつの作品を書く 前に百の小説を読みなさいと答えていると。そのように言うと、質問した相手は百ですかといちように顔をしかめるのだそうだが、少なくとも小説を書こうとし ているのなら、すでに百くらいの小説は読んでいるに違いないし、それほどたいへんなことではないのにと小説家は心底から嘆息していた。 いくつかの新人文学賞の選考にかかわっていて、毎年この時期になると応募されてきた膨大な量の原稿と向き合うことになるのだが、それらを 読んでいて思うのは、いったいこの人たちの何人が、作品を書く前に百の小説を読んでいるのだろうかと疑心暗鬼になってしまうのである。小説を読んでいれば 当然わかっているはずの、原稿を書く際のルール、あるいは人称や時制の問題。それらのことにいったい何人の人が自覚的に対処しているのか、読んでいて疑問 を抱いてしまうことが多いのだ。 小説が文章で書く物語であると定義するのならば、誰でも小説は書けることになる。しかし、小説は書かれただけでは小説とはいえない。読ま れてこそ初めて小説として成立することになるし、そうなれば前述した小説家が言う百の小説を読むということは、読まれるためのコツや秘訣をそこから学ぶと いうことなのかと思ったりもする。カンのいい人ならそれをひとつの作品を読んでたちどころにマスターすることもあるかもしれない。まあ、仮に天才と呼ぼ う。しかし、すべての人が天才になってしまったら、天才の価値は暴落するばかりだ。 よく冗談のように言われていることに、いまは小説を読む人より書く人のほうが多いのではないかという話がある。確かにパソコンやネット環 境の普及で小説を書く人が増えているのは確かなことだと思うが、ならば読む人間がもっと爆発的に増えてもいいのではないかと、小説にかかわって仕事をして いる身としては考えてしまう。しかし現実は、どうしてもみなさん読むより書くほうがお好きなようなのである。少なくとももっと読んでいただければ、仕事も 楽になるのだが、と思ったりもする。 ということで、これから新人文学賞の募集要項には、必ず作品を書く前に百の小説を読んでくださいという一項を加えようかと、小説業界の人間は真面目に考えているのである。 ( I ) 2009年11月号 【66】先日、同年代の小説家と電話で話していたときに、「ボルって聞いたことがありますか?」と尋ねられた。「カフェオレを飲むお碗でしょ」と答える と、「じゃあそのボルが出てくるフランス映画、何か思い出せます?」と訊かれたので、「ゴダールの『中国女』」と即座に返答した。 小説家はボルについてエッセイで書こうとしていたらしく、すぐにレンタルショップへ行き、『中国女』のDVDを借り、ボルが出てくるシー ンを確認したようだ。後日、小説家が書いたボルについての文章を読んだが、僕の記憶力に関して多少揶揄めいたニュアンスを交えながらも、「ヤフーとかグー グルの検索速度にも似た離れ業」と書かれてあった。 常日頃から小説家の作品を読んでその仕事にリスペクトを感じていたので、お褒めの言葉は嬉しかったのだが、内心は複雑な思いも生じた。な ぜなら僕はその映画についてボルのシーンしか記憶になく、どんなストーリーであったか、またどのような展開でボルのシーンが出てきたのか、まったく思い出 せなかったのだ。もちろん、ご覧になった方ならおわかりかと思うが、『中国女』という映画はアンヌ・ヴィアゼムスキー(わが10代最後のヒロインだった) をはじめとする5人の登場人物がひたすら毛沢東主義について語る「演説映画」で、あまりストーリーらしきものは存在しない。それでもいまこの映画に関する 記事をネットで検索してみると、物語にはクライマックスが存在し、確かにストーリーはあったのだ。 昔からストーリーを追うのが苦手で、小説を読んでいてもたびたび前の部分に立ち戻り物語の流れを確認しつつ読み進めていくという癖があっ た。読んだあともすぐにストーリーの部分は抜け落ち、印象的な文章や卓越した描写だけが記憶の中に残った。のちにストーリーを記憶することにかけては非常 に秀でた才能を持った人に出会ったとき(その女性はどんな長い映画を見たあとでも、筋をすらすらと語ることができた)、世の中にふた通りの人間がいること に気づいた。すなわちストーリーをたやすく憶えられる人と憶えられない人。 後者の人間にとっては、小説を読むことにおいてストーリーの面白さはあまり気にならない。むしろ描写の巧みさや比喩の面白さが小説を読むうえでの楽しみであるのだ。僕にとっては、小説の優劣は明らかにストーリーで下されるものではないのだ。ゴダール万歳! ( I ) 2009年10月号 【65】これまでこの欄で具体的な小説の良し悪しについて触れるのは慎重に避けていたのですが、ついにそれを書かずにはおれない作品があらわれました。「きらら」の2006年12月号から2009年3月号まで連載され、このたび単行本となった吉田篤弘さんの『圏外へ』です。 翻訳家の柴田元幸さんが「『実験的』と『面白い』の奇跡的両立。すごい」と推薦文を寄せてくれているこの512ページにも及ぶ長編小説で すが、自ら校了していてこれほど胸躍らせながら読み進んだ作品はありません。もちろん連載時も毎回毎回、吉田さんから届く原稿を読んでいたのですが、今回 このようにひとつの作品として通読してみると、あらためて『圏外へ』という作品が内包している、読む楽しさというものに触れることができるのです。 『圏外へ』は柴田さんが言うように、ある意味できわめて実験的な小説です。主人公の「カタリテ」という小説家は、小説を書き始めようとする のですが、書き出しで行き詰ってしまいます。先を書きあぐねているうちに「カタリテ」は自分が書こうとしている作中の登場人物たちから反撥や反抗を受け、 やがて自分が書く作品の中に取り込まれていきます。どこまでが現実で、どこからが小説の世界なのか、読む側もやがて、いやがおうでもその境界線を往き来す るようになります。その間、南新宿にある雲呑ソバ屋さんや古いレンズばかりを集める写真機店の父と娘の話など魅力的なエピソードがちりばめられ、いつのま にかこの作品の「圏内へ」と引き込まれていきます。 作者の吉田篤弘さんは物語を書くとはどういうことなのかというテーマを作品中で縦横無尽に展開していますが、読む側も同じように物語を読 むとはどういうことなのかという命題を否が応でも突きつけられる作品なのです。『圏外へ』という象徴的なタイトル(もちろん携帯電話の「圏外」という言葉 にもリンクしています)が持つ意味も最後まで読み進めていくとはらりとわかる仕組みとなっています。 小説を物語るとはどういうことなのか。かつて、母国語ではなくフランス語で小説を書いていたサミュエル・ベケットが『モロイ』から始まる 三部作で果敢にも挑んだテーマですが、それぞれがたどりついた地点は同じような気がします。しかし、読後の気分にはまったく異なったものを感じました。ベ ケットは三部作の最後の作品『名づけえぬもの』でかなり絶望的なラストに達しているのですが、吉田さんは自らの位置をそこで確かめ、さらに高みの世界へ踏 み出したような気がしてなりません。 ( I ) 2009年9月号 【64】文学賞の受賞会見などめったに出かけることはないのだが、このあいだ、ずっと興味を持って読み続けてきた作家がその栄誉に浴したので、たくさんの人の前でどんなことを話すのだろうかと興味を持ち、聞きに行ってきた。彼は集まった大勢の報道陣の前でこう語った。 〈自分が小説で何ができるのかと考えたとき、時間を描くことだと思ってきた。時間というのはとらえどころのないもので、それを言葉に表すとしたら小説ではないかと思う〉 自分も、これまでこの作家の作品を読んで感じてきたのは、「時間」というものに対してかなり意識的に企みをめぐらしているなということ だったので、この会見での言葉を聞いて少しわが意を得たりとほっとした気持ちになったのだが、実は「時間」というのは、小説を書こうとする者がもっともシ リアスに直面しなければいけない根源的なテーマであるのだ。 18世紀のドイツでラオコオン論争というものが持ち上がった。論争の発端となったゴットホールト・エフライム・レッシングは絵画や彫刻な どを「空間芸術」、文学や舞台を「時間芸術」と定義して、これまで同根のものとして見られてきた絵画と詩を区別することとした。論争そのものの行方はここ で話題にすることではないのだが、言語という手段を用いる限りその表現は「時間」というものに著しく拘束されるのだということを、この論争は厳然と後世の 人間に示唆してくれている。 いうまでもなくレッシングの定義でいえば、小説はもちろん「時間芸術」である。鑑賞するにしても美術のように一瞬で全体を見渡せるもので はなく、最初の1行から順番に読み進めていかなければならない。もちろんそのルールは書く側にも適用され、小説に対して誠実に取り組もうとすればするほ ど、「時間」というものを慎重に注意深く顕微鏡の上に載せ、ピンセットで扱うように対処していかなければならない。よりシンプルにいえば、小説における描 写とは、この「時間」というものに他ならないし、その密度が濃ければ濃いほど、私たちが「純文学」という業界用語で呼んでいるものに近づいていくのかもし れない。 冒頭の受賞作家は会見でこうも語っていた。「今回の受賞によって書く場を与えていただけることが嬉しい。とにかくこれから一生、90歳になるまで小説を書き続けていきたい」 この真摯な作家の仕事を見守っていくためにも、もう一度、「時間芸術」としての小説をきちんと考えていかなければならない。 ( I ) 2009年8月号 【63】このところ電車に乗るとハードカバーの単行本を熱心に読んでいる人が目につく。商売柄、何を読んでいるのかとても気になるので、さりげなく近づいて のぞきこんでみると、やはりあれだ。1巻で500ページにもなるあの小説(その割には紙が薄いせいなのかあまり大著には感じられない)、特徴的なふたりの 登場人物の名前をそこに発見することができるので何を読んでいるのかはすぐにわかる。そんなことが実はこのところ何度もあった。 この世界に足を踏み入れたとき、電車の中で人々が手にしているのは週刊誌かコミック雑誌と相場は決まっていた。とりあえず週刊誌に携るこ とになった身としては、毎週、週明けの電車で自分が担当した記事を読んでいる人を見つけるのが、一種の職業的快感であったことを覚えている。実はそれから 夏季オリンピックだけで8回もあったのだが、いま、電車の中で人々が手にしているものといえば、それは十中八九、携帯電話であり、たまに文庫本を開いて熱 心に活字を追っている人を見ると妙に安堵の念を感じずにはいられなかった。 たぶんこれがベストセラーという現象なのだろうと思うが、いまその本を読んでいる人を街でたくさん見かける。本づくりを生業としている人間としては、もちろんそれは歓迎すべき出来事なのだが、この現象が少しでも長持ちしてくれることをひたすら望んでいる。 数年前にも同じような光景に出くわしたことがある。普通の単行本よりひと回り大きいその本を読んでいるのを、主に若い女性を中心に電車の 中で見かけた。それはファンタジーブームの先駆けともなった作品で、その後シリーズが刊行されるたびに話題を集めた。しかし、だからといってその本が切り 拓いたブームがその後も続いたかというとこれは少々心もとない。しかもこの作品は翻訳作品であったため、国内でそれに続くものが現れなかったことにも起因 しているのかもしれない。 われわれの業界に棲む人たちは得てしてベストセラーには冷淡である。たぶんプライドが高い人種が多いためか、この現象に対してまともに立 ち向かおうとする人間はあまり多くない。しかし出版業に生きるものとしては読書の退潮が叫ばれる中で生まれたこのチャンスを、今回はしっかりとものにしな ければいけないのだと思う。そしてこの小説に続 く第二、第三の矢を放たなければいけないのだ。電車の中から携帯電話を駆逐するのが当面これからのわれわれの仕事なのかもしれない。 ( I ) 2009年7月号 【62】今月の〈Pick UP〉コーナーに登場していただいている道尾秀介さんが、テレビの情報番組「王様のブランチ」(50ページの松田哲夫さんの本『「王様のブランチ」のブックガイド200』もよろしく)のインタビューに応えてたいへん気になる発言をしていた。 小説を書くきっかけになった本として太宰治の『人間失格』を挙げ、その有名な書き出し〈私は、その男の写真を三葉、見たことがある〉に続く、〈三葉の写真〉についての描写を読んだことで、書くことでしか表現できないものがあると確信し、小説家を志したというのだ。 確かに、『人間失格』の冒頭の描写は秀逸だ。幼年時代、旧制高等学校時代、そしていつかはわからないが白髪となった主人公の姿、その〈三 葉の写真〉を細密に描写することで、これから登場する人物の人生の輪郭を鮮やかに紹介し、なおかついやがうえにも読者の興味をかきたてる物語へのプロロー グとしている。 私も10代のときにこの小説を読んだのだが、書き出しの描写には何かひきつけられる異様なものを感じ、そのあとに続く主人公・大庭葉蔵の 三つの手記を一気に読み進めた記憶がある。ただあまりに若すぎたため、書かれている内容についてはじゅうぶん理解するにはいたらなかったが、ともかく太宰 治という手だれの小説家の語りの術中にはまんまとはまってしまったのは事実だ。 最近、小説は結局、語りの表現芸術だと思っている。語りというのは、もちろん小説では書くということと同義語だが、いかに語るか、いかに書くかということが小説の良し悪しを決定しているような気がしてならない。 たとえば、一斉に同じテーマ、同じストーリーが与えられたとしても、その語り方、書き方は語る人、書く人の数だけ存在するように思う。そして、その中で最良のものを選択し、実行していこうとする姿勢が、プロを自任する小説家たちの証しに他ならない。 そういう意味で、「人間失格」の冒頭の描写を読んで小説家を目ざすことになった道尾秀介さんは、最初からこの強烈なプロ意識に貫かれていたのにちがいない。それが道尾さんが読者の期待を絶対に裏切らない作品を次々と生み出している秘密だと思う。 道尾さんが言っていた、書くことでしか表現できないものがあるということに、10代の私も気づいていれば、もっと違った道をたどっていたかもしれないが、この言葉の持つ意味は、いまはとてもシリアスに自分に響く。 ( I ) 2009年6月号 【61】インターネット上の電子図書館「青空文庫」で全文を読むことができるが、芥川龍之介が谷崎潤一郎に反論するかたちで著した『文芸的な、余りに文芸的な』という論考は、小説というものを考えるうえで、いまでも重要なイシューを含んでいると考えられる。 芥川はその文章を発表するに先立って、文芸誌の座談会で谷崎潤一郎の小説を射程におき、「(小説の)筋の面白さが作品そのものの芸術的価 値を強めるということはない」と述べる。芥川にとって小説はイコール芸術だったわけだが、これに対して谷崎は、「筋の面白さを除外するのは、小説という形 式がもつ特権を捨ててしまうことである」と反駁する。 「文芸的な、余りに文芸的な」は、この谷崎の主張に応えるべく発表された四十の断章からなる文芸評論だが、芥川は冒頭で、「『話』らしい話 のない小説を最上のものとは思っていない」とエクスキューズしながらも、やはり話の面白さは小説の良し悪しを左右するものではなく、それよりも重要なのは 作品に含まれる「詩的精神」の有無だと述べている。そして芥川にとって最上の小説は志賀直哉の作品であり、彼自身も晩年には「蜃気楼」や「歯車」のような 「話のない小説」を発表することになる。 八十年以上も前の芥川と谷崎の論争を僕は「小説は文章かストーリーか」の論争と読み換えているのだが、いまこの『文芸的な、余りに文芸的な』を読み返すと、やはり芥川の切迫した心情にシンパシーを感ぜざるを得ない。 たぶん芥川と谷崎の時代、「ストーリー」は小説の特権的専有物だった。いまのように映画もなくゲームもなく、「ストーリー」は小説だけで 味わえる独占的愉楽であったにちがいない。しかし映像やネットなどのメディアの発達とともに「ストーリー」も市場開放の洗礼を受け、それこそ谷崎の作品を はるかにしのぐ奇異で奇抜なものも登場してくる。 「ストーリー」が小説というジャンルのなかから逃げ出していくこの時代にあって、では、何が小説を小説たらしめているのか。それは間違いな く「文章」であると考えている。芥川の言葉を借りれば「詩的精神」、これに裏打ちされた「文章」の表現技法、これが小説というジャンルをこれからもより強 靭にしていくのだと思う。 考えてみれば、芥川龍之介も谷崎潤一郎も志賀直哉もすぐれた文章家であった。彼らがこの時代に生きていたとしたら、その「文章」でどんな「ストーリー」を紡ぎ出してくれるのか、そんな想像をするのもまた楽しい。 ( I ) 2009年5月号 【60】はじめて小説というものを楽しむようになってすでに40年近くはたつのだが、そのときからいままで小説は描写が命だとずっと思っている。最近では会 話ばかりで成り立っている物語が「小説」と呼ばれているようだが、これは断じて小説ではないと考えている。仕事柄そういうものにも接しなければならない局 面は多々あるのだが、自らの度量の狭小さにあきれつつも、やはりこれは自分が読んできた小説とは違うものだと思わざるを得ない。 小説の楽しさは文章を読むことにあったしこれからもそうあるべきだと信じている。そして文章というのは自分にとっては、やはり会話ではな く地の文を指していた。もちろんきわめて優秀な会話を書く作家もいたが、これとて前後にすぐれた地の文が配されてはじめて成り立つものである。そしていう までもなく地の文で表現されるのは描写なのである。描写の優劣を鑑賞するのが、自分にとっては小説を楽しむということにつながっていたのだ。 まだ物語を印刷物で楽しむということがなかった時代、それは人から人への口伝で伝えられていた。印刷技術の発展で書物というものが一般化 するとともに、近代の小説が誕生する。その時点で活字に定着されることになった過去から伝えられてきた物語もあったが、それは個人から発したものというよ りも、共同体の中を生き抜いてきた物語たちである。つまりかつては物語が発せられる現場にはつねに耳を傾ける聴衆があり、ある種の共同作業が存在していた のだ。 印刷技術の発展と書物の普及とともに物語から小説というジャンルが派生する。小説はこれまでの物語とは違い、あくまで個から発していた。そしてそれは近代的自我の覚醒とともにやがて物語の王道を歩み始めることになる。 しかし近代の物語作者たる小説家たちにとっての困難はここから始まった。小説を書くという作業は徹底的に孤独な作業である。小説家たちは 書斎の机に向かって(あるときは酒場のカウンターのうえで)、呻吟し試行錯誤を繰り返し自らの文章表現と格闘することになったのだ。いかにしたら自分の語 らんとする物語がうまく他者に伝わるのだろうかと。 冒頭に小説を楽しむとひと言で書いてしまったが、それは小説家たちの格闘の軌跡を追っていることに他ならない。会話ばかりで成り立っている物語に強く抵抗感を覚えるのは、小説が本来持つ表現へのひりひりするような切実さが感じられないからかもしれない。 ( I ) 2009年4月号 【59】携帯電話が小説に登場するようになったのはいつのころからだろう。おぼろげな記憶では、1990年代の初頭に読んだ推理小説のなかに、小説にとって はまことに便利なこの「道具」を発見していたように思う。いまのようなメールやネット機能もなかったが、登場人物がどこにいてもどんなことをしていても会 話を交わせるというこの万能の道具は、小説作法に革新的な変化をもたらした(と僕は見ている)。 最近読んだ小説のなかで、夫婦の危機をむかえている男女が、少しずつ心情的にも距離的にも離れ離れとなり崩壊していくというストーリーの ものがあった。ある場所で決定的な別れが訪れてふたりは二度と出会わぬ運命となるのだが、物語の最後で作者はこの男女に携帯電話を持たせてしまった。別れ に至る双方の感情が、印象的なエピソードと丹念な描写で細やかに描かれていたなかなかの秀作だったのだが、ラストを締めたのが携帯電話によるふたりの会話 だったのだ。 元来会話によってストーリーが進行する小説はあまり好きではないのだが、このラストには恐ろしく興が醒めるのを覚えた。それまで作者が心 血注いで描写してきたものが、この携帯電話の会話で台無しになっていたのだ。結末部分でふたりにもう一度会話をさせることで物語を終結させようとしたのだ ろうが、もとより無理矢理ストーリーを閉じる必要のない小説だと感じていたので、このラストはまったくいただけないものだった。 携帯電話の出現以来、小説のなかで交わされる会話の量は確実に増えていると思う。作者は会話に至るまでの描写をくどくどすることなく、い きなり「 」に入れる。たとえ主人公が地獄の底で蜘蛛の糸にぶらさがっていようとも、大きな白い鯨の腹のなかで消化されかかっていようとも、携帯電話の圏 内でさえあれば会話を始めることができるのである。 前出のようなシチュエーションでいきなり会話が始まるという設定も魅力的ではあるが、多くの場合そのようなファンタスティックな状況描写 にもならず、いきなり会話が始まるケースが多い。本来ならば会話にたどり着くまでの描写が書き込まれるべきであるのに、それが省略される場合が多いように 思う。 言うまでもなくこれは物語のなかに携帯電話を登場させるときだけに言えることではない。 ちなみに1990年代初頭に読んだ推理小説のなかでは、主人公が携帯電話を手に入れるまでの顛末も事細かに描かれていた。 ( I ) 2009年3月号 【58】恋愛小説が成り立たない時代だといわれている。そういえば最近の恋愛小説は、時代小説であったりファンタジーであったり、あらかじめ決められた枠組 みの中で語られるものが多く、同時代のリアルな現実を前に狂おしいまでにもがき苦しむ恋愛小説にはとんとお目にかかることが少ない。スタンダールの「赤と 黒」、ヘルマン・ヘッセの「春の嵐」、エミリー・ブロンテの「嵐が丘」、D.H.ロレンスの「チャタレイ夫人の恋人」など、恋愛に対して真正面から勇敢に 立ち向かってきた作品は数多いが(ヘンリー・ミラーの「北回帰線」だってすぐれた恋愛小説だと思っている)、どうも最近の恋愛小説家たちは、最初から歴史 やファンタジーの中に逃げ込んで、恋愛との真剣勝負を避けているような気がしてならない。 むしろ恋愛に関する作品はいわゆるケータイ小説と呼ばれているものに多いようで、生粋の恋愛小説マニアとしてはこれには看過できないもの を感じ、いくつかの作品を読んではみたのだが、実はこれらからも満足を得ることはなかった。なぜならそこで語られている恋愛はいかにも幼稚で、手練手管で 世の中を渡ってきた恋愛小説マニアにはいかにも物足りないものとして映ったからである。そんなに簡単に好きになって、そんなにすぐに病気になって、そんな にいきなり死んでしまって、それでいいのかと嘆息してしまうことが多いのである。 恋愛とは人間と人間の関係の中ではもっともミステリアスなものだと考えている。人を好きになるということは、実に無前提で、実に無自覚 で、実に無意識である。この「無」を「有」にする作業が、古今の恋愛小説家たちが力を尽くして成し遂げようと試みてきたことのように思える。自らの感情の 名づけようのないものを、文章と言葉と技巧で物語っていく、その困難に満ちた作業の果てに恋愛小説の名作たちは生まれてきたのである。 いまのように情報があふれる社会の中では、人間は自らの精神の安定をはかるため、必死であらゆるものを記号化しようとしている。そして恋 愛にもそれは当てはまるのだが、こればかりは記号化すればするほど、そこからこぼれ落ちていくものが多くて、ますます人間は混迷の森を彷徨うこととなる。 恋愛小説とは、いわばこの森をそっくりそのまま世界として提示することにちがいない。安易な記号化からは決然として背を向けながら。 ( I ) 2009年2月号 【57】機会あって書評家の方たちと話していたら、「最近は小説を読む人より書く人のほうが多いのではないか」という話題になった。書評家の方たちは職業柄 いくつかの小説新人賞の選考にかかわっていて、主に「下読み」と呼ばれる最初の応募原稿を読むという作業を担当しているケースが多いのだが、それを読んで いて冒頭のような実感を得るのだという。 確かに小説の新人賞は近年とても増えている。万年筆に原稿用紙という時代は去って、いまはキーボードにパソコンで手軽に小説を書ける時代 だ。小説の原稿枚数は増え、書店の店頭には分厚い小説の本が並ぶ。小説の新人賞も色とりどりで、恋愛などにテーマを絞った賞から老舗の文学新人賞まで、投 稿ガイド誌などをのぞくとびっしりと並んでいる。 自分自身もいくつかの賞にかかわって、小説を書く人口は確実に増えているということは実感することができる。パソコン時代になりハードルが低くなったぶん書きやすくなっているのだと思う。これがいいことなのか悪いことなのかまだ結論は出せないとは思うが。 書評家の方たちとの話は少し発展して、「もしかしたらいまの人たちは小説をまったく読まないで小説を書いているのではないか」という推論 に移っていった。新人賞の応募原稿を読んでいると、まず原稿の書き方がわかっていない人が目につく。会話の後の一段下げとか、少なくとも小説を読んでいれ ばわかるような原稿の不備が目立つのだという。もちろんまったく小説を読まずに小説を書いているというわけではないだろうが、それは「読む」より先に「書 く」という行為が先んじているからではないだろうかという意見でその場が一致した。 かつて小説を書くという行為は、読むという行為の延長線上に位置していた。すぐれた小説家は優れた読書家でもあった。文学史を革新してきた小説家たちは、自分が読んだ小説に飽き足らずに新しい作品を生み出してきた。 「書く」という行為は、言うまでもなく自己表現である。しかし「小説を書く」という行為は自己表現でもあるが、もうひとつ作品をつくりあげ るという要素も持ち合わせている。そしてよりよい自分なりの作品をつくりあげるために、やはり他人の作品を研究することは不可欠なのである。最近考えてい るのは、小説の新人賞の応募条件の中に、読書論文を付け加えたらどうかということである。 ( I ) 2009年1月号 【56】生来の放浪癖がたたり、ひとつの場所に一時間以上はおられない性格ゆえ、読書というものはいつも電車やバスなど乗り物の中でしていた記憶がある。大 江健三郎さんの「セブンティーン」は高校の通学の電車の中で読み終わったし、同じように三島由紀夫氏の「仮面の告白」は京都への修学旅行、夜行列車の暗い 席でページを繰っていた思い出がある。 さて最近は、すっかり朝の日課となった一時間の入浴の最中に小説の本を手にすることが多い。もともと長い時間ひとつのところにいられない ような騒々しい人間なのだが、この朝の入浴は(というより最近は読書の時間といってもよいが)、自分の心を落ち着かせる数少ない黄金の時間といってもよ い。そしてこの安息のときにかつて読んできた外国文学を読むのがこのところのわが読書の慣わしである。 実は過去の人生において一度だけ文学全集を購入したことがあって、それはずばり「世界の文学」というシリーズであったのだが、とはいって も収録されている作家はスタンダールやドストエフスキーなどではなく、ロブ=グリエであったり、バースであったり、ボルヘスであったり、ブランショであっ たり、コルタサールであったりと、ジョイスから始まる二十世紀文学の新しい試みに名を連ねた作家ばかりで編まれた全集であった(そう今年のノーベル文学賞 に輝いたル・クレジオもいちばん若い作家としてリストアップされていた)。 ともかくぬるめのお湯を注いだ浴槽の中で読む「嫉妬」はなかなかおつなものだし、また「酔いどれ草の仲買人」の舞台、アメリカ東海岸チェサピーク湾のことに思いを馳せながら浸かる芳香剤入りの湯は至福でもある。 考えてみれば、机の前に座って小説を読んだ記憶はあまりないが、読書はつねに自分に知的でエキサイティングな時間を提供してくれてきたよ うに思う。とくにいまでも読み継がれるような時代を切り拓いてきた小説たちは、いつでも頭の中をリフレッシュさせてくれるし、新たなヴィジョンを明示して くれる。 いろいろなメディアが発達してきて、本を読む時間が少なくなってきているのではといわれる昨今だが、実は生活の中に積極的に読書という習 慣を取り入れることで、他のメディアでは追随できない豊かな知的活力が得られるような気がする。そしてとくに小説はしっかりとそれに応えてくれるとずっと 信じている。 ( I ) |
|||||||