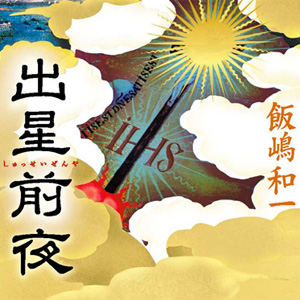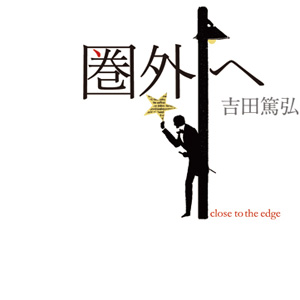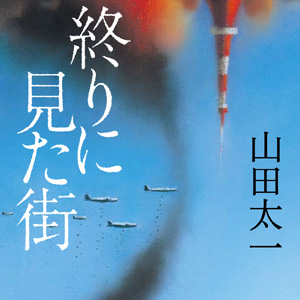| ホーム > きらら通信 > 2007年 |

|
|||||||
2007年12月号 【43】ある文学賞の受賞式で女性作家の方が次のような挨拶を述べられたのが心に残った。 「恋愛小説を読むことが好きか嫌いかは、その人の動物的価値を左右することになります」 「人間的価値」ではなく、あえて「動物的価値」と女性作家の方が言い切った部分に僕は強く反応したのだが、これは小説というものの本質を鋭く突いた発言だと直感したからである。 では、「人間」と「動物」の間にどのような差異があるのか、自分の考えを少し述べてみたいと思う。(もちろん、あくまでもこちらが勝手に推し量ったことなので、その女性作家の方本来の考えではないということはお断りしておきます) 「人間」が代表するものを「知」とか「情」とするなら、「動物」のそれは「本能」ということになる。なぜ生物学的に私たちは生きているの か。なぜ食べるのか。どうして生殖という営みをくりひろげているのか。「本能」という領域にあるものは、かくのごとく人間にとってはほとんど不可知なもの としてある。しかし、僕の考えではその部分にまでシリアスに切り込んでいくのが小説の使命であるという気がする。 「知」とか「情」とかを扱った小説が意味を持たないと言っているわけではない。でも、それらを突き抜けたところにある人間の存在の根本にまで迫った作品に強く魅かれるのである。 ヘンリー・ミラーの『北回帰線』を読んだとき、人間の性をめぐって展開される混沌が自分の内部にも強く存在することを感じたし、ガルシ ア・マルケスの『百年の孤独』を前にして、何故か自分のDNAの中にあるかもしれない、人間が魚類だった頃の記憶に想いを馳せたりもした。 冒頭の女性作家の方の言葉を受けると、僕は「動物的価値観」を揺さぶる恋愛小説がとても好きだ。というよりも、あらゆる小説は恋愛小説に 至ると信じている。人間がひとつの個体としてもうひとつの個体を必要とするさまを描くこと、それは自分と自分以外のものとの関係性を解き明かす重要な作業 であるに違いないと考えている。人間の神秘に近づく行為なのだ。 「知」と「情」の彼方に存在する「本能」にまでたどり着こうとする小説的試み。最近のいわゆる恋愛小説といわれているものの中に、そういう強い意志を感じとることができないのは、僕だけなのだろうか。少し寂しい気がする。 このところ千年以上も前に書かれた『源氏物語』が気になっている。平安の人たちの動物的価値観を揺るがしたであろう、その小説が。 ( I ) 2007年11月号 【42】高校のクラブ活動の夏合宿にドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を持っていったことがある。所属していたのはまがりなりにも運動部だったの だが、部室には安部公房や大江健三郎の小説が何冊も置いてあり、先輩たちがそれを後輩たちに薦める奇妙な運動部だったので(小説に対する興味はほとんどこ こでつくられた気がする)、『カラマーゾフの兄弟』を持参したのもあながち不自然ではなかった。 緑色の箱に入った上下巻だったが、夕食が終わって就寝までの時間にページを開いた。しかし、真夏の炎天下の練習で疲れ果てていたせいか、2段組で活字がびっしり組まれていたその本は、格好の誘眠剤となり枕となった。 もちろんその夏の合宿で読み終えることはなかったのだが、後に異なる訳者のもので(1段組でした)、三兄弟の運命を知ることになる。 そんな苦い経験もあった『カラマーゾフの兄弟』だが、最近新訳が出て読者に支持されているというので、さっそく手にとってみた。かつては ゾシマ長老の話にずいぶんと難渋させられた記憶があるのだが、今回の新訳はまるでミステリ小説でも読むかのようにすんなりラストまでたどり着いた。ただ、 これがドストエフスキーの小説なのかと問われれば少し複雑な気持ちになるが、そのドストエフスキー観さえ、先達たちの訳業を通してかたちづくられてきたも ので、原語で読まない限りは彼の小説をほんとうに味わうことなどできないと思う。 さて人間がまだ文字を持たなかった頃、物語は人から人へと口伝で受け継がれていった。たぶんその過程で伝えるべき物語の取捨選択も働いた だろうし、脚色やストーリーの変更もあったに違いない。また物語を語り継ぐ人の「身振り手振り」で、同じ物語でさえ違ったニュアンスで伝えられていったと 考えられる。 翻訳というのはある意味でこの「身振り手振り」のような気がする。翻訳者のパフォーマンスひとつで元の作品はまったく違ったものにもなり うる。もちろん原著者の表現しようとしたものを忠実に置き換えることが翻訳者の正当な仕事だとは思うが、それを完璧に成し遂げるのはどだい無理な話だ。な らば音楽の世界にサンプリングという新しい表現が生まれたように、小説の世界にも同じようなものが登場してきてもいいように思う。新訳の「赤と黒」も読み 始めたが、ジュリアン・ソレルにはなぜか日本の俳優の顔が妙に重なる。 ( I ) 2007年10月号 【41】昔、友人で、一度読んだだけで小説の筋をすらすらと話せる人間がいた。もちろん映画のストーリーに関しても同じで、作品を観たそのすぐ後に主人公 の行動を逐一語ることができるのだ。自分が見逃していた物語のキーポイントともなる動作などももちろん見逃さない。小説の場合なら主人公がそのとき右手左 手どちらを握っていたかまで記憶していた。 このところ記憶力の減退で、小説を読んでいても登場人物のアクションや物語のストーリーなどをすっかり忘れてしまう自分にとって、その友人の素晴らしい能力はいまも羨むばかりなのだが、それにしても小説を読むことは依然としてとても楽しい体験である。 では、いったい何を自分は楽しんでいるのだろうか。もちろん先をついつい読みたくなるような心躍らせるストーリーにも期待はしているのだ が、それよりも著者が繰り出してくる比喩――直喩や暗喩、慎重にちりばめられたスタイリッシュな語り口、それと何よりもそれらによって表現される登場人物 たちの心の在りよう、どうもそういうものに触れるのが楽しみで、小説を読んでいるような気がする。そして、それらに気をとられる結果として、ストーリーを 辿る能力がお留守になっているにちがいないのだ(ささやかな自己弁護です)。 芥川龍之介と谷崎潤一郎の昔から、表現が重要か、ストーリーが大切かは小説家たちの激しい論争の的になっていたが、これはどちらがどうと いう、優劣がつく問題ではないと思う。小説にとって、このふたつの要素は不即不離の関係であるし、強いて後先を論ずれば、ストーリーをよりよい形で伝える ために表現が存在する。そしてその巧みさを争うのが小説というジャンルということになるのだろう。 ストーリーの原型となるものはギリシャ神話と旧約聖書の中に出尽くしていて、それから後の物語はみなこれらのヴァリエーションでしかない と言い切る人もいるが、あながち間違いではないような気もする。小説家は出し尽くされたストーリーをいかに料理するか、読者はそれをどのように味わうか、 いまでもそれが繰り返されている。そして、あいかわらず自分はストーリーを追うのが苦手だ。 前述の友人がある小説を読んだ後、ひどく疲労困憊していたことがあった。興奮して彼に薦めた小説だったのだが、それはアラン・ロブ=グリエの『嫉妬』という小説であった。 ( I ) 2007年9月号 【40】小説を書くためには何が必要か。知り合いの小説家は即座に次のように答えました。 まずは小説を読むことである。 「小説を読むこと」とは、文字通り、他の作家が書いたものを読むこと。つまり作品を研究するということです。その作家はこうも続けました。少なくとも自分の好きな作家を5人ほど見つけて、徹底的に読み込め、と。 若かった頃、好きな作家が3人ほどいて、その3人が書いた小説ばかりを読んでいた時期がありました。特にそのうちの1人に関しては、自分 の人生を重ね合わせるように熱中して読んでいたせいか、試験の答案などを書くときも、その作家の幾重にも構文が交錯する難渋な文章が飛び出してきたりして (およそ試験の答案などには不向きな文章なので)、ずいぶん解答にてこずった記憶があります。 小説を徹底的に読み込むと、どういうことが起こるかというと、つまりはこういうことなのです。その作家の作品が自らのからだにしみこんで いき、血肉と化し、アウトプットするときに今度はその影響が自然に立ち現れる。ワードプロセッサーが出始めの頃、キータッチの訓練のために、好きな作家の 長編小説を丸ごと1冊打ちこんだことがありますが、これは得がたい体験でした(読書の時間に余裕のある方にはぜひおすすめします)。ただ小説を読むのとは 違って、作家が文章を書くときの息遣いや癖などが鋭敏に感じられる。そして別の機会にワープロのキーなどを叩いていると、打ちあがってきたものの中にその 作家の言い回しがいつのまにか紛れ込んでいたりするのです。 一時期、新人作家の作品を読んでいると、必ずある作家の影響を感じずにはいられないということがよくありました。もちろんそれだけその世 代にとってその作家の存在が偉大であることの証左なのでしょうが、最近はそういうことさえあまり経験することがなくなりました。いったいこの人たちはどん な小説を読んできたのだろうと頭をひねるものばかり。もしかしたら、ほとんど他の人の書いたものなど読んでいないのではないかと疑ったりしてしまいます。 まあそれはそれで新奇な表現として価値あるものなのかもしれませんが、少し寂しく感じるのは自分だけなのでしょうか。 若い時期にもう2人ほど好きな作家をつくっておいたら、自分にも小説が書けたのだろうかと、いまにして思ったりしています。 ( I ) 2007年8月号 【39】このところ小説を読んでいてしきりに気になってしまうことがある。あまりにそのことに注意を払うせいで、ときどき辿ってきたストーリーが記憶の中で崩壊してしまったり、いま小説の中に流れている時間がいつのものなのかわからなくなってしまったりする。 さて最近の僕を、小説の中で行方不明者にさせるものは何か。それは物語の語り手は誰で、語り手と物語の関係はどのようなものなのか、とい うきわめてシンプルな疑問である。 たぶんそれはふつうに小説を楽しんでいれば立ち現れることはないのだろうが、編集者として文章のチェックや物語の構成 などに気をつかいながら文字を追っていると、とたんに頭をもたげてくる。そういう場合、最初から疑惑にみちた眼差しで作品に接しているわけだが、気になり 始めるとなかなかその疑問は頭を去らなくなり、挙句、小説を読みながら語り手の身元探しになってしまうのだ。 小説や映画などの手法で、「信頼できない語り手」というものがある。これは物語の語り手の信頼性をぐらつかせることで、物語にどんでん返 しを生じさせたり、より劇的な展開を生んだりという荒技的手法だ。例えばミステリー小説で終盤、語り手自身が犯人であるということが明かされる。また一般 小説でそれまで語られていたものがすべて語り手の頭の中で起こったこととしてピリオドが打たれる。読者にとってそれは「騙し」とも映るやり方だが、この手 際があざやかであればあるほど、妙に納得させられたりする。映画の『ユージュアル・サスペクツ』という作品では、この「信頼できない語り手」が爽快なほど 機能している。 冒頭に告白したような疑り深い物語の受け手としては、「信頼できない語り手」が登場しない小説にも、つい行間や文章の背後にその存在を感じてしまう。作者の企みは何なのか、語りに仕掛けはないだろうか、そういうことを実はとても期待していたりするのだ。 しかし、残念ながら期待は失望で終わることが最近は増えている。あまりにも「信頼できない『信頼できない語り手』」が多いのだ。読者を気 持ちよく騙してくれる物語、作者が全編に企みの罠をはりめぐらしている小説、それらにめぐりあう機会が少なくなっているような気がする。とはいえ今日も僕 は、ひとつの小説の中に登場する「僕」と「わたし」の違いに細心の注意を払いながらページを繰っている。 ( I ) 2007年7月号 【38】書店で大好きな小説家の新作を手に取った。 職業柄、本を見ると装丁や、オビに書かれている言葉などが気になってしまうが、最新作として並べられたその作品のオビには、あまり刺激的 な言葉はなく(編集者はすぐに派手な惹句を並べたがる)、静かに、これは恋愛小説であることと、主人公が作品中で置かれている状況が、必要最小限の言葉で 書かれてあった。カバーに使われたシンプルで不思議な佇まいを感じさせる絵と相俟って、それは素敵な「顔」をした本であったのだが、編集者の目から見れ ば、そのカバーの言葉にはとても物足りないものを感じたのも事実だった。 さて、その大好きな小説家の新作を読んで、謎がわかった。その作品は、なかなか内容をひとつの言葉で言い表せないのだ。まず明確なわかり やすいストーリーがあるわけではない。描かれているのは、ひとりの男を支点として、心を惑わすふたりのヒロインの心の在り方、精神的な危機の前兆ともいえ る不安定な心模様なのだ。それらが場面場面を追いながら、丁寧にきめ細かく見事に描かれている。 編集者というのはともすればオビにストーリーを書きたがる。流通の現場からそのような要請が出されるからでもあるのだが(いわく「これは ひと言で言ってどんな作品なのですか」)、われわれのような稚拙な表現力の持ち主は、ストーリーに絡めておけばオビの言葉に間違いはないと考えているから でもある。 ストーリーのない小説があるかという設問は無意味かもしれないが、ストーリー性が薄い小説はある。昔からどうもそういう作品ばかりがフェ バリットリストに載ってしまう自分としては、その大好きな小説家の新作もまた実に好もしい素晴らしい作品であった。しかしオビを考えなければいけなかった 編集者のことを思うと、ずいぶん苦労をしたのではないかといらぬ同情をしてしまったりする。 小説はストーリーか表現かという二元論は古今東西ずいぶん語られてきた気がする。自分としては先ほども述べたように、ストーリーより表現 である。書き手はひと言で言い表せないものがあるから小説を書き、小説全体で何かを語りかけてくる。それを自分は受け止めていきたい。そういう意味では編 集者泣かせの小説家がどんどん出てきて欲しいと思うのだ。もちろんわれわれとしてもオビの言葉の表現力を磨かなければいけないが。 ( I ) 2007年6月号 【37】またまた小説以外の話で申し訳ありません。 『バベル』を観ました。言うまでもなく、日本人女優の菊地凛子さんがアカデミー賞助演女優賞の候補となり、今年に入りずっと話題を集めて いた映画です。イニャリトゥ監督の作品は好きで、『アモーレス・ぺロス』にも『21グラム』にもずいぶん感心した記憶があり、この『バベル』も、これほど 騒がれなくとも確実に劇場には足を運んでいたと思います。 封切りの日にシネコンで観たのですが、計4スクリーンで上映しており、少なくとも自分の観た回は満席で、アカデミー賞などで話題にならなかったら、これほどの観客は集まっただろうかなどといらぬ心配もしながら、いつしかスクリーンに引き込まれていきました。 『バベル』という題名は、旧約聖書「創世記」のバベルの塔のエピソードに由来しており、宣伝物などにもそれをにおわす惹句が書かれていました。かつて言葉はひとつだったが、天まで届く高い塔をつくったことに怒り、神は人間たちの言葉を別々なものにしたということです。 物語はその言語が異なる三つの場所、モロッコ、メキシコ、日本で起こる出来事を、時間軸を微妙にずらしながら丹念に追っていきます。それ ぞれの地でコミュニケーション不全に陥ってしまった人間たち、いわば神の仕業によって混乱させられた人間たちの姿を描いていきます。未見の方のためにス トーリーを書くことは控えますが、注目すべきは、三つの場所で起こる出来事が同時進行ではなく、微妙な時間軸のずれがそこには存在し、それが観る者を少し ずつ困惑させ考えさせ、この現代の聖書のような物語の中に引き込んでいく点です。 通常、ハリウッド映画などでは、観客を物語の中に取り込むために、登場人物への感情移入というやり方をとるケースを多々見ますが、イニャ リトゥ監督の作品では、この時間軸の仕掛けが、観客を物語のまっただなかに放り込みます。そしてこれはきわめて小説的なやり方のように思いました。つまり スクリーンの上で繰り広げられていく物語を、観客は提示された時間軸をつなぎ合わせながら、「読んで」いくのです。 その意味で『バベル』はきわめて小説的な愉しみを感じさせてくれる映画でした。あらためてやはり自分は小説の側に立っている人間だということも再認識しました。 おかげさまで、『きらら』も4年目に入りました。これからもよろしくお願いします。 ( I ) 2007年5月号 【36】小説には何ができるのだろうと考え込むことがよくある。それはすぐれた映画やコミックを観たり読んだりしたとき、最近で言えば浅野いにおさんの 『虹ヶ原ホログラフ』を読んだとき、その思いに囚われ頭を抱えた。この作品は昨夏単行本として刊行されたもので、いまごろ読んでどうのこうのと言うのも時 機を失しているかもしれないが、編集部から出ている樋口直哉さんの『大人ドロップ』という本の装画を浅野さんが描いていることもあり、書店でこの作品を見 かけ手に取ったのだ。 正直言って驚愕した。あまり熱心なコミックの読者ではなく、過去には宮谷一彦さんや岡崎京子さんの作品などがマイフェバリットリストにあ るくらいの人間なのだが、この『虹ヶ原ホログラフ』に触れ、『ねむりにつくとき』や『リバーズ・エッジ』を読んだときに感じた「ああ、やられた」というあ る種の無力感を伴う感慨に読後強く襲われたのだ。 『虹ヶ原ホログラフ』という作品は、現在と過去が章ごとに交互に進行していく二重構造をとっている。それだけなら小説でもよくある手法だ が、問題はそのふたつの時間の「融合」の仕方である。たんに現在と過去を交互に語れば、過去は回想の中に押し込められてしまうわけだが、『虹ヶ原ホログラ フ』ではこのふたつの時間はひとつの円のように繋がっており、読む者はその中を行ったり来たりしながら不思議な物語体験を味わうことになる。円をつくるの は浅野さんの美しい絵で作品中に描き込まれた蝶で、蝶は過去と現在を自由に飛びまわり、読者をやすやすと瞬間移動させていく。これは文章や言葉ではなかな かできない芸当であり、どうしても覚えてしまう無力感はどうもこのあたりに由来している。 映画やコミックを観たり読んだりするとき自分はしみじみ小説の側の人間だと思う。すぐれた他のジャンルの作品に出合ったとき、嫉妬に近い感情を抱いてしまうことがその証拠であり、前述の無力感もその証明である。 さて小説の側に立つ人間として発言したい。実は小説は映画やコミックに比べより自由なジャンルなのである。なにせ文章と言葉があれば成立 する。しかし自由であるがゆえに表現に対するたゆまざる努力も必要である。自ら立ってある場所を疑うことからすべては始まる。映画やコミックに嫉妬や無力 感を感じなくなったらおしまいなのかもしれない。 ( I ) 2007年4月号 【35】昔から一人称の小説が好きでした。一人称の小説というのは、文字通り一人称で書かれた小説。英語で言えば「I」、フランス語ならば「Je」、とこ ろがわれらが母国語となると「私」や「僕」、さらにたどれば「小生」や「拙者」という一人称で書かれた小説さえ読んだ記憶があります。さて、日本語におけ る一人称の多様性についてはなかなか興味深いものもありますが、それについて考えるのは別の機会に譲るとして、ここでは一人称の小説についてです。 一人称の小説が好きなのは、それがどちらかというととてもストイックな小説の書き方であるという、きわめて個人的な感想に起因していま す。一人称で書かれた小説では、語り手である「私」あるいは「僕」は(もちろん「拙者」でも)、その作中で起こる出来事すべてに関わっていかなければいけ ない。つまり書き手側からすると、「私」あるいは「僕」が見聞きしたもの以外は登場させることができなくなるのです。 少し飛躍した言い方になるかもしれませんが、一人称の小説に登場する「私」やら「僕」は、物語に対して重大な責任を負っている。その潔 さ、そしてあえて困難な道を選ぶ書き手の側の禁欲的な決意がたいへん好ましく映るのです。表現への挑戦とでもいうのでしょうか、どうやらそういう企みのあ る小説に昔から心を惹かれてしまうようなのです。 最近読んだ小説のなかで、三人称で書き出しているのに、途中から一人称になっていくという素晴らしく知的な作業を施している作品に出合い ました。もちろん書き出しの三人称は、主人公の「僕」が伝え聞いた話というふうにあとで理解できるのですが、この三人称と一人称の混在は、この小説全編に わたるのです。読む側はそのつど視点の切り替えを強いられるわけですが、これが知らず知らずのうちに物語の核心へと読む者を誘ってくれる。そしていつしか 作者の企図した人間関係の不可思議な渦のなかにどっぷりと放り込まれている自分を発見するのです。 最近、レイモンド・チャンドラーの『The Long Goodbye』の新訳が出ました。翻訳は一人称小説の名手と自分で勝手に思っている村上春樹さん。旧訳では一行目の最初から「私」で始まるのに、新訳で は注意深くそれは伏せられ、数十行をへた後にはじめて「私」が登場します。前述の小説と同様に企みを感じさせられる一人称小説です。 ( I ) 2007年3月号 【34】最近、「小説の時間」というものが気になっている。たとえば主人公が自分の部屋に帰るとする。ドアを開け、まず目に入るのがテーブルの上に置かれ た飲みかけのコーヒーカップ。目を転じると、窓の外に見える葉を落とした銀杏の木。そして視線はまた部屋に戻り、壁に掛けられたカレンダー。21日に赤い 丸がつけられている。この速度をまどろっこしいものと受け止めるか、快いものと感じるか。 自分としては後者なのであるが、このところ小説を読んでいて、なかなか自分の生理にフィットした「時間」に出合うことが少ない。 小説の中に流れる時間、それは作者が書き込む描写の多寡で決まると思うのだが、かつて大学でフランスのヌーボー・ロマンを学んでいたとき (あくまでも「学んで」いたのだ)、その時間の進み具合に難渋した記憶がある。つまり顕微鏡で覗くようにひとりの人間の行動を描写する。もちろんそこでス トーリーは停滞し、時間軸さえもひっくり返ったりする。もとより如何に語るかへの問いかけから生まれた試みなので、そこでは楽しみより実験が優先していた のだが、そのときの読書体験はけっして快いといえるものではなかった。 ライトノベルといわれる、またはそれに近いものを読む機会が増えている。ライトノベルは絵のついている小説ですと、それに携わる現場の人 から聞かされたことがあるが、この定義はなかなか明快だと思う。ビジュアルがあるぶん、描写は少なくなる。さきほどの時間の概念でいえば、より速い時間が 物語の中を流れている。この時間を快いと感じるか、あわただしいと思うかは、もちろん読者しだいで、現にこのスピーディーさが活字を追う読者を近年増やし ているとも考えられる。 小説は昔から人間とは何か、その存在を突き詰めていくものだと「学んで」きている。この古めかしいテーゼに縛られた小説読みにとって、正 直に言えば最近のスピード化は少々しんどい。そこで描写されなかったものが、妙に気になったりしてしまう。もしかしたら自分が時代遅れになってしまってい るだけなのかもしれないが、いまさらモデルチェンジできる器用さも持ち合わせていない。そういえば、ドストエフスキーもフォークナーも書店の棚でとんと見 かけなくなった。さあ今日はひさしぶりに自分の書架からロブ・グリエの小説でも取り出して読んでみることにしようか。 ( I ) 2007年2月号 【33】昔から好き嫌いが激しくて、低く見積もっても出合う文章の半分以上は自分としては受け付けませんでした。とくに教科書に載っているテキストに至っ てはそのパーセンテージは急増し、ほとんどのものに最初から嫌悪を持って処しているありさまでした。当然そのような理由から、現代国語の試験などではいつ も難儀をしていた記憶が残っています。 この文章の意図を解釈せよ、作者の言わんとするところを要約せよ、こういう設問はなかでももっとも苦手で、白紙の答案用紙を前に呆然自失に陥っていた自分を思い出します。 あるとき、人生を決定する重要なメルクマールでもあった大学の入学試験で、後にノーベル賞を受賞する作家の最新作が問題文として出題され たことがありました。実はその小説は前年の暮れに書き下ろし上下巻で発表されたばかりのもので、ひそかにその作家の小説を愛読していた身としては、いち早 く読み終えてもいた作品でした。余談ですが、そういう世の中に出たばかりのホットな小説を、入試問題として出題する大学に妙なシンパシーを覚え、いっそう そのキャンパスで学ぶことに強い意欲を感じたことも憶えています。 さて、その入学試験は自らの現代国語の試験史上もっともよく解答を果たせたもののひとつになるわけですが、そのとき文章や小説における出合いというものの大切さについて、あらためて考えさせられることとなりました。 世の中の半分以上のものは好きではないという人間にとって、文章や小説との出合いはことのほか重要なものになります。ものごとの好悪とい うのはある意味その人間の美意識に支えられている部分が多いとは思うのですが、それをきちんと発揮しようとすればするほど出合いの機会は少なくなるような 気がします。 個人として文章や小説を楽しむのであればこれはこれでよいとは思うのですが、編集者として考えた場合、少し仕事の間口を狭くするようなこ とになるのではないかと心配しています。よってふだんから自分の美意識はいったん忘れ、許容のレンジを広く取り、文章や作品に接しようと考えています。自 省と寛容の毎日の中で、生来の好き嫌いをいつもよしよしとなだめつつ、とはいえ峻別する力だけは熱をもって鉄のように鍛えながら、今日も目の前の原稿の山 に取り組んでいます。でも最後に恃むのはやっぱり美意識でしょ。 ( I ) 2007年1月号 【32】編集者はよくファースト・リーダーと呼ばれます。文字通り最初の読者。作家によっては配偶者や親近者に書きあがった原稿をまず見せるという人もいますが、たいていの場合、編集者は作家にとっての最初の読者となります。 もちろん編集者は評論家でも、ましてや実作者でもないので、とりあえずは読者の立場から原稿に接します。面白いのか面白くないのか。わか りにくいところはないか。読みやすいかそれとも……。もちろん職業本能で誤字や脱字も探したりはしますが、初回に読むときはともかく一般の読者と変わらな い目線で原稿を読むことが多いのです。そして、それはまた、この仕事を続けていていちばん素敵だなと思える瞬間でもあるのです。 作家のファースト・リーダーになれる、これは編集者の特権です。この権利を生かして「きらら」の中でいくつかの作品にかかわっています が、たとえば連載がクライマックスに近づいてくると、この最初の読者もにわかに興奮してきます。とくに結末が思いもかけない場所に向かっていることがわ かってきたりすると、ボルテージはいやがうえにも高まります。駒沢敏器さんが執筆する「ボイジャーに伝えて」(P28〜)が、このところその興奮をとても 味わわせてくれています。 駒沢敏器さんはこの雑誌を始める前からファースト・リーダーに立候補したかった作家のひとりでした。アメリカ文学に造詣が深く、思いつい たように(気ままなのではなく寡作なのです)発表する短編小説は端正な文章でキレがよく、いつも胸にストンと落ちるものを感じさせてくれる佳品でした。機 会があれば長編を読んでみたいと思っていた書き手でもありました。さいわい連載をお引き受けいただき、半年間ほど何回も打ち合わせをし、始まってからも人 称の問題やら時制の流れなどかなり突っ込んだ話し合いもしました。いま思えば作品の全体像も知らず、そのようなやりとりをしていたことは汗顔の至りです。 連載開始から1年半がたち、「ボイジャーに伝えて」はいまクライマックスに向かいつつあります。この何回かは新しい原稿をもらうのにとて もわくわくし、ファースト・リーダーとしての興奮と特権を味わい尽くしています。やがて読者の方には1冊の本としてお届けすることもできると思いますが、 まずは盛り上がっている連載をお楽しみください。 ( I ) |
|||||||