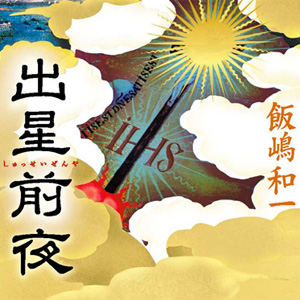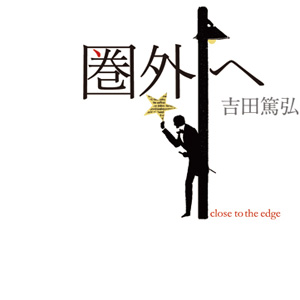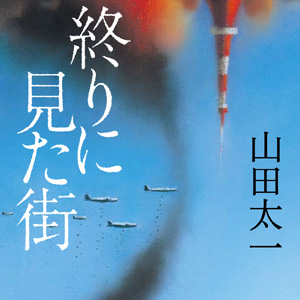| ホーム > きらら通信 > 2012年 |

|
|||||||
2012年12月号 【103】小説を読んでいて(というか、フィクション全般にいえることだが)、なんとなく疑問に思っていることがある。 なぜ、屋上ではドラマティックな出来事が起こるのか。なぜ、悪いことは玉突き事故のようにして負の連鎖を持ってしまうのか。なぜ、旅の最後は、海にたどり着くのか。なぜ、犯人逮捕の瞬間、「○○か」とか「○○だな」とかいった紋切型の口調になってしまうのか──。 これらの事は、おそらく現実に起こっている。 中高生は、屋上で告白したり、風に吹かれて髪を切ったり、8ミリ映画を回したりしているだろうし、ひとつの負の感情が芽生えたことで衝動的にとる 事後の行動は、だいたい坂道を転がるように制御不能なものになっていく。旅に出れば、だいたい行き止まりの場所として海が見えてきてしまうし、犯人逮捕の 瞬間も、いまだに新聞記事などを読むと、そんな風なやりとりがかわされていることが多いことがわかる。 でも、こういったフラグメンツは、現実に起こっているかもしれないから小説でもそう描かれているというよりも、なんとなく、「お約束事」のようにして、そうしたルールのようなものに則って書かれている面が強いように思う。 もっと大きなことでいえば、ミステリー、ホラー、恋愛、青春などといったジャンル小説を読むとき、読者は事前にそのモードに入って読む心構えを強いられているはずだ。 かように小説には、大げさにいえば、なにかある種のコードのようなものが大なり小なり張り巡らされているように思える(もともと、小説が書かれていることばそのものが、規則性をその属性として備えていることに端を発しているのかもしれないが)。 一方で、だからこそ、そうした「規制」からの少なからぬ逸脱というか脱線を自覚的に心がけている書き手の方もいると思うし、そもそも、そんな考えなど思いもよらぬところで何かに取りつかれたように一心不乱に執筆している方も出てくるように思う。 モーツァルトが交響曲「リンツ」を三日間で書いたという逸話を確認すべく、試しにスコアを写譜してみたところ、とてもその日数では追いつかなかっ たという話をある方から聞いたことがあるが、ジャンルは違いこそすれ、小説でも、そうした神がかった思いで出来上がる奇跡の一作のようなものもまた、実在 するように思う。 ( II ) 2012年11月号 【102】いきなりプロ野球の話で恐縮だが、先日、ある方から印象深いお話をうかがった。日本プロ野球界の至宝・王貞治氏と現役時代に何度も対戦したことの ある某球団の元投手の話だ。マウンド上で現役時代の王氏と対峙すると、とにかく他の打者にはない殺気のようなものを感じてしまい、畏怖する思いを打ち消す ように投げ続けていたという(そういえば、ある企画で、横綱白鵬と土俵上で向かい合った格闘家も、同じく殺意のようなものが相手から立ち上っていたとテレ ビで話していた)。王氏のこの特別感がどこからやってくるのかについて、その元投手は、こんな理由で納得していた。彼はもともと凄い打者なのに、一年で たった一日をのぞき毎日素振りを日に1500回義務づけていた。ちなみに、王氏クラスの選手でも真剣に素振りをその回数こなすためには、一日の半分以上の 時間バットを振っていなくてはならないようだ。要は、バットを持っている時間の方が、持っていない時間よりも長く、ある意味、バットが体の一部になってい るような状態に近かったことになる。そんな人が打席に入って、マウンド上の自分に正対してくるのだから、当然、殺気めいたものを感じないほうがおかしいの だ、と。 この話を聞いていて、天才が努力をすると、とんでもないことになる、というよく聞く話のバリエーションの一つだとは確かに思った。だけ ど、作家の方々も、自分の手をペンやパソコンのキーに触れさせている時間は、ひとによっては、触れていない時間より長いなんてことも起こりうるだろうし、 そこまで長時間の耐久レースをエンドレスに繰り返していなくても、ふとした時に、自作のことを考えていたりすることは少なくないのではないだろうか。少し 前に、この項でも触れた話だが、ある作家さんが執筆のために長年使用していたワードプロセッサーが破損した際、その型のものがすでに製造中止になっていた ため、執筆に支障が出てしまうのではないかと懸念しているという話を聞いたことがあった。この話なども、日々の反復のなかで、バットが身体の一部になって いくがごとく、ワープロのキーが自分の指先の延長のようなものとしてあるような感覚なのかもしれないと思う。そうなってくると、例えば漱石の自前の原稿用 紙が一行あたり19字×10行だったことも、そうした日々の反復の作業のなかで生まれてきたもののような気がしてきてしまうが、これはさすがに考えすぎだ ろうか。 ( II ) 2012年10月号 【101】少し前に、ある作家さんにリアリティと小説的リアリティは違う、という内容のことを聞いた。その時は、言葉のみをぽんと聞いただけだったので、なんとなくわかったような気になっていたら、こんなことが起こった。 自分の住んでいる家の二軒隣の家が、火事になったのだ。平日の昼間のことだ。かなりの勢いで火があがり、窓ガラスが激しく割れる音がす る。なぜかその日家にいた私は、思わず外に出た。時間帯のせいか、私をのぞいて出火した家の住人以外見当たらない。風の強い日で、自分の家の方角に煙が激 しく流れている。消防隊はまだ来ない。 圧倒的な煙を前に、恐らく呆けた表情を浮かべていたであろう私に、声がかかる。あのう、すみません。火元の家の住人が懇願する表情で見ている。自 分の家の車を駐車場から直ちに移動させてほしい、という内容だった。その家の主人は会社に行っていて奥さんしかいない。車を運転できる人間が他にいないの だ。早くしないと、車に引火して被害が拡大する可能性がある。とにかく時間がない。 ほとんど思考停止状態のまま、私はその家の車のキーを握り、運転席に向かっていた。エンジンをかける。その瞬間、およそこの状況に全く似つかわし くない音楽が、カーステレオから流れてきた。たぶん、TUBEかなんかの昔のヒット曲だったと思う。本当に危機的状況にあるとき、当たり前の話だが、スリ リングな効果音など脳内で鳴り響くこともなく、“よりによって”な曲が、こんな間抜けな感じでかかってしまったりするのだ。結局、私は、サイドブレーキを 解除し忘れたままアクセルを踏み続け、タイヤをガリガリいわせながら車を移動させて、事なきを得た(その直後に、消防車も到着して、出火した家は半焼です んだ)。 このことがあって、少し腑に落ちたことがある。リアルな感覚というのは、恐らくこうした状況を指すのだろうが、これが小説的なリアリティとなる と、話は少し異なってくる。要は、決して本当のことは起こらなくてもよく、本当らしい、本当に起こりそうなことが書かれていればよい、ということに恐らく はなるのだろう。だから、プロの書き手がここに書いたような場面を描写するような場合、いくらか、というか場合によっては原形を留めないくらいに事実を改 変させ、読者を首肯せしめてしまうのだと思う。まるで見てきたかのように書くことによって。 ( II ) 2012年9月号 【100】仕事柄、本やゲラを多く読む毎日だが、読むスピードが遅すぎて、困っている。例えば、以下の一文。 〈長い歳月が流れて銃殺隊の前に立つはめになったとき、恐らくアウレリャノ・ブエンディア大佐は、父親のお供をして初めて氷というものを見た、あの遠い日の午後を思いだしたにちがいない〉(ガブリエル・ガルシア=マルケス著「百年の孤独」鼓直訳、新潮社刊)。 有名な書き出しの部分だが、ざっと一読しただけでは、なかなか意味が判じ辛いのではないだろうか。いやいや、そこまで読みにくい、というほどでもない、というお方も、以下の一文はどうだろう。 〈川走、イブとアダム礼盃亭を過ぎ、く寝る岸辺から輪ん曲する湾へ、今も度失せぬ巡り路を媚行し、巡り戻るは栄地四囲委蛇たるホウス城とその周円〉(ジェイムズ・ジョイス著「フィネガンズ・ウェイク・」柳瀬尚紀訳、河出書房新社刊)。 正直、従来の読書の仕方を一度宙づりにされるような気にすらなる。 例に出した文章のようなものばかりではもちろんないが、いずれにせよ、文章を読むとき、私はどこか身構えるような気持ちになってしまう。それがなんなのか、よくわからなかったのだが、最近、架空の小説の文章を読んでいる夢を見て、気付いたことがある。 小説を読むとき、脳内で、音読をしているようなのだ。しかも、じつに野太く、低い声で。それは、およそ自分が常日頃発している声とは異なったもの だ。要するに、ふだん黙読しているとき、ほとんど意識野には上らせていなかったのだが、どうやら必ず微弱な音量で音読をしていて、しかも、その声が自分の ものとも思えない、ということになる。 考えるまでもなく、ラング(言葉)とパロール(発話)が表裏一体の関係である以上、こうしたことは自明の理なのだろうが、文章を読んで、意味を理 解しようとする時、私の場合、とにかくこの脳内の声が確実に邪魔になっているようだ。以来、脳内でバリトンを効かせた声や、普段通りの自分の声を思い浮か べながら読もうとしているのだが、なかなかうまくいかない。 * 今号で、弊誌「きらら」は、おかげさまを持ちまして、創刊100号を迎えることができました。今後も、ご愛読くださいますよう、どうかよろしくお願いいたします。 ( II ) 2012年8月号 【99】たいへんお恥ずかしい話をひとつ。先日、スマートフォンに不具合が生じて、電話帳などのデータが全部消えてしまう事態に陥ってしまった。バックアップデータも残っていない。PCとスマホを同期させるいう基本的なことができていなかったので、当然である。阿呆である。 そんな沈んだ気持ちである映画を見ていたら、事故で部分的に記憶を失ってしまった妻と愛を取り戻そうとする夫の物語だった。妻には夫と会 う前の記憶は残っていて、一緒にしてはいけないが、クラッシュしたあと、バックアップのデータが古すぎて、かなり前の設定に戻ってしまったような状態だ な、とへんなところで符牒が合った気がした。 すぐに小説の話と結びつけてしまうのは悪い癖なのかもしれないが、偶発的に生じた時間的空白に対しての向き合い方によって、人と人、もの、こととの関係性の強度が図らずも瞬時に測られてしまうような、そんな小説が読んでみたいとふと思った。 そんなことを考えていたら、妙なシンクロニシティは続くもので、今度は、ある作家さんから、90年代から使っていたパソコンのワード用ソフト的な もの(説明を聞いたが、あまりに自分の知識が乏しいため、このようにしか書くことができない)がついに壊れてしまい、途方に暮れてしまったという話を聞い た。 普通に考えると、この機に新しいものに替えれば済む話のような気がするが、その作家さん曰く、そのソフト的なものでないとしっくりこず、べつのも のではきちんと執筆できるかどうかもあやしいとのことだった。いわば、自分の手の延長というか、体の一部になってしまっていて、そこには、たんなる使い慣 れた何かを越えるものがあるようだ。そういえば、以前、ブックデザイナーの方で、同じように、かなり古い型のデスクトップ形のPCを十年以上使い続けてい て、これが壊れたらこの仕事を辞めるかもしれない、と真剣な顔をして話していたのを思い出した。 おそらく、この作家さんたちにとっては、マシンと人間のような距離はない状態なのだろう。愛すら感じる。ほとんどの人には、マシン(というかス マートフォン)との距離が当たり前にあって、それらを完全には信用していないところがあるから、バックアップデータを取りもするだろう。もちろん、私のよ うに、スマホをたんなる恒常的に便利な道具としてしか捉えない輩は、論外だ。少しだけ反省した。 ( II ) 2012年7月号 【98】パリに行くと(というほど、繰り返し何度も、という訳ではないが)必ず訪れる場所のひとつが、16区にあるマルモッタン美術館である。パッシー地 区の山の手な空気感漂う、緑多き場所に佇む個人の邸宅だったところで、モネが三十代前半で描いた「印象・日の出」など多数の氏の作品が所蔵されている。い つ行っても、割と空いていて、しかも、好きなモネの絵を惚けて見ていてもあまり周囲の邪魔にならない、お気に入りの場所だ。 そこにいると、だいたい同じことを考えているのだが、その一つが、モネが同じ構図の絵を繰り返し描いていたことに関してだ。光そのものに 執着した画家らしく、描いているものというか構図は同じでも、一枚として同じものはない。定点カメラを現場に設置していたら、恐ろしく長い時間、しかも、 時季を違えながら反復して描き続けているモネの動かざるその姿を捉えることができるのではないだろうか。その滞留時間は途方もなく、狂気の域に達している ようにすら思われる。 しかし、である。そんなことをいえば、作家も引けをとらないのではないだろうか。以前、ある作家の方の密着ドキュメンタリーの番組を見ていて吃驚 したのだが、執筆の部屋に設置されたカメラの早回しの映像に、ほぼ夜を徹して、机のまわりからほとんど動かないその姿が映し出されていた。 これは、もはや、人間椅子のような状態というべきだろう。書き手の業というか、宿痾のようなものなのかもしれない。もちろん、執筆のスタイルはま ちまちで、寝そべって書き続けたり、時間によって執筆する場所を適度に替えたり、場合によっては、お酒を嗜みながらの「酔拳」で、といった方もいらっしゃ る。執筆時間に関してもまちまちで、集中力の続く数時間のみ、しかも、脳がいちばん動く早朝起きてからの数時間のみという方まで多岐に及ぶ。なので、作家 の人間椅子化は、あくまで、一部の書き手に限られるという留保が付くことは断っておきたい。しかし、その行動半径の狭さと全く反比例するように、脳内の小 説世界は広大であり、外部からは捉えがたい。物心ついたころから、二体の人形を左右に持ち、それぞれに会話を延々続けさせて二時間近く平気で遊んでいたこ とが、作家としての起源かもしれない、などと平気で宣う方もおり、そんな方々を相手に仕事をすることは、今更ながら、恐れ多い行ないのような気すらしてし まうのだ。 ( II ) 2012年9月号 【97】ある書店さんから「編集者が薦める本」というお題で、POP(店頭によく掲げられている葉書大の宣伝文句等々を綴ったもの)を書くよう依頼されたことがあった。 そのとき挙げた本が、夏目漱石の「行人」で、そこに大きく「棺桶本」という言葉を用いたことを覚えている。なぜ、こんなことを書いたのか というと、墓場まで持っていきたいほど感銘を受けた本であることもさることながら、もう、死ぬまで再読するのを避けようという意思表示も含まれていた。 若い、とくに十代の頃、熱病に罹ったように読んだ一連の本にディープ・インパクトを受けてしまうことは多々あることだ。ところが、そうした本に限って、折節に再読してみると、いろんな意味で不可思議な思いに囚われることも少なくないように思う。 それが、本と読み手の関係性のおもしろいところではある。読んだ時期によって、また、一日のなかの短いレンジでも、「読み」の状況は可変する。そ して、本のほうも、読み手の知識や意識の状態に対応して、様々な相貌を表す(ロラン・バルトがいうところの「読みのレクシ」が、これに当たるように思 う)。 それはわかるのだが、いや、わかるからこそ、ものすごいものを読んだという、ただそれだけの「記憶」をそっと封印しておきたい気にもなったりす る。決して、再読したらつまらない本だった……と思うような状況を回避したいと言っている訳ではない。ただ、なんだか訳のわからないくらい感銘を受けた 「記憶」が穢されてしまうことが残念に思えてならないのだ。 「行人」に対して、「棺桶本」というフレーズが思い浮かんだのはそうした理由からで、十代の頃、一度読んだきり、あえて再読を自分に禁じている。 物語の最終章に出てくる、一郎という登場人物を克明にレポートする彼の友人Hからの長い長い手紙。ひとがマージナルな、ギリギリの状態に追い詰められたと き、精神に支障を来すか、宗教に救いを求めるか、自らの命を絶つしかない、といった言説(小説の書き手は、それ以外の第四の道として、小説を書いているよ うにも思う)。漱石という作家が、教科書レベルで漠然と理解していた「三四郎」や「坊っちゃん」「猫」などを書いている国民的ベストセラー作家の顔とは異 なる、ある種の狂気を孕んだ人だったという衝撃。うまく言い表せないが、そんないろんな「読後の思い」が渾然となって、いまも残っている。 ( II ) 2012年5月号 【96】こんなことを書いてしまうと、頭がどうかしているんじゃないかと思われてしまうかもしれないが、十代の頃、「当たり前の感覚」というものがいった いどこからやってくるのか、気になって仕方がないときがあった。それは、例えば、「コーラのCMを見ると、なぜ、さわやかな感じがするんだろう」といった 類のもので、当たり前に認識していることの根拠を突き止めたい気持ちから来ていたように思う。 明るい日差しのもと、コーラを手にした若い人たちが笑顔で戯れている様子がスローモーションで繰り広げられ、「さわやかテイスティ」とい うコピーが短い歌のフレーズのなかでさりげなく強調される。こうしたCMが際限なく反復され、さわやかさといえば、即座に黒褐色のあの液体を連想してしま うほど、「コーラ=さわやかさ」というイメージの刷り込みが完遂されていく。しかし、なぜ、笑顔の若い男女のスローモーションの映像がさわやかなものと結 びつくのか。そうしたことが知りたかった。 当たり前のこと、たとえば、世間一般で常識と呼ばれていることや、社会通念として広く受け入れられていることは、大前提として「だいたいそういう もの」といった塩梅で認識されているように思うが、その「だいたい」の感じは、なぜ、そうしたところに収まっているのか、本気で疑問を感じていたのだ。 ひょっとしたら、目に見えないところでそんな風に思わされてしまうような、巧妙な仕掛けが施してあるんじゃないのか。自分で無自覚に思ったり、感じたりし ていることの背景には、何か大きな力が作用しているんじゃないのか(病的レベルの妄想としかいいようがない)。 いまにして思うと、じつにどうでもいいようなことに妙にこだわる、ひまな学生生活を送っていた面倒くさい自分に説教のひとつでもしてやりたい気分だが、そんな時に、救いを求めるようにして手にした本が「共同幻想論」だった。 結果的に、自分がわからなくなっていたのは、「常識」というものの生成過程のほうに近く、ほぼ同じ時期に読んだ中村雄二郎著の「共通感覚論」のほ うが、参考にはなったように思う。だけど、思わぬかたちで手にした「共同幻想論」の発想のシャープさ、鮮やかさ、そして文章の美しさに心を奪われ、本来の 疑問などどうでもよくなってしまうほど惑溺するように読んだことだけは覚えている。吉本隆明氏逝去の報に触れ、そんな愚直な十代の頃の自分のリアルな感覚 が図らずも立ち上がってきて、赤面した。 ( II ) 2012年4月号 【95】ここ数年、春めいてきたこの時季になると、脳内ヘビーローテーションになってしまう曲がある。ブラームス最晩年の作とされるピアノ曲「6つのピア ノ小品 作品118より第二番間奏曲」である。ひとによって印象は異なるように思われるが、自分にとっては、なんとなく春を想起させる曲になってしまっている。そ れにしても、毎度毎度のことながら、なぜ、そう思ってしまうのだろう。いろいろと考えていたら、ある記憶に行き当たった。 少し前のことになるが、仕事で向かった先で、1日休暇をプラスして、鹿児島・奄美大島に足を延ばしたことがあった。奄美大島加計呂麻島呑 之浦には、島尾敏雄の文学碑が建てられていて、春のそぼふる雨のなか、夕景に彼の地を訪れた。若き日の島尾が特別攻撃隊指揮官として発進準備をしたまま終 戦を迎えた地として有名だが、碑のすぐそばでひっそりと佇んでいる小さな湾の様子は、自分にある種の衝撃を与えた。 普通、名所・旧跡の類は、当時の建立物などの褪色した様子などが、そのまま年月の経過を表していて、当然、時間的な距離のようなものを感じさせて くれる。ところが、彼の地には、当時と寸分違わない「自然」があるだけである。ちょうど、訪れている客人も他におらず、物静かな場所ということもあり、も し、ここが、終戦間際の時制であるといわれても、その風景だけ見れば、なんの反論すべき要素を見つけることもできなかった。 大仰な物言いだが、そんな風にある種、歴史的事象が眼前に迫ってくるような経験はしたことがなかったので、まるで、自分がタイムスリップしてしまったかのような錯覚にしばし陥った。そして、その道中、iPodで繰り返し聴いていた曲が、先のブラームスのピアノ曲だった。 よく耳にする話ではあるが、ある曲を聴くと、ワンセットのようにして同じ記憶が立ち上がってくることがある(村上春樹の「ノルウェイの森」のイン トロダクションのように)。ブラームスの118‐2に関しては、奄美大島の島尾敏雄の文学碑そばの風景と自分のなかでは固着してしまっているのだろう。音 楽を聴いて、ある特定の記憶が引っ張り出されるようなことは、むろん、小説を読んだり、映画を見たりしても起こりうるように思われる。その場合、小説や映 画とある特定の記憶が結びついているのだろうが、なぜ、そのようなかたちで固着化してしまうのかは自分にはよくわからない。つくづく記憶のメカニズムは不 思議なものである。 ( II ) 2012年3月号 【94】ある作家さんから、震災後に書道を始めた、という話を聞いた。普段、パソコンなどで原稿を打つことに慣れてしまっているが、電力の供給が断たれて しまったら元も子もない→蝋燭一本の状態で書けるのは、手書きの状態だけだ→しかし、自分の書く字があまり好きではないので、だんだん手書きの文字を書か なくなってしまっている→ひとまず、文字を書くことから始めて自分の書く字を好きになってみよう、という思考回路の果ての書道のようだ。 この文字を書いている時の感覚に関して、その作家さんが示唆に富むことを言っていた。だんだん同じ文字を書き続けていると、次第に何も考 えなくなっていき、その状態がさらに続くと、今度は、文字の形そのものが気になってくるというのだ。作家の方々に自著のサイン本を短い時間に大量に書いて もらうと、その間、呼吸を止めているような、本当に何も考えていない気分になるという話をよく聞く。我が身に置き換えてみても、例えば、宅配便の受け取り やクレジットカードでの支払いなどの際、自分の名前を書いているときは、確かに何も考えていない。そのようなある種の真空状態が、自分の名前を繰り返し書 き続けている間じゅう、ずっと続くのかと思うと何やら怖くなる。 しかし、問題なのは、この次の段階である。次第に文字の形が気になりだす、という状態は、もはや、その文字から受け取る意味が一旦留保され、ただ の形状としてのみ認識されていることを意味している。漱石も「門」のなかで、ずっと「今」という文字を飽かず眺めているうちに、その文字がそうではないよ うに見えてきた、といった旨のことを書いている(ゲシュタルト崩壊という奴である)。以前、自分も「美」という文字を百枚近く書で書いたことがあるが、だ んだん字が人や毛むくじゃらの虫や東京タワーに見えてきたりしてしまい、「美」という文字に対して黙契のようにして持っていたものがどんどんそぎ落とされ ていくような奇妙な感覚を味わった。 そんなことばかり考えていたら、先日、あるミュージシャンと別の作家さんの対談に立ち会った際、その作家の方が、こんなことを言っていた。小説は 音楽と違って不利である。その理由の一つとして、小説は読まれなければ、ただ紙に文字が羅列されているだけのものでしかない、と。ある人が小説を書き、そ れを誰かが読むということは、そんな風に考えていくと、今更ながら非常に不思議な事に思えてならない。 ( II ) 2012年2月号 【93】先日ある作家さんから、福島への取材を兼ねた道中を動画で収めたものを編集したドキュメント風のDVDを見させてもらった。ガイガーカウンターで 数値を測りながらドライブを続け、福島県南相馬市で、被災のため行く先の道がなくなったところで、東京へ引き返してくるという映像を収めたもので、最後、 道のなくなった場所のそばに流れている川にむかって、同乗者が途方に暮れながら石を投げるシーンが様々なことを喚起させ印象に残った。 しかし、この映像集のなかで私がいちばん心に留めた部分は、車窓から流れる風景そのものだった(被災地の風景それ自体に関しては、この項 の紙片に限りもあり、言及は避けたい)。ヴェンダースやジャームッシュのロードムービーを観ていても思うことだが、この車窓から流れる風景(映像の場合、 そこに流れる効果的な音楽も、自分にとっては重要になってくるのだが)が、殊の外、自分には何かを感じさせてくれる。 思考や感覚の流れと、風景の流れがシンクロするところに何かツボのようなものがあるのかも知れない。例えば、新幹線に乗って、ボーッと流れゆく風景を見ているだけでも、それまで漠然と考えていたことが、着地する方向へ向かっていったりするから不思議だ。 この何かが流れていく時間の連続性のようなものは、小説との相性もよいように思う。幸田文が「流れる」の巻末にある「著者のことば」のなかで、川 にさしかかると思わず見入ってしまったり、橋の手前でふと一瞬足が止まり、なにも考えずに橋を渡れない「不可思議なためらい」を持ち続けていて、この小説 を書く際の種になっていることを示唆している。「流れる」は、タイトルそのものもさることながら、着物姿の女性が腰に平均を持たせつつ、抗いながら畳に 徐々に、美しく崩れていく様をつぶさに描写していたり、ある種の流れというか動きそのものに意識をかなりはっきり向けた小説だ。 こうした一連の動きというか流れに「美しさ」を見いだして描写に熱量を加えている作家は多い。川端康成の「雪国」の最後、火事で女性が二階から落 ちていく瞬間を「人形じみた無抵抗さ、命の通っていない自由さで、生も死も休止したような」状態で「水平に」落下していったと描写している。これなども、 時間の流れというか、動きのようなものを小説のなかに美しく封じ込めようという企図が強く感じられる。 ( II ) 2012年1月号 【92】故・江藤淳氏の名著『漱石とその時代』には、漱石が『こころ』を朝日新聞に連載したときの状況が詳らかにされている。それによると、本来、この作 品は数編の短編集として連載を試行され、そのなかの一編として、まずは「先生の遺書」という標題で執筆が開始された。ところが、執筆していくうちに、次第 に短編で終わる長さではないことに思いを改め、一編の小説としてそのまま連載を続けることになった。そして、そろそろ終わりが見え始めた頃合いになったあ たりで、不測の事態が起こる。漱石の次に連載を予定していた志賀直哉が、書こうと思っていたものを一度留保したい意向を示してきたのだ。その結果、他の執 筆者を探す一方(漱石は、朝日新聞社との契約により、執筆者を探すという任も負っていた)、『こころ』の最終章、すなわち「先生と遺書」の章を出来うる限 り、引き延ばす羽目に陥ったのだ。こうした新聞社側というか、執筆を依頼する側の事情により、作品の構成にまで大きな変更点が加えられることになったので ある。 この記述に触れた際は大いに吃驚したものだが、編集者という我が身に置き換えてみると、似たようなことがいまも起きていることに気づく。 ここのところ、連作短編集を多く目にするようになって久しい。こうした作品は、掲載誌に毎月か隔月で連載、もしくは、数ヶ月に一度の掲載、というかたちを 取りながら、一話完結でお話が進んでいくという基本構造を持っている。これなど、間違いなく今の掲載誌の「事情」(もちろん、毎月の連載がスケジュール的 に厳しい場合など、著者側の「事情」も多分に含まれている場合もあるだろうが)による部分が多いように思われる。 こうして考えていくと、カフカのように、生前は数作品しか世に出ていなかった作家が、友人の編集者の手によって、二十世紀を代表する作家として認 知されるまでに至る場合もあり、小説がその全貌を現し、世に出るまでの過程における、偶発性も含めた外的要因のようなものが、時に大きな意味合いを持って しまうことは否定できない。 「小説は生き物である」といった言説をよく耳にするが、作者内部での純然たる創作活動のみならず、その外部との、あるいは、その時代・風潮との「化学反応」のようなものとして立ち上がるという意味合いもそこには含まれているのだろう。 ( II ) |
|||||||