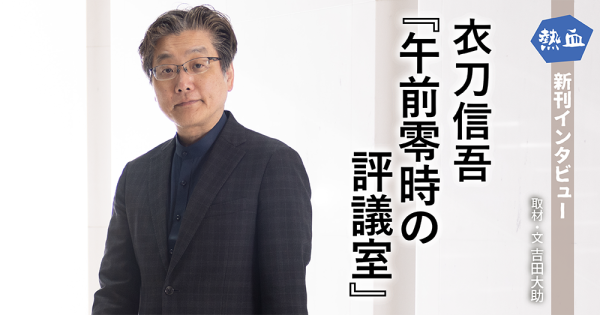衣刀信吾『午前零時の評議室』◆熱血新刊インタビュー◆
書き上げてからが始まり
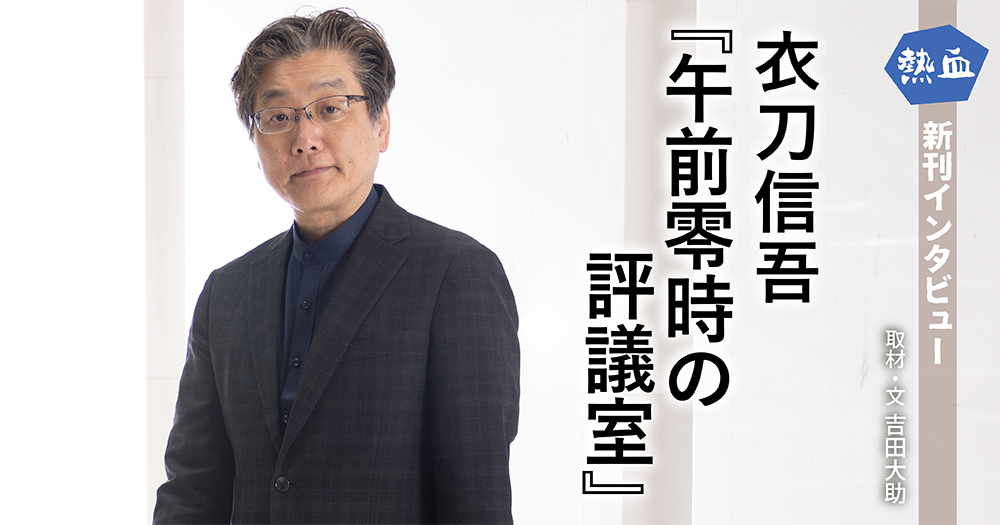
オビに銘打たれた文言は、「法廷×デスゲーム×本格ミステリ」。いったいどういうことなんだと驚くが、読んでみれば、その言葉通りであったことにさらに驚く。
着想の出発点は、映画だったという。
「僕は小説を読んだり映画を観ている時に、お話を思いつくことが多いんです。この作品は、『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』(2019年)という映画を観ていて、翻訳家たちを地下に閉じ込めるという話があるなら、裁判員でもアリなんじゃないかな、と。裁判員に選ばれましたという手紙を受け取った男女が、評議室に監禁されるところからスタートする話はどうだろうと考えました」
大学3年生の神山実帆は、裁判員裁判の補充裁判員に選ばれたという手紙に記されていた、事前オリエンテーションへの出席を決める。神奈川の田舎にあるビルに赴くと、そこには自分と同じように選ばれた6人の裁判員が集まっていた。この会を主催した元邑太朗判事は、7人を評議室に迎え、外からドアの鍵をかけた。外にいる元邑が操作していると思われるAI音声が、恐ろしいルールを告げる。被告人・赤根菜々絵が、深夜の公園で元恋人と口論ののち殺害した疑いが持たれる裁判の評議を、午前零時までに終了させろ。指紋認証システムが搭載された各人のパソコンから、有罪か無罪かいずれかの同じボタンを、全員で押せ。「タイムリミットは文字どおり、最終時刻です……その時間までに正解のボタンが押されない場合、もしくは時間前でも間違った回答が押された場合には、この部屋は自動的に爆破されます」。不正解は死、となるデスゲームの開幕だ。
「零時までというタイムリミットがあった方がキャッチーだし、死ぬかもしれないと設定があった方が単純にワクワクしますよね(笑)。この設定だけでもなかなか面白いし、最初に考えたオチでもそれなりに驚いてもらえると思ったんです。ただ、構想を進めていくうちにまだまだ足りない、もっと膨らまさなきゃ、となっていきました。〝そのネタがダメでも、こっちがありますよ〟という保険をかけるうちに、ネタが盛り盛りになっていったんです」
被告人・赤根菜々絵の担当弁護士は、刑事事件専門弁護士として名を馳せる羽水圭だ。評議室での議論が描かれるパートの合間合間に、羽水と部下の佐藤孝信弁護士が事件について独自の捜査を行う姿が挿入されていく。さらに「インタールード」と題した断章では、赤根菜々絵本人の視点から裁判当日の様子が描かれていく。
「〝じゃあ、評議室での議論はどうなったの?〟という謎も生まれますし、法廷のシーンがなければこの話はつまらなくなってしまうんじゃないかな、と。被告人の顔がしっかり見えてくるような場面がなければ、7人の裁判官が命懸けで臨んだ評議室での議論が、机上の空論で終わってしまうと思ったんです」
結末部のどんでん返しはもちろん、伏線の回収に次ぐ回収が鮮やかだ。
「僕の場合、いびつでもいいので最後まで書き上げてからが本当の始まりなんです。論理的矛盾を一つ一つ潰していきながら、どこにどうやって伏線を入れていこうかなと、延々と考えていくんですね。特にこの作品は、これまでで一番、そこの作業に時間をかけました。これがダメなら、デビューは難しいかもしれないと思っていました」
思考や行動によって、人を書く
実は、弁護士でもある衣刀は去る3月31日まで1年間にわたり、日本弁護士連合会の副会長を務めていた。
「日本ミステリー文学大賞新人賞に投稿するのは3回目で、過去2回(※2022年、2023年)とも最終候補になっていました。三度目の正直と言いますか、次が勝負だなと思っていたんです。そんな時に、副会長をやってくれないかという打診が来たので、困ったな、と。そちらの仕事が忙しいことは知っていたので、小説が書けなくなることは明らかだったんです」
勝負をかけるうえでおこなったことの一つは、過去2回の選評を読み込むことだった。
「小説を書いていることは家族にも誰にも言っていなかったので、読んでくれる人が周りにいませんでした。選考委員の方が書かれた内容だけが頼りで、そこを直したら良くなるのかな、と藁にもすがる思いだったんです。例えば、辻村深月さんからは女性の描き方に関して弱い部分がある、薬丸岳さんからは躍動感がないというご指摘をいただいて、その反省が今回の作品に生かされていると思います」
特に印象に残っているのは、2回目の最終候補となった際の湊かなえの選評だったという。〈人物描写は男女ともに、体型等の外見を強調するのではなく、内面から出る言葉や行動で表現した方が作品により立体感が出るはずです。ぜひ、新しい作品を読ませてください〉。
「小説を長年書かれている方にとっては常識なのかもしれないんですが、湊さんのご指摘には目を開かされる感覚がありました。私が書くものは、ひとえに説明的だったんです。その人が何を考え、どういう行動をして、起きたことに対してどういうふうに思ったかによって、人を書く。以前までのものよりも、そこを意識して書いていたつもりです」
社会的に訴えたいことや深い感動よりも
ミステリー小説を読むことは昔から好きだったそうだ。弁護士になってすぐの30歳の時には、神奈川県弁護士会で先輩だった同業者の藤村耕造が横溝正史賞を受賞(第15回佳作「盟約の砦」)したことに刺激を受け、自分でも小説を書いてみたことがあった。しかし、当時は書き終えることもできなかった。コロナ禍になって時間ができたことをきっかけに、再び筆を執ったのは57歳の時だ。
「弁護士として過ごしてきた年月が味方をしてくれたと思っています。弁護士は、特に刑事事件をやれば日常的に、犯罪を犯してしまった人と直接会うことになります。何かしらの犯罪を題材にすることが多いミステリーのお話を書くうえで、弁護士としての経験が生かされたのは間違いないです。同業者の雑談の中で、依頼人から〝前にも同じことで捕まったんです〟と言われた話を聞いたことがあります。被告人が〝無罪になりました〟と言うので、〝じゃあ、やっていなかったんですか?〟と聞くと、〝いや、やっていたんです〟と。表には出ないだけで稀にそういうことはあるんだろうなと思ったところから、『午前零時の評議室』の中で重要なエピソードとなる、13年前の事件のあらましを作っていったんです」
本編終了後の、あとがきの一文が感動的だった。〈本書を手にした若い読者の皆様が、弁護士になると、創作ができるほど、刺激的で生き生きとした人生を送れるかも……と思ってくださり、弁護士を目指していただけたら、作者として望外の喜びです〉。
「〝法律は温かいもののはずだ〟といった登場人物たちのセリフには、意識していたわけではなかったんですが、自分が仕事の中で考えてきたことが入っていたのかもしれません。テレビとかだと弁護士さんは 〝異議あり!〟とかやっているから、口で論破する仕事というイメージが強すぎると思うんですが、実態は違うんですよ。裁判当日に裁判官に提出する、依頼人の言い分をまとめた陳述書を書くことが仕事の大部分を占めるんです。陳述書を作成するうえでは、相手の話をいかに分かりやすく文章にするか、いかに緻密な文章で法律構成ができるかが大事になってくる。それは、小説を書く訓練にもなっていたかもしれないと思うんです」
わかりやすく、ロジカルに、緻密に。『午前零時の評議室』が兼ね備えた美点そのものだ。しかし、ある一点で陳述書とは大きく異なる点がある。それは──面白い!
「今後も、リーガルものを書いていくことになると思っています。社会的に訴えたいことであるとか、深い感動なども必要かもしれないんですが、ついページをめくってしまうような面白さを追求したいんです。それからやっぱり、読んでくれた方を驚かせたい。今回のお話も、途中までは〝あぁ、やっぱりね〟とバレる可能性はあると思うんですよ。ただ、その後の展開は誰も分からないだろう、みんな驚くだろうという自信があるんです」
大学生の実帆に届いた裁判員選任の案内状。記載された被告人の名前に聞き覚えがあったが、それはアルバイト先の羽水弁護士事務所が担当する事件だった。事前オリエンテーションとして担当判事に呼び出された裁判員たちに、通常とは違う異例の事態が訪れる。一方、弁護士の羽水は検察のストーリーに疑問を抱き、見逃された謎に着目する。被害者の靴下が片方だけ持ち去られたのはなぜか? それを元に事件の洗い直しを始めるが……。現役弁護士が仕掛ける伏線の数々……あなたはいくつ見破れる? 法廷×デスゲーム×本格ミステリ! 第28回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作。
衣刀信吾(いとう・しんご)
1964年3月16日、東京都中野区生まれ。早稲田大学法学部卒。弁護士(弁護士法人相模原法律事務所代表)。令和元年度、神奈川県弁護士会会長を務める。令和6年度、日本弁護士連合会副会長。初投稿から3年連続で最終候補に選出され、2024年、本作で第28回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞しデビュー。