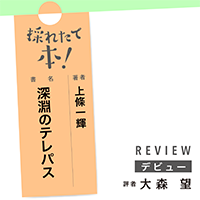上條一輝さん『ポルターガイストの囚人』*PickUPインタビュー*

「怖い」だけじゃない
大評判のホラーエンタメ、第2弾がいよいよ刊行に
構成が巧みで、怖くて面白くて、展開がダイナミック。昨年創元ホラー長編賞を受賞した上條一輝さんの『深淵のテレパス』は、デビュー作ながらホラーエンタメとしての高い完成度で話題をさらい、「ベストホラー2024」(国内部門)と『このホラーがすごい!2025年版』(国内編)で1位を獲得した。その待望のシリーズ第2弾、『ポルターガイストの囚人』が刊行されたばかりだ。
「第1作で超心理学をテーマにしたので、第2作も自然とその流れになりました。超心理学の研究テーマは大きく分けてふたつあります。ひとつはESPで、いわゆるテレパシーや未来予知のことです。もうひとつはPKといって、サイコキネシスのことですね。1作目でESPを扱ったので、2作目でPKを扱うことは早い段階で決まりました。ただ、そこからたいへん苦労しまして……。作ったプロットを自分で全ボツにする、ということを3回くらい繰り返し、そこからさらに紆余曲折を経てなんとか形にしました」
つまりは妥協せずにとことん取り組んで完成させたのが、本作なのだ。
怪奇現象を単なる現象として検証する二人組
父親が施設に入居したため実家の古い一軒家に戻り、一人で暮らし始めた俳優の東城。18歳まで暮らした家だけに勝手知ったるはずだったが、なにかがおかしい。誰もいない部屋で物音がし、襖が勝手に開き、こけしがひとりでに動き、姿見が回転する──。奇妙な現象が続き弱りきった彼が調査を依頼したのが、前作にも登場した動画チャンネル「あしや超常現象調査」の二人組だ。映画宣伝会社に勤める芦屋晴子と部下の越野草太が配信するこのチャンネルのスタンスは、ちょっと変わっている。不気味な現象をオカルトとも非オカルトとも決めつけず、ただ純粋に現象だけを検証し、合理的な解決を試みているのである。
「僕自身の超常現象に対するスタンスが反映されています。僕もずっとホラーは好きでしたし興味はあったんです。それで超常現象を解き明かすというコンセプトの書籍をいろいろ読みましたが、かなり極端に二分されているなと感じて。幽霊は存在するという前提で、それこそ自分には霊感があると言い切っている人か、超常現象を真っ向から否定して、あらゆることを科学的に説明しようとする人に分かれるんです。超常現象があるのかないのか分からない、という前提の人は珍しいんだと気付きました。それで、自分がホラー小説を書く時に、そのスタンスを登場人物に託せば新規性が出るのではないかと思いました」

晴子たちが、怪奇現象や超能力はあったとしても「しょぼい」と考えているところも、ホラー小説としてはユニークだ。
「超心理学の書籍にもいろいろ当たってみたんです。現在までの研究によるとどうも超能力はあるらしいけれど、ただ、本当にしょぼいものはしょぼいんですよね(笑)。作中でも実際の実験データに近い数字を出して説明しているんですけれど、たとえば一般の人間がやると当たる確率が4分の1の実験が、超能力者がやると3分の1くらいになる、という程度の違いしかないんです」
東城家のポルターガイスト現象も、独自の方法で対処し収束しうる程度のものかと思えた。しかしほどなく東城が姿を消し、今度は晴子や越野が奇妙な現象に見舞われるようになり──。
物語は越野、そして東城の視点で進んでいく。一連の出来事はオカルトなのか、人為的なものなのか、読者も翻弄されてしまう。
苦労したホラーとエンタメのバランス
晴子たちには協力者がいる。超現実主義でオカルトを信じない「探偵」の倉元と、自身も超能力者であるオカルトマニアの犬井。前作でもおなじみの2人である。
「倉元と犬井は再び登場させるつもりでした。前作を読んだ方々にも指摘されていますけれど、小野不由美さんの『ゴーストハント』シリーズのように、それぞれが自分の特技を活かして事件を解決していく、というイメージがありました。それと、倉元と犬井の2人が幽霊否定派と肯定派という極端な立場をとっているからこそ、主人公2人が中間の立場でいられるので、その点からも彼らは必要でした」
今作では新たに、倉元の助手が仲間に加わる。前作を読んでいる人なら、おやっと思うはずだ。
「『深淵のテレパス』を改稿している時に、登場人物の一人を続篇で倉元の助手にしたらどうかと編集者さんに提案したんです。そうしたら即座に〝やりましょう〟と言ってもらえたので、第1作に伏線として倉本が助手に逃げられた、ということをちょっとだけ書き加えました」

彼らは実際の超心理学の研究結果やオカルト周辺の言説や理論を繰り出しながら、今回のポルターガイストを検証していく。そのやりとりが楽しく、そこから起きる出来事は実にスリリング。
「1作目を書く時から、怖いだけではなく、読者さんにエンタメとして楽しい、面白い、と感じてほしいと思っていました。私も、たとえば映画なら『バトルシップ』や『トランスフォーマー』のような、エンタメに極振りした作品が好きなんです。なので、延々と恐怖が持続するようなホラー小説も受け手としては好きなんですけれど、作り手としてはエンタメ性に重心を置くつもりでした。ただ、面白くすればするほど怖さが損なわれてしまうんですよね。1作目でエンタメに振り切ってしまったことで、2作目はかなり苦労しました」
と上條さんはいうが、本作も十二分に怖い。読者を震撼させる工夫は、どのように考えたのか。
「文字情報だけでどこまで怖がってもらうかは、すごく考えました。それで、裏側に介在する悪意を読ませる、というのがいいんじゃないかなと思いつきまして。たとえば、誰も触れていないのに反対側を向いていた姿見が回転してこちら側を向こうとしている場合、鏡が勝手に動いていることよりも、誰かがそれを動かして鏡に映る何かを見せようとしていることのほうが怖いと思うんです。現象の裏側にある意思、みたいなものはかなり意識して作りました」

もうひとつ意識したのは、リアリティラインだという。
「最近のYouTube などにある心霊ドキュメンタリーでは、実際に幽霊が現れることはほとんどなくて、足音や声だけ、といったものが多い。だから視聴者も受け入れられるのかなと思います。本当に人間の形をした幽霊が出てきたら、たぶん〝これは作りものだろう〟と白けてしまう。音だけくらいのバランスのほうが逆にリアルかなと考えました。だからポルターガイストも、実際の研究論文の中で確認されている程度の現象を書いて、リアリティラインを大きく損なわないように気を付けました。それに、このシリーズはミステリー的な要素もあって、最終的に晴子たちが謎を解き明かさないといけない。となると、ある程度現象から遡って原因を特定できるようにしなきゃいけないんですよね。それもあり、現実のリアリティラインからとびぬけ過ぎないようにしました」
とはいえ、終盤に話は啞然とするほどスケールが広がっていく。「そこは勇気をもって踏み越えたところではありました(笑)」とのこと。前作に続き、度肝を抜く展開が待っている。
一念発起して書いた作品でデビュー
すでに確かな筆力を感じさせる上條さん。執筆&制作経験の遍歴を聞いてみた。
「昔から実話系の怪談やホラーも好きでしたが、中学生の頃は北方謙三さんの小説が好きで、自分で時代物を書いてみたりしていました。大学生の時は劇団に入っていて、そこは企画が通れば誰でも脚本を書いて演出できたんです。1回だけ企画が通って上演したのが、ミステリーの皮をかぶったハリウッド的な派手派手な芝居でした」
社会人になってから、芸能事務所の依頼を受けて YouTube で短篇ドラマを制作したことも。また、現在も会社勤務の傍ら、加味條名義で webメディア〈オモコロ〉の記者としても活動している。
「〈オモコロ〉で書き始めたのは、自由に面白いものを作れる環境に憧れたからでした。ただ、あのフォーマットでホラー系の記事を書いても面白そうだなと思っていたんです。新人なので攻めた企画を出せずにいた頃に雨穴さんが〈オモコロ〉で『変な家』を発表されて、バズりまして。編集部的にもホラーいけるぞ、という空気になったので、すかさず企画を出して、『おかんぎょさま』というホラー系の記事を書いたら、結構好意的な感想をもらえたんです。そんな時、東京創元社さんがホラー長編賞を1回だけ開催すると知りました。1回だけだし、しかも選考委員が、私が好きな澤村伊智さんだったので、今やるしかないと思って書いたのが、『深淵のテレパス』でした」

ちなみに当初単発の予定だった創元ホラー長編賞は、『深淵のテレパス』のヒットを受け、第2回の開催が決定している。では、今後どんな小説を書いていきたいのか。
「ホラーでデビューさせていただきましたので、まずは憶えてもらうという意味でも、しばらくホラー小説を書いていくつもりです。ただ、ありがたいことにホラー以外のオファーもいただいているので、ゆくゆくはちょっと手を広げるかもしれないです」
上條一輝(かみじょう・かずき)
1992年長野県生まれ。早稲田大学卒。現在は会社員の傍ら、webメディア〈オモコロ〉にて加味條名義でライターとして活動している。2024年、『深淵のテレパス』(応募時タイトル「パラ・サイコ」)で創元ホラー長編賞を受賞し作家デビュー。