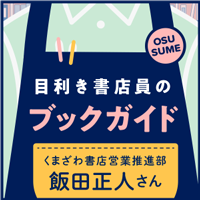金子玲介『死んだ山田と教室』◆熱血新刊インタビュー◆
生きているか死んでいるか分からないからこそ

プロローグに当たる2ページで、タイトルロールである二年E組「山田」の死が確定する。二学期が始まる少し前に、飲酒運転の車に轢かれたという。通夜に参列した生徒たちは口々に嘆く。〈山田のおかげで、男子校まじ最高だなって──〉〈もっともっと山田くんと話したかったです──〉。金髪がトレードマークだった山田は、みんなに愛される人気者だった。
二学期の始業日、教室の沈痛な空気を変えるために担任の花浦先生は「席替えでもするか」と提案する。しかし、クラスメイトたちは静まり返ったままだ。すると、〈男子校の席替えがこの世で最も意味のないものだとは言え、誰か返事しなきゃ花浦先生かわいそうだろ〉。黒板の上に設置された四角いスピーカーから流れてきたツッコミは、山田の声だった。ギョッとしたのは声の主も同じだ。〈つーか声しか聞こえねぇ。どうなってんすか? 俺、今〉。死んだ山田が声だけの存在となって、二年E組の教室のスピーカーに憑依したのだ。
そこからホラーやミステリーな展開が始まるかと言えば、事態はそうは進まない。
「ミステリーを書こうと意識して始まった作品なので、人が死ぬことは大前提でした。でも、人が死ぬとふざけられないじゃないですか。どうしても会話が重くなってしまう。人が死んでいるんだけれども軽快な会話が続けられるような状況はないかな……というところから、死んだクラスメイトが教室のスピーカーに憑依して喋り続ける、という設定を思いついたんです」
これって一体どういう状況なのと探っているうちに、二年E組の面々がわりとすんなり死んだ山田の存在を受け入れてしまう展開がまず、楽しい。
「戸惑う時間が長いと、スタートダッシュが切れないなと思ったんです。戸惑いつつも状況を受け入れることに対してあまり違和感がないように、死んだ山田は根っからの人気者という設定にして、また山田と喋れることが楽しいという方向に教室の気分を持っていきました。そこで山田に『最強の配置』を発表させることで、二年E組にはこういう子達がいるんですよと読者さんに紹介しつつ、山田はこのクラスのことが本当に好きなんだということも伝えたかったんです」
前半は一幕ものの会話劇をエチュードで作った
全10話からなる物語は、1話ごとに新たなシチュエーションやお題が登場し、声だけになった山田と二年E組のクラスメイトたちとのやり取りが描かれていく。「第一話 死んだ山田と席替え」に始まり、「第二話 死んだ山田と夕焼け」「第三話 死んだ山田とスクープ」「第四話 死んだ山田とカフェ」「第五話 死んだ山田と誕生日」……。
「コントで言えばジャルジャル、ゾフィー、かが屋など、演劇だと本谷有希子さん、ハイバイ、ロロなどが好きです。この作品も、特に前半は一幕ものの会話劇になっていると思っています。作り方も、演劇で言うエチュード(※演出家に与えられた簡単な設定のもとで俳優たちが行う即興劇)に近かったのかもしれません。二年E組全員の簡単なキャラ設定を事前に決めておいて、お題をもとにみんなで喋らせながら書いていく。例えば〝死んだ山田に誕生日プレゼントを贈るとしたら何にする?〟というお題で大喜利をさせてみたら、〝耳は生きているんだよな。じゃあ録音した何かを聞かせるか〟と考えるやつが出てきて、ああいう展開になりました」
舞台を男子校としたからこそ、さらなる笑いが招き入れられることとなった。例えば、死んだ山田の存在を二年E組と花浦先生だけの秘密とするために、山田に話しかける際は合い言葉を口にしてから会話を始めるというルールができた時。討議のすえに決定した合い言葉は「おちんちん体操第二」だったが、当初は「おちんちん体操」に決まりかけていた。医学部志望でクラス一の秀才・高見沢が「男子校なんだから、他のクラスの人がなんとなく『おちんちん体操』と口にしてしまう可能性もなくはないのでは?」と指摘して、語尾に「第二」が追加されることになった……というエピソードの一部始終が、バカバカしくも妙にリアルだ。
「あの年頃の男子ってバカだから、『おちんちん体操』までは本当に言いそうだぞという判断でした(笑)」
男子だけしかいない教室であれば、異性の目を気にしてかっこつけたりする必要はなく、等身大の自分のままでいられるという面もある。
「僕自身も10代の頃、男子しかいない教室に6年間通っていたんです。その時に感じた楽しさを、いつか小説で書いてみたいとずっと思っていました。ただ、男子校って危うい題材なんですよね。女性に無遠慮な視線や言葉を投げがちな空間ですし、ホモソーシャル(=男性中心社会を醸成しがちな男性間の閉鎖的な結びつき)な価値観は社会にとって有害で批判されるべき対象であると僕も思っています。できる限りそういった要素を脱臭したうえで、男子校のわちゃわちゃ感、あっけらかんとした感じを書けたらな、と。男子校時代から約10年の隔たりを挟んで、あの空間の良さも悪さも客観的に見えてきたからこそ、いいバランスで書くことができたんじゃないかと思っています」
二年E組が解体してから本当のこの物語が始まる
とにかく、楽しい。10代男子特有の明るさと、そして優しさが、不条理状況を元にしたシチュエーションコメディの内側で弾け飛んでいる。その一方で、自分の声を聞く者がいなくなった夜の教室で、死んだ山田がラジオ番組の真似事をしているシーンでは、一言一言に得も言われぬ寂しさが匂い立つ。〈メールを送ってくれたリスナーの中から、抽選で五名に、番組ステッカープレゼントします。デザインはリスナーのみんなの心に浮かんでるそれね〉。
「会話劇だけで進めていくとちょっと飽きてしまうかなと思い、合間合間に山田のモノローグを挟んで味を変えてみました。山田は死んでいるんだ、孤独なんだということを通奏低音的に響かせておきたかった。孤独だからこそ、山田はみんなと喋れることが嬉しいということを伝えておきたかったんです」
物語が大きく色を変えるのは、総ページ数のほぼ真ん中、「第六話 死んだ山田と最終回」の終盤からだ。不穏なムードがぶわっと溢れ出していく。
「本当の『死んだ山田と教室』という物語は、二年E組のみんなが三年生に進級してから始まるなと思っていました。みんなとバカ話がしたいから山田は蘇ったんだ、二年E組が解体されたらきっと消えるんだとクラスメイトたちも本人も思っていたのに、消えずに教室に存在し続けるんです。それでも最初は喋りに来てくれるクラスメイトがいっぱいいるんだけれど、時間が経つにつれて徐々に減っていく。後半では山田の語りを増やして、山田が感じている孤独や寂しさについて書いていきました」
メフィスト賞に応募する前までは長らく純文学の賞に応募し、書き継いできたテーマがそこで接続された。
「人の生き死にについて、自分なりにずっと考えてきました。この作品でも、生きているのか死んでいるのか分からない山田の存在を通して、そこを掘っていきたいと思ったんです。生きているか死んでいるか分からないからこそ、じゃあ生きているってどういう状態なのか、死ぬってどういうことなのか、と」
スピーカーに憑依し声だけの存在となった山田が、他の状況や存在のメタファーであると考えられる点にも、文学の脈動が感じられる。例えば、故人が生前に残したデータを用いてデジタル上にその存在を復活させる「故人AI」。
「AIになった人って、生きているのか死んでいるのか分からないじゃないですか。そういう存在がどうやって終わっていくのかについて気になっていた感覚が、この作品の中にも入ってきているのかなと思います」
ならば、山田はどうなるのか? 本作が冒頭からきっちり伏線が張られたミステリーであったと明かされるのと同時に、「青春の終わり」を描く青春小説としての濃度が一気に高まる最終話は、感動の一言だ。ラストシーンは、一人きりでは辿り着けなかったものだったと言う。
「受賞後に編集者さんたちと何度も打ち合わせを重ねる中で、もっと深くいけるんじゃないか、もっと読者に伝わるように書き直そうということになり、今のラストにがらっと書き換えたんです。編集者さんたちがこの作品の可能性を探っていってくれたことが、すごく嬉しかったんですよね。本になることで、今度は読者さんから自分が気づかなかったこの作品の可能性を教えてもらえるかもしれません。そのことが今、ものすごく楽しみなんです」
夏休みが終わる直前、山田が死んだ。飲酒運転の車に轢かれたらしい。山田は勉強が出来て、面白くて、誰にでも優しい、二年E組の人気者だった。二学期初日の教室。悲しみに沈むクラスを元気づけようと担任の花浦が席替えを提案したタイミングで教室のスピーカーから山田の声が聞こえてきた──。教室は騒然となった。山田の魂はどうやらスピーカーに憑依してしまったらしい。〈俺、二年E組が大好きなんで〉。声だけになった山田と、二Eの仲間たちの不思議な日々がはじまった──。
金子玲介(かねこ・れいすけ)
1993年神奈川県生まれ。慶應義塾大学卒業。『死んだ山田と教室』で第65回メフィスト賞受賞。