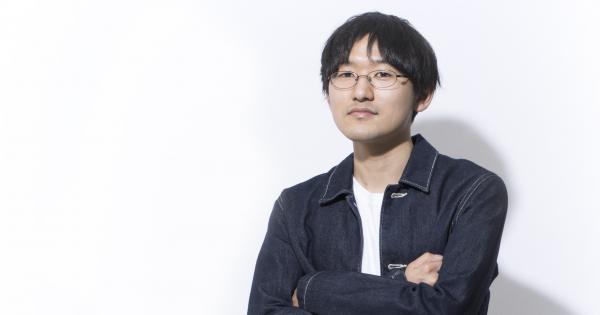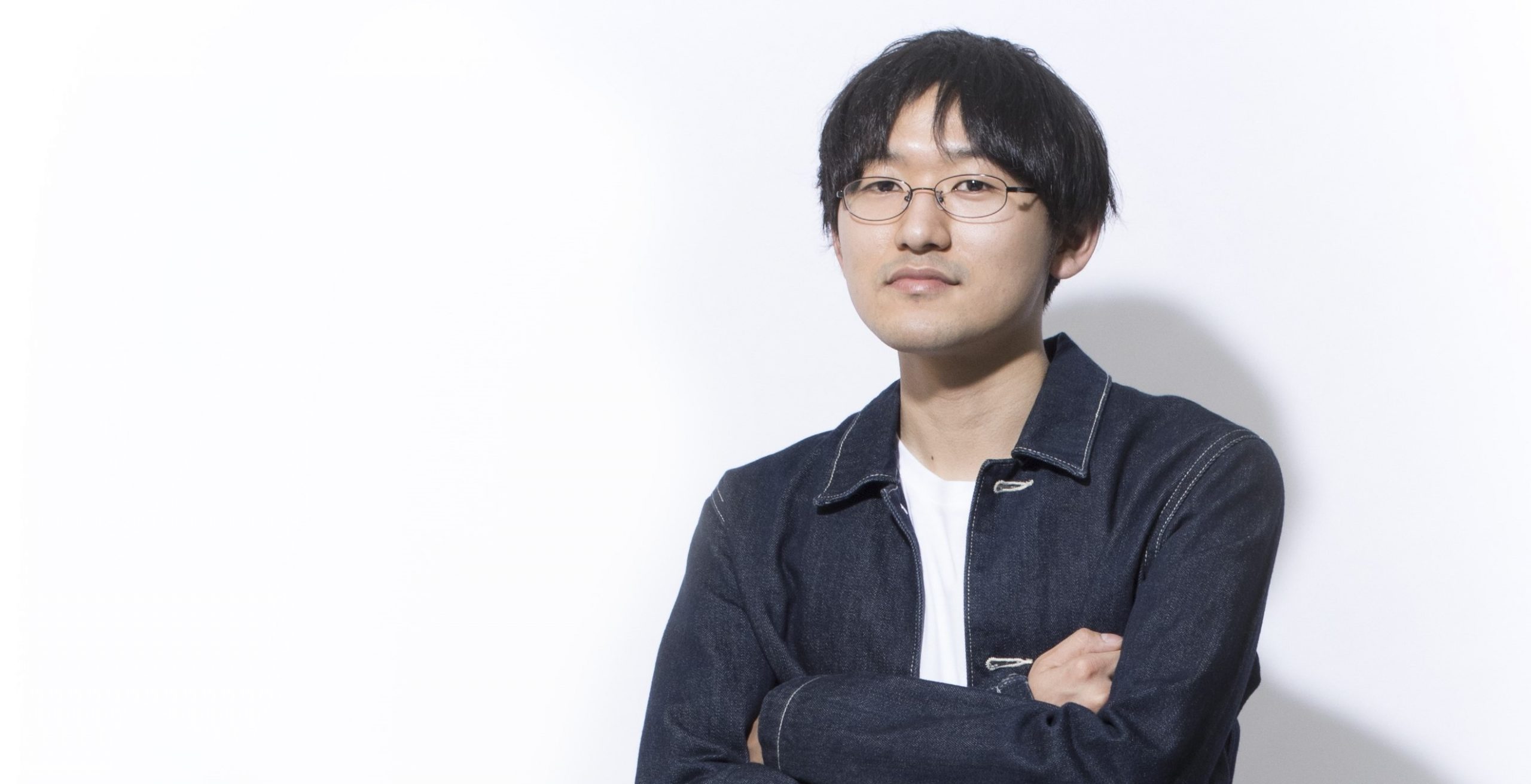小嶋陽太郎さん『悲しい話は終わりにしよう』
信州大学在学中の二〇一四年秋にデビューした小嶋陽太郎は、 青春のきらめきにミステリーのスパイスを効かせた チャーミングな青春小説の書き手として注目を集めてきた。 第七作に当たる書き下ろし長編は、 これまでとがらっと異なる温度で執筆された、新境地となる小説だ。
インタビュー当日の朝、小嶋陽太郎は特急あずさに乗って長野県松本市から上京した。彼は生まれ故郷である松本に今も暮らしている。『悲しい話は終わりにしよう』は、第七作にして初めて、この町を実名で登場させた小説だ。母校である信州大学も、主要舞台となっている。
「デビュー作を担当してくれたKADOKAWAの編集さんに・いつか松本を舞台にした青春小説をやりましょう・と、デビューしてすぐの頃に提案されていたんです。❝『白線流し』みたいなキラキラした切ない青春群像劇を書いてください❞とも言われていたんですけど、何作か書いていくうちにキラキラした話は他でやったからいいかなと思い始めて。せっかく松本を舞台にするんだから、自分が書きたいなと思うものを書いていったら、だいぶ暗くなりました(笑)」
プロローグに当たる冒頭の四ページで、これまでの作品で描いてきたような「キラキラ」からの暗転が示唆されている。夢の中では青空が広がる草原で親友と明るい話をしていたのに、目を覚ました「僕」が独りでいる場所は、大学附属図書館にあるソファだった。雨音に耳を澄ましながら〈あと数日で二十一になる怠さに満ちた体〉を持て余していると、足音が近づいていることに気付く──。実際の執筆も、このプロローグを書き出すことから始めたと言う。
「ユーモアのあるタッチや明るく爽やかなタッチは嫌いではないのですが、続けて書いていると異様に疲れてしまう。今回はより自分の体感に近いところまで落として、無理のないトーンで書きました。僕自身が大学の時に、図書館のソファでいつも寝ていたんです。とりあえずその時の感覚を思い出して描写してみたら、❝ここへ誰かが来る❞という主人公の予感が自然に出てきた。その時点で誰が来るかははっきり決めていなかったんですが、ああ、うまく行きそうだなという予感が僕自身にも出てきたんです」
本編は、二人の「僕」の視点が入れ替わりながら進んでいく。
一人目の「僕」は、大学生の「市川」だ。松本で生まれ育った彼は、高校卒業のタイミングで上京することなく、地元の大学に進学した。大学生活は退屈の極みだったが、学部のオリエンテーションでたまたまとなりに座っていた大柄な男・広崎と友情を結び、かすかな色が付く。
キラキラより
イライラ先行
「主人公は二〇一〇年に入学したと書いたんですけど、それは自分の入学年です。自分の中にある、使える道具はそのまま主人公に投影したほうが、作品のトーンとしてはしっくりくるものになるんじゃないかと思いました。松本は、『好き』という言葉を超えた、自分の体に馴染んだ大事な場所なんですが、大学生活への思いをそのまま投影したら、鬱屈や煮え切らない感じが自然と出てきました」
裏返されたその感情が、音楽に打ち込む広崎という男の造形を生んだ。
「僕も大学時代は音楽サークルに入っていました。こんなことを言ったらよくないかもしれないんですが、大学は嘘くさい人ばかりいる空間だと思っていました。サークルの先輩で、ひとり、音楽に人生をかけてるなと思う人がいて、人間的には軽蔑している部分もあったんですが、同時に尊敬してもいました。本気でやってる感じがしたので心を打たれるときもあって、そういう人に本当はもっと会いたかったなという気持ちが小説の中に出ている気がします」
市川と広崎のコンビに、同級生の女の子・吉岡が加わったところで、章が変わり視点人物が移る。二人目の「僕」は、中学生の「佐野」だ。一年の時に父を自殺で亡くした直後、クラスメイトのある発言がきっかけでキレて、周囲から腫れ物扱いされていた。このエピソードにも、自身の実感が形を変えて反映されている。
「日々生きていて、佐野の感情に類する怒りを感じることは多いです。意見がころころ変わる人や自分の発言に責任を持たない人を見て、❝俺はああいう都合のいいことを言うやつは許さねえ❞と怒るのと同時に、自分はそうならないようにしなければと思います。こちらのパートでもやはりそういう苛立ちのようなものが先行していました」
そんな彼に手を差し伸べたのは、誰からも好かれる奥村という男子生徒だった。親友となった二人の関係性は、柔らかな光に満ちている。しかし、転校生の少女・沖田の登場によって、少しずつ変化し始める。
「視点を交互に書いていく構成にしたのは、二つの三角関係が描けるからです。自分で生み出した世界に対する興味を、いかに持続させられるかが小説にとって一番大事だと思っています。せっかくなら今までやったことのない構造を取り入れた方が、執筆のモチベーションをより高く維持できるのではないかという思いもありました」
二つの視点は、もちろん、ある地点で重なり合う。
「ミステリーの要素も入っているとは思うんですが、読者を驚かせたいという思いはほとんどないです。なんとなく見当をつけながら読んでもらっていいし、謎が明かされたときに❝そういうことだよね❞となってもらっていい。書き手として勝負だなと思ったのは、その先で何が描けるか、でした」
奥手である二人の「僕」を主人公にしたのは、「触れる」ということが一つのキーワードとなるからだ。
手を握ったり、肩を抱いたりと、人に触れることは、そう簡単ではない。家族や恋人でもなければ、肌を触れ合わす機会などそうそうあるものではないだろう。その一方で、勇気を出して触れることで、深まる関係もある。しかし、多くの人にとって、普段の生活の中で、そういったことに想いをはせる機会は少ないはずだ。
「触れるということは、本当は非常に重いことだと思うんです。だから、主人公が、ある人物の手に触れることを、自分の中に抱えてしまった何かを乗り越える象徴として描いてみたかったんです」
自分の中には
❝何か❞がある
信州大学に通いながら、「就職について真面目に考えなければいけないことからの現実逃避」として執筆した『気障でけっこうです』で、第一六回ボイルドエッグズ新人賞を受賞したのは二〇一四年秋だった。受賞後第一作『今夜、きみは火星にもどる』(単行本刊行時の題名は『火星の話』)までは順調だったが、それ以降は、とくに書きたい題材があるわけではなかった。そんな新人作家に、所属する著作権エージェント「ボイルドエッグズ」の代表・村上達朗は、策を放った。「むちゃぶり」だ。
「❝なぎなた少女❞とか❝漫画編集者❞とか、お題を与えてもらったんです。どれも最初から興味のあった分野ではないし、絶対書けないなとはじめは思いました。でも書かなければ生きていけない。とりあえず書いていくうちに、その中に何かしら自分のエッセンスが出てくるのを感じました」
自分自身と向き合うことから始める。その姿勢は、この物語が放つメッセージとぴったりシンクロしている。
「人生を振り返ってみると、いろんな物事を放り出して生きてきた気がします。しんどいことはそぎ落として、無かったことにして生きていくほうが楽なので。でも本当はしんどいことや現実から目を逸らさないで、ちゃんと向き合っていかなきゃいけないんだよなと思っている。そうあるべきだと、誰かにではなくて、自分に言いたいんだなとこの小説を書き終えたときに思いました」
丸三年の小説家としての青春期を終え、本作で新たなスタートラインに立った小嶋陽太郎にとって、これは第二のデビュー作だ。 「自分の中に何かあるような気がするけれど、それが何かわからない。でも書くことによって知ることができる。小説にはそういう機能もあるんだと、この作品を書くことで気付きました」