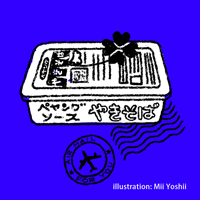思い出の味 ◈ 阿部智里
第2回

もう、あのさくらんぼは食べられないのか。
そう思った時、古くからの友人をなくしてしまったかのような喪失感を覚えた。
我が家には、さくらんぼの木がある。畑で一番大きな木で、実が鈴なりとなると、まるで花が咲いているかのような鮮やかさだ。熟したさくらんぼはみずみずしく、赤い宝石そのものである。幼い頃は、木に登り食べごろとなったものを下の人に落とすのが私の役目だった。しかし最高に美味しいのは、生っている実を洗いもせず樹上で食べ、ぷっと種だけ吐き出した時だろう。スーパーで売っている大きなアメリカンチェリーよりも、家族や友達と一緒に収穫した、野趣あふれる小粒のさくらんぼの方が、私にとってはごちそうだった。
しかし部活や受験で忙しくなるにつれ、徐々にさくらんぼ狩りの機会は減っていってしまった。上京して数年が経った頃、ようやく食べごろの時期に帰省することが出来た。久しぶりのさくらんぼだ、とわくわくしながら口にして、ぎょっとした。
味が、前と全然違う!
サラリーマンの父が素人なりに面倒を見てくれていたが、とうとう木に限界が来たのだ。よくよく見れば、かつて木登りで使っていた大枝はすっかり枯れ果て、実の数も少ない。がっかりする私を見て、しかし父はニヤリと笑い、木の反対側へと私を連れて行った。
そこにはなんと、私の記憶にはない、若々しいさくらんぼの木が生えていた。
「え、わざわざ植えたの?」
「いいや、勝手に生えてきたんだ」
もしかしたら、昔お前が吐き捨てた種かもしれないぞ、とからかうように父は言う。
その木の実を口に含み歯を立てた瞬間、ぷちりと果肉が弾け、ほんのりと甘く、それ以上に酸っぱくて初夏の太陽の香りがする果汁が、口いっぱいに広がった。
なんとも懐かしい味だった。