白石一文さん『ファウンテンブルーの魔人たち』
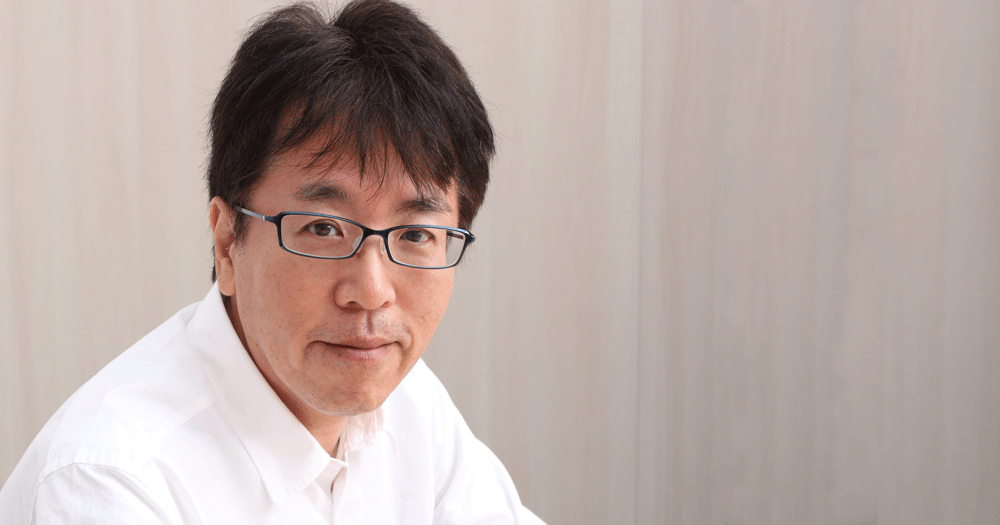
女と男は一度、本気で戦う必要があるのかもしれない。
単行本で600ページ超の大作『ファウンテンブルーの魔人たち』について、まったく展開を決めずに自由に書いたという白石一文さん。だが、書き進めるうちに、自身の中にあった問題意識が鮮明になっていったという。それは男と女、そしてセックスに対する違和感で──。
新宿に隕石が落ちた後の世界
白石一文さんの新作『ファウンテンブルーの魔人たち』は、一年四か月にわたって「週刊新潮」に連載された長篇だ。当初の予定の倍ほどの長さになったという。
「誌面の連載の予定が急に変更になったようで、突然、一か月後から連載を始めてほしいと依頼がきたんです。それでもう、好きなように書かせてもらうことにしました。連載が長引いても、編集部側も急なお願いだったという負い目があったからなのか、〝そろそろやめてくれ〟と言えなかったんでしょうね(笑)。小説を書くのはいつでも楽しい作業ですが、今回はとりわけ楽しかったですね」
舞台は近未来。新宿二丁目に隕石が落下、跡地に建設されたのは大型複合商業施設に囲まれた六十階建ての高層マンション「ファウンテンブルータワー新宿」。この五十八階に暮らしている作家の前沢倫文は、十七階で立て続けに米露中の要人の不審死が発生したと知り、独自に真相を調べ始める。が、その方法が驚きだ。彼は気管支拡張剤を飲むと幽体離脱できる体質なのである。薬を服用し浮遊して十七階に行った前沢は、ある部屋で奇妙なものを見つけてしまう──。
「小さい頃、うちの親父(作家の白石一郎)が、面白い雑誌や本を見つけると夜中でも子どもたちを叩き起こして読み聞かせをしていたんです。そのたびに僕と弟は寝ぼけ眼で父の朗読を拝聴しなくてはならなかった。これは、うろ覚えの記憶なんですが、ある晩、何かの雑誌に載っていた司馬遼太郎さんの文体を完全に模倣した短編小説を読んでくれたことがあったんです。僕は小学生の頃にはすでに司馬ファンだったので、それが司馬さんの書き方にそっくりだとも分かったし、しかし、内容自体はまったくのでたらめだというのもよく分かったんです。父も抱腹絶倒でその結構長い文章を読み聞かせてくれたんですが、僕自身も、いかにももっともらしいでたらめっぷりが本当に面白かった。
このときの痛快な印象が強く残ったものだから、いつか自分も物書きになったら、いかにももっともらしいんだけれど、実は壮大なでたらめ物語を書きたいとずっと思っていたんです。そして今回、作家生活二十年を経て、ようやくその宿願を果たしたというわけです(笑)。
そもそも人間、歳を取ってくると頭が固くなるし、いろんな常識や分別、それに知識が身についちゃって、自由な発想ができなくなってくる。作家の場合もしかりで、だから、すでに還暦を過ぎた自分が一体どれくらい、めちゃくちゃな話がいまでも書けるのかを一度試してみたいという気持ちもありました。
最初は現在時点の物語として書き始めたんですけれど、書いているうちに、それじゃつまらないような気がしてきて、じゃあ、こうしようってことで数年前に新宿に隕石が落ちて、二丁目が焼け野原になったという設定をでっち上げたんです。だとしたら、その隕石は普通に落下したわけじゃなくて、何か特別な理由があって新宿二丁目に激突したことにしちゃおう─といった進め方で書いていきました。つまりは、そんな感じで小説の舞台がいつの間にか近未来になっちゃった。
でも、これは結果的にはよかったと思います。だって、連載を始めて半年もした頃から、新型コロナウイルスの大流行が起きて、仮に現在時間で書き続けていたらコロナをどのように物語に組み込むかで四苦八苦していたはずですからね。
というわけで、この小説に出てくるいろんな小道具も、最初は何にも考えてはいなくて、『ふーん、近未来か。だったらこういうの使えるよなー』というように、その場その場で思いついたことをチャカチャカ取り込んでいったんです。
最初から考えていたのは幽体離脱と白い幽霊くらいのもので、後から出てくるAIロボット、031TC4、人工子宮HM1&2、インドの財閥や中国のハイテク企業、地球の中軸や根本原理なんかは全部成り行きです。ただ、そうやって行き当たりばったりで書いていると、自分がかねて抱えていた問題意識のようなものがより自然に、そして鮮やかに作品の中で浮き彫りになっていくんですよね。なので、物語の後半三分の一くらいからは、自分の顕在意識に浮上してきた年来のテーマに寄り添って、物語を緻密で丁寧に収束させていくことに全神経を集中させることができましたね」
つまり、執筆開始の時点では近未来にするつもりすらなかったのだ。それが国家間の軋轢や、極秘裏に進行する人類の未来を握るプロジェクトの話へと膨らんでいくのだから驚く。では最初に書こうとしたイメージはなんだったのか。
「とにかく、真っ先に思ったのは、男性が男性とセックスをする話にしようということでした。僕は女性が好きだし男性とのセックスの経験はないんですが、最近はなんだかそうしたことにすごく息苦しさを感じていて。それと、〝T〟について書きたかった。なぜ人が行うさまざまなことは、いつの間にか本人の感覚や意識とズレていってしまうのか、その根源的な理由をずっと考え続けてきましたから」
〝T〟とは前沢が勝手につけた名前で、〈この世界の真実をわたしたちの目から覆い隠す何者かの存在〉のこと。というと昨今よく耳にする陰謀論じみたものを感じてしまうが、ここで言及されている〈何者かの存在〉とは特定の人物や集団のことではなく、自然の摂理のようなものを指す。
「人間の心理はいろんなものに影響を受けている。たとえば経済学者のフリードマンは、人間は常に自分の最大利益のために活動する存在だなんて言っていましたけど、そんなの噓っぱちでしょう? 人間というのは、肝腎なことに限って論理的に行動しないものです。憎悪や執着、情熱やある種の啓示、さらには自分以外の人間の思惑に自ら進んで乗っかって、自分が望んでいなかったこと、または望んでいた以上のことをしたりされたりしてしまう。どうして人間というのはそういう動物なんだろうと、いつも僕は疑問に思うんです。人間のこころを駆り立ててやまないものとは一体なんだろうって。
そんなふうに考えていくと、まずは人間を規定する本質的な枠組みを求めなくてはならなくなる。つまり人間の最大公約数みたいなものです。そして、そこから人間個々がはみ出していく部分を観察し、そのはみ出しの要因を突き止めようとするわけです。
たとえば、この地球の閉じられた系は、人間にとってはアプリオリに与えられた枠組みですよね。だとすれば、人間は少なくともこの系が備えている生々流転の法則のようなもの─僕はそれを地球のコードと呼ぶんですけど、から外れた行動を起こすことはやはりできない。恐らく、この宇宙にはさまざまな生命体が存在しているのだろうけれど、人間にしろ彼等にしろ、そうやって自分たちが生まれた惑星のコードに常に縛られた形で生存しているのだろうと思います。
ただ、非常に稀なことではあるけれど、そのコードが別のコードに置き換わることがあり得る。その象徴的な事例として、僕は星と星との衝突をいつも思い浮かべるんです。この作品でも何回か言及しているんですが、たとえば六千五百五十万年前にメキシコ・ユカタン半島沖に落下した巨大隕石は地球上の生物の大半を消滅させてしまいました。なかでも、当時、陸上の覇権を握っていた恐竜の絶滅は、次代におけるわれわれ哺乳類の繁栄へとつながっていく。
これなんかは、隕石の地球衝突によるコードの置換と考えることもできる。というか、そんなふうに考えて、地球の閉じられた系も隕石のような別の惑星の衝突によって新しい系へと変化し得ると見立てると、とてもエキサイティングですよね。今回の作品では、僕のそういうはちゃめちゃな妄想をこれからの人類の未来に投影して、自分自身のかねての問題意識を掘り下げていったんです」
性差とセックスに対する違和感が表れた
では、本作において、別のコードを持った隕石の落下は、地球に何をもたらしたのか。
「未来に何が起きるのか想像したというより、自分がいま何を問題として捉えているのかを書きながら考えていきました。そんなふうに物語の進行に身を委ねながら思考の焦点を合わせていくと、ああ、自分はこれからの男と女の関係に絶望しているんだなあと深く納得できたんです。だから、やったこともないのに男と男のセックスがどうしても書きたくなったんだなと……」
その思いの根本にあるのは、セックスに対する違和感。
「セックスは食べることや寝ることと同じように、必要不可欠なものであると同時にすぐれて快楽を追求する手段の一つでもありますよね。ただ、われわれの人生においてセックスが必要不可欠なものであるのは、それをしないと人類という種が滅亡してしまうからです。その点では食事や睡眠とセックスはかなりニュアンスが異なっている。食事や睡眠は、断ってしまうと自分という個人がたちどころに死んでしまうものですが、しかし、セックスというのは別にしなくたって自分が死んじゃうわけではない。あくまで人類の一員として、社会的な存在として、僕たちに要請されているものなんです。
しかも、そのとき人類社会から僕たちが求められているセックスというのは、男と女のセックス一種類ということになります。理由は至極簡単で、男女のセックス以外では子供が生まれないからです。
僕たちは思春期になると性欲を持ちます。が、この性欲は出産へと繫がる男女間のセックスのためであることが義務づけられます。同性間でのセックスは非生産的なものとして男女間のセックスよりもはるかに地位の低いものとされてきたし、たとえば性欲の無い人間は、そうした存在がいることさえ半ば隠されてきたと言ってもいいでしょう。
要するに、男女のセックスだけが神棚にまつられていて、他のセックスは全部、人類の発展に貢献しない無意味なセックスという烙印を捺されてきた─極端な言い方ですが、それがこれまでの社会の現状だったと僕は思います。
そして、どうやら僕たちはそうしたドグマチックなセックス観にうんざりしてきているんじゃないかという気がするんです。
そもそも男女のセックスにおいて、女性にとって最も有効な武器は容姿ということになっています。より美しい女性がより多くの男性を引き寄せ、優秀な遺伝子を持った男性を選別する。そうやってセックスに勝利し、実際に優れた人間を生産する。こうしたストーリーをわれわれは生まれてすぐから信じ込まされ、成長していくとその種の〝美貌神話〟が現実の世界を完全に支配していることを知ります。
しかしですよ、これって実はめちゃくちゃな話じゃないですか?
女性の容姿が美しいかどうかは、ほぼ生まれながらに決まったものであって本人の努力とはまるで関係がありませんし、女性の他の能力との関わりも皆無に近い。にもかかわらず美しくない女性は、それだけで大きなハンデを背負っていることになり、一方、美しい女性は、自身の外見だけで男性や社会から評価され続けることになる。
そういったどう考えても道理に合わない現実が平気で罷り通っているのは、ひとえに男女間のセックスが神棚に上がっていて、人類繁栄にとって何よりも重要なものであると誰もが考えているからですよね。
だとすると、もしも、男女間のセックスによって子供を作らなくても、別の方法で子供を作れるようになったらわれわれは一体どうなっちゃうんだろうか? 今回の作品で僕の頭の中に途中から浮かび上がってきたのは、そういうことが可能になった社会のイメージでした。
そして、実際、すでにわれわれが手にしている遺伝子操作技術や人工授精技術、さらには人工子宮の技術を使えば、男女間のセックス抜きで子供を作ることも充分にできるようになってきている。少なくとも、この小説の舞台となっている近未来では、それが本当に実現していても何ら不思議ではないわけです。
そういう世界では、セックスは人間にとって必要不可欠な行為ではなくなり、単なる快楽の追求手段に過ぎなくなります。男女のセックスだろうが、男同士、女同士のセックスだろうが似たようなものであって、そもそもセックスをしたくない人間は別にしなくても構わないし、そのことで誰かから揶揄されたり、非生産的だと批判されたりすることもなくなる。
一度そうやって皆さんも、セックスをしてもいいけどしなくてもいい世界、セックスがそれほど重要ではない世界を思い描いてみてほしい。
そういう世界になれば、女性や男性の容姿がいまのようにもてはやされることもなくなりますし、若さがいまのように大きな価値を持つこともなくなる。もちろん身体の大きさや肌の色であれこれとやかく言われるようなこともきっと少なくなってくると思います。
子供は男女の間でも作れるし、場合によっては男性同士、女性同士でも作れるようになります。男女で子作りをするにしても、女性が妊娠、出産という大きな負担を無理に引き受ける必要はなくなってくる。むろん高齢者が子供を持つことだって可能になるでしょう」
だが、物語のはじまりから、主人公の前沢には、男性優位社会での思考回路的なものがうっすらと感じられる。どこか女性たちをみな〝女〟としてジャッジしている視線があるのだが、そんな彼がある人物から「(前沢は)女の人が嫌いなんだよ」、また「(周囲の女性たちも)全員〝女〟に過ぎない」と思っている、と指摘される。それがなんとも痛快ではあるのだが、著者の作品としてはやや意外な気も─と、率直に言ってみた。
「もうね、昔から僕の小説についていろんな人から〝男尊女卑だ〟〝精神的マッチョだ〟って批判されるんですよ。僕としては、そんなふうに言われるといつもかなしくなるし、文脈に込めた本当の意図を汲み取ってほしいと思いつづけてきました。そもそも、前沢の個々の行動や言動にしたって小説の作法に従っている部分も大きく、すべて正しいと思って書いているわけではないですからね」
ご自身は、女性への性的暴力についても、#MeToo 運動や海外の女性虐待の記事を見ながらより深く考えていたようだ。
「たとえばインドの女性の性的被害を調べてみると、それはもう悲惨なものがある。ただ、遠いインドに限らず、この日本でも性被害の報告はそれこそ枚挙にいとまがなく、大半は男性による女性への性暴力です。しかも、潜在的な性被害者は、表に出ている数字より何倍も多いと考えられています。
そうしたことで、僕にとって一番印象的だったのは、もう十年近く前に聞いた話なんです。その頃、親しかった作家さんが関西の女子大の学長になっていて、彼を頼るような形で僕はしばらく神戸に移住しました。そのとき、彼が学長になって最も驚いたこととして話してくれたのが、『いや、とにかく若い女子大生の話を聞くようになって、彼女たちがこれほどまでに性被害に遭っているのかと驚愕した』というものでした。何しろ著名な作家さんなので女学生たちも彼にはいろいろとプライベートな話を打ち明けてくれるらしく、そうやって深く聞いていくとびっくりするほど多くの学生が、親や兄弟、親戚、知人などによる性的被害に遭っていて、そのことでずっと苦しんできているというんです。
『世間ではいろいろと言われているけれど、まさかここまでとは……』
と彼も啞然としていましたが、僕もその話を耳にして背筋が冷たくなるような心地を覚えました。
なので、現在 #MeToo 運動で声を上げている人たちの後ろには、声すら上げられなくて生きてきた膨大な数の性被害者たちが存在するのだろうと思います。
僕自身は加害側に立ったことはないけれど、でも今の話でも分かるとおりで、深刻な現実に対して見て見ないふりをしたり、気づかなかったのは確かでしょう。
加害者のみならず、そういう僕みたいな男たちの存在に対しても女性たちは長年にわたって強い不信感を持ってきていて、いまようやく彼女たちはその不信の一端を社会に向けて発信するようになったのだろうと思います。
結局、男女のあり方というのは、否応なく繁殖によって規定されてきたわけだけど、仮にその繁殖を男女で行う必要がなくなってくるのであれば、もうこれまでのような男女関係は変えていった方がいいんじゃないか─そういう気分が女性のみならず男性側にもかなり強く醸成されてきているのではないかと僕は感じている。
結婚する人が減ってきていたり、セックスレスが一貫して増えているのも、要はそういう心理の顕在化なのかもしれません。
神棚からおろされた〝男女間のセックス〟は、やがて繁殖という大義名分を失って、ある種のギャンブルやゲームのような娯楽の一部門に落ち着くのではないでしょうか? そして、そういう社会が生まれるとますますセックスレスは当たり前になり、性暴力もまた徐々に減っていくのかもしれないと思いますね。
当然、〝一回産んでみなよ〟とか〝子どもは産んだほうがいいよ〟といった母親神話や母親幸福論も廃れてしまって、産まないことを選択する女性も爆発的に増えるような気がする」
神棚からセックスをおろすということ
読み進めながら、〝神棚に載ったセックス〟に、どれだけ大変な思いをさせられてきたか改めて気づく女性も多そうだ。
「この奇想天外な物語を書きながら、男女はいずれ激しく対立せざるを得ないよう宿命づけられているんだろうと感じました。女と男は一度、本気で戦う必要があり、その大きな関門を通過しないと新しい関係を結べないところまでもう来ているのかもしれません。
いままでは男性が圧倒的な暴力によって女性たちを徹底的に抑圧してきたわけですし、そこには、なんだかんだ言っても女性に子供を産んで貰わない限り人類は消滅してしまうという、ある種の差し迫った大義名分があった。男女間のセックスは必要不可欠なもので、そのセックスにつきまとう、いわばどうにもならない行き過ぎた行為として売買春や性暴力のようなものが存在し、これらは当然摘発の対象ではあるのですが、逆に言えば見えない場所でそれらが行われる分には『まあ、仕方がないか』といった形でずっと見過ごされてきた。同時に男女間のセックスから外れた性的指向は、正当なものではないアブノーマルな存在として常に片隅に追いやられてきたわけです。
そして、現在、その両方の面において大きな地殻変動のようなものが起きているのではないかと僕は感じています。
まずもって、男と女が、ごく自然に愛し合い、ごく自然に子供を作るという〝自然観〟が疑われ始めている。そうやって子供を成した夫婦が生涯添い遂げるというのは、もはやオワコン状態でしょう。
さらには、男と女という組み合わせが当たり前という常識にも人々の疑いの目が向けられ始めています。先日、ある女性の教育評論家の方と話していたら、『LGBTQという言葉がこんなに早く広く、多くの世代に浸透するとは思わなかった』と彼女が言っていました。確かに、LGBTQという言葉はいまやお年寄りの間でも充分に共有されている。少なくとも僕のような還暦をとうに過ぎた世代でも、この言葉はごく普通に使われ、世界にはさまざまな性的な指向を持った人たちがいるのが当然なんだと受け入れられている気がします。ですが、そうした共通認識の変化は件の教育評論家氏が言うように、最近になって急速に浸透してきたものでもあるように思う。
要するに、みんな昔から男と女という単純な区分けをそんなにすんなり受け入れてはいなかったんじゃないでしょうか。でも、男女間のセックスだけが正しいセックスだ、という固定観念に誰もが縛られていたから、『自分はそうじゃないんだけど』と表だって口にするのは憚られ、黙って慣習に従っていた。実はそういう〝違う人たち〟がもの凄い数、存在していたのではないかと思いますね。この小説でも、性欲を持たないアセクシャルな人物を主要登場人物の一人として出していますし、マサシゲというAIロボットは男性にも女性にも両性具有にもなれる人物として主人公とセックスをしまくります。
実際、性というのは誰にとってもかなり曖昧な領域に存在するんじゃないかと僕は感じているんです」
その大きな関門を通り抜ければ、人々の価値観にも大きな変化があるだろう。作中、富を求めず贅沢を望まず、のんびりと暮らそうとする〝ノーブルチルドレン〟に言及する箇所もあり、予言的だ。
「物質的な満足を追求することによって幸福を得るという考え方は、先進国ではどんどん薄れてきていますね。ノーブルチルドレンやノーブルデスというのは僕が勝手に命名したんですが、今の若い人たちは高級ブランドにもさして興味がないし、高級外車を乗り回して女の子を助手席に乗せたいなんて思ってる男も少ない。むしろそういう旧来型のガツガツ系は小馬鹿にされているのが実情なんじゃないでしょうか。
彼等は、今回の作品でも書いたように静かな田園生活のようなものを望んでいて、ほどほどの暮らしの中で、仕事や、場合によっては夫婦関係や子育てにも煩わされずに穏やかに生涯を終えたいと願っている。日本人はこうなるべきとか、この国をどうすべきかとか、そういうことには余り興味を持たない。小説の中でも、日本経済はとっくに中国やインドの経済力に飲み込まれていて、日本人は非正規で働いている人が多くなっているくらいなんですが、少子化のなかで衣食住にさして困らない生活を送れている限り、ノーブルチルドレンは大した不満は持たないんです。そういうこの国の未来は、大いにあり得ると僕は思っています」
もちろん今後、完全にセックスがなくなるわけではない。
「快楽としてのセックスがなくなることはないでしょうが、現実に生身の相手とセックスするかどうかはまた別の話だと思います。実際、今のアダルトビデオのラインナップを眺めるとVRがたくさん出回っています。ああ、こういうものをVRゴーグルで視聴しながら今の人はマスターベーションをしているのか、と思うと、僕などはちょっと厳粛な気持ちになってしまうんです。時代の変化を痛感します。
セックスが遺伝子操作技術や生殖医療、人工子宮などによって繁殖と切り離されて、一つの快楽追求の手段になれば、そのためのハイテク商品が次々に市場に投入されるようになるでしょうね。作品ではAIロボットが変幻自在な生殖器で主人公を魅了するのですが、そこまでのロボットは難しいにしても、セックスに特化したロボットは早晩、開発されるのではないかと思います。要するに、そうやってセックスは神棚からおろされて、数ある欲望の一つとしておさまるところにおさまっていくのかもしれない」
神棚に載ったセックスがなくなった世界についても、ぜひ思考実験して書いてもらいたくなる。現在は小学館のポータルサイト「小説丸」に長篇小説『道』を連載中。第二回までを読むとコロナ禍が舞台の話と思うが、実は違うようで──。
「小学生の頃に広瀬正さんのSF小説『マイナス・ゼロ』を読んで、大げさでなく、死ぬほど面白いと思ったんです。ずっと僕にとって特別な小説だったんですけれど、数年前に読み返してみたら、自分だったらもっと凄いのが書けるかもしれないって気がしました。時間や次元に関する物理学は広瀬さんの時代よりかなり進歩しているわけですし。だったら、やらない手はないなと思って、今回の『道』という作品を書き始めました。これも僕にとってはすごく楽しい仕事ですね」
ということはタイムトラベルが絡んでくるのかも? 今後の展開が楽しみだ。
白石一文(しらいし・かずふみ)
1958年福岡県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。文藝春秋勤務を経て、2000年『一瞬の光』でデビュー。09年『この胸に深々と突き刺さる矢を抜け』で山本周五郎賞を、10年には『ほかならぬ人へ』で直木賞を受賞。他の著書に『不自由な心』『すぐそばの彼方』『私という運命について』『心に龍をちりばめて』『この世の全部を敵に回して』『砂の上のあなた』『翼』『幻影の星』『火口のふたり』『神秘』『一億円のさようなら』『プラスチックの祈り』など多数。最新作は『我が産声を聞きに』(講談社)。
(撮影/浅野剛)
〈「WEBきらら」2021年8月号掲載〉




