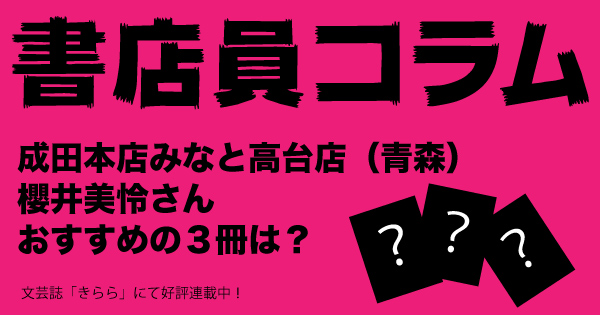初恋の魔法が解ける日
思い出は美化するものだ。たとえば初恋マジックがそのいい例だろう。青春の1ページは年を重ねるごとに美化されていき、中は上に、上は特上へと上書き保存されてゆく。いくら他の人と付き合ってもやっぱりあの人を忘れられないというのはよく聞く話だが、なにもこれは初恋に限った話ではない。ある作家さんにハマるきっかけになった一冊を忘れられずに、それからいくら同じ著者の作品を読んでもその本の面白さを超えられない、という経験を皆さんもされたことはないだろうか。
私と吉田修一の出会いは『パーク・ライフ』だった。文芸書の担当になったばかりで、芥川賞の受賞作をはりきって手にしたのだ。けれどこれは通りすがりの先輩が落としたハンカチを拾ってくれただけのこと。素敵だな、とは思っても、恋に落ちるまでにはいかなかった。

私にとっての吉田修一の初恋本は『悪人』である。悪人が傑作であることは疑いようがなくたとえ2番目、3番目の彼であったとしても、ぞっこんになったとは思うのだが、いかんせん初恋の彼が優良物件だったというのは私にとって不幸であった。どうしても忘れることができないのだ。むろん、初恋の彼を思い続けることはできる。単行本が擦り切れるまで読み、いい加減に二人に倦怠期が訪れる頃になると、見計らったかのように文庫でカジュアルな装いになった彼がイメチェンを図ってくる。文庫になったからとはいえ、これは同じ人を愛しているのであって決して浮気ではない。

けれど、初恋はあくまでも初恋。恋に恋していた少女もやがてままごとではない恋をする。
そう、ついに私を大人の女にしてくれる作品が現れたのだ。それが、任侠の一門に生まれた美貌の少年が仁義の世界から飛び出し、その内に秘めた才とたゆまぬ努力で歌舞伎役者として生きていく様を描いた、『国宝』である。十年越しの初恋の彼の面影を消し去るほどの圧倒的な熱量で、日本の誇る伝統芸能に文学で触れられる喜びに痺れさせてくれる、血が沸き立つ熱い漢たちの物語だ。実際に黒衣として舞台の裏方に立って取材したというだけあり、微に入り細を穿つ歌舞伎の場面は圧巻である。けれど、いつかこの『国宝』さえ凌ぐ作品が生まれる日がくるだろう。恋する女は貪欲なのだ。