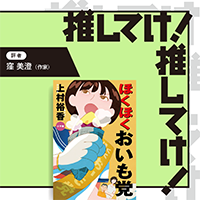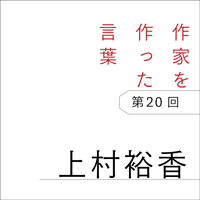著者の窓 第48回 ◈ 上村裕香『ほくほくおいも党』

まだ語られていない「活動家二世」のもやもやを形に
──小学館のWEBマガジン「STORY BOX」連載中から話題を呼んでいた『ほくほくおいも党』が単行本になりました。この作品のオリジナル版は、京都芸術大学の卒業制作として執筆されたものだそうですね。執筆のきっかけを教えていただけますか。
きっかけになったのは大学時代に知り合った、ある編集者さんの言葉でした。学生時代、左翼政党の活動家の娘を主人公にした作品を書いたことがあるんですが、それを読んで「わたしも活動家二世なんです」と話してくれたんです。世の中に「活動家二世」という言葉があることを初めて知りました。わたし自身、同じような環境で育ってきたことに対するもやもやをうまく言葉に表すことができずにいたんですが、「活動家二世」という言葉に触れたことで、輪郭を持ち始めたんです。その編集者さんをはじめ何人かの活動家二世の方にお話を聞くうちに、そうした人々の物語を書きたいとあらためて思うようになりました。
──そうだったんですね。では上村さんの経験や気持ちもかなり反映されているんでしょうか。
この作品はフィクションなので、主人公の豊田千秋とわたしは性格も家庭環境も違います。ただよその人には説明しづらい、親が左翼政党員だからこその微妙な感情を抱えているという点は一緒です。千秋が離れて暮らす母親に自分の苦しさを打ち明けたとき、「お父さんに、殴られたことあると? 食事抜きにされた? 学校行かせてもらえなかった?」「なにも、されとらんやろ?」と返される場面がありますが、分かりやすく不利益を被っているわけではないだけに外側からは見えにくい。親が一番身近な他者である子どもではなく、世の中や社会にばかり目を向けているという不満は、親が活動家でなくても生じるものですよね。読者の方から〝家族が教師でもこういう気持ちになります〟という感想をいただいて、ああ、それは似てるかもと思いました。

──千秋は高校生3年生。18歳の誕生日を迎えたその日、党の事務所に行き、入党の手続きをすることになります。自分をなぜ党員にしたいのか、父の正に聞いてもはっきり答えてはくれません。
活動してたらすごい人に会えるとか、党員はみんな成功しているとか、千秋はそう言って勧誘される。このあたりは党員あるあるというか、くすっと笑ってもらえるようなエピソードとして書いています。気に入っているのは、正の活動を立派だという同じ学校の生徒に対して、「町中に父親の顔写真が貼られてるのなんて、指名手配犯か政治家の子どもだけだよ」という千秋の台詞。活動家二世でないと出てこない台詞ですが、そうじゃない人が読んでも面白いと思います(笑)。
──正が関わっている左翼政党は、実在する政党を連想させる部分があります。モデルとの距離の取り方については、どんな点に気をつけられましたか。
左翼政党の活動を家族の立場から書いていますが、それが実在する政党への攻撃材料になってしまってはいけない。書き方はかなり気をつけています。たとえば千秋や左翼政党に批判的な兄・健二を出すだけでなく、他の活動家二世や党員たちの声も拾い上げて、できるだけ多面的でフラットな書き方になるよう心がけました。
外側からはうかがいしれない各家庭の事情
──千秋の兄・健二は父が選挙運動をしていることを学校でからかわれ、以来6年も部屋に引きこもっています。千秋はそんな家族を支え、繋ぎとめるようなポジションですね。
そうですね。正は政治活動ばかりで家のことには関心がない、健二はそんな父にうんざりして心を閉ざして、インターネットの世界で左翼政党を攻撃したり、差別発言をくり返したりしている。千秋はそんな家族の間で、言葉を発し続けます。彼女がいるから家族がばらばらにならずにすんでいるんです。といっても心の中は単純ではなくて、「選挙出て、負けて、赤字になってうちを貧乏にするお父さんが恥ずかしくてたまんない」という気持ちもあります。思春期の女子ですからね。
──そんな千秋はインターネット上で、「ほくほくおいも党」という活動家二世のコミュニティに出合い「会ってみたい。自分以外の、活動家二世に」という気持ちがわき上がってくるのを感じます。こうしたコミュニティは架空の存在ですね。
フィクションです。ただ「活動家二世」という言葉を知って気持ちが軽くなったのは事実。誰にも言えなかった悩みを分かち合うことで、自分が変わっていくという体験を書きたくて、活動家二世の互助グループを登場させました。グループ名は、ほくほくしたおいもの匂いが好きな人なら誰でも参加できる、くらいの意味(笑)。つまりは「すべての人を歓迎する」ってことです。登場させるならそのくらいのゆるいつながりがいいのかなと思いました。

──物語は連作形式で、6つのエピソードからなっています。第2話「佐和子とうそつき」ではほくほくおいも党のオフ会に参加した千秋が、長年熱心な党員として活動してきた佐和子さんの複雑な胸中を聞くという作品。
第2話は取材がなければ書くことができないエピソードでした。佐和子さんは外から見たら、人生にそれほど不満があるようには思えないんです。親が左翼政党員で、その思想を受け継いで自然に党員になり、リベラルな生き方を実践してきた。でも思想的には親と合致していても、感情的にはやっぱりずれが生じたり、もやもやを抱えているということを、二世の方々へのインタビューを通して初めて知りました。母親は大好きだけど、党のために仕事をしている母親は全肯定できない、そんな佐和子さんの心の揺れ動きや、後半での彼女の選択は、自分の中からは出てこなかったものだと思います。
──第3話「和樹とファインダー」はうってかわって高校の生徒会長選挙の候補者のドキュメンタリー映像を撮ることになった高校生・和樹の物語。映画好きの彼は、これまで政治に深い関心はありませんでした。
物語に多面性を出すために、千秋や政党関係の人だけではなく、まったく政治に関心がなかった人の視点も入れるべきだと思いました。それで出てきたのが、先生の言いつけで候補者のドキュメンタリーを撮ることになった和樹です。生徒会長選挙は規模こそ小さいけれど、選挙であり政治。ちょうど千秋たちが18歳で選挙権を持つ年齢ということもあって、県知事選と重ねるような形で、生徒会長選挙を書いてみようと思いました。
──第4話「康太郎と雨」は党員岩崎さんの学生時代の物語。震災ボランティアでの経験とそこでの出会いを通して、彼はごく自然に党の活動に参加していきます。
岩崎さんのエピソードは純粋に党員に憧れる、純粋できらきらした学生を書いてみようと思って書きました。東日本大震災のボランティアについては、ノンフィクションを読んだり、震災を扱った作品に触れたりしました。実はわたしの父も震災ボランティアで結構長いこと家を空けていて、その間の行動が謎だったんですけど、資料に当たることで、自分の知らない父の一面を知ったような気持ちでした。
ばらばらになりかけていた家族の再出発
──第5話「健二とインターネット」は6年間部屋に引きこもり、ネット上で左翼政党を攻撃するような書き込みを続ける健二の物語。父のブログにも批判的なコメントをつける彼の心の屈折が、さまざまな角度から描かれていて印象的でした。
健二のような人はSNSを見ているといますよね。リベラルな人に攻撃的で、女性を蔑視するようなコメントを大量に投稿している人。健二もそのタイプなのですが、そこにいたるまでにはやっぱりその人なりの感情の動きがあると想像します。左翼を揶揄する時に使う「パヨク」という言葉をネット上で知って、それを自分でも使ってみたいと思う背景には、差別用語でなければ言い表せない何かが、あるのだろうなと。そんなことを考えながら、健二のエピソードは書きました。

──そして第6話「千秋と投票日」はいよいよ訪れた県知事選挙の投票日、千秋たち一家はある事件に直面します。ここには現実に起こった元首相銃撃事件が影を落としていますね。
わたしも同世代なので分かるのですが、千秋が生きていた18年は保守政権がずっと続いて、政治は変わらないもの、という諦めの感情が若い人たちに共有されていた時代だと思います。そんな中で、正や周囲の人たちはまったく違った思想を持って活動している。40代、50代の読者の方から「親が活動家って、そんなに悩むこと?」という感想もいただくんですが、千秋の抱える葛藤は現代に特有の活動家二世の感覚だと思います。この時代の家族の形を描くのであれば、やっぱり保守政権を揺るがした銃撃事件についても、触れないわけにはいきませんでしたし、それによって健二がどう変わったかも書くべきだと思いました。
──一夏の選挙戦を戦ったちぐはぐな豊田家。第6話のラストではその未来が示されるようなシーンが描かれます。こういう展開にすることは決めていましたか?
健二が積もり積もった思いをぶつけるというのは考えていましたが、それに対して正がどう反応するか、千秋がどんな言葉を発するかは決めていなくて。書きながら3人に自由に語らせたという感じです。みんなそれぞれ思いの丈を口にしてくれたので、わたしとしても良かったなと思います。
小説を書くのは、人と対話ができるから
──ヤングケアラーを描いた前作『救われてんじゃねえよ』は大きな話題になりました。『ほくほくおいも党』と前作で、共通する部分はあるでしょうか。
『救われてんじゃねえよ』は確かにヤングケアラーの物語ではあるんですが、むしろその言葉で語られる一般的なイメージからこぼれ落ちるような部分に目を向けた小説です。『ほくほくおいも党』もそれは同じで、社会問題として大きく取り上げられることはないけれど、確かに存在しているもやもやについて書いておきたいと思いました。確かにある気持ちを、存在しないことにはしたくないというか。社会の隙間にいる人たちを見つけて、小説にしていきたいなという気持ちは共通していますね。
──どちらも親子関係が扱われていますが、そこはご自身の中では大事なテーマなのでしょうか。
親子関係を扱っていない作品もたくさん書いているので、それが一番のテーマというわけではありません。書くとしたらあまりメディアで報じられていない親子関係、たとえば「親ガチャ」とか「毒親」という分かりやすい切り取り方をするのではなく、多くの人は気づいていない、でも確かに存在する傷について書いていきたいです。

──ちょっと大きな質問になってしまいますが、上村さんにとって小説を書くとはどんな意味を持っていますか。
めっちゃ難しい質問ですね(笑)。くり返しになりますが社会の隙間、石と石の間にひっそり隠れているダンゴムシみたいなものを見つけて、「これ面白いよ」と見せたいという気持ちの表れでしょうね。大人からすると「何それ」というものかもしれません。それがなぜ小説なのかといえば、人と一番対話できる表現だからだと思います。エッセイだと自分を出さないといけないので恥ずかしいですが、小説だと物語を挟めるから恥ずかしくない。仮に実話でも「フィクションですから」と言えるのが、小説の良さかなと思います。
──活動家二世というあまり注目されてこなかった問題を扱ってはいますが、普遍的な家族の物語でもあると思いました。豊田家だけじゃなく、佐和子さんと母の関係などを通して、いろんなことを考えさせられました。
書店員さんからの感想にも、「多くの人に届く家族小説として読みました」という声があって、とても励みになりました。政治の話だと思って敬遠する方もいるかもしれませんが、面白い小説になっていると思うので、気軽に手に取ってみてください。
上村裕香(かみむら・ゆたか)
2000年佐賀県佐賀市生まれ。京都芸術大学大学院在学中。22年、「救われてんじゃねえよ」で第21回「女による女のためのR-18文学賞」大賞を受賞。25年、受賞作を表題とする短編集を刊行。