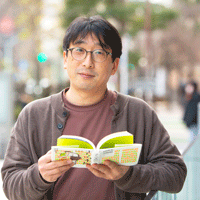田口幹人「読書の時間 ─未来読書研究所日記─」第32回
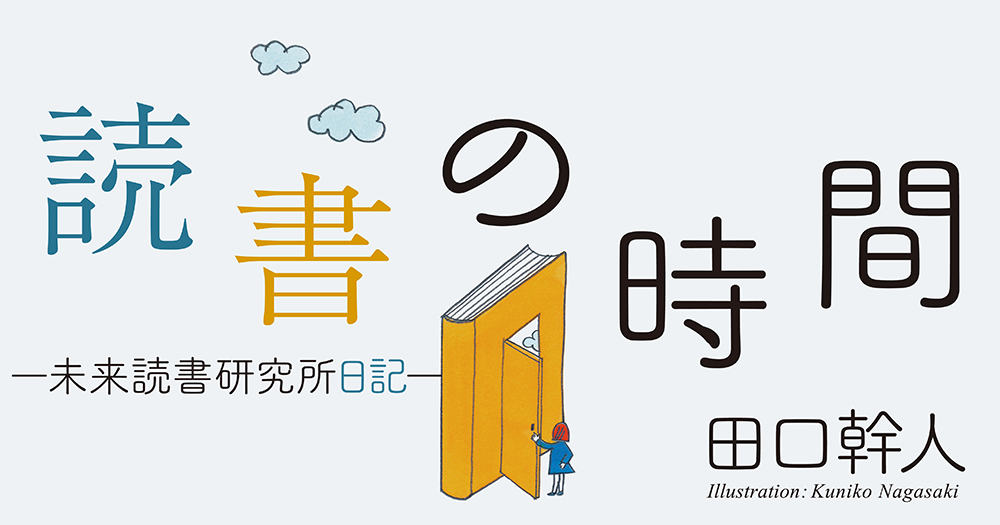
「すべてのまちに本屋を」
本と読者の未来のために、奔走する日々を綴るエッセイ
6月10日に7省庁連名(経済産業省・内閣官房・文部科学省・公正取引委員会・中小企業庁・文化庁・国土交通省)による「書店活性化プラン」が公表され、「骨太の方針」にもこのプランの推進が盛り込まれた。
これに基づく施策として文部科学省では、地域における文学・活字文化振興モデル構築事業や、図書館と学校図書館、書店を含む地域の様々な関係機関の連携協働による「読書」を通じたまちづくり推進事業を開始するなど、具体的な動きが出てきた。
本プランは、本年1月に経済産業省が取りまとめた「関係者から指摘された書店活性化のための課題」のうち、書店特有の課題として挙げた29項目を、「1.読書人口の減少や書店の魅力向上に関する課題」「2.地域における書店と図書館・自治体との連携の在り方」「3.業界慣行における課題」「4.経営における効率化・省力化に関する課題」「5.新規開店やキャッシュレス決済に関する課題」の5つに分類し、関係省庁を含めた政府が、単独または民間と協力して取り組む施策を整理したものである。
様々な施策が記載されているが、中でも「返品抑制に向けた業界を巻き込んだ研究会の開催」「書店への RFID 機器の導入支援」「業界団体を活用した低廉な決済手数料率の広報」については、太字で記載されており、今後は、この3つの施策が集中的に進められるのだろうと推察できる。
施策としては、RFID(電磁波でICタグの情報を自動認識する技術のこと)導入支援や手数料率が低いキャッシュレスサービスの周知などを行うというこれまでの情報通りであり、目新しさは感じられなかった。一方で、当初は消耗材である RFID 導入への支援に消極的だった経済産業省が、書店振興プランの切り札として RFID 導入支援を謳うに至った背景にどんなやりとりがあったのかは気になるところであり、今後の RFID 導入に向けたプロセスに注目したい。
6月16日の書店議連の総会から間を空けずに経済産業省で開催された第1回「出版産業における返品削減研究会」においても、本につけるICタグの有効性が話題の中心となっていたことを考えると、「書店への RFID 機器の導入促進」への本気度がうかがえる。
一方で、書店や取次が導入する RFID 機器については何らかの支援があると思われるが、本に付けるICタグは消耗材であることから直接的な支援は期待できない。その負担は出版社に伸し掛かることになり、研究会においても出版社サイドから懸念を表明する声が上がっていた。RFID 機器だけが普及しても、すべての本にタグが付かないことには返品抑制以上の効果を得られる施策となるかどうかは不透明である。その辺りに注目しつつ、今後の「返品削減研究会」の議論の行方を見て行きたい。
書店活性化プランの公表を受け、6月16日には「街の本屋さんを元気にして、日本の文化を守る議員連盟」(書店議連)の総会において、書店振興関係施策の拡充を求める決議がなされ、書店振興プランが本格的に動き出した。
■書店活性化の実現に向けた書店振興関係施策の拡充を求める決議(抜粋)
政府には、書店活性化プランに記載された取組に留まらず、書店の更なる活性化のため、次の取組を求める。
以下決議する。一.日本において3割近い自治体から書店がなくなるという事態は、そこに育つ子どもが書店というものを知らずに育つことを意味する。政府だけではなく、自治体においても書店振興に取り組んでいくことが期待されている。自治体により状況は様々であるが、例えば新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用することにより、地域の実情に応じて創意工夫を凝らした書店が各自治体に最低限1つは存在する「一村一書店運動」のようなものが展開されることが強く求められる。政府においてそれらの取り組みを支援していくべきである。【内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局】一.キャッシュレス決済の増加により書店における収益が減少する中、クレジットカード会社から1%台後半から2%台半ばの手数料率が提示されていることは大変大きな意味がある。ただし、その周知が徹底されていない。政府は、この取組が早期に大きく広がるよう、業界団体とともに低い手数料率の周知を徹底するべきである。【経済産業省】一.読書人口の増加は書店振興のための本質的課題であることから、読書推進人材の支援は極めて重要な取組である。政府は、絵本専門士や認定絵本士の拡大、強化、周知に向けた施策を早急に具体化し、必要があれば、予算を獲得し、実効的な対策を行うべきである。【文部科学省】一.地域の書店からの図書の購入及び装備費の扱い等についての調査にあたっては、政府の関係各省において、よく連携すべきである。【文部科学省・経済産業省】一.付録付き雑誌のセット組み作業について、その作業を無償で書店に担わせることは、書店に過度な負担を強いる行為となる可能性がある。このための適切な対価の支払いなど、政府と関係団体において対応を検討していくべきである。【公正取引委員会】一.書店の活性化には、書店自体が魅力的な書店作りに取り組むことが必要であり、そうしたチャレンジを、中小企業庁をはじめとした政府・政府機関が支援していくべきである。実体をみると、政府・政府機関の支援策がまだ行き渡っていないことから、政府は施策の周知を徹底的に行うべきである。【中小企業庁】一.再販制度下において、大手書店やネット書店における過度なポイント還元や送料無料は、特に小規模書店の経営には大きな影響が生じている。このため、例えばフランスの反アマゾン法のように規制する法律も一つのアイデアである。政府において、競争政策上の観点も踏まえて海外の事例等を参考に調査を行い、対策の必要性について検討すべきである。【文化庁】
政府において、本決議に基づく対応を強く求めたい。
以上が、経産省が発表した「書店活性化プラン」に加えて重点的に取り組む課題として決議された項目となっている。
中でも、「内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局」パートに注目したい。
現政府の政策の柱である地方創生の目玉となる「新しい地方経済・生活環境創生交付金」の活用が盛り込まれている。活用するためには、地域の事情に応じて自主性と創意工夫が求められている。各書店や書店の開業を目指す方々にとっては、可能性が広がるのではないだろうか。
ここからは、書店の地域を巻き込む推進力と企画力が試されることになる。新しいアイデアから、新しい書店(本が買える場所)が生まれるのか、すごく楽しみである。
もう1つ経済産業省の動きを挙げておきたい。
6月に入り、「エンタメ・クリエイティブ産業戦略 ~コンテンツ産業の海外売上高20兆円に向けた5ヵ年アクションプラン~」が公表された点に注目したい。
この産業戦略の中に、以下の通り書店の項目が追加されている。
【アクション】書店活性化
現状・課題⚫︎国内制作のアニメや映像化の源泉を考えると漫画を原作としているものが多く、流通経路として、書店・ネット書店・図書館がバランス良く存在することが望ましい。⚫︎一方、雑誌の売上減による収益構造の変化や、雑誌で4割、書籍で3割を超える高い返品率に伴うコスト増、キャッシュレス決済の普及による手数料負担や物流費・人件費等の上昇により書店の経営が厳しさを増し、書店の閉店が続いており、読書離れへの対応、書店への利益配分の拡大等が喫緊の課題。⚫︎こうした中で、出版社は、返本率の引き下げを条件に、書店の粗利率の向上を受け入れる旨を表明しているほか、無線技術を用いた RFID により、在庫状況、売れ筋の把握、万引き防止のためのシステムも構築。個別の本を管理することにより、委託と買取の区別を認識し、利益配分の見直しに利用されることも期待される。アクションプラン⚫︎2025年1月に公表した「関係者から指摘された書店活性化のための課題」を踏まえ、2025年6月に策定した「書店活性化プラン」を各省連携で進める。⚫︎バリューチェーン全体で返本を減らすため、デジタル化の支援に着手する。⚫︎書店が利用できる中小企業施策を発信する。
時を同じくして、遠藤利明書店議連会長は自身の Facebook で、「街の本屋さんを元気にして、日本の文化を守る議員連盟総会」の報告をしている。その中で、「読書活動を支える地域の身近な書店は、気軽に訪れることのできる夢のある空間であり、地域の重要な財産としてしっかりと守っていくべきもの」と定義する一方で、「書店や書店街は、世界に誇る日本文化・コンテンツの発信拠点ともなり得る重要な場所でもあります」とも謳っている。
これまでとは違う意味合いで書店の存在が必要であることを強調していることに、注目しておきたい。前半部分は、齋藤健前経済産業大臣時代に書店議連が挙げていた書店支援の理由を引き継いだものだが、その後の「世界に誇る日本文化・コンテンツの発信拠点」としての書店の役割を謳った言葉は、遠藤会長のオリジナルというよりも、これこそが経済産業省が書店を支える真の理由ではないだろうかと感じている。
昨今、日本の出版コンテンツは海外から注目を集めている。しかし、そこに参画することができている書店はごく一部である。世界に誇る日本文化・コンテンツの発信拠点として、書店はどんな形でここに参画することができるだろうか。
田口幹人(たぐち・みきと)
1973年岩手県生まれ。盛岡市の「第一書店」勤務を経て、実家の「まりや書店」を継ぐ。同店を閉じた後、盛岡市の「さわや書店」に入社、同社フェザン店統括店長に。地域の中にいかに本を根づかせるかをテーマに活動し話題となる。2019年に退社、合同会社 未来読書研究所の代表に。楽天ブックスネットワークの提供する少部数卸売サービス「Foyer」を手掛ける。著書に『まちの本屋』(ポプラ社)など。

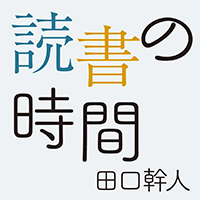
![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[後編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/10/honmado202211SP_t.png)
![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[前編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/08/honmado202209SP_t.png)