東山彰良『怪物』
「愛と自由」の物語
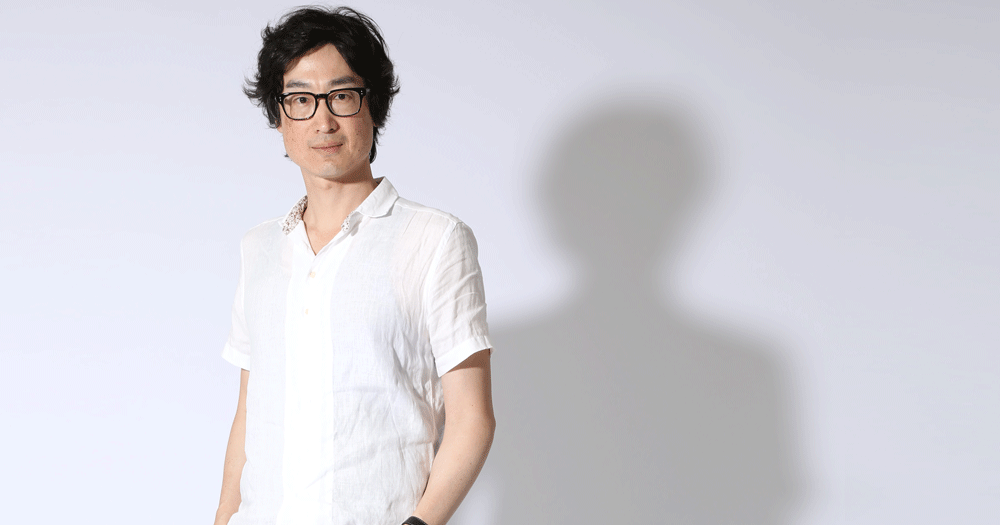
台湾を舞台にした青春ミステリー『流』で二〇一五年に第一五三回直木賞を受賞した東山彰良が、まもなくデビュー二〇周年を迎える。最新長編『怪物』は、日本に暮らす小説家の現実が自作小説によってじわじわ侵食される様子を綴りながら、戦後アジアの歴史をも浮かび上がらせる。二〇年の蓄積があったからこそ飛び立つことができた、新境地だ。
東山彰良にとって直木賞受賞作『流』は、台湾出身という己のルーツを題材にした初めての作品だった。しかし、決して勝負作のつもりで書いたわけではなかった。
「自分の父親から聞いた思い出話などを利用して、気楽に書いた小説でした(笑)。その小説が大きな賞をいただき、他言語に翻訳されたり海外のブックフェアにお招きいただいたりするようになって、台湾や中国や日本、自分が関わってきた国のことを考える機会が一気に増えたんです」
そして、自らのルーツなどを意識するなか、それぞれの国の歴史やかつて実際に起きた不幸な出来事の記憶などを、作品の中に織り込んで伝えるという着想を得たという。
「ただ、自分が書くべきものは歴史小説ではないという判断は最初からありました。歴史的事実だけにフォーカスして書くのではなく、現代のエンタメ小説の中に史実を入れ込んでいったほうが、印象に残るものになるのではないかと思ったんです」
脳裏に思い浮かんだのは、ある文学作品だった。
「村上春樹さんの『ねじまき鳥クロニクル』です。あの小説は主人公と家出した奥さんの関係が本筋としてあるんですが、そこはあくまでも読者にページをめくらせるエンジンのような役割であって、村上さんが本当に書きたかったもののひとつは、途中に出てくるノモンハン事件のエピソードではないかという気がします」
一九三九年五月から九月にかけて、日本軍とソビエト・モンゴル人民共和国連合軍との間で起きた満州国境線をめぐる紛争だ。
「読み終えた後にあの紛争の描写が妙に心に残るのは、〝恋愛小説の中にどうして戦争が出てきたんだ?〟という違和感が作用しているからではないかと思ったんです」
現代に暮らす男性の主人公が女性との恋愛問題で煩悶する、その過程でかつての戦争や悲劇のエピソードが生々しいほど綴られていく──。自身の読書体験を振り返った時に、パキスタン出身の作家モーシン・ハミッドの『西への出口』など、こうした構造を採用している文学作品がいくつも思い浮かんだ。そして、その営みの末端に、自作を位置付けてみようと決めた。
「男女の恋愛感情は、ぼくがこれまであまり手をつけてこなかった題材でした。そこをどう描くかは今回、自分に掲げた大きな課題でした」
タイトルは『怪物』。台湾出身、日本育ちの小説家・柏山康平を主人公に据えた、恋愛と創作の地獄巡りの物語だ。
足場を現実に置くことでフィクションが膨らんだ
本冒頭の一文は、〈鹿康平が怪物を撃ったのは一九六二年のことだった──『怪物』という小説を、私はそのように書きだした〉。
『怪物』は、現在四七歳の柏山康平が一〇年前に発表した小説のタイトルでもある。同作が英訳され国際的な賞の最終候補となったことで、柏山康平はにわかに文壇のスターとなった。そんなおり、台北世界貿易センターで開かれたブックフェアに招かれ、通訳として担当に付いたのが、日本の出版社で働く二九歳の椎葉リサだった。「先生の本が好きなんです」と初対面の彼女は言った。柏山康平が書くものの魅力は、「愚直なまでの素直さ」だという。
柏山は男女関係へと発展することを期待するが、彼女に夫がいることを知らされ、冷静さを取り戻す。しかしその夜、二人はホテルの一室で抱き合った──。
「中国、台湾の歴史について書くことは決まっていましたから、現実パートはできる限り身の丈に合ったもの、自分自身をモデルにしたお話のほうが、読者さんも読みやすいんじゃないかなと思いました。足場はしっかりさせておいたほうが、その先のフィクションが膨らむという予感もあったんです。僕はプロットをきちんと練り込んで書き始めるタイプではないので、作品に対していい予感が持てるかどうかが非常に重要なんですよね」
リサと一夜を共にした直後から、柏山の現実に自作小説『怪物』で書いた場面がフラッシュバックするようになる。展開が進むにつれて、作中作として挿入される『怪物』のボリュームがどんどん増えていく。それは、こんな物語だ。
戦後台湾の空軍に実在した「黒蝙蝠中隊」の一員だった二四歳の鹿康平──モデルは柏山の叔父・王康平、彼は一九五九年五月二九日、B−17に乗り込み中国大陸へと偵察飛行に出かけ、撃墜される。当時、毛沢東による大躍進政策真っ只中の中国は、鉄鋼事業に心血を注ぎ人民の食糧需給は二の次とする、飢餓大国だった。にもかかわらず三年後の一九六二年、鹿康平は家族と婚約者が待つ台湾へ帰還することに成功した。空白の三年間に何があったのか?
「中国の現代史を俯瞰すると、大躍進政策の前には国共内戦や日中戦争があり、後には文化大革命が起こります。大事件の谷間に起こっているため、当事者たちを除けば大躍進政策はあまり日の当たらない存在かもしれません。ですが、僕は大学院の時に中国経済を専攻していたので馴染みがありました。中国という国の一側面が、そこに象徴されていると思っていたんです。この時代の中国に、台湾人の青年をさまよわせてみたら何が起こるか。生き延びるために彼はどこまで自分の心を腐らせるか。もしくは越えてはならない一線を自分なりにどう引くのか」
愛と自由を反復し意味を増幅させる
そもそもなぜフラッシュバックが起こるようになったのか? 柏山はリサとの恋愛をきっかけに、「愛と自由」の関係について考えざるを得なくなったからだ。『怪物』の主人公・鹿康平は、愛のために自由を捨てた。ならば自分はどうか……。出版社から『怪物』の文庫化を打診されていた柏山は、リライト作業に臨む。
「平時であっても戦時中であっても、人生の分岐点においてどの道を選ぶかという場面では、愛と自由が関わってくるという確信があります。自由に生きていると思っていても、どこかで愛に縛られている。愛が一番だと言いながら、どこかで自由を求めている。このテーマを現実パートと作中作パートの双方で反復することで、意味を増幅させることができたらと考えました」
柏山の内側で小説と現実の境界線が少しずつ混じり合っていくプロセスには、ホラーの感触さえ宿っている。しかし、暗闇をくぐり抜けた先には、新たなる地平が広がっている。例えば、物語が幕を開けた当初の柏山康平は、愛は相手から与えられることから始まるものだ、と思っていた。しかし、恋愛と創作の地獄巡りのすえ、愛とは自分から先に相手へ差し出すものであると認識を変える。
〈自分の弱さにリボンをかけて相手に差し出したその瞬間、愛が芽吹くのだ〉
初稿時にはなかったという、この一文は、「頭から何遍も何遍も推敲していく中で、僕自身がこの物語から学んだ」末に生み出されたのだという。
書くことは自分を救うことである、と柏山康平は考えている。ならば、自分にできたことを書くのではない。できなかったことを書くのだ。つまり──「愛と自由を両方手に入れる」。新たなる『怪物』を完成させようと挑む柏山康平の格闘は、東山彰良自身を投影させたのだろう。歴史パートを読みこなしやすくするために恋愛小説の衣をまとう、という執筆当初の思惑は、いい意味で裏切られていった。
「第二部の冒頭でちょっとだけ出てくる主人公の妹が、兄の小説に対して非難めいた台詞をいう場面があります。〝自由について書いた本をありがたがる人って、けっきょく愛のない人たちだったんだね〟と。この台詞は、東山彰良という作家自身に向けた台詞でもあるんですよね。ですが、興味がなかったわけではなかったんですよ。むしろ人生の中では、〝愛とは何か?〟とずっと考えてきたんです。その部分が、自分でもびっくりするぐらい出てしまった小説になりました」
脱獄モノのデビュー作『逃亡作法 TURD ON THE RUN』(二〇〇三年)以来、自由をテーマにした小説を書き継いできた著者による、「愛と自由」の物語はこうして完成した。
台湾生まれの小説家柏山は、『怪物』の執筆によって国際的な評価を得た。台湾空軍の精鋭ながら撃墜され、毛沢東治世下の中国に落下した叔父をモデルとする小説だ。叔父は台湾に生還を果たす。だが、飢餓の大陸でいかに生き抜いたかについては謎が残った。小説内の叔父と実在の叔父、小説家自身の物語が織り成す傑作長編。
東山彰良(ひがしやま・あきら)
1968年、台湾台北市生まれ。9歳の時に家族で福岡県に移住。2003年、「このミステリーがすごい!」大賞銀賞・読者賞受賞の長編を改題した『逃亡作法 TURD ON THE RUN』でデビュー。15年『流』で直木賞、16年『罪の終わり』で中央公論文芸賞、17年から18年にかけて『僕が殺した人と僕を殺した人』で読売文学賞などを、それぞれ受賞。
(文・取材/吉田大助 写真提供/太田真三)
〈「STORY BOX」2022年3月号掲載〉



