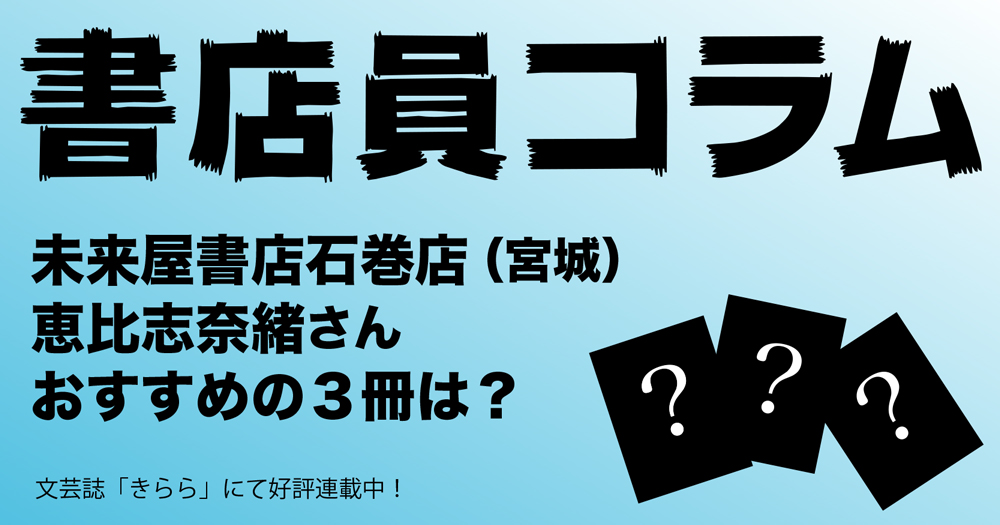小さな本棚から
生きているもの以外は、ただはっきりと死んでいる。ティム・オブライエン『本当の戦争の話をしよう』は、作者が自らの従軍体験を基にベトナム戦争でのアメリカ兵を描いた短編集だ。そこに英雄はおらず、華々しき死もまた存在しない。躍動し死線を掻い潜る戦闘の活写も、愛国を叫ぶ突撃の場面も。ある者は地雷に吹き飛ばされて形をなくし、ある者は汚物のぬかるみに沈み消えてゆく。理不尽で不恰好で愛想のないシュールな絵画の連続は、それを眺める者によって意味を与えられる事を、強く拒絶する。

小川洋子『ブラフマンの埋葬』は美しい物語だ。芸術家に作業場所を提供する〈創作者の家〉の管理人と、彼のもとに現れた小動物(のちにブラフマンと名付けられる)が過ごした時間が、職人の手仕事を思わせる無駄のない筆致で、丁寧に描かれる。ブラフマンは陽光の輝く庭を駆け、世界の秘密を探るようにあらゆる匂いを嗅ぎまわり、たっぷりと湧き水を湛えた泉を、優雅に伸びやかに泳ぐ。いくたびも語られる死者や古代墓地の風景との対比が、眩しく愛くるしい生命の輪郭をいっそう際立たせる。これらの情景は、初読から十数年が過ぎた今でも、私の胸に余韻を残したままだ。

「落としたコンタクトレンズ」を探すのはOK、「蝶々の唇」を探すのはNG。前者は具体的な役割や社会的に認められた価値を持つが、後者は具体性がなく、役に立たない代物ゆえ、社会的には無価値とされる。歌人の目が捉えるのは後者に宿る美しさだ。穂村弘『はじめての短歌』で著者は様々な短歌を取り上げ、自らによる改悪例と解説を示し、すぐれた歌の魅力の所以をロジカルに説く。社会は言葉を手酷く扱うものだ。みなが円滑に「生きのびる」ために、数多の言葉は飲み込まれ削られ希釈され毒を抜かれ、蝶々の唇など初めからなかった事にされてしまう。抜け殻となった言葉と画一化された関係性。その狭間を「生きる」ために、一見して無価値な出来事や日々の繰り返しの中に美しさを見出そうとする時、短歌は強靭な武器となる。めいめいが「社会的価値の有無」というくすんだフィルタを剥ぎとり、むきだしの感性をもって向き合えば、日常は鮮やかな短歌の世界へと色調を変えるだろう。社会という味気ないフィクションは息絶え、言葉は息を吹き返すのだ。