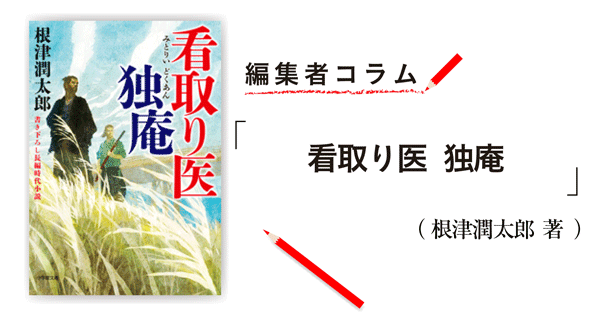◎編集者コラム◎ 『看取り医 独庵』根津潤太郎
◎編集者コラム◎
『看取り医 独庵』根津潤太郎

どなたとは申しませんが、ある直木賞作家が、こうおっしゃいました。人生で大事なものは、健康、愛情、学問、それもこの順番で大事なのだと。読者諸兄姉もこの見解に否やはありますまい。さて、江戸時代の庶民はどう病を克服していたのか。また、患者を診る医者は、どんな心構えで医療を行っていたのか。そんな思いにとらわれた現役の医師が時代小説に挑戦しました。さて、現代の医学博士が思い至った、あるべき医者の姿とは――。
頃は江戸中期。京の山脇玄脩(はるなが)に師事した独庵こと壬生玄宗は、長崎にも遊学して、古方(漢方)と西洋医学を修めた。父の跡を継ぐべく、仙台藩の奥医師を務めていたが、ゆえあって江戸に出ると、浅草諏訪町に診療所を開いた。
医術の腕は天下一品、時の老中・田安備前守の病を治したことで評判が評判を呼び、診療所を切り盛りする女中のすず、代診の弟子・市蔵ともども休む間もない。だが、門前市をなす理由はそれだけではなかった。
裕福な商人からは法外ともいえる診察代を頂戴する。弱みを握った札差には、医学の進歩のためと称して遠慮会釈なく無心する。そのくせ、大枚を要求された相手方が、独庵を蛇蝎のごとく嫌うかというと、そういうこともない。医者の腕前を測る基準は金しかないと思い定めているくせに、庶民の診察代は一律三分と決めて揺るがない。
医者の本分はもとより病を治すこと、では、治らぬ病はどうする。医者ができることはあまりに少ない。独庵が悩んだ末にたどり着いた結論は、不治の病に苦しむ人々に希望を与えることだった。独庵は、人らしい生き方、死に方を望まれれば、看取りも辞さない、と覚悟する。
仙台にいた16歳の時、敬愛していた姉が病没し、最初の妻は結婚2年目で死別した。江戸に移り住んで十有余年、四十の坂を越えた総髪の大男は剣の腕もたち、一見強面だが、酒はまったくの不調法、女人にはついつい腰が引けてしまう質らしい。どうにも煙たい二度目の妻は、元服近い息子とともに仙台藩下屋敷に住んでいる。
そんな独庵に妙な往診依頼があった。人目を忍んでやってきた材木問屋『扇橋屋』の内儀・志乃の話では、主の徳右衛門が、なにかに憑りつかれたように、薪割りを始めたという。独庵と徳右衛門は旧知の間柄、早速、屋敷に出向くと、惚けたのではないかと疑う志乃の心配をよそに、上半身裸の当人が薪割りの真っ最中。どうやら、脇腹に腫物があり、さる奥医に診てもらったところ、不治の病だと言われたようだ。せめて女房の志乃に、一生使えるだけの薪を残してやりたい、と徳右衛門は言い張る。しかし、独庵が触診したところ、ただの腫物に過ぎない。どうやら、徳兵衛もうすうす、命にかかわる病ではないと知っているようだ。では、いったいなんのための薪割りか。
独庵とて、そんな与太話を真に受けるわけがない。独庵の手となり足となって、さまざまな事件の真相を探る絵師・久米吉に調べさせたところ、思いもよらぬ仇討ち話が浮かんできた。徳兵衛の家は元武家で、志乃は徳兵衛が通っていた肥前柳生流の道場師範の娘だった。しかも、志乃が徳兵衛に縁付いた裏には、複雑な事情があった。
生きるも死ぬも、江戸庶民とともに!看取り医にして馬庭念流の遣い手・独庵が一刀のもとに悪を両断する痛快書き下ろし時代小説。

──『看取り医 独庵』担当者より