貴志祐介さん『我々は、みな孤独である』
自分はなぜ自分なのか
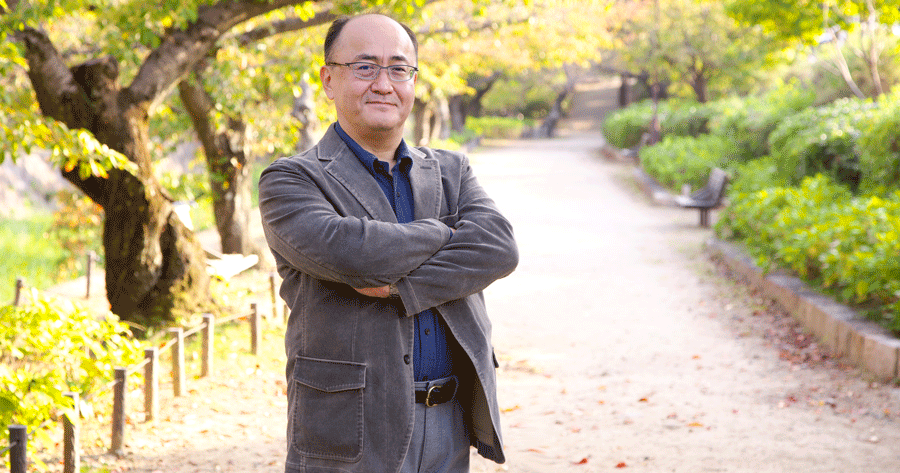
『黒い家』『悪の教典』などで知られる貴志祐介が、実に七年ぶりとなる長編『我々は、みな孤独である』を刊行した。
主人公たる私立探偵にもたらされた「前世の殺人」を巡る依頼は、やがて人々が「前世」なる概念を求める理由そのものを巡る問いへとつながっていく。まごうことなき、新たなる代表作だ。
最初はショートショートで書こうかと思ったアイデア
唯一の小説指南本『エンタテインメントの作り方 売れる小説はこう書く』において、貴志祐介は次のように記している。〈小説の本質は妄想であると、私は思う。いかに詳細に説得力を持って妄想できるかが、勝負の分かれ目なのだ。そして、もうひとつ。どこまでオリジナリティのある、つまり異様な妄想を紡げるかが重要である〉。
最新長編『我々は、みな孤独である』ほど、その信念が体現された作品はないかもしれない。何よりもまず、「異様な妄想」のスケールが甚だしく大きい。その妄想が「詳細に説得力を持って」綴られていく点も、徹底されている。
「前世にまつわるオチのアイデアを思い付いたことが、きっかけでした。最初はショートショートで書こうかなと思ったぐらいの、ある意味で無茶なワンアイデアなんです。人によっては〝ふざけるな!〟と言うんじゃないかと思います(苦笑)。そういったアイデアをちゃんと説得力の感じられるものとして伝えようとするならば、具体的なエピソードを重ねることが重要になってくる。幾世代にもわたる、さまざまな人生を描く必要もありました。その結果、四〇〇ページを超える長編になっていったんです」
リアルな世界の探偵ならリアルな解決を探索する
冒頭で掲げられるのは、不可解な「謎」だ。私立探偵の茶畑徹朗は、大企業の会長・正木栄之介から人捜しの依頼を受ける。相手の氏名は不詳であり、場所も特定できない。そもそも実在したのかどうかもわからない。なぜならば、正木が夢で見た人物だからだ。夢の中で正木は、江戸時代の無名の百姓だった。そしてある夜、殺された。「犯人……つまり、私を殺したのが何者だったのかということ」。しかも正木は、自分が見たものは夢ではなく「前世の記憶」だと主張した──。
「最初はできるだけ現実感があってミステリーらしい、前世にまつわる謎を出した、つもりです(笑)。謎そのものよりも、主人公像が大事だったかもしれません。こういったオカルトめいた謎を追う物語では、主人公もオカルトを信じているパターンが比較的多いのではと思うんですが、茶畑は全く信じていない。とことんリアリストなんです」
茶畑は、正木からヒアリングした夢の話のテープ起こし原稿を、売れない作家に渡して短編小説にしてもらう。「これは失踪した小説家の残した原稿だが、どうも史実に基づいているらしい」。そう言って小説を郷土史家に読ませ、情報を拾い上げることによって、リアリティのあるウソをでっちあげようとするのだ。
「彼はカネのために依頼を受けますけれども、どうせ正しいか否かなんて誰もわかりはしないんだから、依頼人が満足すれば別にそれでいいじゃないかと考える。ミステリーの世界の探偵としては異端ですが、リアルな世界に生きている人は、リアルだと感じられるような解決を探すと思うんですよ。つまり、相手にとって受け入れやすいようなかたちに、真実を加工してみせる。茶畑が問題解決のためにおこなっていることは、現実的な思考法だという気がします」
面白いのはその短編小説が、本文中に劇中劇のかたちで掲載されているところだ。
「視点人物が主人公ですから、背後からやってきた何者かに鎌で喉を掻き切られたところで小説は終わります。謎に明確な答えが与えられないまま話が終わる、いわゆるリドルストーリー(riddle story)なんです。以前からリドルストーリーは書きたいなとは思っていたんですが、単独の作品として書くのは難しかったんですよ。昔は良かったんだと思うんですが、今やると手抜きだ、解決編はどこにあるんだと読者さんから怒られてしまうのが目に見える(笑)。長編の中にひとつのアイデアとして入れ込むことで、今回ようやく書くことができたんです」
実は、このリドルストーリー(「前世の私を殺したのは誰だ?」という冒頭の謎)は、全体の三分の一を過ぎたところであっさりと解決がもたらされる。そして、その謎を追うことよりも切迫した、危険な状況が立ち上がってくる。くだんの小説を読んだ人間が、前世の記憶を思い出し始めるのだ。謎が謎を呼ぶ、とはこのことだ。
「奇想を何か一つ思い付けば小説が書けた、という時代はもう終わりましたよね。ミステリーの話をするとわかりやすいんですが、単体で勝負できるような斬新なトリックはほぼ出尽くしている。ですが、個々のトリックを自分なりに現代的にアレンジし、なおかつそれらを組み合わせることによって、これまでにはなかった全く違うものが生まれてくると思うんです」
不可能を排除していった時、最後に残ったものが真実だ
物語が進展するにつれて、リアリストであるはずの茶畑が徐々に、前世の存在を信じざるを得なくなってくる。その変化を丁寧に描くことは、終盤の展開のためにも重要だった。
「シャーロック・ホームズは〝不可能を排除していった時、最後に残ったものがどんなにあり得ないことであっても、それが真実だ〟と言っています。そうは言っても、その真実は到底あり得ないと読者さんに思われてしまったら、作品としては失敗ですよね。そこのバランスは、ミステリーを書いていていつも難しいなと思うところなんです。今回であれば、茶畑が頭で考えるだけではなく、自分の肉体で何かを実感して、納得していくという過程を読者さんに追体験してもらうことが大事だったのかなと思います」
茶畑はヤクザの丹野から、失踪した探偵事務所の従業員・北川遼太の借金返済を迫られる。丹野のせいで事件に巻き込まれ、暴力にさらされる展開というのも……。
「私は残虐シーンを書くのが好きだ、と思っている読者さんも多いかもしれないですが、そんなことはないです(笑)。特にこの作品は、最後に出てくる結論があまりにも突拍子もないものだからこそ、そこへ辿り着くためにさまざまな角度からはしごを掛けていく必要がありました。躊躇なく暴力を振るう丹野の非道さを通して、痛みや残虐性を目の当たりにすることは、不可欠なはしごの一つでした」
もう一つ、不可欠なはしごがあった。東日本大震災で津波に襲われ、亡くなった茶畑の恋人・亜未の存在だ。
「雑誌連載が終わってから本になるまで六年半かかったのは、何かが決定的に足りないとずっと思っていたからなんです。具体的にいうならば、連載時はもっとバイオレントでしたし、終幕に向かうにつれて作品世界が本当に殺伐としていました。でも、主人公を救う方向にストーリーを考えるのが、小説の肝なのかなという気がするんですよ。悩んだ結果導き出したのが、連載時には登場すらしていなかった亜未の存在でした。茶畑は日々、亜未のつらい記憶を引きずって生きているわけです。その記憶が、土壇場へとやってきた時に、自分を発狂から救う最後のよすがになる。マイナスがプラスになる、逆転の展開を付け加えられたことで、ようやく完成したという気がしました」
この物語が最後に辿り着く、あまりにオリジナルであまりにも奇想天外な結論は、実際に読んで体験してもらう以外に、リアリティを持って伝えるすべはない。
しかし、この物語に埋め込まれた「真の謎」については、語ることができるかもしれない。誰しも共感できる、普遍性を持っているからだ。
「幼稚園に入るもっと前、おそらくは物心がついてすぐの頃から〝どうして自分は、自分なんだろう?〟と疑問に思っていました。生まれた時から幸せな人生が約束された環境にいる人もいれば、個人の努力ではもはやどうにもならない環境にいる人も大勢いる。前世とか来世って、今世がままならないと感じた人がたくさんいるからこそ生まれたし、信じられてきた考え方だと思うんですよね。
いずれにせよ〝どうして自分は、自分なんだろう?〟と考えていっても、明快な答えなんて当然出ません。そこで生じる気持ち悪さに決着をつけるつもりで書いたのが、この小説の結末でした。これが真実である、と言うつもりは毛頭ありません。ですがこの小説を読んだ後は、自分が自分であることの苦痛がちょっと和らいで、人に対して優しくなれるかもしれないなと思うんです」
闇金から取り立てをうける零細探偵事務所に、VIPクライアントから不思議な依頼がもたらされた。前世の自分を殺した犯人は誰か。依頼者の見た夢を頼りに「前世」の時代や地域を特定していくが──。一風変わった探偵物語は、次第に人類の大いなる謎を巡るミステリーへと変貌を遂げる。
貴志祐介(きし・ゆうすけ)
1959年大阪府生まれ。京都大学経済学部卒業。96年「ISOLA」で日本ホラー小説大賞長編賞佳作を受賞し、『十三番目の人格ISOLA』と改題し刊行される。97年『黒い家』で日本ホラー小説大賞、2005年『硝子のハンマー』で日本推理作家協会賞を受賞。08年『新世界より』で日本SF大賞、10年『悪の教典』で山田風太郎賞を受賞した。
(文・取材/吉田大助 撮影/林 景沢)
〈「STORY BOX」2021年1月号掲載〉


