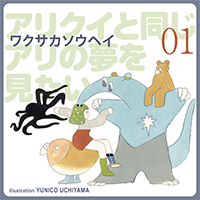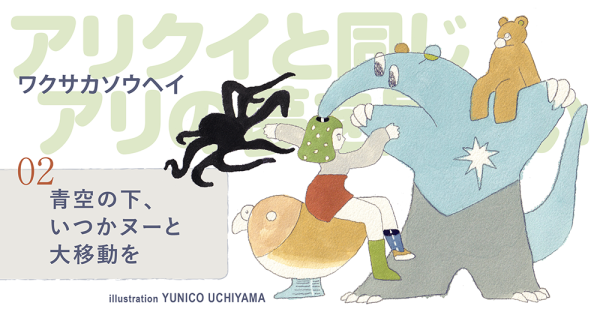ワクサカソウヘイ「アリクイと同じアリの夢を見たい」#02
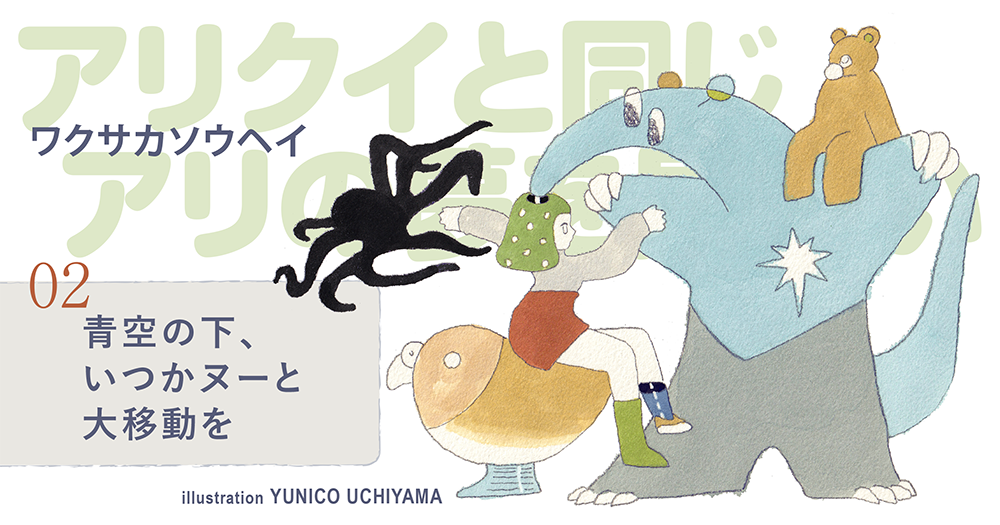
02 青空の下、いつかヌーと大移動を
ヌーの大移動に参加したい。
そんな衝動を抱くようになったのは、いつの頃からか。
ヌーの大移動を、ただ傍観したいのではない。
ヌーたちの中に混じって、一緒に大移動をやり遂げたいのだ。
自分の人生の卒業アルバム、そこの一面を大きく飾るような。そんな体験を、ヌーたちと共に達成してみたいのだ。
生き物全般に興味がない人であっても、「ヌーの大移動」というフレーズだったら、一度は聞いたことがあるだろう。
アフリカ大陸の中南部に生息する、ウシ科の哺乳類。それがヌー。面長であり、意味深に湾曲した角を頭上に持ち、修行僧のような髭を喉元から生やしている。上半身はたくましい筋肉を纏っているが、打って変わって下半身はほっそりとした印象。なんとも奇妙な味わいを風貌から醸している生き物である。
彼らはある時期に、北海道から沖縄までの距離に匹敵する、二千八百キロメートルにも及ぶ大移動の旅へと繰り出す。
その数、約百三十万頭。東京都世田谷区の総人口数を超える、巨大な群れでの移動である。
ヌーはなぜ、そのような大移動を群れで繰り返すのか。最も有力な説は、「雨季の草地を求めるため」である。乾季が来れば、食物としている植物たちが枯れてしまう。そうなる前に、彼らは旅へと出発する。道中に草を食みながら、より緑の豊かな大地を目指して、歩き続けるのである。
規格外のピクニック、と呼びたくなるが、しかしヌーの大移動はそこまで平和的なものではない。移動の最中、ライオンに襲われる者もいれば、川の濁流に飲み込まれてしまう者もいる。それは命を賭して開催される、野生の大祭なのである。
そんなヌーの大移動に、どうしても、参加したい。
それが私の、積年の願いであった。
その切望の根底には、青い季節の苦い記憶が広がっていた。
青春時代の本番が始まった高校入学時、私は途方もない絶望感を味わっていた。
クラスメイトたちは、入部届を次々に担任の先生へと提出している。テニス部、バレー部、演劇部。誰もが、放課後にどのような部活動に参加するのか、はっきりとそこに表明していた。
そんな中、私はひとり、それを白紙のままでゴミ箱へと捨てる。
そう、「帰宅部」という選択をしたのである。
本当は、なにかしらの部活動に打ち込んでみたかった。青春の甘い蜜を全力で吸ってみたかった。しかし、私には勇気がなかった。
何に対しての勇気なのか。それは「集団性」に参加するための勇気である。
思いきって定義するならば、青春とはつまり、「集団性」に他ならない。
仲間たちと共に、汗をかく。
仲間たちと肩を組み、涙を流す。
仲間たちと達成感を得て、笑い、そしてハイタッチをする。
群れて、つるんで、結束することでしか、青春の髄液というものは堪能できない。孤独な者のもとには、鮮やかな青春など訪れることはない。
しかし。
以前から薄々気がついてはいたのだが、自分はどうにも、「集団性」が苦手な性質であるようなのだ。
協調性や同調性が必要な場面の中にいると、どうしてもそこから逃げ出したくなってしまう自分がいた。中学校の移動教室の際には、班からそっと抜け出して、ひとりでお弁当を食べるなどしていた。
こうした人間が、高校生になって、颯爽と部活動に参加できるわけがない。楽しい学校生活を送るためには、集団の輪の中に入ったほうがいいってことくらい、自分だってわかっている。でも、入部届を前にしたら、右手が動かなかったのだ。
私は、青春にエントリーするための勇気を、持ち合わせてはいなかった。
こうして、根の暗い放課後が始まってしまった。
帰宅部の活動というのは、それはそれは陰惨なものである。顧問も、全国大会も、目指すべきタイムも存在していない。それが帰宅部。ただひたすらに、ひとり、放課後に家路を辿るだけ。
他の同級生たちが仲間たちと部活動の中で青春の輝きを煌めかせていたその頃、私は道の上に落ちている乾いた軍手や雨水を含んでぶよぶよになった湿布を目に留めて「……新種の生き物!?」と一瞬だけびくっとする、みたいな誰とも分かち合えない鈍色の情緒をささやかに展開するばかりであった。ああ、帰宅部。それは青春の景色から最も遠い場所にある部活動。
そんな孤独な高校生活を送る私にも、二学期になるとチャンスが巡ってきた。
青春の大祭、すなわち文化祭である。
私の通う高校では、秋の文化祭にてクラスごとの演劇作品を発表するしきたりが設けられていた。クラスメイト達が一丸となって、声を嗄らしながらの稽古を行い、本番に向かって結束するのである。帰宅部である私も、青春の動脈に触れることができる、またとない機会だ。
ところが私は、ここでも怯みを発揮してしまう。
文化祭実行委員に自ら立候補し、会の書記係に収まってしまったのだ。
運営側にまわると、クラスの演劇活動には参加ができなくなる。本当は、同級生たちと発声練習をしたり、作品に対する演出解釈の違いについて討論したりと、いましか味わうことのできない青春のあれやこれやに触れてみたかった。しかし、どうしても「集団性」というものに及び腰になってしまう私は、そこに足を踏み入れることができず、直前で「運営サイド」という免罪符を手に入れて、青春の重要シーンから逃げ出してしまったのである。
文化祭実行委員会の書記係として私に与えられた役目は、とにかく議事録を作成することだけである。そして文化祭の本番が近づくと、議事録をとるような会も開催されなくなり、手持ち無沙汰の状態になる。生き甲斐もなく、ただぼんやりと虚ろな時間の中に漂っていると、そこに目を付けられ、実行委員長からある仕事を命じられた。
「門を作ってくれないか」
文化祭開催当日は、地域住民などの一般客も校内へと訪れる。その客たちを迎え入れるための、校門前に設置する特別仕様のアーチを作る役目を、仰せつかったのである。
私の他にも、暇そうにしていた各学年の委員たちが数名集められ(全員が帰宅部だった)、校内の隅の陽の当たらない場所で、木材やらブロックやら不織布やらで「門」を作ることに精を出す、という放課後が始まった。
「青春の門」というのは聞いたことがあるが、「門の青春」というのは、聞いたことがない。お互いの「門」観の相違について熱くディスカッションを交わしたり、「最高の門を作ろうぜ!」とリーダーシップを発揮する先輩が登場したり、メンバーのひとりが釘を打ち付けている最中に指を負傷、「門のことはお前たちに任せたぜ……」と言いながら病院に運ばれていき、全員で涙する、みたいなドラマが発生したり、なんてことは一切ないまま、「門」は無言の中でひっそりと完成した。もちろん、なんの達成感も得なかった。
そして文化祭本番の翌日、「門」は解体され、焼却炉の中へと消えていった。
クラスメイト達は、演劇発表の打ち上げでファミレスに行き、そこで誰々がドリンクバーのコーラを九杯も飲んでいた、みたいな話で盛り上がっていた。私はもちろん、その打ち上げには参加していない。「門」を作っていただけの者は、そんな青春の輪の中に参加する資格を持ち合わせてはいないのだ。クラス中に響く弾んだ声たちを、ひとり静かに、苦々しく聞いていた。
私の青春は、そんな感じで、常に日陰と共にあった。
青春を、青春として果たすことができなかった。
その事実は、大人となってからも、尾を引いた。
社会に参加しているはずなのに、なんだか自分だけが浮いているような、なんだか仲間外れにされているような、そんな居心地の悪さが全身に纏わりついている。だから、大きなものに巻き込まれそうになると、つい尻込みをしてしまう。
「集団性」に耐性をつけることなく、大人になってしまった。それはある種のコンプレックスであった。
ああ、勇気を出して、あの頃に青春を全うしてさえいれば。
私は、一回性である青い季節を、大人になってから呪うようになっていた。
ある時に、NHKで「ヌーの大移動」についての特番が放映されていた。
それに目を留めた瞬間、衝撃に貫かれた。
百万頭以上の黒い群れが、一心不乱に川を越えていく。ワニに仲間が屠られ、血に染まる水辺。それでもヌーたちは大移動を止めることをしない。草原をひた走り、目指すべき場所へと猛然と行進を続ける。
画面越しで観ても、その「集団性」のスケール感に腰が抜けそうになった。
部活動や文化祭なんて、比較にもならない。圧倒的な青春ではないか。
野生には、このように人智の及ばぬシーンが存在しているのか。
帰宅部や書記係であったことをいまだに引け目として思っている自分。そんなものは、このヌーたちの躍動の前では、ひどくちっぽけなものに思えた。頰を殴られたような気分だった。
それから、折に触れて「ヌーの大移動」のことを頭に思い浮かべるようになった。
次第に「ヌーの大移動の景色」と「理想的な青春の景色」とが、私の中で、どんどん強く結びつくようになっていく。
自分もヌーのように、仲間と共に駆け抜ける青春を送ってみたかった。
青春は、二度と戻らない。しかしヌーの大移動は、いまもアフリカ大陸で巻き起こっている。
その想いは、時間をかけ、ゆっくりと積もり続け、やがてこのような衝動へと化けていった。
「ヌーの大移動にマジで参加したい。そして、無二の達成感を得たい」
そうすれば、失われた青春の輝きを、いまからでも取り戻すことができるのではないか。
そうだ、私の青春は、校舎の中には存在していなかったのだ。あのヌーの群れの中にこそ、かけがえのない盛りの瞬間が待っているのだ。
もう衝動を、止めることはできなかった。あの頃に出せなかった勇気、それを振り絞るタイミングが、ついに訪れた。
気づけば私は、アフリカ大陸のタンザニアへと向かっていた。
ウシ科の集団に混じるために。青春をやり直すために。
その時期、ヌーの大移動はフィナーレを迎えようとしている最中だった。
終着点であるセレンゲティという大草原へと、長い旅路のラストスパートを駆け抜けている、そんな絶好のタイミングである。
当たり前だが、ヌーの大集団の中に、生身の人間が参加していい権利などはない。そもそも移動中のヌーは神経質になっており、人間が近づくだけでうろたえることもあるという。
野生の邪魔をすることは、絶対的な禁忌だ。ヌーの方向感覚を失わせるような真似はしたくない。私はヌーの現在の移動ルートを調べてから、四駆車をチャーターした。そしてドライバーを務めてくれるエマニュエル氏というベテランのサファリガイドに「なるべくヌーには近づかず、遠くに見える集団の影を横目で追いながら、大移動と並走してください」とお願いした。
アルーシャという小さな街から出発し、八日間にわたる「ヌーの大移動に参加する」旅が始まる。
ンゴロンゴロ・クレーターという巨大なカルデラを抜けていくと、果てしない大草原の広がりがある。その上空を、無限の青空が覆っている。この世の景色とは思えない。
悪路に揺れながら、四駆車は真っすぐに駆け抜けていく。
車窓の先を見ると、句読点みたいな感じで、ポツポツとインパラやトムソンガゼルの姿がある。あれ、なんだか樹が動いているぞ、と思ったらキリンだったり、大きな岩がこちらに向かってのっそり向かってくるぞ、と思ったらゾウだったりする。ああ、タンザニアのサバンナは、非日常的な景色の連続だ。
そして、旅の開始から三日が経過した頃。
草原の向こうに、長く連なる黒い列が突如として立ち昇った。
あれは、まさか……。
ヌーの大移動だ……!
長きにわたって、ずっと想いを馳せてきたあの景色が、実体としていま、眼の先に出現したのだ。おもわず、「ヌー!ヌー!ヌー!」と叫んでしまう。
エマニュエル氏は静かに頷くと、ヌーたちと一定の距離を保ったまま、前進を続けた。
私の胸はざわめいた。ついにヌーたちとの並走が始まったのである。
すなわち、私の青春は、いまやっと、火蓋が切られたのである。
ヌーたちの姿を追いかけながら、草原の奥へ奥へと走っていく。
すると、あっちの方角からも、こっちの方角からも、ヌーの大集団の姿が登場する。
「ヌーの大移動」は、百万頭以上が一塊になっているのではなく、いくつもの小分けされた集団班によって行われているのだ。しかし、小分けといっても千頭以上の班であったりするので、それはそれは眩暈のするような行列である。
その巨大な群れたちは、同じ方向に向かって、歩を進めていく。目印となるような「門」などないのに、よく目的地を見失わないものだ。これが人間の修学旅行だったら、「ちょっと木刀を買ってくる」とか「清水寺には興味がないから、あぶらとり紙の店で待ってるわ」などと和を乱す私のような非同調者が現れて、結果として班行動のタイムスケジュールが失われ、宿に戻る時間が遅れたことを生活指導の体育教師にめっちゃ𠮟られる、みたいな事態が発生するというのに。ヌーの世界の規律は、思っていた以上にしっかりしているではないか。
感心していると、エマニュエルが遠くのヌーの集団を指さす。
「群れの中にシマウマたちがいるだろう。彼らもヌーと一緒にずっと移動をしているんだ。シマウマは地理の把握感覚に優れている。一説によれば、ヌーのガイド役を務めているのがシマウマらしい。だから彼らは、道に迷わないんだよ」
本当だ、よくよく観れば、黒い影の中に、白黒の縦模様がいくつも紛れている。そうか、ヌーの大移動は、シマウマの大移動でもあったのだ。
しかし「シマウマの大移動」というフレーズは、これまでに聞いたこともなかった。これは、ヌーのプロモーション戦略が巧みであったということなのか。
シマウマは、ヌーの集団を時に先導したり、また時には様子を見守るようにして後ろから追って行ったりと、大移動の運営を裏方で担当しているのだとエマニュエル氏は説明する。
なんだなんだ、それって実行委員会ではないか。大勢を誘導しているという意味では、シマウマは「門」の役割も果たしている、ともいえる。ヌーにばかり脚光が当たっているが、実は日陰の存在であるシマウマによって、大移動は実現していたのか。
私は自身の高校生活の記憶と、シマウマの姿を重ね合わせる。
「シマウマのおかげで、ヌーたちは一糸乱れぬ行動をとることができているんだね」
そうエマニュエルに感想を漏らすと、
「いや、それはどうかな。ほら、あそこを見てごらん」
そこには、突然に逆走を始めた一頭の若いヌーの姿があった。集団からどんどん離れて、草原の先へと消えていく。どうした、急に木刀でも買いたくなったのか。
「たまに大移動の途中で単独行動を選ぶヌーが現れるんだ。理由はいくつか考えられるけど、リスクを分散させるためだとも言われている。この集団が進む先にライオンとかの捕食者が待ち構えている可能性もあるからね。自然っていうのは、我々の想像を超えるような緻密さと複雑さで作られているんだ」
なるほど、あの集団から逆走したヌーにも、彼なりに決めた生き方があるのだ。
「うん。孤独を選択するっていうのも、またひとつの勇気の姿なのかもしれないね」
それからも、日を重ねながら、ヌーとの並走を続けた。
だんだんと周りを囲むヌーの集団の姿が、濃くなっていく。こっちが距離を保とうにも、向こうがこちらを巻き込んでくるような状態で、なるべく彼らに刺激を与えないよう、エマニュエル氏はゆっくりとアクセルを踏んでいる。もうゴール間近ということで、気も和らいでいるのだろうか。ヌーたちはこっちのことなど気にも留めずに、車のすぐ近くをのっそりのっそりと歩いている。
いま私は、完全に、ヌーの大移動に参加している。
背筋にぞわぞわとした感覚が走る。黒い獣のうねりの中に、自分が溶け合ってしまったような。境界線を見失い、落ち着きのない心の動きに翻弄される。
意図せずして群れと接近の状態となり、そこで初めて気がついたのだが、ヌーの鳴き声は「ヌ~」であった。そんなことって、あるのか。アヒルは「アヒル~」とは鳴かないし、ロバは「ロバ~」とは鳴かないし、メガネ屋の店員は「ゾフ~」とは鳴かない。
肉薄しないとわからないことって、色々とあるものだ。そんなシンプルな感想を頭に浮かべながら、なんとか冷静になろうと努めるが、しかしこの非日常感の中にいては、興奮を押し留めることはできない。
ヌーたちは「ヌ~」という鳴き声を上げながら、豊かな草地を目指して進んでいく。そしてその草地に乾季が訪れると、また元の草地へと戻っていく。そんな一年間のサイクルを送っているのだという。いわば、青々とした草地こそが彼らの「ホーム」であり、ヌーとはその生涯をかけて延々と帰宅を続ける生き物なのだ。そう考えると、元・帰宅部としては胸が震えてくる。帰宅部は孤独でしかないと思っていたのに、遠く離れたタンザニアの地に、こんなにも同志がいただなんて。なんだか救われたような思いだ。
ヌーたちのここまでの「帰宅」の道は、決して穏やかではなかったはずだ。途中にある川を越える時、彼らは一日に九千頭近くもの仲間を失うという。
そして彼らは、移動の最中に出産をしたりもする。ヌーの赤ん坊は、生まれてから十分後には立てるようになり、そして一時間後には集団と共に走ることもできるようになるらしい。サバンナでは、ハイエナがうろつき、上空ではハゲワシが旋回をしている。そんな危険に常に晒されている状態では、たとえ乳飲み子であったとしても、ゆっくりしている間などないのである。
それは実に苛烈な大移動であるわけだが、それでも彼らは「帰宅」をやめることをしない。遠くで待っている家、そこでの安息を目指して、四本の脚で大地を踏み続ける。
そういえば。
同級生たちの気づかぬところで、静かに帰宅を続けていた高校生活だったけど、家があることの安心感には生かされていたな、なんて思う。校門を飛び出して、自宅方面へと足を踏み出す時、青春に参加できていない寂寥感を抱きつつも、なんだか穏やかな気分も同時に得ていたように思う。
ヌーが草地を求めて移動を続けるように、私は自分だけしか味わうことのできない安堵を求めて、あの帰宅の日々を紡いでいたんだった。
そうか、帰宅部は帰宅部で、それなりに満足した青春を送っていたんじゃないか。
そして、移動を続けること、八日目。
ヌーとの並走は、いよいよ終盤を迎えた。
列の歩みがだんだんと遅くなり、そのうちに立ち止まって悠然と草を食べているヌーやシマウマの姿が増えてくる。
「よし、この辺りがヌーの大移動の最終地点だ」
そういってエンジンを停めるエマニュエル。
車のサンルーフから顔を出して周囲を眺めれば、そこには圧巻の光景が広がっていた。
ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー、ヌー………………。
「ひしめき合う」という言葉は、漢字では「犇めき合う」と書くわけだが、牛が三頭ではとても足りないほどに、そこではヌーたちが高密度に犇めきあっていた。「犇」×無限、である。
数か月にもわたる長い長い旅路を終えて、彼らは大きな青空の下、時の流れを忘れるように草を穏やかに咀嚼していた。
そこは、ヌーの大移動の、打ち上げ会場だった。
「ヌ~」「ヌ~」「ヌ~」
あらゆる方向から、ドルビーサラウンドのように、ヌーたちの鳴き声が響いてくる。それは私の耳に、互いをねぎらい合うような会話として聞こえてきた。
ヌーのみなさんも、シマウマのみなさんも、おつかれさまでした。
カバンからコーラの瓶を出して、彼らに向かって静かに乾杯する。
すっかりぬるくなったコーラであったが、しかしそれはとても美味しかった。高校の文化祭では飲むことのできなかった、達成感の味であった。
こうして私は青春のわだかまりに、ひとまずの終止符を打つことができたのである。
一頭のヌーが、興味なさそうにこちらを眺めながら、喉元を震わせた。
ヌ~。
ワクサカソウヘイ
文筆家。1983年東京都生まれ。エッセイから小説、ルポ、脚本など、執筆活動は多岐にわたる。著書に『今日もひとり、ディズニーランドで』『夜の墓場で反省会』『男だけど、』『ふざける力』『出セイカツ記』など多数。また制作業や構成作家として多くの舞台やコントライブ、イベントにも携わっている。