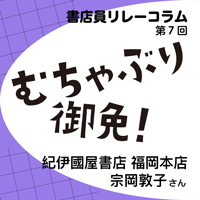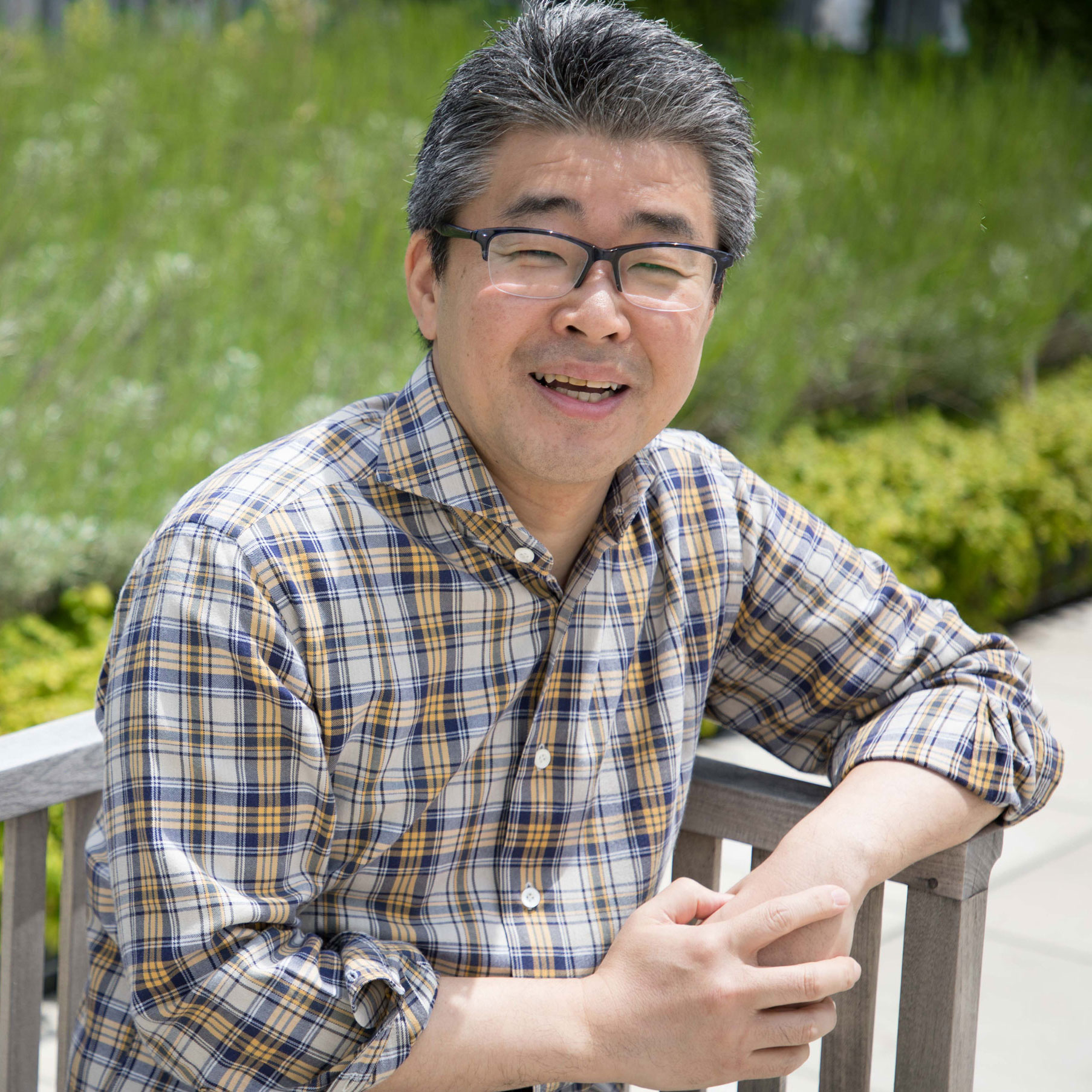私の本 第1回 若松英輔さん ▶︎▷02

新連載「私の本」は、あらゆるジャンルでご活躍されている方々に、「この本のおかげで、いまの私がある」をテーマに、本のお話をお伺いする企画です。
第1回は、批評家であり、詩人でもある若松英輔さん。貴重なお話を3回に分け、連載しています。読書の意義、読書の喜びについて、語ってくださった若松さん。今回は「言葉」の役割について、話してくださいました。
宗教と文学と哲学は、ひとつの営み
内村鑑三は、「近代日本を代表するキリスト思想家」あるいは、「教会や儀式を否定する無教会主義者」とよく語られます。
これらも誤りではありませんが、こうした言葉が部分的に映るほど大きな人物でもあります。何よりも内村は、近代日本の精神のゆくえを根源から問い直した人物でした。
明治になり、洋服や暮らし方が、いわゆる西洋化していきます。
いまも私たちの多くは西洋式の住まいに暮らし、洋服を着ている。西洋化はじつに深く私たちの生活を変えました。このことによって私たちが受けた恩恵も少なくありません。
しかし、その一方で、洋服を換えるように、私たちの美意識や自然観、あるいは人間を超えたものに対する感覚を変えることはできません。
近代日本は、外的文化と内なる精神、さらには仏教哲学者の鈴木大拙がいう「日本的霊性」とが、本当の意味で融和し、融合し、内面、外面の両方で創造的であることを求められました。
未知なる文化を受け容れ、内なる「古く」、変わらないものを発展的に継承するためにも、新しい土壌を開拓しなくてはならなかった。
こうした変革の時代において、真剣に生きようとする者が大きな悩みと迷いを背負うのは当然のことです。
多くの青年たちが内村のもとに集う。
そこには、矢内原忠雄や南原繁のようなのちの東大の総長になる人物や志賀直哉や有島武郎、正宗白鳥といった、のちに文学者になる人々もいました。
本来、宗教と文学と哲学というのはひとつの営みです。
ひとつの営みのなかに3つの側面が内包されるはずなのに、現代では宗教者と文学者と哲学者が、それぞれ別々に存在しています。宗教者は宗教のことのみ、哲学者は哲学のことのみしか語らない。
しかし本来、宗教や文学や哲学のあいだに私たちの苦しみがある。
こうした私たちの悩みに、現代の宗教や文学や哲学は、十分な答えを与えてはいない。
このような状況で、宗教や文学、あるいは哲学から、人が離れていくのは当然といえます。
言葉が残り、作者が消えるということ
容易に言葉にはできないような大きな出来事が襲った時、大いなる者は人を選んで、永遠なる世界の理を語らせようとする。旧約聖書の預言者、日本でいえば巫者などもかつてはそういう存在でした。
内村鑑三、それに『苦海浄土 わが水俣病』などで水俣病患者の存在を世に知らしめた石牟礼道子もそうした血脈を継いだ人物でした。
石牟礼道子は内村を愛読していました。
海とともに生き、もっとも海を愛した人たちが、海により命を奪われることになった。
石牟礼は言葉にならない数えきれない呻きを聞き、それを書きとめます。彼女が言葉を用いて他者を表現したのではなく、彼女は、語らない者たちの内なる言葉の通路となった。

精神科医の神谷美恵子も同じような存在です。
神谷の名著に、『生きがいについて』があります。現在では当たり前に使われているこの「生きがい」という言葉は、じつは神谷がよみがえらせたものだといってよいと思います。
神谷は岡山県にあるハンセン病療養施設・長島愛生園に暮らす人々と交わり、西洋から入ってきた従来の精神医学的研究という方法論を放棄しました。
研究だけでは魂を救うことはできない。魂を救うのは、本当の意味での言葉なのだと、彼女は知った。
かつて、ハンセン病を生きた人々――戦後、ハンセン病は完治する病になりました。――のなかには、自らの魂を救うために、自ら言葉を紡いでいる人もいた。そうした人たちとの出会いにより、神谷は「生きがい」とは何かを思考し続けました。
今、「生きがい」という言葉は、私たちの生活のなかで日常的に使われています。
言葉の通路になるとは、このように言葉が残り、それを語った者の姿が隠れていく、ということです。
言葉は、魂を繋ぐことができる
『万葉集』や『古今和歌集』などにある、詠み人知らずの和歌や民謡、祈りの言葉は、すべて誰が書いたのか分かりません。
作者は存在するのですが、その人はそこに自分の名前を付すことを拒むのです。
どの宗教にも根幹をなす祈りがありますが、いわゆる作者は記されていない。浄土教の「南無阿弥陀仏」という名号もそうです。
しかし、こうした無私の、無名の言葉こそが深く、強く人を支えている。

私たち人間は、言葉そのものともいえる存在です。
だから、言葉を軽んじると大変なことになる。ひとつの言葉が見えなくなったがゆえに、大変に大きな苦労を背負うこともある。
反対に、言葉をたったひとつ見出すことができたなら、人は生まれ変わることも、立ち上がることもできる。
世の中には、探しているものが言葉だとわからなくて、お金のような目に見え、手にふれるものばかりを探している人もいます。何を探すかは慎重でなくてはならない。
お金はとても大切なものです。しかし、それは一番大事なものではない。
一番大切なものを探すときに私たちを助けてくれるものではある。
お金でなくてはできないこともありますが、お金にはできないことがある。お金では利害関係を結ぶことはできても、魂を繋ぐことができない。
ここで「お金」と書いたのは、「量的」なものです。そしてこれまで述べてきた「言葉」は「質的」なものの象徴です。量的なものには代わりがある。しかし、質的なものはつねに、世にただ一つのものです。
ですから、人は自分の人生に裏打ちされた、世にただ一つの、意味と共にある人生の一語を探さなくてはならない。
見た目には、世に流布しているものと変わらなくても、意味においてはまったく独自の、自分の人生そのものである、小さな言葉と出会わなくてはならないように思うのです。
言葉は、魂を繋ぐことができる。
東日本大震災では亡くなった家族や友人に宛てて、人々は手紙を書きました。それは必然といえます。言葉は、死者と私たちを繋ぐものだからです。
和歌はそもそも挽歌、つまりは死者を悼むものから始まりました。
そう思えば、東日本大震災で人々が死者に向かって手紙を書いたことも、じつに自然なことだと理解できるのではないでしょうか。
前の記事はこちらからお読みいただけます
若松英輔さん▶︎▷01
つづきはこちらからお読みいただけます
若松英輔さん▶︎▷03