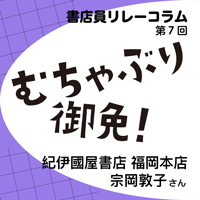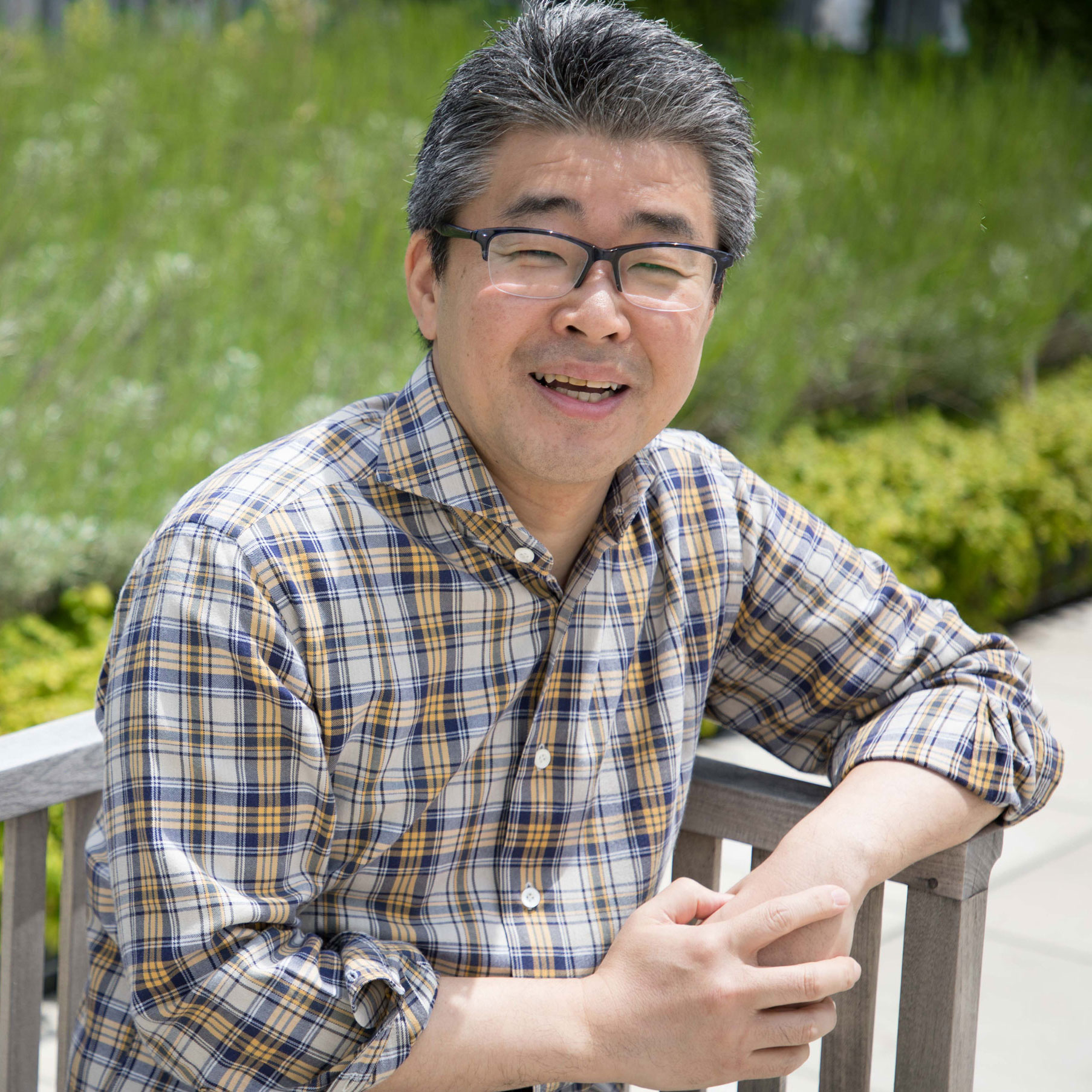私の本 第1回 若松英輔さん ▶︎▷01

このたび、小説丸では新連載を始めます。その名も「私の本」。あらゆるジャンルでご活躍されている方々に、「この本のおかげで、いまの私がある」をテーマに、本のお話をお伺いする企画です。
第1回は、批評家であり、詩人でもある若松英輔さん。すでに数々の名著を世に送り出している若松さんは、どんな本を読んでこられたのでしょうか。貴重なお話を3回に分け、連載していきます。
いまも読み終わらない本
16歳まで、僕は2冊しか本を読んだことがなかったんです。
学校の課題図書だった、坂本龍馬と同じシリーズの田中正造の伝記です。
そんなほとんど本にふれない生活が一変したのは、高校に入学してひとり暮らしを始めてからでした。
父親は、中学を卒業したら家を出るように、という方針でした。でも、ひとり暮らしの下宿にはテレビがない。その時間を埋めるように読書を始めたのです。
当時、よく手にしていたのが岩波文庫で、その一冊に内村鑑三の『後世への最大遺物』がありました。

内村鑑三は思想家であり、キリスト教者でもあります。
明治27年にキリスト教青年会夏期学校で行われた講演内容をまとめたこの本は、人にとって真の生き方とは何か、私たちは後世に何を遺せるのかという人生の根本問題について語ったもので、それを大変に面白く読んだ。
内容すべてを理解したわけではありません。でも、実在する何かにふれたという感触だけは強く残ったのです。
しかし、この本が、本当に意味を持ち始めたのはそれからおよそ25年後のことでした。40代前半で近しい人を喪うという出来事があり、再読したのです。
その時、この本を読んだつもりでいたけれど、じつは読めていなかったことに気づいた。
読書の意味とは「読めた」経験も悪くはないけれど、最大の発見は「読めていなかった」のを知ることです。そこで初めて、真の意味で本を「読み始め」ることができる。
「読めた」と思っているあいだは、「読めていない」。その本の内容をただ感じているに過ぎないのかもしれない。それを体得することができたのが、この一冊でした。
薄い本なのですが、いつ読んでも新しい。いまだに読み終わらない本でもあります。
読書の喜びとはなにか
読書の大きな喜びは、自分の変化や成長とともに、そこに書かれている言葉やテクストも変化し、育っていくことです。
当たり前のことなのですが、こうした経験を得るためには、再読しなければなりません。私たちは言葉というものにふれながら、その奥にある意味にも同時にふれているわけで、その真の意味を感じるには、時間がかかる。
本当に読書がうまくいった時は、言葉を媒介として、著書と最上の対話ができます。
読むというのは、文字を単に情報として読むことではありません。同様のことはデカルトも『方法序説』で書いています。
また江戸期の儒学者であり、思想家だった伊藤仁斎も孔子の『論語』を読むと、そこに孔子が現れて手を叩き、足踊っているように感じると綴っています。ここに比喩などありません。まざまざと孔子の存在を感じるというのです。
仁斎に言わせれば、もしそれが喩えめいた話に聞こえるなら、読み方が足りないと思わねばならない、ということになる。

「たくさん」ではなく「確かに」読む
「読書百遍」という言葉もあるように、書物はそもそも何度も読み返すということを前提にした営みです。
「読書百遍」のあとには次の言葉が続きます。「意、おのずから通ず」。
「読書百遍、意、おのずから通ず」、百回、繰り返して読むことができれば、そこに記されていることが自ずとわかる、というのです。
しかし、ここでも「わかる」は知的理解ではありません。いわば、全身全霊で何かを感じ始める、というのです。「読書百遍義自ずから見る」という同質の意味のことわざもあります。
それにもかかわらず、現代の私たちは、多くの場合、1回読んだだけで終えてしまっているかもしれない。
たとえば話題となっている本を買ったらさっと1週間で読み終えて、あとは本棚にしまうか、人にあげる。あるいは売る人もいるかもしれない。
現代人は、なるべく多くの本を読むことに価値を求め、エネルギーを使ってきました。当然、本とつき合う時間が、とても短くなる。
しかし本当は一冊の本を、「確かに読む」ことが肝要なのです。
また、本は、何を読むかも大事ですが、いつ読むかが、大変に大事になってくる。
たとえばドストエフスキーを読む。再読することを心に留めておくなら、たとえ充分に理解できなくても、一度、読んでおくとよいということになる。
人生はいつ終わりが来るかわかりませんから、「思い立ったが吉日」で、すぐ始めるのがよいと思います。
「わかり始める」には時間が必要です。先にも述べましたが、私の場合、『後世への最大遺物』の真の意味がわかるまでに四半世紀かかっています。
たとえば、ある本を25歳で初読する。四半世紀後となれば50歳です。良書には早く出合っておいたほうがいいということになる。
人間は自分が生きたいようには生きられない。
人生というものは、私たちの希望をしばしば裏切る。
明日、絶対に生きているという保証はありません。しかし、それは残念なことではなく、それが生きるという営みなのです。
今読んでいる本が、果たして人生最期の一冊になってもいいかと、そう自問しながら、読書をするのもあながち空想とばかりもいえないのです。
つづきはこちらからお読みいただけます
若松英輔さん▶︎▷02