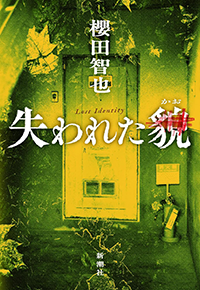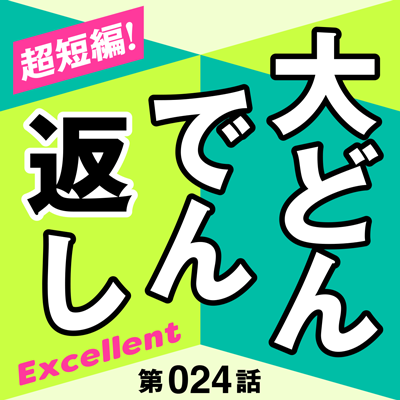櫻田智也『失われた貌』◆熱血新刊インタビュー◆
罪は暴かなければいけない

昆虫好きの青年・魞沢泉を探偵役に据えた〈魞沢泉〉シリーズで知られる櫻田智也は、短編ミステリーの名手だ。生物学の知識をちりばめた謎と切れ味鋭いロジック、そしてとぼけたユーモアが魅力の同シリーズは、現在までに3作発表され文学賞も受賞している。しかし、初挑戦となる長編『失われた貌』は、これまでとガラッと作風が変わっている。違うものを書こう、と決めたことが本作の出発点だった。
「〈魞沢泉〉はアマチュア探偵なので、彼が事件にリアルタイムで立ち会うような場面はなかなかありませんでした。過去に起きた事件に光が当てられる、という話の流れになることがほとんどだったんです。今回の作品では、殺人事件が起こり、主人公がその事件について捜査する姿をリアルタイムで追っていくという書き方をしようと最初に決めました。そうなると当然、探偵役は刑事ということになる。僕が最初に推理小説を好きになったきっかけが、西村京太郎さんの〈十津川警部〉シリーズだったことも大きかったかもしれません。まっすぐに奇をてらわず、ザ・推理小説というものを書きたかったんです」
まっすぐさは、冒頭の殺人事件でも印象づけられている。
「この作品は警察小説っぽいんだけれども謎解きものでもあるよという宣言のつもりで、顔のない死体という古典的なモチーフを使ってみることにしました。〝今さらそれをやるのか?〟という反応もあるかもしれませんが、たぶん想像とはちょっとズレた方向に話が進んでいくと思うんです」
「顔のない死体」の謎と向き合うことになるのが、J県警媛上警察署捜査係長の日野雪彦だ。6月29日の早朝、日野は変死体発見の一報を受け現場に駆けつける。谷底で発見された遺体は40代から50代とみられる男性で、顔が叩き潰され人相の判別がつかない。両手首は切断され歯も抜かれており、犯人による身元隠しの意図は明白だった。不法投棄のためにやって来たという第一発見者の男・佐竹亘が怪しまれるが……。隣接する市のアパートで老人の変死体が見つかったことから、状況は大きく動き出す。殺害現場となった部屋に住んでいた八木辰夫という男の特徴が、「顔のない死体」の所見と合致したのだ。
その事実が明かされるのは、46ページ目だ。展開が早い。
「顔のない死体の身元の謎で引っ張るという手もあったんですが、逆に〝あれ? もう分かっちゃうんだ〟みたいな拍子抜け感をフックにしてみました。もったいぶりたくなかったんです。最後に全ての謎が一気に解けるような構造も面白いんですが、それを長編でとなると、読んでいる途中でストレスを感じることにもなりかねない。真相に確実に近づいていっていると思いながら読める方が、この作品に関してはいいだろうという判断でした」
それは、刑事を語り手にしたからこその判断でもあったという。
「名探偵のように〝自分なりに気づいたことや考えたことはあるけれども、今はまだ言えない〟というわけにはいかないんですよ。刑事は組織人なので、上司にも部下にも報連相は欠かせないからです(笑)。周りに隠せないってことは読者にも隠せないので、タネを明かしながら進めていく必要があったんです」
真相を納得してもらわなければいけない
1つ目の遺体の身元が判明するのと同じ頃、その遺体は失踪した自分のお父さんじゃないのか、と疑う小学4年生の男の子・隼斗が警察署にやって来る。日野は隼斗に別人だと説いて伏せると、「入れ替わってる可能性はゼロってこと?」という言葉が飛んでくる。
「うん。ドラマでみたことあるんだ。首を切られちゃった死体があって、みんなそれを佐々木さんだと思ってたけど、ほんとうは鈴木さんだった──みたいな話」
「……それ、犯人は誰だったんだい?」
「殺されたと思ってた佐々木さん」
まあ、そうだろうな。
一連のやり取りは、そうは話が進まない、というシグナルだ。本格ミステリーという性格上、ここから先の展開を明かすことは憚られるが、その後は意外な展開が次々に連鎖していく。
「私立探偵小説の味もちょっと出したいなと思っていました。日野は刑事であり組織人で、部下を率いて実直な捜査をしているんだけれども、街をひとりでさまよいながら、手がかりを集める面もあるんです」
看護師の妻と中学3年生の娘、バディとなり一緒に動く29歳の巡査部長・入江文乃、警察学校時代から因縁がある同期で生活安全課長の羽幌警部、有力な地方紙に警察への苦情を投書した上村杏子……。意識していたのは、主人公とのやりとりを通して、登場人物たちの多面性を描くことだったという。
「他の登場人物たちの多面性は、主人公が会いに行くたびに少しずつ見せられるんですが、一番難しかったのは主人公です。家庭では情けない顔も見せれば、バーのマスターの前ではちょっとハードボイルドを気取ってカッコつけている顔も見せる。捜査の現場から離れた彼の姿を描くことで、トータルでこの人物はどういう人なのかという部分が表現できたらなと思っていました」
登場人物たちの多面性を積み上げることは、作品を人間ドラマとして濃厚なものにするだけでなく、ミステリーとしても不可欠だった。
「古典的なミステリーでは、〝この人はこういう人〟という決めつけで話を動かしていけたと思うんです。几帳面な人はこんなことしない、あるいは几帳面だからこんなことする、だからこうだ……というふうにロジックを展開させることができた。でも、現代でそれをやるのはもう難しいと思うんですね。推理小説って結局、真相はこれだとただ突き付ければ終わりではなくて、その真相を読者さんに納得してもらわなければいけないんです。犯人サイドの人物はもちろん探偵役の人物に対しても、この人は自分と似ているところがあるなとか、本当に生きているなと感じられるような多面性がちゃんと表現されていなければ、読者さんの中に真相に対しての納得が生まれないように思います」
本作は派手で飛び道具的な設定もなければ、トリック満載というタイプの作品でもない。ミステリーとしては古典的と言える形態でありながらも、確実にアップデートされているという感触はここにあるのだ。
「今回の作品もそうだったんですが、さてミステリーを作るかっていう時に、いきなり〝よし、密室を考えてやるぞ〟となることはあまりないんです。〝人ってこういう時こういう行動するかもしれないな〟という発想が出発点にあり、そこに至る人物の心の動きとか考え方を詰めていくというやり方なんですね。逆に言うと、ミステリーの構造だけでは僕の作品の場合、そんなに話がもたない(苦笑)。ミステリー以外の部分にも力を入れることで、物語として、小説としてなんとか成立させられると思っています」
物語全体を俯瞰し、エピソードを配置する
とにかく伏線回収が鮮やかだ。記憶に残る書き方がされているから、読み返さなくても「あの時のあれか!」と瞬発的に思い出すことができる。基本はシリアスな空気感の中にしばしば登場する、ほっこり、ニコッとなるようなエピソードが、真相に辿り着くための手掛かりとなることもあるから油断できない。
「伏線ももちろん重視していましたが、テーマをどう表現できるかにもこだわりました。これは短編を書いてきたことで染み付いたやり方なんですが、物語全体を俯瞰して、例えば最初に出てきた対立の構図が最後にもう一度リフレインされる、というふうにエピソードを配置したり整える作業に時間をかけるんです。あるいは、物語の中に同じような、似たような構図をいくつか出して、重ね合わせる。そうすることで、読み終わった時に、これがテーマだったんだなと感じてもらいたい」
今回の作品で言えば、家族というテーマがそうだ。そして、もう一つ。
「刑事を主人公にするからには、罪は暴かなければいけないし、例えばその罪を加害者に同情して隠すとか、加害者に自殺を促してしまうような着地点は絶対に取れないなと思っていました。そうしなければ、刑事を主人公にした意味がないと思っていた。ただ、実際に書いてみると、僕自身もそうだし日野の中にも揺れるものが出てきたんです。どんな悲劇であっても、罪は暴かなければいけないという時の倫理とは何なのか。長く粘り強くこの物語と付き合ってきたからこそ、そこに辿り着けたと思っています」
櫻田智也(さくらだ・ともや)
1977年生まれ。北海道出身。2013年、昆虫好きの青年・魞沢泉を主人公とした「サーチライトと誘蛾灯」で第10回ミステリーズ!新人賞を受賞しデビュー。2017年に、受賞作を表題作とした連作短編集が刊行された。2021年には、魞沢泉シリーズの2冊目『蟬かえる』で、第74回日本推理作家協会賞と第21回本格ミステリ大賞をW受賞。他著に、『六色の蛹』(いずれも、東京創元社刊)がある。『失われた貌』は、初の長編となる。