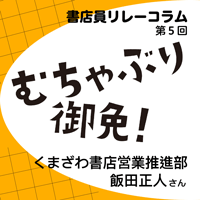「拾う人」森絵都

「カラーッ」
「カラーーッ」
「カラーーーッ」
甲高い声と床の振動で目を覚ますと、ぼやけた視界に赤茶けた天井が染みこむように広がった。ナミブ砂漠の灼熱を思わせる赤茶。その下を、同じ顔をした三人の女の子がどたばた駆けまわっている。癖のあるショートヘアも黒いワンピースもぽっこり膨れたお腹もコピペしたかのようにそっくりで、「カラーッ」「カラーッ」と張りあげる声も一羽の九官鳥を思わせる。
そっか。ばあちゃんちか。
夢以上にシュールな現実に順応できずにいるうちに、開け放たれた襖の向こうから細い男の顔が現れ、「こらこら」と三つ子をたしなめた。
「まだ武(たけし)おじさんが休んでるんだから、騒いではいけないよ」
端からあきらめきっている感じで威厳のかけらもない。火に油をそそがれた三つ子は「だってカライんだもん!」「カライんだもん!」「もん!」とひときわ高々と絶叫し、畳の上で跳んだりはねたり、俺の布団を蹴散らしたりと傍若無人の度を高めた。
「すみません」
百パーあきらめた男の顔を見て、ふいに名前を思い出した。須和(すわ)さんだ。
「でも、たしかに途方もなく辛かったのは事実でして」
なんの弁明にもなっていなかったが、一つの謎は晴れた。やはり「カライ」は「辛い」を意味するらしい。
三つ子がうるさくてそれ以上話をする気にならず、俺はやむなく布団を離れて部屋を出た。長い廊下を突っきり、幅広の階段を下る。一階へ近づくほどに線香の匂いが濃くなっていく。
二年前までじいちゃんちと呼んでいたばあちゃんちは広い。一階に四間、二階に三間。そのうち一階の四間は目下、仕切りの襖を取り払われて三十畳強の広間仕様となっている。
戸口から覗くと、俺以外はもうとうに起きていたと見え、だだっ広い畳の上で思い思いにまったりしている親戚たちの姿があった。
三脚つなげた座卓の一角で飯を食っている者。飯を終えて話しこんでいる者。テレビの前に陣取っている者。縁側でスマホをいじっている者。昨日のうちに到着した前泊組はざっと十人強か。
眼下の畳に甥の健人(けんと)が転がっていたため、足先で背中を突くと、白目をむいた顔を上げた。
「ヤバい。辛すぎる」
広間の奥から怒声が鳴りわたったのは、俺が「何が」と聞こうとした矢先だった。
「だから言ってんじゃねえか。さっきから何回も言ってるよな、俺」
尚行(なおゆき)の声だ、とすぐにわかった。
となると、怒鳴りつけている相手は良樹(よしき)くんか。
「じいちゃんのことは俺が一番わかってる。兄貴なんかなんも知んねえくせによけいな口出しすんなよ」
「落ちつけ。俺はあくまで常識的なことを言ってるだけだ。カッカすんなって」
やはり良樹くんだ。落ちついた風なことを言っているわりに声のボリュームは尚行と変わらない。
「常識って何だよ、常識って。教えてくれよ」
「だから、そんなもん仏前に供えんなって話だよ」
「じいちゃんの好物をじいちゃんの仏前に供えて何が悪いんだよ」
「何って、どう考えたって辛すぎんだろうがっ」
広間中の視線が二人に集中する中、俺はガーガーやり合う彼らの背後にある仏壇に着目した。まじめくさった顔をしたじいちゃんの遺影の前には、たしかに何やら白い供えものの影がある。茶碗に入った――白い飯? いや、違う。歩みよるほどに質感の違いがあきらかになった。白は白でも米とは別種の透明感があって――大根おろし?
「いいか、聞けっ。じいちゃんは辛い大根おろしが大好物だったんだ」
いよいよ尚行がブチギレた。
「醬油は甘口が好きだったけど、大根おろしは辛いのにかぎるっていつも言ってた。辛い大根おろしに甘い醬油をかけて食うのがじいちゃんの流儀だったんだ。ほんとは甘党だったのか辛党だったのかいまいちわかんねえけど、辛くない大根おろしが物足りねえのは俺にだってわかる。そういう意味で、今日の大根おろしは十年に一度の大当たりなんだよ。それを今日、じいちゃんの三回忌の今日、主人公の仏前に供えて何が悪いっ」
「だから、一周まわって大外れってくらい辛すぎるんだよっ」
一歩も引かずに良樹くんも吠えた。
「いくらじいちゃんだって、ここまで辛いのは勘弁だろ。ココイチだったら5辛、中本(なかもと)だったら北極レベルだ。こんな殺人的な大根おろしをあの世のじいちゃんに食わせる気か。死んだ人間をもう一度殺す気か」
稀に見るほどレベルの低い兄弟げんかは続く。到底、四十代同士の言い合いとは思えない。
が、しかし、と俺は冷静に考えた。事の本質はおそらく大根おろしの辛さではなく、いとこの中で最年長の良樹くんと、じいちゃんのことは自分が一番よく知っていると信じて疑わない尚行との、意地と意地のぶつかりあいなのだろう。
こうした場合、父親の昭雄(あきお)おじさんがいれば一喝で収めてくれるのだが、あいにく姿が見えない。まだ離れにいるのだろう。となると、この場を収拾できるのはばあちゃんだけか。
「ばあちゃん、どこか知ってる?」
しばらく部屋を見まわした末、朝飯中の姪に尋ねると、
「こごだよ」
分厚い座卓の板ごしに声がした。
見ると、おばさん二人に挟まれたばあちゃんが茶をすすっている。
「あれ。いたの?」
ばあちゃんは昔からよく周りに擬態する人で、どこにいてもその場の空気に溶け、すっと気配を消してしまう。
「あのアホなけんか、止めなくていいの? 二人とも引くに引けなくなってるよ」
「いいっで、いいっで」
俺の懸念をよそに、ばあちゃんは鷹揚に目尻を垂らして言った。
「元気がいいってごどだ。放っどげ。みんなが来でくれで、にぎやがで、じいぢゃんも喜んでっぺ」
「マジ?」
「それより、武も今のうぢにメシ食っどげ。味噌汁、温めっがら」
よっごら……と腰を上げかけたばあちゃんを、横から佳美(よしみ)おばさんが制した。
「お母さんは座ってて。私がやるから」
その佳美おばさんを俺も制した。
「いえ、自分でやりますよ」
そのまま台所へ直行して豆腐の味噌汁を温めなおし、流しに用意されていたハムエッグ、漬け物、大根おろし、そして白い飯の朝食セットを座卓へ運んだ。
まず最初に箸をつけたのが大根おろしであるのは言うまでもない。
どんなに辛かろうと、しょせん大根は大根。唐辛子や山椒とは出自が違う。大人の余裕でざっくりとすくい、一気にぱくりとやる。
「カレーッ」
たしかに死者もまた死にそうな辛さだった。
三回忌を迎えた今もなお、俺は母方の祖父であるじいちゃんについて、新たな発見を重ねている。
ばあちゃんが使う独特の甘口醬油が好きなのは知っていたものの、辛い大根おろしが好物というのは初耳だった。そもそも何がうまいの何がまずいのと食いものへのこだわりを滅多に口にしなかった印象がある。
じいちゃんにまつわる俺の最初の記憶は、少年時代の夏休みの記憶と重複する。夏が来るたび、俺は弟の昇(のぼる)と二人で茨城のじいちゃんちへ泊まりに行き、うるさい親から離れた自由を一週間ほど満喫した。それは我が家だけでなく親戚全体の習わしだったようで、毎年、同じようにいとこたちがわらわらと集まってきた。
茨城で米農家をしていたじいちゃんばあちゃんには四人の子供と九人の孫がいて、そのうちIT長者と結婚した末っ子+二人の孫はなぜだか疎遠だったが、ほかの皆は親戚づきあいに前向きだった。とりわけ本家の昭雄おじさん&典子(のりこ)おばさん夫妻は面倒見がよく、毎夏、泊まりこみで俺たちの子守役をしてくれた。
大人四人と子供七人。それだけの人数が入り乱れても窮屈さを感じない包容力、そして風通しのよさがじいちゃんの家にはあった。田園と裏山に囲まれたその一軒家には使われていない離れもあり、俺たち子供のいい遊び場となっていた。昔の農具が眠る蔵もあった。
缶蹴りや肝試しに最適なその敷地内で、俺たち子供は朝から晩まで駆けまわって遊んだ。言うまでもなく花火もすれば西瓜割りもした。羽目を外しすぎたときに雷を落とすのは昭雄おじさんの役目で、じいちゃんとばあちゃんは俺たちが何をしようと口を出さず、一歩離れたところから見守っていたように思う。
じいちゃんとの距離がもっとも近づいたのは山歩きの時間だ。日中は田んぼの雑草を抜いたり害虫を駆除したりと忙しく動きまわっていたじいちゃんは、夕方になって日が落ちたころ、よく俺たち孫を家の裏山へ誘った。急勾配の獣道を一時間ほど黙々と歩きまわる山歩き。「苦しいだけで全然楽しくない」との理由からいとこたちはどんどん離脱して誘いに乗らなくなり、結局、最後まで残ったのは俺と尚行の二人きりだった。俺だって全然楽しくなかったが、誰か二人くらいはつきあわなきゃじいちゃんがかわいそうだと思ったのだ。
「そご、滑るがら気ぃつけろ」
「あの葉はかぶれる。触っちゃいげね」
「あんれ、めずらしい花が咲いでんぞ」
山歩きのあいだ、じいちゃんが口にするのはそんな片言程度で、俺と尚行も足を滑らせずについていくのに必死だったから、そこで祖父と孫との親交がぐっと深まったわけではない。何が楽しいのかわからないまま俺たちはただただ山を歩いた。修行や苦行に近かった。
今も忘れられないのは、タフな体と精神を併せもっていたじいちゃんが、山中で何度も不可解な乱れを晒したことだ。
頭上の小枝が風で揺れる。小藪から虫が飛びだしてくる。そんな些細なきっかけ一つで、じいちゃんはぎくっと全身を強ばらせ、別人みたいに険しい表情を覗かせた。そのまま息を殺して何十秒でも身じろぎもせずにいる。もはや孫の存在など眼中にないその様子からはただならぬ緊張感が伝わってきた。
この山には熊が出るにちがいない。
幼い頭で考えた末、そんな結論に行きついた俺は、一度、思いあまって昭雄おじさんに相談した。
「ぼくたち、そのうち食べられちゃうんじゃないの」
「安心しろ。狸は出るけど熊は出ない」
苦笑まじりに昭雄おじさんは言った。
「じいちゃんは、きっと、まだ戦争を忘れてないんだ」
「戦争?」
「森の中で何があったんだかなあ」
本人の口から語られたことはなかったが、じいちゃんが第二次世界大戦中に徴兵された事実は誰もが知るところだった。戦争末期のフィリピンで悲惨な経験をしたという。じいちゃんの腕にはその証拠のような弾痕が跡を留めていて、乾いた梅干しみたいなそれを見るたびに、俺は目をそむけたくなるような、でもちょっと触ってみたいような、両極端の感情をもてあました。
じいちゃんが恐れていたのは熊じゃなく、過去の何かだった。
それを知って以来、俺は山歩きの途中でじいちゃんがぎくっとするたびに、ずきっとした。
法事の参加者たちが続々と集まってきたのは、午前十時をまわったころからだった。
「あらお久しぶり、お元気そうで」
「もう二年か。早いもんだなあ」
「お天気に恵まれてよかったこと」
「立派な娘さんになって、お父さんも心配ねえ。ほほほ」
家のあちこちに小さなかたまりを形成して挨拶合戦をくりひろげる面々の中には、よく見知った顔もあれば、正確な関係のわからない遠縁の姿もあった。血縁はなくてもじいちゃんが世話になった人や、じいちゃんから世話になった人もいるようだった。
会う人会う人から同じことを聞かれるのが億劫で、俺は密度の増した広間を抜けだし、ぶらりと裏山へ足を向けた。子供時代の苦行をたどる気はなく、人を息苦しくする生暖かさを孕んだ親戚の匂いからただ離れたかった。
ばあちゃんちの西に位置する裏山は初秋のくすんだ色に埋もれていた。瑞々しい夏の緑は失われ、赤や黄色にも染まりきっていない。数歩だけ登ってふりむくと、とうに人手に渡っている田んぼも見渡すかぎり冴えない枯れ色だった。
季節はめぐる。しんみりとそれを実感しつつ、山の裏手へぶらりと歩を進める。
と、そこには犬の牛男(うしお)を連れた尚行の姿があった。
「おっ」
「よっ」
そばかすだらけの童顔にバツの悪そうな笑みが浮かぶ。アホな兄弟げんかを恥じているわけではなく、彼はいつもどこかバツが悪そうなのだ。
「牛男の散歩?」
「ん、もう今日二回目。家にいると、まだ嫁さんもらわないのかって全員から言われるからウザくてさ。武は?」
「俺も逃避中。奥さんと柊(しゅう)くんは来てないのかって、いちいち聞かれるのが面倒で」
「お互い長い一日になりそうだな」
「だな」
森 絵都(もり・えと)
1968年生まれ。90年、『リズム』で第31回講談社児童文学新人賞を受賞しデビュー。95年『宇宙のみなしご』で野間児童文芸新人賞、産経児童出版文化賞ニッポン放送賞、98年『アーモンド入りチョコレートのワルツ』で第20回路傍の石文学賞、『つきのふね』で第36回野間児童文芸賞、99年『カラフル』で第46回産経児童出版文化賞、2003年『DIVE!!』で第52回小学館児童出版文化賞、06年『風に舞いあがるビニールシート』で第135回直木賞、17年『みかづき』で第12回中央公論文芸賞を受賞と、数多くの文学賞を受賞している。他の著書に『いつかパラソルの下で』『クラスメイツ』『出会いなおし』『カザアナ』『できない相談』など多数。
関連記事