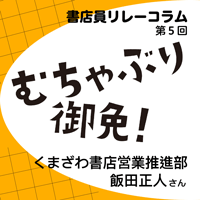「拾う人」森絵都

物憂くうなずきあったあと、俺たちは並んで山の斜面に腰かけた。昨日の夜、仕事のあとで俺が車を走らせて来たとき、尚行はすでに半分酔っぱらっていたから、二人でまともに話をするのは二年前の葬式以来だった。
「聡美(さとみ)さんとはどうなの。あいかわらず?」
「うん。二年前より着実に悪くなってるな」
「柊はいくつになるっけ」
「今、小六」
「お。じゃ、Xデーも近いじゃん」
「うん。けど、ほんとに受験まで持つのかなあ」
一人息子の教育にしか関心がない妻との関係は危うく、数年前から家庭内別居のような状態が続いている。それでも中学受験の面接までは離婚しないと妻は言い張るが、はたしてそんなことが息子の教育にいいのか俺は日に日にわからなくなってきている。
「尚行は順調みたいだな。ばあちゃん、喜んでたよ。尚行の名前が出てくる番組はぜんぶ録画してるって」
「録画してるだけで観てないっぽいけどな」
「じいちゃんもあの世で安心してるだろうな」
「だといいけど」
俺と同い年の尚行は四十五にしてようやく放送作家として認められつつあるようだ。が、仕事の話をすると彼はますますバツが悪そうになるし、その業界のことは俺もよくわからないので、突っこんだ話には至らない。
「芸能人に会ったりするの?」
「ま、たまにね」
「やっぱオーラとかある?」
「そだね。けど、ほんとにすごい人は逆にオーラ出さないっていうか、いつもは普通に暮らしてる気がする」
足下に伏せた牛男の白黒頭をなでながら尚行は言った。
「じいちゃんみたいにさ」
「はあ」
あいかわらずのじいちゃんっ子だ。
小さいころから尚行は孫の誰よりじいちゃんになついていた。総じてワンテンポ遅れる彼はいとこたちから「ノロユキ」とばかにされ、年下にまでいじめられてよく泣いていたのに、山歩きのときだけは一度も弱音を吐かなかった。
「そういえば……」
努めてさりげなく、俺は切りだした。
「例の秘密の件だけどさ」
「秘密?」
「ほら、前に言ってたやつ、おまえとじいちゃんとの。葬式のときに聞きそびれた」
「ああ……ああ、ああ、ああ」
尚行は「ああ」の音量をどんどん上げていき、最後に「へー」とまた下げた。
「武、憶えてたんだ」
「そりゃ忘れられないだろ、あんな話されたら」
「俺、どんな話したっけ」
「じいちゃんに救われたとか、じいちゃんが生きてるうちは誰にも教えないとか」
「そっかー。武って昔のこととかよく憶えてるよな」
「三年前は昔じゃないよ」
「そうかな」
「せめて五年だろ、昔になるのは」
「いや、五年前は昔むかしだよ」
なんだかんだとはぐらかされているうちに、家の庭先から聞きおぼえのあるエンジン音が響き、牛男が耳をひくつかせた。
「あれは……」
「亜純(あすみ)か」
急ぎ確認に向かうと、あんのじょう、庭先の通りに連なる車の最後尾に亜純の中型バイクが停まっている。刻々と昇りゆく太陽光を反射したメタリックな赤。その横でいとこの亜純がヘルメットを外している。
「亜純」
呼びかけると、ぺたんとなった長髪を搔きあげながらふりむき、パッと笑った。
「ひさしぶり。ね、夕子(ゆうこ)おばさん、またベンツ買い換えたよ。場違いなベンツが前を走ってたから、もしかしてと思って追いぬいてやったら、やっぱり夕子おばさんだった。運転手も若返ってた。あんな高性能の車、私だったら絶対自分で運転したいけど、やっぱお金持ちって計り知れないところがあるよね」
五つ下の亜純は舌もなめらかに一人で喋りだし、尾をふる牛男をなでまわし、俺と尚行に「元気?」「何してた?」などと矢継ぎ早の質問を投げ、やることが尽きると急に元気をなくした。
「法事、何時からだっけ」
「十一時半」
「じゃあ私、ぎりぎりまでどっかに隠れてよっかな。あんま誰とも会いたくないし」
バツいちで子供のいない亜純は、いわば俺たちと同じ穴の狢である。
「そう言うなって。どうせどこに隠れたって三つ子に見つかるし、いいじゃん、堂々としてろよ」
「そうだよ、どうせなら早いとこ洗礼受けちまえ。俺たちも質問攻めをくぐりぬけてここにいるんだし」
口々になだめるも、亜純はなかなかうなずかない。
「私の場合、質問だけじゃなくて、そこに説教も加わるんだよ。親戚のおじちゃんたちの説教好きは、おばちゃんたちの噂好きよりタチ悪いからね」
渋っていた亜純が折れたのは、そうこうしているあいだに夕子おばさんのベンツが到着したためだ。
「お、今度は黒か」
「やば。夕子おばさん、こっち見てる」
「行こ」
親戚が嫌いなのか、庶民が嫌いなのか、身内の集いに滅多に顔を見せない夕子おばさんは謎の人だ。
田舎道でさえ狭く見えるほど恰幅のいい車体に押しだされるように、俺たちはそそくさと家の玄関をくぐった。
ほんの少し留守にしていたあいだに広間の座卓は撤去され、畳の上にはどこから搔き集めたのか大量の座布団が敷きつめられていた。仏壇前に設えられた台の上には花やら果物やらが供えられ、着々と法要の準備が進められている。
とりあえずじいちゃんの遺影に手を合わせたいという亜純につきあい、尚行と両脇から彼女をガードするように仏壇へ進むと、遺影の前にはまだ例の大根おろしがあった。
「良樹くん、折れたんだ」
亜純が長々と手を合わせているあいだ、頭をそらして尚行にささやくと、
「最終的にはばあちゃんが解決した」
知られざる一幕を彼は語った。
「砂糖ぶっかけてな」
「砂糖?」
「辛すぎるなら甘味を足せばいいと」
「マジか」
目を凝らしてよく見ると、たしかに大根おろしの表面を質感の違う白が覆っている。
ばあちゃんらしいといえばばあちゃんらしい解決策だ。ひとしきり感心し、ようやく祈り終えた亜純とともに回れ右をすると、いつの間にやらそこには三つ子が立ちはだかっていた。
「ね、おじさんとおばさんたち、あたしたちの誰が誰だかわかる?」
「どれがアイでどれがマイでどれがユイでしょう?」
「当たったら通してあげてもいいよ」
二年前はたしかまだ幼稚園児だった三つ子は、俺がどこの誰だか知っているのか怪しいものだが、それよりも自分たちが誰であるのかというアイデンティティのほうが重要らしい。三つ子であるというだけで来客中から注目されて構われて、完全に調子に乗っている。
「ねえねえ、どれがアイどれがマイでどれがユイ?」
「十秒以内に答えること」
「外れたらアイスおごること! いーち、にー、さーん、しー……」
ご、と同時に亜純がひざを折り、三つ子と目の位置を合わせた。
「マイ、ユイ、アイ」
右から一人ずつ指さしながら言う。
どうやら正解したらしく、三つ子は動揺をあらわに彼女たちの叔母にあたる亜純をにらんだ。
「なんでわかったの?」
「みんな外れるのに」
「こんなにそっくりなのに」
露骨にくやしがっている。
「コツはほくろと細部の特徴。ポイントさえつかめば当てられるよ」
亜純はにんまり笑って返し、「たとえ五つ子でもね」と言いそえた。
五つ子。その超越的な一語に打たれたように三つ子が絶句する中、さっと起立して廊下へ歩きだす。
「私、ちょっと上で喪服に着替えてくる」
「さすがだな」
足早に去っていく背中を目で追い、尚行がうなった。
「秒殺で三つ子を鎮圧した」
見ると、三つ子はうつろな瞳を宙にさまよわせ、悄然と立ちつくしている。
「武」
と、そこにまたべつの声がして、ふりむくと俺のおふくろがいた。
「あ、来てたの?」
「さっき着いたところ。あんた、ちゃんと喪服持ってきたんでしょうね」
「もちろん」
「アイロンちゃんとかかってる?」
「大丈夫だって。これから着替えに行くところ」
妻子の話にならないうちに二階へ逃げようとすると、
「その前に」
と、おふくろの手が俺の手首をつかんだ。
「ちょっと頼みがあんのよ」
この声色は厄介な用件だとピンときた。
「着替えてからじゃダメ?」
「急いでるのよ」
「昇に頼めば」
「ダメ、ダメ。美也子(みやこ)さん、さっきからずっとお勝手仕事を手伝ってくれてるから、昇は子供たちについててやらないと」
俺は言葉に詰まった。義妹の名前を持ちだされただけで、言外に聡美の不在を責められている気がしてしまう。
「わかったよ。なに?」
「夕子がね、また大きな車に乗ってきたのよ、外国の」
「うん、見たよ。ベンツだろ」
「困るのよ、家の前にあんなの置かれちゃうと。あんた、ちょっと運転手の人に言って、山の裏手にでも隠してきてもらってくれない?」
「え、なんで」
話がまるで見えない。
「どういうこと?」
「だって、私たちから夕子に言うと角が立つじゃない。あの子すぐにへそを曲げるし、ここで揉めたらもう七回忌には来なくなるかもしれないし。そしたら親戚がへんに思うし、おじいちゃんだってかわいそうでしょう」
要するに、四きょうだいで一人だけ浮いている末っ子と必要以上に関わりたくはないが、決定的な断絶も避けたい、ということらしい。
「けど、なんで家の前にベンツがあるとまずいの」
「もうすぐ住職さんが来るでしょう、お経あげに」
「うん」
「住職さんの車、国産なのよ」
「ええっ、そんな理由?」
ばかばかしすぎて啞然とするも、おふくろはあくまで真剣だ。
「そういうもんなのよ、田舎って。住職さんの覚えを悪くすると、これからなにかと昭雄兄さんが困るじゃない。それにね、ここだけの話、今日いらっしゃる住職さん、ちょっとむらっ気があるって噂なの。機嫌がいいときと悪いときと、お経のノリが別人みたいに違うんですって。せっかくのおじいちゃんの三回忌だから、どうせならいいノリでやってほしいじゃない。ベンツなんか見て機嫌損ねられちゃったら困るのよ」
「ごめん、俺、話についていけない。お経のノリっていったい……」
「いいの、いいの。わかんないならわかんないでいいから、とにかく行って、運転手さんに車の移動をお願いしてちょうだい。くれぐれも丁重に、気を悪くさせないようにね。住職さんが国産車に乗って来る前に、早く!」
言っていることがめちゃくちゃだ。
森 絵都(もり・えと)
1968年生まれ。90年、『リズム』で第31回講談社児童文学新人賞を受賞しデビュー。95年『宇宙のみなしご』で野間児童文芸新人賞、産経児童出版文化賞ニッポン放送賞、98年『アーモンド入りチョコレートのワルツ』で第20回路傍の石文学賞、『つきのふね』で第36回野間児童文芸賞、99年『カラフル』で第46回産経児童出版文化賞、2003年『DIVE!!』で第52回小学館児童出版文化賞、06年『風に舞いあがるビニールシート』で第135回直木賞、17年『みかづき』で第12回中央公論文芸賞を受賞と、数多くの文学賞を受賞している。他の著書に『いつかパラソルの下で』『クラスメイツ』『出会いなおし』『カザアナ』『できない相談』など多数。
関連記事