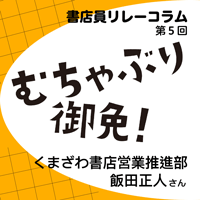森 絵都さん『みかづき』
森絵都が五年ぶりとなる長編小説『みかづき』を発表した。昭和から平成にかけての学習塾の隆盛を活写した大河小説であり、三世代にわたって熱い思いが受け継がれていく家族小説だ。日本の戦後教育の変遷を総ざらいし、辿り着いた先には旧来のイメージとは異なる家族像が現れることとなった。
昭和三六年から物語は始まる。千葉の小学校で用務員の職についていた大島吾郎は、放課後に子供たちを集めて勉強を教えていた。その噂を聞きつけ、長女の蕗子を潜入させたのが、シングルマザーの赤坂千明だ。吾郎に優れた教師の資質を見いだした千明は、自身が立ち上げる塾を手伝ってほしいと口説く。「私、学校教育が太陽だとしたら、塾は月のような存在になると思うんです。(中略)今はまだ儚げな三日月にすぎないけれど、かならず、満ちていきますわ」。塾の共同経営者となり夫婦にもなった二人を起点に、平成二〇年代へと至る親子三代のドラマが展開される──。
文芸誌で丸二年に渡って連載されていた『みかづき』は、「長い時間軸の中でひとつの家族を追う、大河ドラマのようなものを書いてみたい」という挑戦心が出発点だった。
「普通の家族とは違う、特別な舞台を設定したほうが面白いんじゃないかと考えていたんですが、ある日ふっと、塾は題材として面白いかもと思ったんです。ちょうどその頃、戦後日本の教育はどういう変遷を辿って今に至ったのか、流れを一回整理しておきたいと思っていたところだったんですね。私が一〇代の頃は詰め込み教育全盛で、受験戦争も過熱し始めました。その反動でゆとり教育が始まり、ゆとりが失敗し……とバッタバッタしている。裏に何があってこんなことになったのか、仕事とは関係なしに個人的に調べてみようと思ったんです。でも、どうせなら仕事にしたほうが一生懸命調べるじゃないですか(笑)。自分が書きたかった家族のドラマと、調べたかった教育の流れが、塾という舞台で合致したんです」
山積みの資料と向き合い、教育関係者に取材をおこなう日々が始まった。下準備でもっとも大切にした作業は、年表作りだ。
「この時代にこんな出来事があったというトピックに対して、塾側の人間からはどのような反応が起こり、公教育側の人間はどう考えて、文部省・文科省側の人間はどんなことを目論んでいたのか。それぞれの視点を把握しながら、土台となる年表を作っていきました。そこにひとつの家族を放り込めば、おのずとドラマは生まれていくだろうという予感があったんです」
絶対に書いておきたかった八〇年代の「津田沼戦争」
物語は大きく全三部に分かれる。第一部(第一章~第四章)の主人公=視点人物は大島吾郎だ。「塾は子どもを食いものにする悪徳商売だ」とメディアからバッシングを受けていた塾勃興期の大波を、吾郎はおおらかな教育方針で乗り切っていく。千明との間に二人の娘も生まれ順風満帆かと思いきや、「補習塾」から「進学塾」への転換の波に揉まれ……。
「私がイメージする大河ドラマの基本は、"試練に次ぐ試練"なんです。登場人物たちにどれだけの試練を与え、彼らがどう乗り越えていくのか。今回であれば塾業界ならではの試練や困難を、時代背景を意識しながらできるだけ盛り込んでいきたいと思いました。そうしたら、あまりにも試練が起こりすぎて一家が離散してしまった感じです(笑)。もしもこれが短い期間の話だったら、離散したままで終わっていますよね。長いものを書くと決めていたからこそ、"また繋がれるかもしれない"という希望を、私自身も持ちながら書き進めることができました」
第二部(第五章~第七章)では、千明が主人公に変わる。
「ひとりの人物でこの長い時間を引っ張らせるのは難しい、誰かに交代するだろうなとは思っていたんです。"子供かな?"と想像しながら書いていたんですが、ずっと吾郎の視点から読んでいた人にとっては悪者に見えたであろう、千明の視点を書いてあげたいなと思いました。彼女にも彼女の事情があるということを示したかったし、高度成長期やバブル期の"塾戦争"がもっとも激しかった時代を生き抜くには、千明のような人間がふさわしいという判断もありました」
吾郎はあくまで「教育者」だったが、千明は「経営者」だ。津田沼に本社ビルを建設し、塾のチェーン展開を成功させる。小説の中で「津田沼戦争」と称されたライバル塾との競争は、実際にあった出来事だと言う。
「塾業界なり教育業界で大きな出来事が起こった年を起点にして、章を立てるようにしたんです。津田沼戦争のことは絶対に入れたかったので、第五章の始まりは昭和五九年にしました。もうひとつ絶対に入れたかった出来事は、平成一一年の文部省と塾関係者との初会議です。敵対関係にあった両者が初めて同じテーブルに着いた、その衝撃は第七章のメインテーマです」
その衝撃に匹敵する家族のドラマも、第七章で勃発する。そして、第三部に当たる最終第八章で、主人公=視点人物が再び変わる。
「連載中の二年間で、子供の貧困問題が報道されるようになりました。もともと塾って、学校の補完機関としての役割を担って急速に広まったものです。でも、今の社会では月謝が払えず、塾に通えない子どもたちがたくさんいる。私はこの小説を、塾の経営者の気持ちになって書いていました。だからこそ感じたのかもしれないんですが、塾業界にいる方たちにとっては、塾に通えない子どもたちの存在がすごく気になると思ったんです。その思いを、吾郎と千明の孫である一郎に託して、頑張ってもらいました」
その時々で一緒にいる人と家族のような関係を築く
吾郎と一郎は、戸籍上は祖父と孫という関係ではあるものの、血の繋がりはない。だが、教育者としての吾郎の血を誰よりも色濃く継いだのは、一郎だった。また、千明の最大の理解者は、家族ではなく、事務室長の国分寺だ。そうした選択の裏には、作家の思いがあった。
「血縁に重きを置きたくなかったんです。私はこの小説で家族を書きたかったんですが、血の繋がっている者同士を書きたかったわけではありません。縁あって一緒に生きている者同士、自立した者同士の結びつきを書きたかったんです。血が繋がっている家族だから助け合わなきゃとか分かり合わなきゃって思うと、とっても窮屈ですよね。そこで衝突することもたくさんあるし、誰もがみんな家族に恵まれているわけではありません。ましてや無縁社会とも言われる今、他人同士が仲良くしたほうが、よっぽど明るい未来があるんじゃないでしょうか。血の繋がりはないけれども、人はその時々で一緒にいる人と家族のような関係を築ける、それがベストだと私は思うんですよ」
平成二〇年代の「今」をゴールに据えた『みかづき』は、教育の理想像を描くとともに、家族の未来像をも導き出す物語だったのだ。
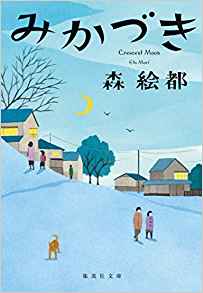
集英社文庫