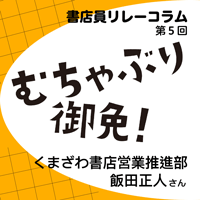「拾う人」森絵都

「どんな秘密?」
「だから秘密」
「ん?」
「秘密は秘密だよ。男と男の約束だから、言えない」
「じゃ、なんで今、言ったの?」
「なんか急に思い出したから」
「気になるなあ。ますます眠れねえよ」
俺がどんなにぼやいても、尚行は頑としてそれ以上を語ろうとせず、しまいには分厚い羽毛布団に頭を突っこんでしまった。
「言わないったら、言わない。少なくとも、じいちゃんが生きてるうちはな」
じいちゃんが生きてるうちは。
あとから思うと、これは暗示的な一言だった。というのも、この日からひと月と経たずにじいちゃんは倒れたのだ。
いつか過労で倒れる。誰もがその恐れを抱いてはいた。が、現実はもっと悪かった。
突然の脳梗塞で病院へ運ばれたじいちゃんは、緊急手術でどうにか一命をとりとめたものの、重い言語障害と半身の麻痺が残り、数ヶ月にわたるその治療中に二度目の発作を起こして帰らぬ人となった。
「お、なんだ武、どこ行ってたんだ。これから墓参りだぞ」
夕子おばさんが去ったあと、俺はなかなか広間へ戻って酒を飲む気にならず、じいちゃんが磨いたベンチの上でずいぶん長いこと呆けつづけた。尿意に負けてようやく家の玄関をくぐったころには、三和土に雑然としていた来客たちの靴がだいぶ減っていた。座卓のコップや皿が片づけられた広間では、居残り組の十数人が化粧を直したり上着をはおったりしているところだった。
三回忌のシメにじいちゃんの墓参りをすることになったらしい。
「武、おまえも来い」
墓参りは夕べのうちに済ましていたものの、昭雄おじさんの鶴の一声で、俺も同行することになった。どのみち河井家の墓までは徒歩八分とかからない。
先頭を行くばあちゃんの歩調に合わせ、俺たち一行はゆっくりと田んぼの畦道を進んだ。雲間から覗く陽は傾き、ほのかに橙がかっていた。
「つまりさ、大根は大根でも、からすみ大根と大根おろしとでは、あきらかに時間的膨張を引きおこす刺激の度合いが違ってくるわけだ」
「うん、うんっ」
「大根おろしの辛さは問題じゃない。辛かろうが甘かろうが大根おろしはしょせん大根おろしで、からすみのパンチはそこにない」
「うん、うん、うんっ」
恐ろしいことに尚行と亜純はまだ大根ネタを引っぱっていて、俺はそんな二人から距離を置き、誰だか知らない七十くらいのおっさんの斜め後ろについていた。
額に深いしわを刻んだ丸刈り頭のおっさん。たしか法要の終わりごろに来て廊下の予備ざぶとんに座った人だが、どうやら親戚筋ではないらしく、その正体はよくわからない。今さら聞くに聞けない。
「いやあ、酔った、酔った。ワタシ、たんまり飲みすぎました。年には勝てませんなあ。酔って頭がどうかしてたのか、女の子の顔がね、三つに見えるんです。三つに見えるんですよ」
墓地までのあいだ、延々と同じ話をくりかえすおっさんに、俺は「ほう、そうですか」だとか「それはまた」だとか適当な相づちを打ちつづけた。
おっさんを幻惑した三つ子の姿はもうない。曲がりくねった列に連なっているのはリタイア組か身軽な四十代のどちらかだ。子連れの家族はのきなみ先に引きあげたようだが、彼らも墓参りはしていったと見え、到着した墓には昨夜はなかった花やらビールやらが所狭しと供えられていた。
「あんれ、線香を忘れだわ」
尚行がひとっ走りして取りにもどった線香を、まず最初に墓前へ供えたのはばあちゃんだ。
「ばあちゃん、やけどすんな」
「足もと気をつけてくださいね」
両脇からばあちゃんを気遣う昭雄おじさんと典子おばさんは、じいちゃんの死後、千葉にあった自宅を売り払い、その金で茨城の家の離れを自分たちの住処として改築した。当時は皆がびっくりしたものの、転居後、長く患っていた昭雄おじさんがめきめき元気になったのを見るに、よほど故郷の空気が合っているのかもしれない。ばあちゃんもばあちゃんで、ふくよかな長男夫婦にすっかり擬態し、顔がまん丸になっている。
――じいちゃん。ばあちゃんは元気だ。俺たちもみんなそれぞれなんとかやってるし、これからもなんとかやっていく。心配すんな。
俺は一番最後に線香を供え、じいちゃんに本日二度目の声をかけた。ついでに、今さら愚にもつかないと思いつつ、じいちゃんに一番聞きたいことを心でつぶやいた。
――じいちゃん、あのころ何を思ってゴミを拾ってたんだ?
じいちゃんが死んでから幾度となく考えてきたことだ。
脳梗塞を起こしてからのじいちゃんは、たんに言語中枢をやられただけでなく、意識自体がうつろになって、ひねもす浅い眠りの中にいるかのようだった。表情も失い、とりわけ瞳が力をなくした。月いちで見舞っていた俺たちを認識していたのかもわからない。必然的にじいちゃんのゴミ拾いはそこで幕を閉じ、「じいちゃんにとってゴミ拾いとは何だったのか」という謎も迷宮入りとなった。
こんなことなら、じいちゃんがじいちゃんであるうちに、一度でもひざを突きあわせて聞いておけばよかった。
今も引きずる後悔を胸に、俺が墓前から数歩離れたところで、
「な、ちょっと」
待っていたように尚行がやってきて、肩にかけていたナップザックを開いた。
「一杯やってかないか」
ナップザックの中には四、五缶のビールがある。
「ここで?」
「そ」
「墓で?」
「怖いの?」
「まさか」
「じゃ、亜純も呼んでくる」
かくして、尚行の思惑がわからないまま、他の皆が去った墓地で三人水いらずの献杯をすることになった。
「じいちゃんに」
「じいちゃんに」
「おじいちゃんに」
冷たく湿った土を尻に敷き、ようやく火照りがさめてきた体にまたもビールを流しこむ。この面子で飲むのは三年ぶりだが、場所が場所であるせいか、思ったほどには気分が乗らない。以前は月いちの飲み会がなくなったのを物足りなく感じたり、無性に茨城へ足を向けたくなったりもしたけれど、いざこうやって三人顔を合わせると、今度はじいちゃんがここにいないことが物足りない。
「なんか……涼しいな」
「うん。ひんやりしてきたね」
「墓地だしな」
会話はとんと盛りあがらず、誘ったわりに尚行もあまり喋らず、亜純も瞳をとろんとさせていて、だらけたムードの中で俺たちはビールをちびちびやりつづけた。徐々に強まってきた風を受けながら、野性味あふれるトンボがぶんぶん飛び交う墓地で。どう考えても酔狂だった。
なんで尚行はじいちゃんの墓前で飲もうなんて考えたのか。
その答えがはたとひらめいたのは、250mlの缶がだいぶ軽くなってからだ。
「秘密?」
つぶやいた瞬間、尚行と目が合った。
「例のアレ、教えてくれんの?」
どうやら当たったようだ。尚行は急に落ちつきをなくしてあぐらの足を組みなおし、ガキみたいに鼻の下をごしごしとこすった。
「一度だけ言う。こそこそしないで、じいちゃんの前で言う。亜純も聞け」
「なんのこと?」
「じいちゃんの秘密だよ。たぶんばあちゃんも知らない。俺にだけ教えてくれたんだ」
小六のころ、タチの悪いクラスの男子からいじめの標的にされ、不登校になった。家に閉じこもるのを恐れた典子おばさんは尚行をしばらく茨城へ預けることにしたのだが、昭雄おじさんはそれに反対だったらしく、毎日のように電話を寄こしては「早く帰ってまた学校に通え」と言いつづけた。「逃げたら負けだ」と。その呪文のような説教に屈し、尚行はひと月ほどで家へ帰ろうとした。
そんな前説をざっくりしたあと、尚行はいざやと切りだした。
「そのとき、じいちゃんに言われたんだ。おまえ、本当に大丈夫なのか、まだ学校は無理なんじゃないかって。実際、ぜんぜん無理だったんだよな。俺、学校に通うどころか、千葉に帰ったら生きてける気もしなかったし。けど、そのまま逃げきれるとも思ってなかったし、逃げたら負けだから帰るってじいちゃんに言ったんだ」
三十年強の年月をまたいだ余裕だろう、苦い少年時代を語る尚行の声は至極淡々としていて、昔の自分にそっけないほどだった。
その口調が急に引きしまった。
「そしたら、じいちゃんに阿呆って言われた。逃げようが、戦おうが、人間、負けるときは負けるんだって。だから命があるうちに逃げろって、ここ……」
ここ、と尚行は自分の左腕の上部を右手でぽんと叩いた。
「ここにあっただろ、じいちゃんの傷。じいちゃん、あれ俺に見せてさ、言ったんだ。『秘密だぞ』って。『これは、俺が生きて逃げるために自分でこさえた傷だ』って」
「え」
「じいちゃん、自分で自分を撃ったんだ」
俺は尚行をまじまじとながめ、それから視線をじいちゃんの墓石へスライドさせた。自分で自分を撃った?
思い出す。じいちゃんの腕の傷。戦争の痕跡。負傷したおかげで日本へ帰れた、だから撃たれてラッキーだった――そんな言葉を昭雄おじさんの口から聞いたことがあるけれど、俺にはとてもそうは思えなかった。俺の目にその傷は悲惨な戦争の象徴として映っていた。そして――それが敵の銃撃ではなくじいちゃん自身の手で刻まれた弾痕であるならば、じいちゃんは俺が思っていたよりも遥かに悲惨な地獄をくぐりぬけてきたことになる。
命からがら逃げてきたんだ。自分で自分を撃ってまで。生きて日本へ帰ってくるために。
と、俺がそんなことを重く考えていたころ、亜純は亜純の回路で思索をめぐらせ、遥か彼方の地平へ到達していたらしい。
「おじいちゃん、すごい」
のどかな声にはたと顔を上げると、亜純がじいちゃんの墓石に翳りのない笑顔を向けていた。
「すごいよ。おじいちゃん、敵じゃなくて、自分を撃ったんだ。それで日本に帰ってきたんだ。よく逃げてきてくれたよ。グッジョブだよ。だって、そのおかげで今、私たちがここにいるわけだし」
俺は一瞬あっけにとられ、それから「そっか」と亜純の言う意味を受けとめた。たしかに、じいちゃんの命が戦場で散っていたとしたならば、俺たちどころか今日集まっていた多くの縁者たちがこの世に生まれていなかっただろう。
「うん、俺も小六のときいろいろ考えて、そこにたどりついたんだよな。で、俺も生きるために逃げようって決めて、結局、卒業ぎりぎりまでじいちゃんちにいたんだ」
だから、今でもじいちゃんのことは命の恩人だと思ってる。それだけ言い残し、尚行は「以上」といきなり腰を上げた。
「秘密の暴露おしまい。帰ろ」
「あー、なんかいいこと聞いちゃった。ありがと、尚くん」
「俺もちょっとすっきりした。ぶっちゃけ、一人で墓場まで持ってくにはちと重かったんだよな、あの秘密」
足どりも軽く帰路につく尚行と亜純に、俺はすぐには追いつけなかった。俺の中では「想像以上に悲惨な戦場にいたじいちゃん像」と、亜純的なめでたさに照らされた「逃げて帰って子孫を増やしたじいちゃん像」がせめぎ合っていて、頭の整理には時間がかかりそうだった。
しかし、生者たちは忙しい。
俺がじっくり思索に耽っているいとまもなく、ばあちゃんの家へもどると、そこにはまたも珍妙な騒動が持ちあがっていた。
「お医者さん、お医者さん。土曜の午後もやってるところって、どこ?」
「それより、まずは冷やせ」
「温めたほうがいいんじゃなかったかしら」
例の知らないおっさんが廊下にあった狸の置物にぶつかって転び、足をひねったのだという。
「ご心配なく。恐らく軽いねんざです。おかげでワタシ、酔いもさめました」
おっさんは大丈夫だと言い張ったものの、念のために病院へ連れていくことになり、酒の入っていない典子おばさんが車を出した。尚行も付き添いで同行した。
それを機に、居残り組もみな三々五々で退去したのだが、ついさっきまで酒を飲んでいた俺はさすがに運転を憚られた。
「私もバイク無理だわ。ちょっと一眠りしてくる」
疲れた顔の亜純が二階へ消えると、俺はぽつんと一人、一階に残された。あれだけ人がわさわさしていたのが噓のように、広間も、廊下も、玄関も、どこもかしこもしんとしていた。少年時代の夏休みの終幕、ギャップの激しいあの静けさを思い出す。
唯一、人の気配を感じたのが台所だ。
かぐわしい醬油の匂いに引きよせられていくと、そこではばあちゃんがマイペースに夕飯の支度をしていた。
野菜を切る音。鍋の湯気。いつもと変わらない情景に妙にほっとする。
「ばあちゃん」
何か話しかけたくなり、俺は言った。
「狸にぶつかったあのおっさん、誰か知ってる?」
「ああ、あの人はヤスジさんさ」
キャベツを千切りにする包丁を止めずにばあちゃんは言った。
「ヤスジさんとは、じいぢゃん、昔よぐ一緒に『スナックあざみ』に行っでだ」
スナックあざみ。インパクトのある響きに軽い衝撃をくらった俺に、
「そうだ。いづごろだっけね。ヤスジさん、一年ぐらいうぢに一緒に住んでだごどもあるんだよ」
ばあちゃんは新たな事実を明かした。
「いろいろあって、住むどごろがねえどぎ、じいぢゃんがうぢに来いって言っであげだんだ。部屋はいっぱいあるがらさ」
いわゆる居候ってやつだったらしい。
一瞬、俺の脳裏を住むところをなくしたヤスジさんの人生が掠めたが、あまりに茫洋としていたため、すぐに引き返し、再びじいちゃんのことを考えた。子供時代の尚行。ヤスジさん。どうやらじいちゃんが手厚く家に迎えたのはゴミだけじゃなかったらしい。
と、ちょうどそのとき、台所の窓の外を牛男を連れた昭雄おじさんが通りすぎていった。
そういえば、牛男もじいちゃんが拾った犬だった――そう思った瞬間だ。今日一日、俺の中に積み重なってきたじいちゃんの断片がある目方に達して飽和した。
辛い大根おろし。鉄の斧。弾痕の秘密。スナックあざみ。牛男。どんなに集めても断片は断片で、じいちゃんの核はそこにない。アタック25のパネルにたとえるならば、俺が抜いたのは4とか23とかの端っこばかりで、肝心の真ん中は依然として塞がれている。が、端っこは端っこなりに重なることで見えてくる像がある。
じいちゃんは拾う人だった。戦争で何を失ったのかはわからないけれど、生きて帰ってきてからは、とにかくいろいろなものを拾った。めいっぱい拾った。力のかぎり拾った。
今はそのシンプルな像だけでいい。ぴんと天を指す牛男の尾を目で追い、俺は思った。残りは七回忌におあずけだ。
「ばあちゃん。俺、七回忌には絶対、柊を連れてくるよ。妻はわかんないけど」
急に清々しい気分になって言うと、聞いているのかいないのか、ばあちゃんは何も答えずにコンロの方へと身をひるがえし、ぐつぐついっている鍋の蓋を持ちあげた。
「ね、ちょっど味見してぐれる?」
小皿で差しだされた煮大根は、甘い醬油の匂いがした。
森 絵都(もり・えと)
1968年生まれ。90年、『リズム』で第31回講談社児童文学新人賞を受賞しデビュー。95年『宇宙のみなしご』で野間児童文芸新人賞、産経児童出版文化賞ニッポン放送賞、98年『アーモンド入りチョコレートのワルツ』で第20回路傍の石文学賞、『つきのふね』で第36回野間児童文芸賞、99年『カラフル』で第46回産経児童出版文化賞、2003年『DIVE!!』で第52回小学館児童出版文化賞、06年『風に舞いあがるビニールシート』で第135回直木賞、17年『みかづき』で第12回中央公論文芸賞を受賞と、数多くの文学賞を受賞している。他の著書に『いつかパラソルの下で』『クラスメイツ』『出会いなおし』『カザアナ』『できない相談』など多数。
関連記事