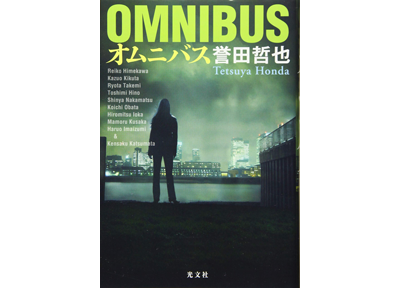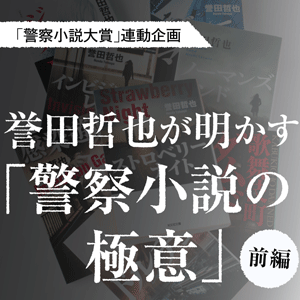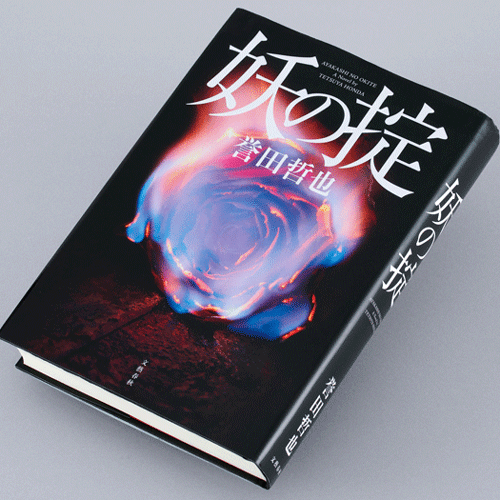「警察小説大賞」連動企画 ◇ 誉田哲也が明かす「警察小説の極意」後編

警察小説においては警察の組織機構や捜査手法を「正しく書く」ことが大前提だ。誉田哲也氏は先月号掲載のインタビュー前編でそう述べた。さらに「警察という実在の組織をお借りして小説を書く際の、礼儀であり職業倫理である」とも言う。では、その一線を越えたうえで、筆者は、自分なりの色をどう付ければいいのか。これから執筆を目指す方に贈る警察小説講義――後編となる今号は「実践編」である。
姫川玲子は犯罪者に近い思考回路を持つ
よく僕の小説はグロテスクな表現が多いと言われます。腐乱死体を一生懸命に描写していたりするんですが、決して怖がらせようとしているわけではありません。端的に言えば、リアリティの追求です。
目の前にある死体はどんな状態なのか、色や匂いはどうか、損壊はあるのか、ウジがわいているのかどうか、直腸内温度はどんなものか、死体を見ることに慣れていない刑事が臨場したのであれば、どれぐらい吐き気を催すものなのか。イヤなことを書いているという自覚はもちろんありますけれども、それらを見なかったことにする、あるいは見ているのにちゃんと描写しないということは、僕は逃げだと思います。そこを書くことによって、初めて「警察小説における死体」の表現になる。暴力の描写に関しても同様ですね。警察組織を見つめる時と同じ視線で、「正しく」書く。
犯人側の視点、犯人側の心理描写がぶ厚いことに関しては、エンターテインメント性を重視した結果ですね。例えば……これは悪いと言っているのではないんですが、佐々淳行さんが書いたノンフィクションをもとにした、『突入せよ!「あさま山荘」事件』(二〇〇二年)という映画があります。あの映画は、連合赤軍の生き残りが軽井沢の山荘に人質とともに立てこもった、という一九七二年に実際に起きた事件で、警察はどんなふうに動いて上層部はどんなオペレーションをしたかがよくわかります。
警察組織の動きという面では、非常にリアルです。ですが、どこか物足りなさを感じてしまうのは、犯人側、連合赤軍側が事件を起こした背景であるとか当事者たちの心理は、何も描かれていないんですよね。
原作者の佐々淳行さんは本物の警察官僚ですから、その選択は極めて当然です。でも、僕はエンターテイナーなので、もしも自分が一連の事件を題材にするのであれば、警察組織だけでなく、連合赤軍側の視点も書くことになると思います。
小説家としてではない、僕個人の感想を言えば、「あさま山荘」事件を起こすに至った連合赤軍側のマインドは一切理解できません。元はと言えば学費値上げの反対運動で集まった連中の一部が、テロ集団へと変貌を遂げて、仲間内でリンチをし警察官を何人も殉職させる。ただただ、狂気の沙汰だなと思う。ですが小説にするのであれば、彼らが犯罪に走ったマインドが、自分の中でかすかにであれ共感できる、納得できるようなロジックを探します。そして、それを書く。
警察小説といえるかどうかは微妙ですが、『ケモノの城』(二〇一四年)に出てくる、まるで人間の皮をかぶった獣のような、一切悪びれもせずひどいことをやる人間は、実際にいます。世の中には一定数存在するんだけれども、多くの犯罪者は理由を持って、人を殺す。その理由にどこか共感できる、自分と繋がっている部分を見つけられるからこそ、追いかける側と追いかけられる側の攻防に興奮するのだし、犯罪者とそうではない人との間のグレーな部分を描けるんじゃないかという思いがあるんです。
ちなみに、姫川玲子は勘で犯罪者の心理や行動を当ててしまう、という能力があります。その能力を得た直接的な理由は一作目の『ストロベリーナイト』(二〇〇六年)に書いてはいるんですが、彼女のキャラクター作りをしていくうえでの発想の出発点は、岡っ引きなんですよ。有名な話ですが、江戸時代に警察組織の末端を担った岡っ引きは、元犯罪者が多い。犯罪者のことは元犯罪者が一番よく知っているからと、同心が手下として使ったんですよね。姫川玲子は潜在的に、犯罪者と非常に近しい思考回路を持っている。だからこそ、犯罪者の発想で、犯人を追いかけていくことができる──。僕が初めて生み出した刑事のキャラクターである姫川玲子の存在も、自分の書く警察小説の方向性を決定づけたのかなと思います。
茶化さず漏らさず感動しながら書く
〈犯罪は時代を映す鏡という。警察はそれを、常に後追いすることを求められる。先回りすることはできない。犯罪は日々進化し、警察組織もそれに合わせて変化する必要がある。時代が犯罪を生み、犯罪が警察を変え、また時代は移ろう〉
日々変わりゆく警察組織、そして変わりゆく警察小説の中で、変わらないものとは何か。
警察組織について、ズブの素人の状態から少しでも疑問に思った点があればどんどん掘り下げて調べていくうちに、「警察ってそうなんだ」というよりは、「警察〝も〟そうなんだ」と感じられることが多くなっていきました。例えば、年間行事に慰安旅行があったりする。あるいは、「四週間で八日間休み」という決まりがあるので、係長が一生懸命シフトを組むんですよ。コンビニ店長の苦労とまったく同じなんです。
もちろん組織ですから、組織内での競争意識は強いです。全国で二十九万人、警視庁だけでも四万六千人、警察官の方はいるので、中には足の引っ張り合いのようなものも当然あるんでしょう。セクハラやパワハラをする人もいるし、お金をちょろまかすような人もいるでしょうし、もしかしたらシャブを打っちゃう人もいるかもしれない。
警察組織内にはびこるネガティブな部分にフォーカスして、露悪的に書くタイプの物語もあり得るんでしょうが、くだらない人間のくだらないことをわざわざ書いても、僕はあまりおもしろいと思わない。そこに、学ぶべきことはない。
どんなに真面目に、強く高潔にやってきた人間でも敵わない悪があるとか、貫き通せない正義がある。悲しいし、悔しいし、辛い。それでも諦めずに、また新たな犯罪に立ち向かっていく姿のほうが、僕は興味があります。不自由なルールの中で、なんとかして職責を全うしようとしている姿を僕は書きたい。
それはエンターテイナーとしての姿勢の問題というよりも、ほとんどの警察官の方が、そういったマインドの持ち主だからです。
彼らのマインドの中心にあるものは何かと言えば、正義感です。なぜ警察官になったのかと尋ねたら、みなさん当たり前のようにこう答えると思うんですよ。
「人を助けたいから」
警察関係者の方と話していた時に、こんな言葉を聞いたこともあります。
「自分が担当している地区で人が殺されたんだってわかると、悔しくて震えるよ」。そういうマインドを持った人たちが、今も昔も社会の治安を担ってくれているんです。
そのことを、綺麗事だと笑われないように書くのが僕らの仕事なのではないでしょうか。薄っぺらく書いてしまったら、意味がない。茶化さず、彼らの仕事一つ一つに感動して、彼らの熱を漏らさず書く。そうしなければ単純に失礼ですし、小説としての重みも出ない。逆にいえば、彼らの存在そのものに感動できないと、警察小説は書けません。
警察官の方々をある種のヒーローとして描くことによって、日々の仕事を頑張れよというエールを贈る。そういった作品を世に送り出すことによって、読んでくれた方にも警察のファンになってもらいたいんです。
テーマとメッセージ両方あってこそ小説
一方で、デビュー作『妖の華』の前日譚となる、伝奇ホラーにして自身初となる時代小説も準備中だ。「五割は警察小説、残り五割はまた違うもの」というバランスで活動していきたい、と作家は語る。
警察小説はとにかく数を書いてきたので、デビュー直後のようなアウェーで戦う感覚ではなく、自分にとってはもうホームだと感じるんです。
他のジャンルの小説にどっぷり浸かったあと、戻ってきて捜査会議のシーンなんかを書いていると、「帰ってきたなぁ」とどこかホッとした気分になる(笑)。これだけ書く機会を与えられたということは、書いてくれという期待の裏返しでもあるんでしょうし、まだまだ書いてみたいことはあります。
警察小説の題材、取り扱う犯罪をどうやって構想するのかとたまに聞かれるんですが、意外と日常生活の中で生まれることが多いです。テレビや新聞、ネットニュースを見ていて「ん?」と思うことって、誰しもあるじゃないですか。そう思ったら「ああ、そういうことか」と自分なりに腑に落ちるまで、詳しく情報を掘っていくし想像も巡らせるようにしています。「ん?」から始まり「ああ」まで辿り着いた経験が、結果的に小説のアイデアに繋がっていっている感覚があります。
ただ、今はもう取り扱う犯罪の目新しさ、面白さに比重を置くような感覚はあまりありません。僕は、小説に必要なものはテーマとメッセージだと思っています。
テーマというのは、謎かけですね。メッセージは、その答えです。つまり犯罪そのものを書くことが大事なのではなくて、犯罪を通して「何々とはなんぞや」というテーマをきっちり提示したうえで、最終的に「何々とはこうである」ということを登場人物の誰かが言い切る。テーマとメッセージ、両方が揃ってなければいけない。
だって、「パンはパンでも食べられないパンはなんだ」「え、わかんない。なに、答え教えて」「いや、俺もわかんない」と言われたらムカつくじゃないですか(笑)。答えを用意してからなぞなぞを出せ、という話ですよね。それは小説も一緒です。答えをきちんと用意したうえでテーマを提示するべきであって、伝えるべきことがないのに問いかけだけするなよ、と僕は思ってしまう。
たまに小説講座みたいなのにお呼ばれして話したりしますが、そういう時は「小説ってどうして小説というのか、不思議に思いません?」というところから始めるんですよ。比較対象がないのに、「小さい」呼ばわりされるいわれはないですよね。では、何と比べて「小」だと言っているのか。大説です。
国家元首であったり為政者が、国とはいかにあるべきものか、国民とはいかにあるべきものかということを、いってしまえば上から目線で説いた大きな説が、大説です。
具体的には中国の四書五経等を指すわけなんですが、現代日本に敷衍して言うならば、安倍晋三さんの『美しい国へ』だったり、田中角栄さんの『日本列島改造論』が大説に当てはまるのかもしれない。
それに対して我々みたいな市井の人間が、日常生活の中でどんな考え方であったり、どんなスタンスを取ったらいいかと提示するのが、小説です。これこれこういう場面ではどう対応したらいいんだろうか、隣人に対してどういう心持ちでいられたらいいのか……。大説と比べて見れば、本当にちっちゃな話をしているんですよ。でも、だからこそ人々の胸に届くものがあるんですよね。
小説は、いわゆる文学とも区別されるものなんじゃないかなと僕は思っています。文学は、言い換えるならば文芸ですね。要は、文章芸術ということです。『プレバト‼』の俳句と一緒で、人がモヤッと思ったり漠然と感じたりすることを、スパッと芸のある言葉で表現してみせる。それが文芸ですが、僕が考える小説とは違う。
小説の本質は「人はいかにあるべきか?」ということを考え、できるだけ幅広い人たちに届くようにさまざまなテーマを設けて、その答えとなるメッセージを提示することなんです。
警察小説は、「警察文学」ではない。それが僕の持論です。
誉田哲也(ほんだ・てつや)
1969年、東京生まれ。学習院大学卒業。2002年、『妖の華』でムー伝奇ノベル大賞優秀賞を獲得しデビュー。警察小説に新風を吹き込んだ『ストロベリーナイト』の姫川玲子シリーズ、「ジウ」シリーズほか、『武士道シックスティーン』『増山超能力師大戦争』などジャンルを越えて執筆。
(取材・構成/吉田大助)
〈「STORY BOX」2021年5月号掲載〉