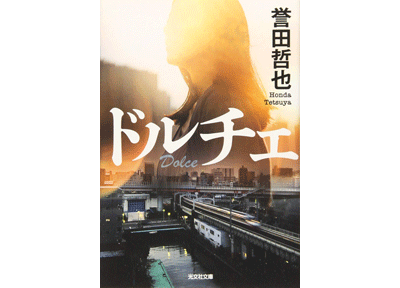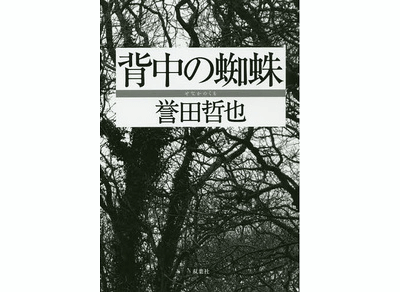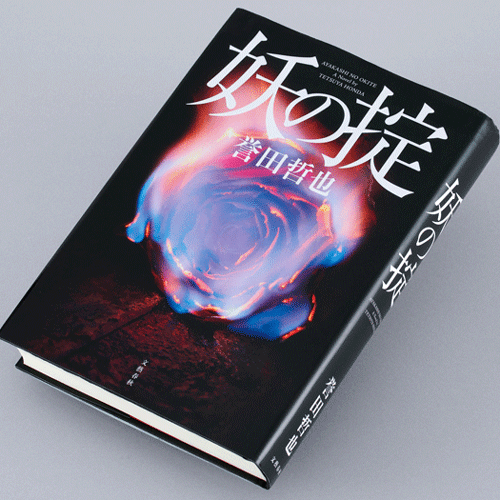「警察小説大賞」連動企画 ◇ 誉田哲也が明かす「警察小説の極意」前編
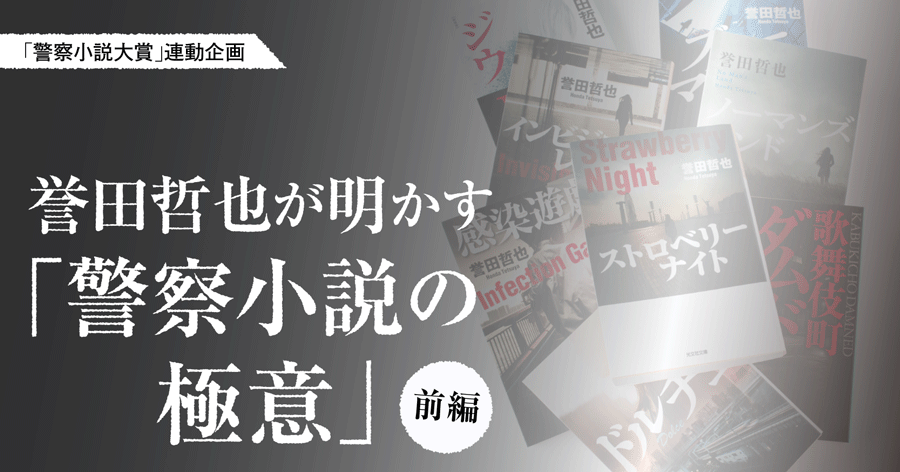
2017年に創設された警察小説大賞も第三回を迎えた。今後も、警察小説のさらなる隆盛、そして革新を願うなか、応募者たちはいかなる姿勢で執筆に臨めばいいのか。女性刑事を主人公に据えた「姫川玲子シリーズ」、また「〈ジウ〉サーガ」では警視庁特殊急襲部隊を登場させるなど、常にジャンルに新風を吹き込んできたのが誉田哲也氏である。名実ともに警察小説のトップランナーの誉田氏に、「創作の極意」を聞いた。
ドラマ『踊る大捜査線』でリアルな組織体系を知った
『妖の華』は吸血鬼の話です。「紅鈴」という江戸時代に生まれた女の吸血鬼が、現代までざっと四〇〇年にわたって生きていたら面白いなと、そんな発想で書いたものでした。
最初の投稿原稿は江戸時代、戦国時代、現代を舞台にした三本の連作短編で、ボツになりました。ただ、自分なりに手応えがあったというか、初めて登場人物の面白さを感じたので、現代ものの一編を長編化してみようと思ったんです。そこで問題になったのが、吸血鬼が人の血を飲んで殺すという描写はあり得ないながらもまぁいいとして(笑)、「死体はどうするんだ?」という部分でした。当然、警察が出てきますよね。
僕が最初に得た警察についての知識というかイメージは、『太陽にほえろ!』(一九七二年〜一九八六年に放送された刑事ドラマ)でした。あのドラマでは、泥棒も殺人も薬物も全て、メインキャストの数人が捜査していたんですよね。
でも、僕が小説を書き始めた頃には、『踊る大捜査線』(一九九七年)の再放送をやっていました。あのドラマは、強行犯係や盗犯係という部署割りであるとか、警視庁を「本店」と呼び所轄署を「支店」と呼ぶことであるとか、『太陽にほえろ!』とは比べ物にならない、リアルな警察の組織体系を表に出していた。再放送されるぐらい人気のドラマで、みんながこれを見ているのであれば、警察について小説の中であまりにデタラメなことを書いたら、興醒めだろうなと思ったんです。
そこから資料を通り寄せて、がつがつ勉強していきました。その過程で、警察小説と出会ったんです。世の中には警察小説と呼ばれる小説があるらしい。そのことは知っていたんですが、「刑事が出てくれば全部、警察小説じゃないの?」と思ったりしていた。大沢在昌さんの『新宿鮫』や逢坂剛さんの『百舌の叫ぶ夜』、髙村薫さんの『マークスの山』など、実際に警察小説と呼ばれているものを手に取って読んでみると、明らかに違うんですよ。それまで書かれてきたミステリーのように、探偵役として一匹狼の刑事が勝手に動いて推理して、事件を解決に導くかたちではなかった。何か事件が起きたらば、警察全体が動く。主人公となる刑事の動きが、警察全体の動きと必ず紐づけられていたんです。
この動かし方、個人と警察組織の連動のさせ方は、ノンフィクションの資料を読むよりも、警察小説を読んだ時の方が数十倍、自分の中に入ってくる感覚がありました。そこでようやく、よし、自分でも書いてみようと思えるようになった。
まず試しに書いたのは、実は『主よ、永遠の休息を』という小説でした。デビュー後に主人公を新聞記者に変え性別と名前も変えて、大幅にリライトして出版させてもらったんですが、元は警察官だったんです。実を言えば、主人公の名前は「姫川玲子」でした(笑)。投稿時の原稿はあまりできがよくなかったんですけど、警察を動かすことに関してはコツがつかめた気がした。じゃあこの警察の動かし方を頭の真ん中に置きつつ、そもそもの懸案だった吸血鬼の話を書いて送ってみたら、賞をいただけたんです。
『妖の華』は吸血鬼の視点と、追う警察の視点が共存しています。いわば、伝奇ホラーと警察小説を融合させた作品だった。ただ、書き終えてみたら、警察小説の方が楽しくなってしまっていたんです。デビュー後は警察小説をメインに書いていくようになり、そのせいでとうの昔に構想済みだった『妖の華』の続編(『妖の掟』)は、一七年後の去年ようやく刊行することになりました(笑)。
警察組織の情報の中から主人公やドラマが生じる
女性を主人公にした警察小説は当時、まだ珍しかったと思います。他の警察小説との差別化をしたかった、というような思惑があったわけではありません。映画の『リング』を観た時に、テレビ局の敏腕ディレクター役だった松嶋菜々子さんの振る舞いがかっこ良かったんですよ。テーブルに大きなクリップで留められた新聞を広げて読んでいたところで、気になるニュースを見つける。でも、すぐに出かけなければいけない用事がある。通りかかった男性のADに、「この記事のこと、調べておいてくれる? 分かったら連絡ちょうだい」と言って、颯爽と立ち去っていく。
背の高いスーツ姿の女性が、部下に指示を出す。そのワンシーンのイメージから、姫川玲子という人物像を立ち上げました。
まずはかっこよさ重視で女性の主任刑事という設定を固めましたが、そこからいろいろな要素が集まってきました。警察という男社会の中で女性であるということは、その組織にとってはメジャーなものを、マイナーな視点から見つめていくことができる。また、昔ながらの作業ジャンパーを着た刑事しか出てこなかったら、どう考えても作品のトーンはくすんだものになるじゃないですか。「姫川玲子」という名前にした理由でもあるんですが、たとえ残酷な事件を扱っていっても、彼女が捜査していればちょっとした華やかさを出せるんです。
「〈ジウ〉サーガ」の出発点は、かなり特殊です。姫川玲子の短編を読んだ編集者が「うちでも警察小説を書いてよ。向こうは女性刑事が一人だからこっちは二人で!」と、エビ天一本追加してくれみたいなノリで言ってきたんですね。まだ右も左もわからない新人ですから、やってみるしかないだろうなあと思っていたところで、「あとさぁ、SAT出してよ、SAT」と、かき揚げも追加してきた(笑)。
SAT(=警備部に編成されている特殊急襲部隊「Special Assault Team」)に所属する女性刑事と、SIT(=警視庁特殊犯捜査係「Special Investigation Team」)に所属する女性刑事のペアにしたのは、警察の組織機構からくる必然の帰結でした。例えば立てこもり事件など、重大な事件が進行中であると判明した場合、完全武装したSATがいきなり現場にやってくることはありません。まず出ていくのは、SITです。刑事部であるSITが、犯人の要求は何でありどうやって説得するか、人質は何人いて今どういう状態なのか、マスコミ対策はどうするかというところまで含めて、できる限り対応していく。その先で、SITではやむにやまれなくなった場合に、警備部であるSATの出番が来るんです。
当時はまだSATの文献が非常に少なく情報把握はかなり苦労したんですが、ひとつはっきりと分かったのは、SATには女性隊員がいないということでした。それならば、SATに初の女性隊員を入れるというストーリーは面白い。その人物はもともとSITにいたことにして、その同僚である女性刑事をもう一人の主人公にしようと考えました。直接的なきっかけはエビ天でありかき揚げでしたが(笑)、警察組織についての知識から、二人の主人公が生まれたんです。
警察小説を書き出した頃は、自分の考えたドラマが警察組織の機構にフィットせず動きづらさを感じていました。しかし、警察組織について詳しく知り、日本の法律についても掘り下げて学んでいくうちに、そうした情報の中からドラマが生まれてくるようになっていった。これがネタ枯れせずに、今でも警察小説を書き続けることができている理由の一つです。
もう一つの理由というか発想法は、「姫川玲子とは違うタイプの主人公にしよう」です。後発シリーズの魚住久江は、警視庁捜査一課の第一線で活躍する姫川玲子とは違い、事件が起こることそのものを止められないかと考え、所轄署の強行犯係で日常生活に根ざした事件と向き合うことに喜びを見出している。あるいは、四二歳という年齢から来る老いを感じている。そもそも小説というものは、主人公がそれまでの人生を通して培ってきた「視点」がフィルターとなり、そのフィルターを通して見える世界が読者に届くわけです。それは書き手にとっても同じで、たとえ似たような事件を取り上げたとしても、フィルターを変えてみれば、見えてくるものはまるっきり変わってくるんです。
警察組織を正しく書くそのうえで例外を書く
事件が起こり、道端に死体がひとつ転がった場合には、警察組織のどこがどういう順番で捜査に関わってくるのかは、現実において厳密に決まっています。警察小説においても、そのルールの通りに「正しく書く」ことが必須です。あるいは、「現実はこういうルールです」という前提となる情報を明示し、その情報の前後に「これはイレギュラーです」と但し書きのようなものを加えたうえで、小説における独自の展開を書く。
よく『警視庁なんとかなんとか班』みたいな、架空の警察組織を描いたお話があるじゃないですか。「いや、ないからね」という感想しか抱きようがない(笑)。現行の警察庁、警視庁、道府県警が、「こういうケースには対応できません」という事件なんてあるわけはありません。どんな事件であれ、必ずその事件に応じたセクションは存在する。ですから、やはり大事なことは「正しく書く」。
ところが、『背中の蜘蛛』で僕は初めて、架空のセクションを書きました。情報管理課の運用第二係まではありますが、第三係は存在しません。詳しい業務内容はストーリーの根幹に関わってくるので伏せますが、もしも新セクションがあり得るのだとしたらこういうものではないのか。「現存の組織がやればいいのに、わざわざ新しい部署を立ち上げて、一体どんなロジックで予算が取れると思ってるの?」といった、かつて『警視庁なんとかなんとか班』的な作品に対して自分が抱いていた疑問を、一つ一つ潰していったつもりです。
今は「小説すばる」で、『フェイクフィクション』という警察小説を連載しています。『ストロベリーナイト』の頃とはだいぶ書き方が違ってきたなと感じる点は、SSBC、捜査支援分析センター(Sousa Sien Bunseki Center)の存在の大きさです。二〇〇九年に警視庁刑事部に設置された、監視カメラや電子機器の分析、および犯人像のプロファイリングを行う部署ですね。
僕が知る限り、警視庁刑事部捜査第一課殺人犯捜査係はかつて、多い時には一四係ぐらいありました。ところが今や、七係にまで減っている。減った分の人員がどこに移っているか? SSBCです。刑事捜査は今や、SSBCありきとなっている。『ストロベリーナイト』の頃の知識だけで書いていたら、自分が書くものはあっという間に時代遅れになっていました。最新の捜査手法や組織変革に関する情報のアップデートを常に意識し、やはりここでも、「正しく書く」。
「正しく書く」ことは、警察小説を書くうえでの、必要十分条件だと思っています。言い換えるならば、警察という実在の組織をお借りして小説を書く際の、礼儀であり職業倫理であると僕は思うんです。
誉田哲也(ほんだ・てつや)
1969年、東京生まれ。学習院大学卒業。ムー伝奇ノベル大賞優秀賞を獲得した『妖の華』でデビュー。警察小説の金字塔である『ストロベリーナイト』の姫川玲子シリーズ、「ジウ」シリーズほか、『武士道シックスティーン』『増山超能力師大戦争』などジャンルを越えて作品を発表。
(取材・構成/吉田大助)
〈「STORY BOX」2021年4月号掲載〉