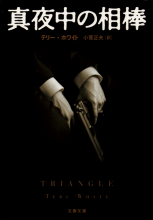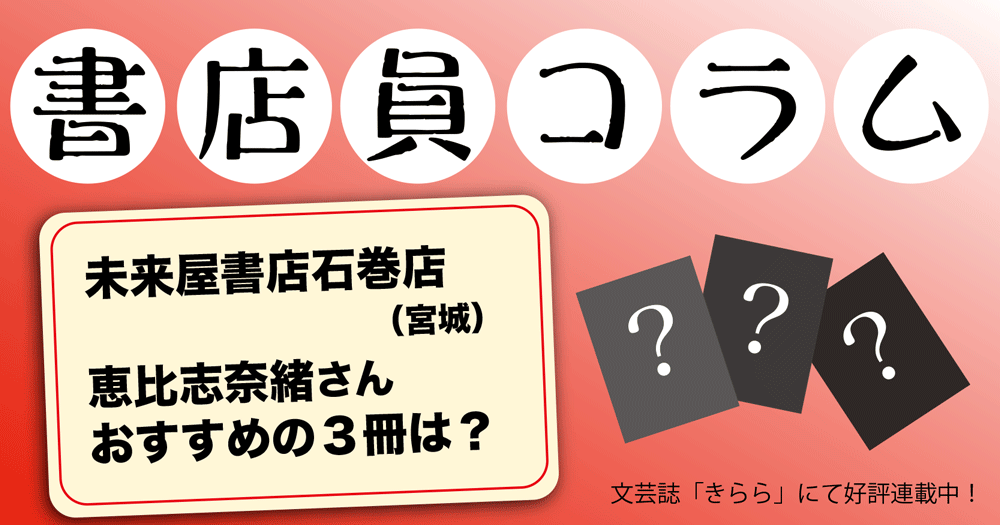この世の夜の底で
崩壊を迎えたばかりの風景の中、瓦礫を背景に浮かぶ一つの林檎。誰かが思いつきで描き加えたような赤色は、均衡を失った眺めには不似合いな、日常そのものの色だった。私はなにか信じ難い気持ちでその林檎を拾い上げ、鼻先を寄せた。燃料油の匂い。なにせ海水・ヘドロ・家屋・車・その他、の混合物に呑まれた代物なのだ。知りながら私はそれを食った。二〇一一年三月、忘れえぬ食の記憶。
作家の辺見庸は、飽食に慣れた舌と胃袋に異境の食を味わわせるため、旅立った。その旅が『もの食う人びと』を生んだ。様々な食の光景を訪ね、ときに人びとの記憶を抉り、記憶に抉られ、じかに触れ、自ら食らう旅。生命のある所には必ず食の営みがある。金持ちの食べ残しを売るバングラデシュの残飯市場。ポーランドの炭鉱で石炭を食ったあとに流し込む具沢山のスープ。ミンダナオ島での残留日本兵による禁忌の食。そしてソマリアの飢餓の中で、ただ死を待つ少女の目。かたや「食えない」環境にあっては、食の不在を埋めるかのように、死の匂いが立ち込める。

車谷長吉『鹽壺の匙』は、自らを私小説作家と称し、作品全てを遺稿のつもりで書いた作者の最初の小説集だ。戦時の暗さと貧しさがこびりついた昭和の田舎で、体裁など構わない剥き出しの卑しさ、浅ましさが互いを食らいあう様が、切れのよい播州弁で語られる。「私」が仏壇に火を放っても尚、焦げた仏壇の前で新興宗教の念仏を唱え続ける母親の姿に、新しい呪いの形式を見た。書く事、これは復讐かもしれず、また捻じ曲がった懺悔なのだと私は思った。

テリー・ホワイト『真夜中の相棒』は、殺し屋の物語だ。心優しい子供のようなジョニーと、家族を知らないポーカー狂のマック。二人はヴェトナムの従軍兵士として出会い、ともに戦場を離れたのち、殺人を請け負って生きる事を選ぶ。未来への希望を語りながらも、彼らは神が片手間に決めた運命の淵を、ままならぬまま落ちていく。ふたつの精神はいつしか深い所で結びつき、歪なひとかたまりとなった。愛であれ依存であれ、彼らは互いを必要としたのだ。都会の間隙をすり抜けるような、滑らかな筆致が心地好い。アメリカの夜の底、息を潜めるように、淡いブルーのBMWが駆けていく。