いまこそ読みたい、「感染症」や「パンデミック」について考えられる本

カミュの小説『ペスト』が世界的に売り上げを伸ばすなど、コロナ禍を受け、感染症の恐ろしさを描いた作品がいま再注目されています。今回は、“パンデミック”や“感染症”について考えるきっかけとなるような本を3作品ご紹介します。
新型コロナウイルスの感染拡大が医療や経済に深刻な影響を及ぼしているいま、フランスの作家・カミュが1947年に発表した小説『ペスト』が全世界的に売れ、注目を集めています。
未知のウイルスの恐怖や日に日に悪化する社会情勢に否が応でも向き合わなければならない状況の中で、『ペスト』を始めとする文学作品から何かしらの考えるヒントを得たい──という方も多いのではないでしょうか。
今回は『ペスト』を中心に、感染症の蔓延やそれに伴う社会の混乱、病気になった人々の生活などを描いた海外文学の中から、いまだからこそ多くの人に読んでほしい小説を3作品ご紹介します。
『ペスト』(カミュ)
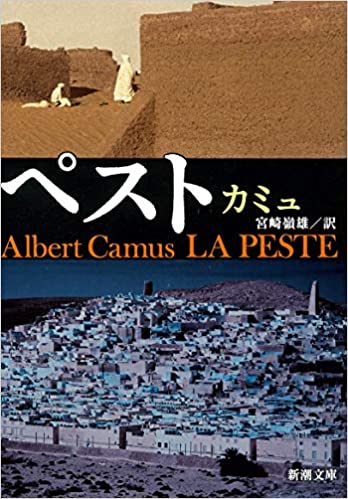
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4102114033/
カミュの『ペスト』は、ペストの猛威に突如襲われたアルジェリアのオラン市を舞台に、外部と遮断され封鎖された孤立状態の中で生きる市民たちの闘いを描いた小説です。本作はカミュのもっとも有名な作品のひとつであるとともに、カフカの『変身』に並ぶ不条理文学の代表作としても知られています。
コロナ禍のもとに生きる私たちの情勢と重ね合わされ、全世界的に売れ行きを伸ばしている『ペスト』。本作がいまこれほど注目されているのは、ペストという感染症が蔓延していくまでの経緯が現在の世界情勢によく似ているのはもちろん、病のような“不条理”に翻弄される人々の姿を、カミュが非常にリアルな筆致で描いていることが大きな理由であるのは疑いようもありません。
本作には、ペストと果敢に闘い続ける医師のリウーや、同じくペスト対策に奔走するタルー、違法に市を脱出する計画をとりやめ、彼らとともにペストと闘う決心を固めるランベールといったさまざまな人物が登場します。中でも、強く読み手の心を掴むであろう人物のひとりが、小説家を志している下級官吏のグランです。
グランは、仕事のかたわら誰に読まれることもない小説の序文を長いあいだ推敲し続けている小市民として描かれます。彼は、ペストが猛威を振るう非常事態の中にあっても、文学的に無価値だと他人にみなされかねない自分の作品に誠実な愛情を注ぎ続けるとともに、役人としての自分の仕事にも淡々と向き合い続けます。
やがてグランは、ペストによる死者が増え機能不全に陥った街で、防疫対策の中心的な人物となっていきます。グランのその仕事ぶりを、カミュはこのように描写しています。
グランは保健隊を動かしていたもの静かな美徳の生きた体現者だった。彼はいつものような善良さを以て、逡巡なく『はい』と答えた。彼は自分にできる仕事があるなら、どんな雑用でも役に立ちたいと言った。
未曾有の事態の中で、自分の仕事やおこないが果たして社会的に意義のあるものなのか疑問を抱いていたり、何をしていても無力感に襲われてしまうという人は少なくないのではないでしょうか。そういった気持ちに苦しんでいる人にとって、自分だけが価値を知っているささやかな喜びとすべき仕事を淡々とするという覚悟を両立させているグランの態度は、心を少し軽くしてくれるものかもしれません。
グランを始め、『ペスト』に登場する人物たちは皆、それぞれに違った態度や武器をもって未知の感染症と向き合い、闘います。社会情勢や出口の見えない現状にうんざりし疲れ果ててしまっている人も、自分がこの状況にどのような態度で向き合い闘っていくべきかのヒントを、『ペスト』を読むことで得られるはずです。
『いいなづけ』(マンゾーニ)
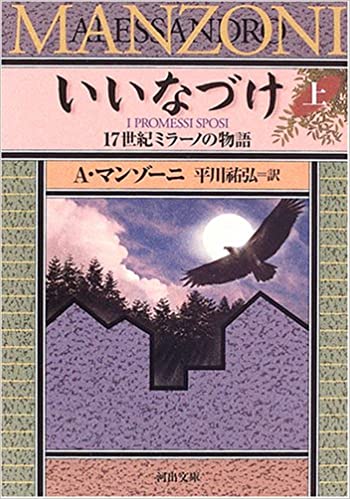
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4309462677/
『いいなづけ』は、ダンテと並ぶイタリアの国民的作家・マンゾーニによる古典作品です。
17世紀のミラノを舞台とするこの長編小説は、数多の困難に満ちた逃避行の末に結ばれるふたりの若者の恋愛物語を主軸としつつ、当時のイタリアの社会情勢や市井の人々の暮らしも鮮やかに描いています。レンツォとルチーアという若き恋人たち、そしてイタリアの人々を襲ったさまざまな困難には、暴動や戦争、飢饉に加え、ペストの大流行がありました。
『いいなづけ』の第31章では、ペストという病がミラノの街、そしてイタリア全土を侵攻していくまでの様子が克明に描かれています。驚かされるのは、カミュの『ペスト』と同様、その描写の中に、現代に通じる点があまりに多いことです。
作中では、始めにペストの兆候に気づきそれを検疫所に伝えた医師たちの警告は信頼に足らないものとして無視され、ドイツ軍がミラノを通ったことによる苦痛と貧困の結果出た病気だと、事実を歪めた形で官吏によって報告されます。感染者数が人知れず増え、厚生局も無視をできない段階になってきてようやく防疫対策が指示されるものの、対策よりも戦争や王室の慶事が優先され、人々はその重大性に気づくことができません。
極めつけとして、ペスト患者の遺体は焼却するようにという支持が厚生局から出ても、市民たちは自分の生活のために死者の持ち物や衣服を盗んでしまい、そこからさらに感染が広まります。
感染源は他国の人々だと考える差別心、感染対策は打ち出すものの補償はしない政府の態度、病気に関する人々の無理解と増幅していく憎悪──など、この小説に書かれていることがコロナ禍にある現代社会の様子と酷似している、と感じる方は多いのではないでしょうか。カルヴァン派信者を経てカトリックに改宗し、強い信仰心と道徳心を終世抱いていたマンゾーニは、この章を次のような教訓的な文章で結んでいます。
どうだろう、はじめは、これはペストではない、絶対にそうではない、ペストなどと言ってはならない、と言っていた。しばらくすると、疑似ペストと名付けられ、本物がわきからそっとさしこまれる。また、しばらくすると、ペストはペストだが、本当のペストではなくて、仮にペストと呼んでおくのだという。最後には、うたがいもなく真正ペストであるが、そこにも毒塗りとか魔法とかがくっつけられて、事実の形を歪める。
歴史をそんなによく知らない者にも分かるだろうが、多くの事実はこういう経過を辿るのである。(中略)大事なことでもそうでないことでも、言う前によく見て、よく聞いて、比較して、考えたら、こういうひどいことにはならないものだ。
『サナトリウム』(モーム)
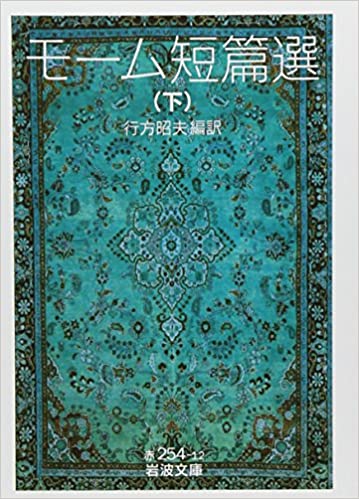
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4003725034/
2020年4月16日現在、日本の新型コロナウイルス感染者の数は9000人弱と発表されています。日に日に増えていく感染者数に危機感を覚えたり、冷静に感染対策をしたりしながらも、どこかでまだ「自分はかからないはず」、あるいは「健康だから、かかっても軽症で済むはず」と思っている人も少なくないのが現状ではないでしょうか。
『月と六ペンス』などの作品で知られるモームの短編小説『サナトリウム』には、結核が“死の病”としていまだ猛威を振るっていた20世紀初頭に結核に感染し、どうして自分が感染しなければならなかったのかと自問自答し続ける男が登場します。
チェスターという名の30代のその男は会計士で、結核にかかるまでは健康そのものの筋骨たくましい人物でした。彼は結核にかかったとわかったときに、思わず次のように考えます。
チェスターの心は折れた。それは運命が仕掛けた残酷で不当な仕打ちのように思えた。放埒な生き方をしてきたならば納得もできよう。暴飲したり女遊びをしたり夜更かしをしていたならば自業自得だが、そんな生活に無縁なチェスターにとってこれは不公平もいいところだ。
チェスターはサナトリウムでの闘病生活を送りながら、自分が病気なのにも関わらず依然として健康でいる妻に対し、苛立ちを覚えるようになります。そんな理不尽とも言える怒りを持て余すチェスターのことを、モームはこのように描写します。
人がどんな深みに落ち込みどんな高みに引き上げられるかなんて誰にも分からない。ヘンリー・チェスターの問題は貧弱な理想しか抱けなかったことにあった。彼はこの世に生まれ落ち、月並みな人生の浮き沈みとやらに晒されながら、その人生を歩んだ。予期せぬ事態が彼の身に降りかかった時、どうにも対処する術を持ち合わせていなかったのだ。
ヘンリー・チェスターが哲学を持っていなかったとしても彼を責めるべきではない。そうした哲学があれば災難を耐え甘んじて受け入れることができたかもしれないのだが、誰もが芸術や思想に慰みを見いだせるわけではないのだ。
彼のように“予期せぬ事態”が自分の身に突如降りかかったとき、自分ならばどのような姿勢でどのように対処するか──ということを、コロナ禍はもちろん、他の震災や台風といった自然災害のリスクにも常に晒されている私たちは、一度立ち止まって考えてみる必要がありそうです。死を含む最悪の可能性も含めてあらゆるリスクを想像し検討してみることは一見悲観的な行為のようですが、むしろ反対に、困難な状況下にあっても絶望せずに生き抜くための活路をそこに見出すことができるかもしれません。
おわりに
ペストを代表とする感染症が蔓延する社会を描いた小説は、時に現在の社会状況の生き写しのようにも見えます。特に、感染が拡大し医療的・経済的な打撃が市民を襲ってもその現実を見ようとせず、具体的な補償に踏み切らない政府や、市民間に生まれる断絶や差別意識といった描写は、まさにいまの社会に重ね合わせることができそうです。
私たちはこの不条理にどう反抗し、この社会をどう生き抜いていくべきなのか──。先人たちの小説をいま改めて読むことは、その思考の一助となるはずです。
初出:P+D MAGAZINE(2020/04/16)

