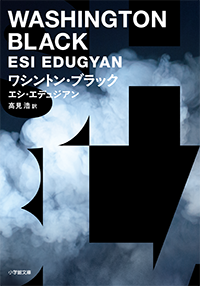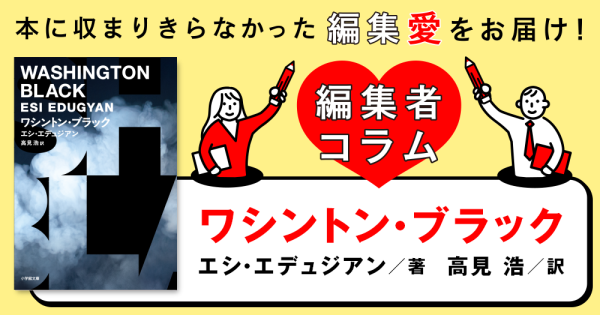◎編集者コラム◎ 『ワシントン・ブラック』エシ・エデュジアン 訳/高見 浩
◎編集者コラム◎
『ワシントン・ブラック』エシ・エデュジアン 訳/高見 浩
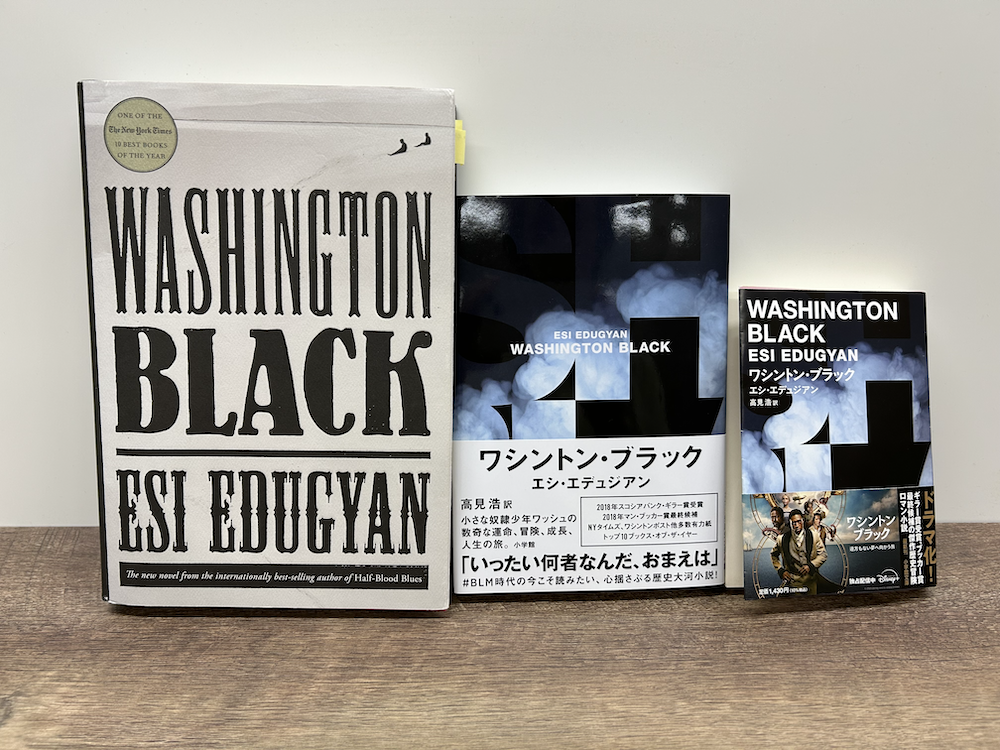
2004年に作家デュー、これまでに発表した長編小説は3作と寡作ながら、すでに2度のブッカー賞最終候補にのぼり、カナダ最高峰の文学賞ギラー賞を受賞すること2度、英語圏を中心に文学界の最重要作家の一人と位置づけられているエシ・エデュジアン。彼女が2018年に発表した『ワシントン・ブラック』は、2020年に高見浩訳にて日本で刊行。今年にはDisney+による映像化が実現、現在絶賛配信中の話題作がついに文庫になりました。
この文庫に収録されている作家・木内昇さんによる解説を特別に全文公開します。1800年代前半の東カリブの島からはじまり、やがて北米、北極、欧州、アフリカと壮大に舞台を広げつつ、奴隷少年ワッシュの成長と冒険、自我を求める心の旅を力強く美しく描く傑作歴史ロマンの魅力を、木内さんがたっぷりと綴っています。ぜひお読みください。
解説
木内 昇
掘り進むごとに色も形も違う幾多の石に突き当たるような感触を、本書に触れている間、ずっと得ていた。それは時に、冷ややかな鉄鉱石であったり、触ると崩れてしまう雲母であったり、暗闇でも美しい光沢を放つ翡翠であったりした。物語の語り手である、ジョージ・ワシントン・ブラック(ワッシュ)の目を通して語られる世界は、けっして明るい光に満ちているわけではなかったけれど、多彩で豊かな実感を伴って伝わってきたのだ。
十九世紀、西インド諸島、バルバドス島のフェイス農園。ここで、奴隷として働かされている少年ワッシュの、七年にわたる軌跡が描かれた物語だ。いわば成長譚なのだが、そのイメージであるところの、若者がさまざまな経験を糧にして一廉の人物になっていく、といった明朗な印象は希薄だ。もちろんワッシュは、天性の画才に加え、理性や探究心を兼ね備えているし、思いがけないきっかけで、科学者・ティッチとともに農園から解き放たれたのちは、確かに多くの経験をし、変化を遂げる。
しかしこの成長譚が特異なのは、ワッシュの旅が、単に「未来」へ向けて羽ばたくものではなく、「過去」へと掘り進んでいくところにある。もっと言えば、その精神世界において、自身のルーツを見出す旅であるように感じるのである。
冒頭、新たにやってきた農園主エラスムスから、奴隷たちがあたかも無機質な「もの」として扱われる、残忍な場面が描かれる。回顧として語られるせいか、どこか淡々として醒めた筆致なのだが、それゆえ、虐待は奴隷たちにとって当たり前の日常なのだと知れて、彼らが置かれた環境の酷さが生々しさを帯びる。だからこそ、ティッチがワッシュを年若い友人のように扱い、旅へと連れ出したとき、大きな安堵に包まれたのだ。ああ、これでワッシュは、「もの」ではなく「人」として生きていけるのだ、と。
外の世界はけれど、ワッシュをたやすく受け容れはしない。「黒んぼ」の上、気球実験の際に顔に大火傷を負った彼を、周囲は意味なく虐げ、傷つける。その都度、ティッチが楯となり、彼を庇護するのだ。農園で、同じく奴隷だったビッグ・キットという中年女性に守られていたように。ワッシュが、けっしてティッチと離れようとしないのは、必ずしも彼が、ひとりで立つ勇気や力を備えていなかったからだとは思えない。ワッシュが「人」として生きていくには、彼を「人」として認めてくれる他者の存在が近くになければならなかった気がするのだ。
旅の途中、ティッチから突き放されたときの、ワッシュの様子が如実にそれを物語っている。農園で奴隷たちが、さしたる理由もなく殺されていくのを見たとき以上に、彼は動揺し、途方もない絶望に苛まれる。なぜ自分は置いていかれたのか──その疑問は次第に、そもそもティッチは多くの奴隷の中からなぜ自分を選んだのかという懐疑へと深まっていく。「人」として見出したのか、それとも「もの」として最適だったからか。容易に答えの出ない問いを抱え、完全にひとりになったワッシュは、なおも旅を続ける。悲壮感の漂う展開ではあるが、しかし彼の本当の人生は、ここから幕を開けたようにも思うのだ。
常に白人たちの顔色を窺い、おどおどするばかりだった少年は、次第に逞しさを育んでいく。ノヴァ・スコシアで出会った白人女性ターナとの恋を育み、ターナの父親であり、ワッシュの尊敬する海洋生物学者・ゴフの研究に参画する。一方で、多額の懸賞金を提示して逃亡者であるワッシュを探すエラスムスや、その懸賞金目当てでワッシュの行方を追うウィラードの影に、怯えて暮らさねばならない。
かつてビッグ・キットは、自由について、こんなふうに語った。
「本当に自由な人間というのはね、働きたくなければシャベルを放り捨ててもいい、気に食わないことを訊かれたら、答えなくたっていいのさ」
ワッシュは足枷を解かれたように見えても、白人社会の中で生きている限り差別を受ける。持って生まれたものが、人生を苛むのだ。自分で選ばなかったもの、自分にはどうにもできない事柄によって、本来の自分として生きる自由を奪われ続けるのである。人間社会の浅ましさと理不尽さが痛々しく伝わってくる。それでも、自分の足で歩きはじめたワッシュは、後ろめたさやコンプレックスを抱えながらも、内なる軸を太く強靱にしていく。恋人であるターナの存在も大きかったろうが、なにより、他人ではなく、自分が自分を認めることで、彼は「人」となり得たのではないか。
対照的なのは、白人たちの寄る辺なさだ。心通い合わない家族、幼い頃の手酷い虐めの記憶、望まない仕事に就かなければならない重圧……。彼らは、自分たちが自由を奪っている奴隷たちと同等に不自由に見える。その憂さを、奴隷たちを虐げることで晴らしたところで、状況はなにひとつよくならないという虚しさに蝕まれながら生きているようにさえ映る。エラスムスが、多額の賞金を懸けてワッシュを追ったのは、単に主人としての面子を保つためだろうか。ワッシュと一緒にいるはずのティッチの居場所をたぐり寄せるためだろうか。いや、それよりも、虐げられる立場にある者が自由を手に入れていることへの憎悪が執着となって、その奥底に巣くっているように思えてならないのだ。
差別する者と差別される者。悲しいことに、どの時代、どの世界でも、この構図が潰えることはない。が、引いた目で見れば、両者は同等に不自由なのだ。内面から来る不自由さと、外からもたらされる不自由さ。それはまた、ティッチとワッシュの在り方でもあるのかもしれない。
ティッチは、科学者としての素晴らしい資質を備えながら、内面世界に閉じこもっていくように見える。彼の内側の世界には、けれど誰の姿も見えない。あれほど邂逅を願っていた父も、温かに通じ合うことの叶わなかった母や兄も、風化した岩のように砂塵となって荒野に消えてしまったのだろうか。ワッシュの姿は、そこにあったのか。それは「人」として? 「もの」として?
苛酷な起伏を辿るワッシュの旅だが、その行程が必ずしも鬱屈したトーンに終始しないのは、彼の目が折々に美しいものを捉えているからだろう。北極ではじめて見た雪が、単一な白ではなく、青や緑、黄色と色相を変化させる様子。スケッチのため赴いたノヴァ・スコシアの浜辺の潮だまりにいる、イソギンチャクやカニ、ウミエラといった生物たち。抜きん出た画才を持つ彼の目は、自然の風景や生き物を常に細やかに観察する。目に映る形状だけではない。光やにおいや感触といった五感を十二分に使い、自分の、自分だけの感覚で、世界を捉え直していくのである。
「洗いたての石のようなにおいと、ぼく自身の汗のにおいがするだけだった」
これは、ある凄惨な現場を目の当たりにしたあとの感慨だ。混乱のさなかにあるときでさえ、彼独自の感じ方は損なわれることがないのである。
本作にはこうした、はっと胸を衝かれるような表現や比喩があまたちりばめられている。奴隷として幼い頃から土にまみれて働いてきた少年の感性を、エシ・エデュジアンの筆はひとつの言葉も妥協することなく描ききった。少年期から青年期へと入るワッシュの変化を、彼の行動や心情以上に、感覚で表現しているところが、この成長譚のもうひとつの素晴らしい特性なのだ。出会ったもの、目に映る景色への感じ方が、少しずつ現実味を帯び、確固とした像を結んでいく様子に、幾度となく胸が震えた。
エシ・エデュジアンの非常に感覚的で繊細な表現を、私たちがあまさず感じとることができるのは、高見浩の翻訳があってこそだろう。ヘミングウェイをはじめ、五十年にわたり多数の翻訳を手掛けてきた氏である。今回、手元にある氏の訳本を改めて読み返してみたが、作品、著者によって風合いがまるで異なる。俗に「翻訳本っぽさ」と言われる、持って回ったような浮ついた文調は皆無、著者の文章をそのまま日本語であぶり出したような、地面にしかと根を下ろした表現と言えばいいだろうか。本作でも、ワッシュの思考が次第に大人びて理論的になっていく様や、旅を続ける中で自信をつけていく様子を、彼の口調や用いる語彙を変化させて見事に伝えてくる。登場人物たちの職制や年齢に合わせた言い回しや慣用句の使い方まで綿密に練られているため、彼らの声が聞こえてくるようである。素晴らしい翻訳とは、訳者自身が抱く豊穣な言葉のひとつひとつに、深く密接に関わっていることによって叶えられるのだと、強く実感する読書になった。
ワッシュは、自身のルーツに辿り着くことができるのだろうか。果たしてそこに、なにを見出すのだろう。
広い世界を知ることの喜びと残酷さ。成長することの素晴らしさと悲しさ。差別する側の空虚さと、される側の強さ。自由の身の不自由さと、不自由な環境における心の自由。この小説には、たくさんのパラドックスが潜んでいる。世界を、ひとつの定規で測ることなどできないのだ。正義も答えも行くべき道も、正解は人の数だけある。曖昧模糊とした日々の中で、私たちはなにを見て、なにを信ずるのか。ワッシュとともに旅をしながら、そんな問いかけが始終頭の中を巡っていた。
(きうち・のぼり/作家)