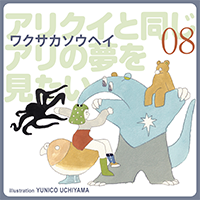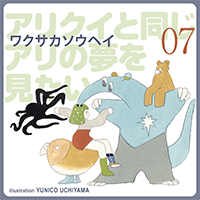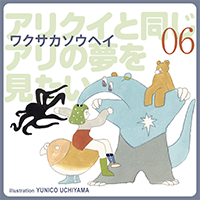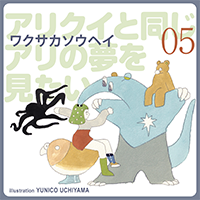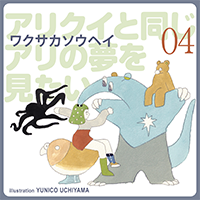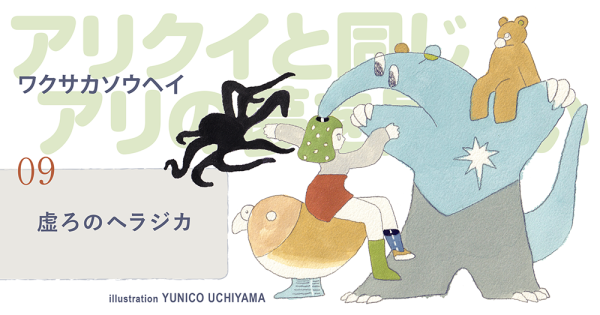ワクサカソウヘイ「アリクイと同じアリの夢を見たい」#09
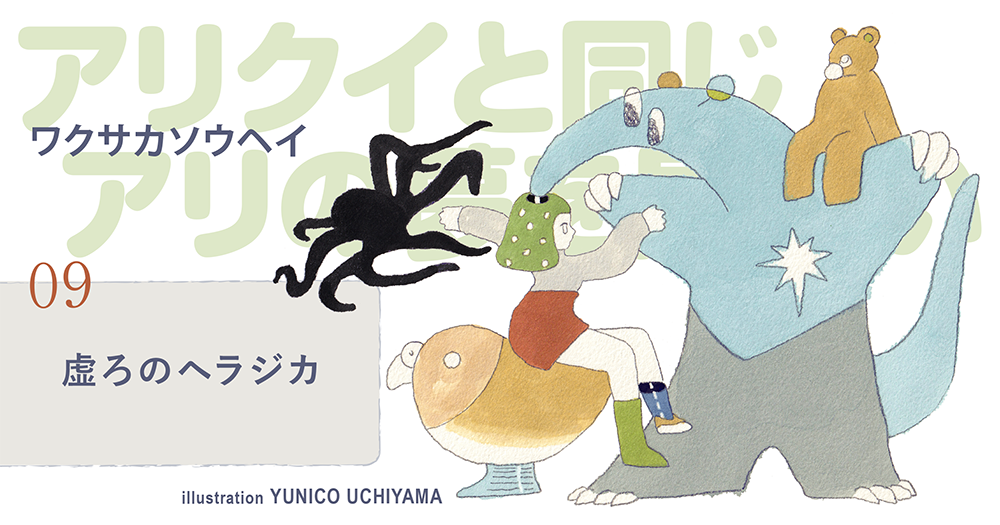
09 虚ろのヘラジカ
車に、まるで興味がない。
SUVだとか、加速性能だとか、サスペンションだとか。それらすべては、遠い世界の言葉のように聞こえる。国産車も外国車も、高級車も軽自動車も、私の目には等しく「移動手段」としか映らない。友人が得意げに「新車を買ったんだ」と報告してきても、「へえ」と生返事をするだけである。そのくらい、興味がない。
だから、街の景色は退屈だ。どこも駐車場ばかりだし、道路はアスファルトで一辺倒に塗り固められているし。この世界は車を中心に設計されている。車が走りやすいように、車を停めやすいように。車に興味のない者にとって、それはもう不気味なほどにつまらない光景である。
ところが、ベンツとなると話は変わってくる。
街角にベンツが現れると、胸をざわつかせてしまう自分がいる。駐車場でベンツを見つけると、息を止めながら、つい近づいてしまう自分がいる。まるで、草木が死に絶えた灰色の森の奥深くで、人智を超えた獣を見つけてしまった時のような反応だ。ベンツだけは、退屈な街並みの中で、唯一特別に輝いて見える車なのである。
どうして私はベンツにだけ心を揺らしてしまうのか。
答えは単純だ。
ベンツは、ヘラジカだからである。
野生のヘラジカの姿を、一度でいいから、この目に焼き付けたい。
そう思い続けて、もう何年が経つのだろう。
ヘラジカは世界最大のシカだ。
怪物のごとき並外れた体長。オスの頭部には巨大なツノが生えており、それは空を引き裂く稲妻が結晶化したような威容である。
「野生のヘラジカとの衝突事故を起こすと、車は木っ端みじんになる」なんていう話があるほどに、そのスケールは現実離れしている。まるでこの世の重心であるような、むしろ宇宙がこの生き物のために存在しているような。そう、ヘラジカとは世界最大にして、異形の風格を背負ったシカなのである。
ドイツ、スウェーデン、フィンランド。彼らはそうした寒冷地で悠然と生きている。
その姿を、この目で見たい。生身のヘラジカと、対峙したい。あらゆる生き物に対して偏愛を注ぎがちな私であるが、ヘラジカには段違いの執着を寄せている。
どうしてこんなにも、その巨大な生き物に惹かれるのか。たぶん私は、ヘラジカを通して、「現実の向こう側」に触れたいのだと思う。
野生動物との邂逅は、いつでも現実の先にある未知の景色を見せてくれる。退屈が渋滞するアスファルトの地平の裏側には、生きるに足る刺激がいくらでも秘められているのだと、そんな確信を得たくて、私は野生動物を追い求めることにずっと執念を燃やし続けてきた。
で、ヘラジカは、まさに現実を凌駕した別格なる存在である。
現実を裏切り、現実を食い破り、現実をねじ伏せて、森を闊歩する二本ヅノの王者。その比類なき姿に触れた瞬間、きっと私は無上の刺激を味わうことになるだろう。
ああ、ヘラジカに、どうして手を伸ばさずにいられようか。
私は知りたい。アスファルトがひび割れを起こすような、駐車場の整列を乱すような、信号の秩序を狂わせるような、つまり現実が形を歪めてしまうような、そんな世界最大級の野生の刺激を、どうしても知りたい。
だが。
私は、いまだにヘラジカに会えないでいる。
それは時間や金銭の問題ではない。時間はいくらでも捻出することができるし、貯金を使い果たす覚悟だってある。
では、なぜヘラジカに会えないでいるのか。
怖いのだ。
私は本物のヘラジカに会うことが、ひどく怖いのである。
ヘラジカに対して長年想いを馳せてきた。
その時間を紡ぐうち、ヘラジカは私の中でずんずんと巨大化していった。
最初は図鑑や動画で見た姿。そこに、目撃談を綴ったブログや生態を解説する論文から得た情報、そして北欧の神話に登場するヘラジカの象徴性などが、厚化粧のように塗り重ねられていく。もちろん憧憬の熱も混ざり合い、そうやって理想像は肥大していき、やがて私の頭の中のヘラジカは、地面をたわませながら歩く巨影となっていた。
目を閉じると、ヘラジカはバスよりも大きい。ダンプカーよりも大きい。下手したら、国道沿いのブックオフよりも大きい。
想像すればするほど、ヘラジカの輪郭は膨らみ、生き物としての形を失っていく。頭部のツノは根を生やすようにして空間へと広がっていき、いまや天を突こうとしている。
癖の際立ったその姿は、さらに次の癖を招いてしまい、留まることを知らない。四肢は強靭なものとなって、毛色は特別な白を纏うようになって。
それはもう、ヘラジカではない。自分の欲望が生んだ虚像である。
しかし困ったことに、その虚像こそが、私にとっての『本当のヘラジカ』となってしまったのだ。
もし、このまま、現実のヘラジカに会ったとしたら。
たぶんそれは、想像よりも小さい。
たぶんそれは、想像よりも地味だ。
そして私は、きっと幻滅する。『本当のヘラジカ』を、失ってしまう。現実はやはり退屈なものなのだと、絶対的に思い知ってしまう。
考えただけでも、身震いがする話だ。現実はどこまでいっても鮮やかではなく、どこまでいっても起伏のないものだなんて、そんなこと、わざわざ異国の地に出向いてまで確信したくはない。
北欧行きの航空チケットの予約を何度も寸前まで進めた。座席を選び、機内食はサーモンにするのかチキンにするのか迷って、クレジットカード番号を入力し、あとは「購入する」のボタンを押すだけ。でも、そこでいつも手が止まる。
会いたい。会いたいけど、会えない。
会ってしまったら、自分の中のヘラジカと、もう二度と会えなくなるかもしれないのだ。怖い、ヘラジカに会うのが、怖い。
私は現実のどうしようもなさに苛まれていた。
そう、現実というのは、どうしようもないことの連続である。
ガソリン代は知らない間に上がってしまう。急いでいる時ほど赤信号に捕まってしまう。駐車違反をすれば容赦なくステッカーを貼られてしまう。
そして、どうしようもないことに、人は最後、必ず死んでしまう。
二十代の終わりの年、最愛の友人を亡くした。
彼女と私は、とても気が合った。互いに旅が好きで、そして生き物が好きで、だから様々な場所を一緒にドライブしては、山や海や森を訪れた。普通免許を持ちながらも車に興味のない私に代わって、いつでも彼女は運転手を務めてくれた。
「未来ある若者を乗せているんだから、安全運転を心がけるね」
少しだけ年上の彼女は、ドライブが始まる前に、そんなことを必ず口にする癖があった。あなたにだっていくらでも未来はあるでしょ、と言うと、まあね、と笑って返される。慎重で繊細で明るくて、優しい人だった。
そんな彼女が死んだと聞いても、私は信じられなかった。なにかの間違いだと思った。
葬儀で、遺影を見た。笑顔の彼女が、額縁の中にいた。ああ、本当に死んでしまったんだ。いくらでも未来はあったはずなのに。もう会えないんだ。そこでやっと、私は現実を知った。現実のどうしようもなさを、思い知った。
その日は雨が降っていて、葬儀の帰り道に見るすべてのものは、灰色だった。彼女を失ってしまった世界は、なにもかもが退屈に覆われていた。
大切なものを失うというのは、当然ながら、とても怖いことである。
胸の内に育てたヘラジカを失いたくない私は、遠い北の地へ赴くことはないままに、その虚像を静かに守り続けていた。眠れない夜は、SNSでヘラジカの最新出没スポットを調べながら、なるほど、こういう場所にヘラジカは現れるのね、ふーん、そうか、まあ、それが知れただけでも満足ですよね、などと嘯き、自分の本当の想いを誤魔化したりしていた。
SNSのアルゴリズムというものは恐ろしくて、ヘラジカのことをしょっちゅう考えている者の「おすすめ」欄には、ヘラジカを中心とした話題や画像がズラッと並ぶ。時にはAIによって作られた、明らかに巨大すぎるヘラジカのフェイク画像が表示されたりもする。それらをまんまと栄養として摂取してしまい、私の頭の中のヘラジカは、さらに肥えていく。虚像がどんどん、膨れ上がっていく。
そんな日々の中で、ある時、ヘラジカにまつわる奇妙な話をひとつ、耳にした。
どういうものか。
ドイツやスウェーデンなどでは、ヘラジカが突然に車道へと現れることが日常的に多発している。ヘラジカは巨体である。それが時速五十キロ以上で走る車の前にいきなり登場したら、果たしてどのような結末を迎えるのか。急ブレーキを踏んでも間に合わず、衝突する。車は大破する。ヘラジカは死ぬ。そして人間も、死ぬ。ああ、辛い話だ。
こうした悲劇を起こさないために、車の開発現場に導入されているのが、「ムーステスト」である。ムースとは、ヘラジカの別称だ。
それは、ヘラジカのような大型動物などが急に目の前に現れても回避することができるかどうかを試す、国際規格の安全評価基準。ヘラジカを安全に避けられることが、高性能車の証といえるのだ。
そして、この「ムーステスト」を受けたことで、飛躍を遂げたマシンが存在する。
それが、ベンツだ。車に興味のない者でも必ず知っている、あのベンツである。
1997年、新型メルセデス・ベンツAクラスは、「ムーステスト」で芳しくない成績を収めてしまう。このことをきっかけに改良が施されたそのベンツは、やがて高い安全性を確保するに至る。純然たる進化である。
ヘラジカがいたからこそ、ベンツはさらなる成長を果たすことができた。ヘラジカの存在は、ベンツの存在に繋がっているのだ。
つまり。
ベンツは、ヘラジカの子どもなのである。
つまり、つまり。
ベンツは、ヘラジカなのである。
この話を、私はそのままツルッと飲み込んだ。
そうか、ベンツとは、ヘラジカであったのか。
ベンツって、ヘラジカに変換できるものであったのか。
それからというもの、私は街に出るたび、ベンツを探すようになった。
駐車場を通り抜ける時も、コンビニの前を横切る時も、視線を泳がせる。ヘラジカはどこだ、ヘラジカはどこかにいないか。しかし目に入ってくるのは、白い軽自動車、黒いミニバン、灰色のセダンなど、街に普段から沈殿しているものばかりである。
それでも諦めずに歩を進めていくと、目の前の交差点から、銀色に輝く三叉の星のエンブレムが、ぬっと顔を現すことがある。
「ヘラジカだ……!」
いや、それはベンツなのだが、しかし心臓がわずかに跳ねる。のっぺりとしていたはずの現実が、かすかに波を打つ。
車道を音もなく滑るベンツの姿を目で追うたび、私は、ヘラジカの生息する森を思い描く。木々の合間に射す薄い光、湿った苔、空気の奥で静かに鳴る鳥の声。そんな虚構の風景が、うっすらとだが、昼の住宅街に立ち昇ってくる。アスファルトの上であるはずなのに、ほんの一瞬だけ、露に濡れた草地に立っているような気分を味わう。
私は現実のベンツを通して、虚像のヘラジカを想起している。虚像のままに、胸の中で眺めている。
それは巨大なシカだ。現実を凌駕するような、とても巨大なシカである。現実には存在することのない、世界最大を超えたシカである。
私はいま、確かに『本当のヘラジカ』の存在を見ているのだ。生息地に足を運ぶことなく、念願の動物の姿を目撃しているのだ。それでもう、いいではないか。
そして、二度とこの現実に存在できなくなってしまった人のことを、思い出す。
大切な友人を失ってから、もう十年以上の年月が経っている。
彼女の顔を思い出すことも、少しずつ減っていった。でも、完全に忘れることはない。時々、ふとした瞬間に、彼女との記憶が蘇る。
「私、左折には自信があるんだ」
ドライブをしている最中、たまに彼女はそんなことを自慢げに漏らしていた。
「いや、だったら右折にも自信を持っていいのでは」
「右折はね、まだまだ修業中なんだけど、左折なら任せてよ」
「だから、なんで左折だけなんだよ」
そんな他愛もない会話の思い出が脳裏によぎり、そしてハンドルを握った彼女の横顔が浮かぶ。確かに彼女は左折が上手かったように思うが、どう上手かったのかまでは、思い出せない。
全部は霞んでいる。浮かんだ横顔だって、なんだか解像度は低い。彼女は本当に、こんな顔をしていたのだろうか。
彼女はもう遠い過去の人となってしまったのだから、雲をつかむような感じでしか思い出すことができないのも、当たり前の話ではある。しかし、この曖昧さは、年月が経ったことによる忘却だけが理由であるとも思わない。彼女は、最初から虚ろだったのだ。彼女は、最初から私が描いた空想だったのだ。
彼女だけではない。すべての他者は、きっとフィクションである。
目の前にいる人でさえ、実は虚像なのだ。
私たちは主観でしか現実の物事を捉えることができない。たとえば、現実のヘラジカが目の前にいるとする。でも、私が見ているヘラジカは、私が主観で構築した像でしかない。
光が網膜に届き、それが電気信号に変換され、脳が「これはヘラジカである」と判断する。そのプロセスには、わずかなタイムラグがある。つまり、私がいま見ているヘラジカは、ほんの少しだけ過去のヘラジカなのだ。生放送のように見えて、実はちょっとだけ前の録画なのである。
そして、私はヘラジカの内面を知ることはできない。ヘラジカがなにを考えているのか、なにを感じているのか、どのような性格を持っているのか。それは推測するしかない。「こういうヘラジカなんじゃないか」と、輪郭を与えるしかない。
そうなのだ、すべての他者は、虚像なのだ。
でも、虚像だからこそ、救いがある。
あなたの正体は、私にとっては架空である。だから、霧のように思い出した架空のあなたを助手席に乗せれば、私たちはまた一緒にドライブをすることができる。遠く離れていたとしても、あなたを虚像として認めさえすれば、いつでも好きな時に、その存在を近くで蘇らせることができる。
彼女はもういない。しかし、私が彼女を想う時、私の中に彼女は存在する。左折をするたびに、私は彼女の存在をそばで知る。
車に興味がなく、運転には不慣れで、左折にも全然自信のない私であるが、しかしいつかは野生のヘラジカを追うために異国で車を走らせなければいけない日が来るかもしれない。それに備えるため、外国車の運転練習を開始することにした。レンタルしたのは、もちろんベンツである。
ハンドルを切ってみれば、その滑らかなコーナリングに驚く。高性能の車というのは、このような角のない癖を持つものなのか。ヘラジカよ、素晴らしいマシンを生んでくれて、ありがとう。
ヘラジカの「突然に車道へと現れる」という癖が、数多くの車に「それを回避する」という癖を与えたのだ。生と死とが繰り返される現実の中で、癖とはそうやって流転しながら、永遠に紡がれていくものなのだろう。誰かの癖が、また誰かの癖を作り、そしてその癖はさらに別の癖となって受け継がれていき、退屈であるはずの現実を、鮮やかで起伏のあるものとして再構築していくのだ。
彼女の口癖を思い出す。
「未来ある若者を乗せているんだから、安全運転を心がけるね」
友人の虚像を助手席に座らせたまま、私はゆっくりと、慎重に、左折をした。
ワクサカソウヘイ
文筆家。1983年東京都生まれ。エッセイから小説、ルポ、脚本など、執筆活動は多岐にわたる。著書に『今日もひとり、ディズニーランドで』『夜の墓場で反省会』『男だけど、』『ふざける力』『出セイカツ記』など多数。また制作業や構成作家として多くの舞台やコントライブ、イベントにも携わっている。