貫井徳郎『罪と祈り』

罪を犯した人が捕まったり刑に服すこと以外での、償いの形を書いてみたかった
貫井徳郎氏、約2年ぶりの新作のタイトルは、罪と罰ならぬ、『罪と祈り』 。
ある時、隅田川・新大橋付近で西浅草在住の元警官〈濱仲辰司〉が遺体で発見される。身元確認のため管轄の久松署を訪れた〈亮輔〉は、父が頭部を鈍器で殴られた上で川に転落したらしいと、幼馴染で父親同士も親友だった久松署刑事〈芦原賢剛〉に聞かされる。
温厚なお巡りさんとして慕われた父親が、なぜ他殺なのか? 折しも勤め先が倒産し、目下無職の亮輔は事件当日の父の足取りを追う。賢剛の父〈智士〉の死以来、家族に対してもどこか心に壁があるように感じた父・辰司の過去とも、やがて向き合うことになる。だがそれは〈知らない方がいい〉過去でもあった―。
物語は平成末期の「亮輔と賢剛」編と、昭和末期の「辰司と智士」編が交互に進み、親世代の禍根に翻弄される2人の姿が時代と人の残酷な関係を映しだす、あまりにも切ない「正義と罪を巡る小説」である。
「元々は手塚治虫が『アドルフに告ぐ』で描いたような、運命に翻弄された2人の友情と対決を書きたくて、現代の亮輔と賢剛のパートありきで考え始めました。
ただ彼らは元ナチスでもユダヤ人でもないし、父親世代に何か謎があって、それを亮輔たちが背負うとしたらどんな過去だろうと考えて、このバブル期に起きた未解決の誘拐事件を思いつきました。僕もかつては不動産業界におり、ヤクザに立ち退きを強要させたり、〈豚の血〉を玄関に撒いたり、相当酷いことをやる某上場企業もあったと聞きますし、それこそバブルを知らない世代には作り話に見えるかもしれません。そうやって人々が金の力に呑み込まれ、常軌を逸していった時代に、彼らの父親がどう抗ったかを、現代と過去とを並行させながら書いてみました」
警察は隅田公園周辺の防犯カメラに映った不審者を追いつつ、逆恨みの線でも捜査を進めていた。しかし賢剛には、父・智士の死後も自分や母親を何かと気遣い、警官の道を開いてくれた辰司が恨みを買うとは思えない。そしてその疑問は、兄弟同然に育った亮輔にとっても同様だった。亮輔は、事件当日に父が立ち寄ったなじみの店で常連客に話を聞き、素顔を探るが、父を最もよく知るのは28年前に自殺した智士だったと、傷心の母までが口を揃えた。
とはいえ、智士が亡くなった時、亮輔たちは4歳。賢剛の母親に今さら事情も聞けず、遺品を検めた彼は、1冊のスクラップブックに目をとめる。そして父が智士の死と前後して起きた2つの事件を調べていたことを知る。1つは89年、〈東芳不動産〉社員の子息をめぐる、未解決誘拐事件。今1つは母親が乳児を衰弱死させた育児放棄事件で、夫がバブルで大金をつかみ、遊興に溺れたのが遠因ともされた。そして2つの事件の接点に〈時代に怒る〉人々の姿を見出した矢先、亮輔のもとにこんな警告文が届くのだ。〈これ以上、かぎ回るな〉
犯人の事情にも理解を示す読者
人情残る下町・浅草で「時代への怒り」を抱いた人々の義憤が、作中の随所で事態を展開させていく。
「今回、誘拐事件を未解決のままとするために、犯人側の動機の設定を工夫しました。結果的にそれが、容赦ない地上げで心理的に人々を追い込んだバブル期という『時代』がもつ背景にうまくリンクしました」
その怒りが、かたや信義に厚い警官、かたや心優しい板前として友情を育んだ「辰司と智士」の章からはひしひしと伝わる。悪辣な地上げに喘ぎ、ビルが建つ度に人々が分断される町の変化には、部外者でも義憤を覚えるほど。だが、〈罪は罪〉として、生温い共感には安住しないのが、貫井作品でもあった。
「例えば『必殺仕事人』も勧善懲悪ものではなく、金をもらって悪党を斬る仕事人もまた悪党として描いています。だから最後は必ず犬死したり酷い目に遭って、因果応報の大原則を僕らに教えてくれたように思う。
ただ最近は犯人側の事情にも一定の理解を示す優しい読者が多く、僕の見方はどうやら厳しすぎるみたいです(苦笑)。それで今回は『罪は罪だ』という意見と、『被害者も加害者もみんなが可哀そう』という意見を拮抗させる形にしたのですが、僕個人は断然、『罪は償うべき派』なんです」
その罪とは必ずしも違法行為を意味せず、ある人は〈今は、どこにも正義が存在しない。いくつもの不正義が罷り通っているだけで、どちらが正しいかは力関係によって決まる〉〈弱者が強者に歯向かおうとしたこと、そのことが罪なのだ〉と言い、またある人は〈罰されない罪があるから、納得できないんじゃないか〉と言った。その両方が切実な説得力を持つ中、罪としかいいようのない非相対的な罪の恐ろしさ、愚かさがまざまざと彼らに突きつけられる瞬間が、本書の白眉といえよう。
「この表題も罪の対義語を考えていた時に、今の世の中に必要なのは他罰よりも、自発的な祈りじゃないかと、直感的に思ったんです。つまり単に捕まるとか刑に服すという形以外での、罪を犯した人々の償いの形を書いてみたかったのです」
仮に時代にも罪があるとして、それらは何ら裁かれることなく忘れられてゆく。その中で怒り、抗った者ばかりが責めを負うのは不公平にも思えるが、その罪と正対し、祈ることができるのも、悲しいかな人間だけなのだ。
貫井徳郎(ぬくい・とくろう)
1968年東京生まれ。早稲田大学商学部卒。「僕自身は渋谷育ちですが、浅草に友人がいまして。亮輔たちが集まる元飴工場の喫茶店のモデルも、案内してもらいました」。不動産会社勤務を経て93年に第4回鮎川哲也賞最終候補作『慟哭』でデビュー。10年『乱反射』で第63回日本推理作家協会賞、『後悔と真実の色』で第23回山本周五郎賞。他に「症候群」シリーズや『プリズム』『愚行録』『私に似た人』『宿命と真実の炎』等。180センチ、64キロ、A型。
背景には、時代に翻弄された
男たちの絆と葛藤があった――
切ない真実が胸揺さぶるミステリ
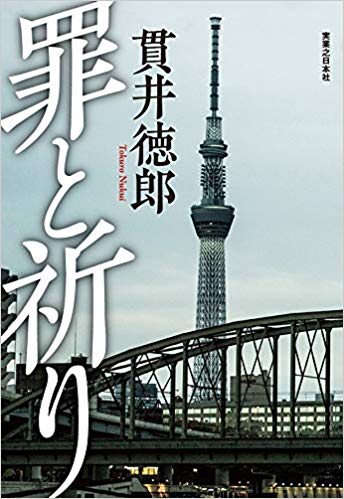
『罪と祈り』
実業之日本社
装丁/岩郷重力
写真/近藤 篤
〈「週刊ポスト」2019年10月4日号掲載〉


