高野和明『踏切の幽霊』
お涙はいらない
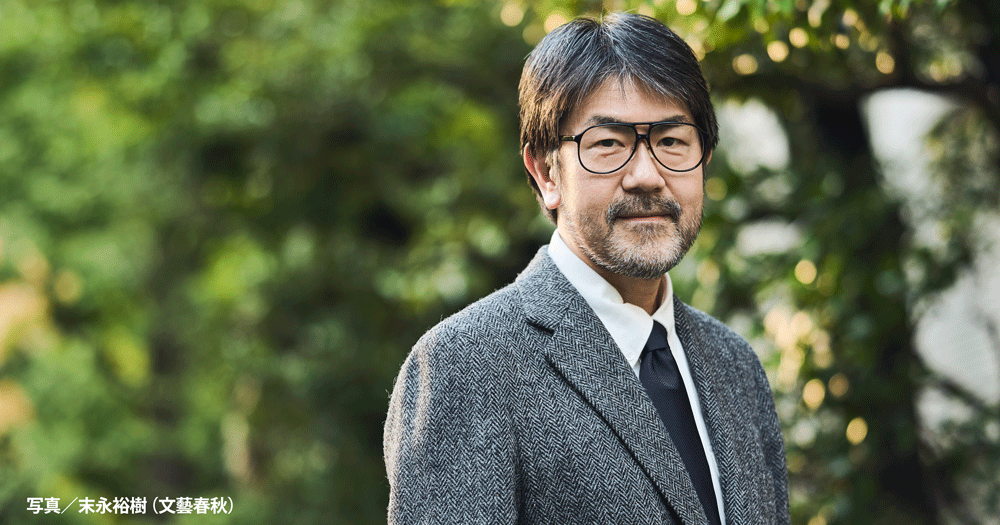
ハリウッド級どエンタメ『ジェノサイド』で第二回山田風太郎賞および第六五回日本推理作家協会賞を受賞した高野和明が、同作から実に一一年ぶりとなる長編『踏切の幽霊』を発表した。タイトルからは「ホラー」を連想させるが、著者は否定する。本作は、まごうことなき「ゴースト・ストーリー」なのだ。
身元不明の犠牲者に物語の着想を得た
死刑制度を題材にしたミステリー『13階段』で第四七回江戸川乱歩賞を受賞し、高野和明がデビューしたのは二〇〇一年、三六歳の時だ。それ以前は(実は作家デビュー後も)、脚本家・映画監督として活動していた。最新作『踏切の幽霊』の着想は、自主映画時代に芽生えたものだという。
「一九八〇年代の初め頃、下北沢駅近くの今はもうなくなってしまった『三号踏切』を自主映画で撮影することになりました。ホームの端から望遠レンズで踏切を撮ったらどうなるかを確認したくて、試しに写真を撮ってみたんです。現像してみたら、よくわからないものが写り込んでいました。遠景の踏切に、人の大きさぐらいの細長い像がぼーっと写っていた。心霊写真のような、薄気味悪い感じは一切ないんです。でも、他は全部ピントが合っているのにそこだけがボケていて、しかもシャッタースピードが速かったから被写体ブレを起こすはずもない。どうにも技術的に説明がつかないものでした。そこから〝もしもこれが幽霊だったら〟という着想を得て、物語を作っていきました」
踏切に出る幽霊の物語──そのアイデアが具体化したのは、国鉄戦後五大事故の一つである「三河島事故」に連想が及んだ時だった。一九六二年、常磐線三河島駅構内で発生し一六〇名もの死者を出した列車脱線多重衝突事故だ。
「たった一人だけ、最後まで身元が分からなかった犠牲者がいたんです。大勢の人間が密集して住んでいる大都市で亡くなったにもかかわらず、犠牲になった男性のことを知っている人がどこにもいなかった。その不思議な出来事と、踏切に出る幽霊の構想が結び付いた時、一番大きな謎の部分ができあがりました」
その幽霊は何者か。なぜ幽霊は踏切に出るのか。本作は、フェアプレー精神にのっとった極上のミステリーである。
「他にも大きな謎があったものの、答えは自分にも分かりませんでした(笑)。鉄道自殺だとありきたりになってしまうので避けたいところですが、他の死因だと、そもそもどうして幽霊が踏切に出るのかという別の謎が出てきてしまうんです。そうやって謎が謎を呼んでいき、主人公と一緒になって解明していったというのが構想段階の状況ですね。最後は、『ああ、そういうことだったのか』と自分でも思いました(笑)」
逃げも隠れもせずに幽霊をはっきり出す
本編は一九九四年一二月から始まる。五四歳の松田法夫は、東京の出版社で働く女性誌の記者だ。以前は全国紙の社会部記者としてバリバリ仕事をしていたが、二年前に最愛の妻を亡くしたことがきっかけで、今では生活のためだけに働いていた。ある日編集長から呼び出され、心霊ネタの取材を発注される。二人の読者から投稿された8ミリ映画とフィルムカメラの写真には、下北沢三号踏切の宙空に浮かぶぼやけた女の姿が写っていた。投稿者と会って話を聞き、調べて来い──。しかし、心霊現象の謎を追う松田は、幽霊という存在そのものに疑いがあった。〈この世に幽霊などいないのは、松田には分かり切っていた。彼自身が、ずっと妻の魂を探してきたからだ〉。この二年間で一度も、妻は松田の前に現れることはなかった。
「単なるオカルトファンの立場で言うと、〝私、見えるんです!〟という人の話が一番つまらない。〝私は幽霊なんかまったく信じてないんだけど、見ちゃいました〟と、普段は否定している人間が信じざるを得ないような状況になるからこそ面白い。だから、主人公は幽霊に対して懐疑的な人でなければいけませんでした。ただ主人公が徹底的に、はなから幽霊なんかとバカにしているようでは、幽霊の側も近付いてこないと思うんですよ。この人なら分かってもらえるかもしれない、と思うから近付いてくる。そういう、期せずして幽霊を引き寄せてしまうような資質を、主人公の人物設定に採り入れました。いつまでも死んだ妻のことを思い続けている、といったことです」
なぜ一九九四年を舞台にしたのか? 主人公に、足を使って調査してもらうためだ。
「Windows 95が発売されてパソコンやインターネットが急速に普及した一九九五年以降では、素人でもデジタル技術を使って心霊写真がいくらでも捏造できてしまう。それは避けたいと思ったので、この年代に設定しました。そもそも自分は、インターネットが大嫌いなんですよ。映画にしても小説にしても、主人公がパソコンにかじりついて調べものをしてる場面なんて全然面白くないので。本作の下調べでは、主人公が新聞記者をやっていた一九七〇年代から九〇年代にかけての資料を読み、当時の記者活動を知る方々からもお話を聞きました。心霊現象は絵空事に捉えられかねないものですから、それ以外のことは極力、現実の通りにしたかったんです」
一方で、幽霊および心霊現象に関しては、現実から遠ざかってしまう可能性を自覚しながらも一歩踏み込んで書いたという。
「幼稚園の頃から母親が怪談話を読み聞かせてくれていたこともあり、幽霊が出てくるお話はもともと好きでした。ただ、ホラーや実話怪談以外の一般小説で幽霊が描かれる場合、結局あれは主人公の幻想じゃなかったかという可能性を残した、曖昧な形でしか出てこない。それが言い訳めいていてイヤだなと思っていたので、私は逃げも隠れもせずに幽霊をはっきり出すことにしたんです。劇中の心霊現象を描いたシーンで、主人公だけが幽霊を見るのか、その場に居合わせた他の登場人物たち全員が見るのか、というのは創作上の大きな分岐点でしたが、全員が見るんだ、幽霊はいるんだ、という方向へ徐々に向かっていくように書きました」
幽霊を怖がるのではなく幽霊となった死者を悼む
本作に登場する幽霊は、怖い。主人公の妄想ではなく、実在を感じさせるものとして描かれているからこそ、なお怖い。しかし、怖さという感情は、この物語にとって一要素にすぎない。
「ホラーは怖がらせることを最優先にするジャンルだと思うのですが、この作品では怖がらせることを最優先にはしませんでした。怖さを描くのは二番目の目標であって、一番大事にしたのは、このストーリーをいかに面白く語っていくか、でした」
本作は、ホラーではない。何らかの事情によって蘇った死者と生者が織りなす感情の交感の物語──ゴースト・ストーリーなのだ。「ホラーとゴースト・ストーリーは、全く同じものではないんですね。自分の構想していた物語が、幽霊という素材をホラーの制約の外に出す初めての小説になるんじゃないかと気づいて、俄然やる気になりました。死者に対する生者の感情もいろいろ書き込めますし」
死者を悼むという感情にフォーカスすることは、ともすればお涙頂戴の展開になりかねない。そのような作劇を、本作は明確に否定している。いくらでもドラマチックに描ける部分を、サラッと書いている。
「二〇代の頃、アメリカに留学していたんですが、いろんな国から来た留学生と映画について話をしていた時に、お涙頂戴を作っているのは日本だけだと気づかされました。あれは欧米人の感覚からしたら、バカバカしいほどレベルの低い創作物で、要するに〝感動ポルノ〟ですよね。いい作品を作って泣かせてるんじゃなくて、観客に悲しい思いをさせているだけなんです。親しい人が死ねば誰だって悲しいのは当たり前で、女性の裸を見せれば男が興奮するのと同じ次元の話です」
お涙頂戴の展開は、悲しみの感情以外にも芽生えていた、さまざまな感情を洗い流してしまう。そうした展開を排することで、読者は豊かな感情体験を最後まで味わうことができるのだ。
「何も押しつけたくなかったんです。〝こういうことがありました〟ってところまでは書きますけど、心霊現象をどう解釈するとか、幽霊のあの行動にどんな意味があったのかという部分に関しては、読んだ人がそれぞれ自由に感じていただきたかった。もしも読者が、主人公と同じように心霊現象に遭遇したら何を感じるのか。すでに死んだはずの人と出会ったら、生命観や死生観はどんな風に変わるだろうか。本を開いている間、主人公と行動を共にしていただいて、死者の声に耳を傾けていただければ嬉しいです。従来のホラー小説とは少し違った、怖いだけではない読後感を味わっていただけるのではないかと思います」
都会の片隅にある踏切で撮影された、一枚の心霊写真。同じ踏切では、列車の非常停止が相次いでいた。雑誌記者の松田は、読者からの投稿をもとに心霊ネタの取材に乗り出すが、やがて彼の調査は幽霊事件にまつわる思わぬ真実に辿り着く。1994年冬、東京・下北沢で起こった怪異の全貌を描き、読む者に慄くような感動をもたらす幽霊小説の決定版!
高野和明(たかの・かずあき)
1964年生まれ。映画監督・岡本喜八氏に師事し、映画・テレビの撮影スタッフを経て脚本家、小説家に。2001年『13階段』で江戸川乱歩賞を、2011年の『ジェノサイド』で山田風太郎賞と日本推理作家協会賞を受賞。他の著書に『グレイヴディッガー』『K・Nの悲劇』『幽霊人命救助隊』『6時間後に君は死ぬ』。
(文・取材/吉田大助)
〈「STORY BOX」2023年2月号掲載〉


