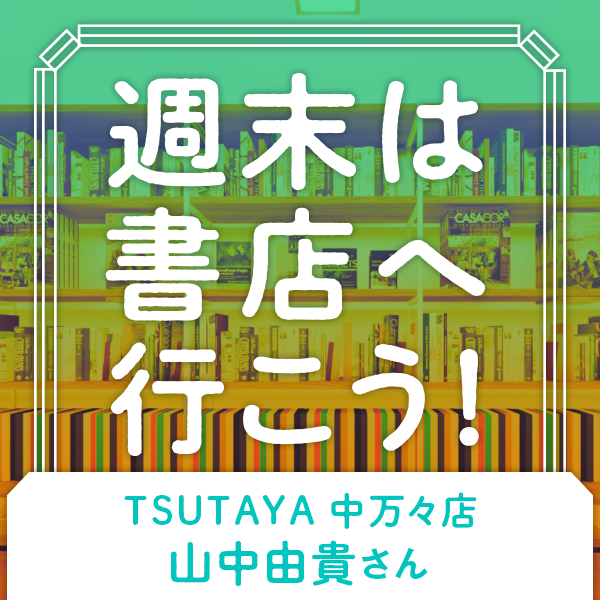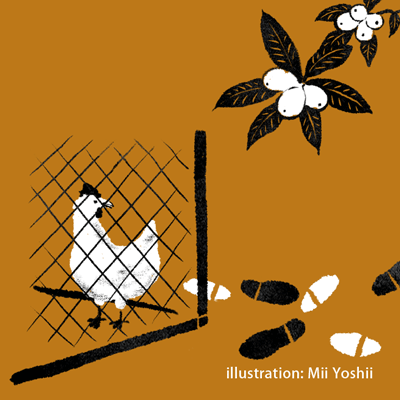道尾秀介さん『風神の手』
ミステリーと人間ドラマのかつてない配合に挑み続ける道尾秀介が、最新刊『風神の手』で新たな達成を遂げた。誰かの些細な嘘が、コミュニティ全体を揺るがす災いとなる──。数十年に渡る因果の物語を全四編の連作中編形式で綴る本作は、作家自身も驚く、偶然の連鎖によって生み出されたものだった。
東西を流れる西取川によって「上上町」と「下上町」に分かれるその地域は、川漁師が舟の上で松明を揺らし、鮎を驚かせて網に追い込む火振り漁で知られている。もうひとつの名所は、全国的にも珍しい「遺影専門」の写真館・鏡影館の存在だ。『風神の手』は、この写真館を訪れた人々の人生にクローズアップし、かつて彼らがついた嘘の顛末を辿る。全四編の連作形式が採用されているのだが、最初に書き出したのは、小学生のまめとでっかちが活躍する「第二章 口笛鳥」だ。事の発端は、作家の元へ大手新聞社から中編(連載期間四ヶ月)の連載依頼がきたことにある。
「この一編で本にするには分量が足りないなとか、この一編を元に連作にしようかなとか、先のことはまったく考えませんでした。今の自分が書ける一番いい中編を目指す、ということだけを考えたんです。その時に、子どもを書くこと、特に男の子を書くことが浮かびました。子どもってどの時代でも同じようなことで悩んで、同じようなことで喜んで、時代性に左右されない普遍的なものが書けるんです。その中でも、子どもならば必ずついたことがあるであろう、嘘を軸にした話にしようと思いました」
小学五年生のまめは、写真館の店主に嘘をつき、ずっと欲しかったコンパクトカメラを首尾よく盗み出す。だが、そんなまめを出し抜いた「嘘の才能」の持ち主が現れる。それが転入生のでっかちだ。
例えば、花火大会の花火について「あれ、花火を上げる人と、音を出す人が、別々にいるんだぞ」。さすがに嘘だよと思いながらも、まめは乗っかる。「じつは前から不思議だったんだよな、光と音がずれるのが」。似た者同士の二人が、嘘のつき合いをして遊ぶ日々の描写に心くすぐられる。
「花火の嘘は、僕自身が子どもの頃に考えていたことを元にしています。親に一回だけ野球場へ連れて行ってもらったことがあるんですけど、バットで球を打った後、少し遅れてカーンと鳴るのが不思議だったんですよ。録音した音を流してるのかな、と本気で思ったんですよね。打ったタイミングに合わせてボタンを押すか何かしてるから、音がちょっとズレるんじゃないかなと(笑)」
まめとでっかちの平穏は、自分たちの嘘が原因で事件に巻き込まれたことで、一変する。そこからミステリーのギアが一気に上がり、やがて意外な真相へと辿り着く。物語も文章も細部までこだわり抜いた一編に仕上がったのだ。すると、書き上がった原稿を前に想像力が誘発された。
「遺影専門の写真館という舞台設定を使って、いろいろな物語が作れるんじゃないかなと思ったんです」
ラストシーンでまめとでっかちが見つめる写真は、この地域で過去に護岸整備工事を請け負った建設会社が起こした、薬剤流出・隠蔽事件の証拠とされたものだった。その写真からも、作家は新たな物語の可能性を感じ取った。
「写真って情報が大量にあるんですよね。たいてい真ん中に写っているものに目が行ってしまうんですが、その周りに目を移すと実はものすごい量の情報が記録されている。まめとでっかちが見る写真にも、何かが隠されているんじゃないかという予感があったんです」
ふと脳裡に浮かんだのが、自然の美しい風物全般を意味する四字熟語「花鳥風月」だった。それを一字ずつ章タイトルに当てはめて、連作化するのはどうか。
「『口笛鳥』は必然的に二編目になるし、原稿のボリュームから逆算して、本編三話プラスエピローグという構成まで見えました。それと同時に、人間に対する自然というイメージから、人間にはコントロールし切れない何かに引っ張られる、運命だとか偶然というテーマが浮かんできたんです。どことも知れない場所から吹いてきた風によって、人生が左右されてしまう。自分ひとりの力ではどうしようもできない、因果律に搦め捕られていく人々の物語を、数十年単位の時間の中で書いてみようと思いました」
騙し絵のような物語のひらめき
次に手掛けた「第一章 心中花」は、遺影専門の写真館・鏡影館へ、撮影のために訪れた母と娘の物語だ。店内にサンプルとして並べられていた一枚の遺影をきっかけに、母は二七年前の記憶を蘇らせ、娘に秘密を語る。若かりし日の初恋の思い出と、自らの嘘が招いた罪の告白を──。こうまとめるとシリアスなミステリーを想像してしまうかもしれないが、嘘から始まる勘違いコメディとしての魅力も兼ね備えている。
「この世界は素晴らしいと言う人もいますし、こんな世界を生きていても意味がないと言う人もいます。僕自身の意見としては、どっちもあるんですよね。両方の感覚が混ざり合って中間色になっている、それが世界だと思っている。だから、小説の中でひとつの嘘が悲劇を引き起こしたということを書いたら、ひとつの嘘が素敵な、面白いことに繋がったよということも書きたくなるんです」
次のエピソードは、本作の成立秘話を象徴するものかもしれない。
「『口笛鳥』を書いた時には、この町で過去に起きた薬剤流出事件は、露見することなく終わったはずだったんです。
でも、『心中花』を書く時に、それを嘘にしようと思ったんですね。つまり、自分で自分に嘘をついた(笑)。その一カ所に大きく修正を入れることにしたら……ルビンの壺という騙し絵があるじゃないですか。最初の印象では向き合った"二人の顔"に見えるんだけど、じっと目を凝らすと"壺"の形が見えてくる。それと同じで、僕も二編を書き上げた時に初めて、"壺"に当たる三編目のメインストーリーが見えてきた。それって一編目、二編目を書き終えるまでは、影も形もなかったものなんですよ」
小説で描かれる世界と現実の世界は地繋がり
「第三章 無常風」は、老女が若き日に犯した罪の語りと並行して、この町に張り巡らされた因果を探る若者たちの姿が描かれる。その先に、「エピローグ 待宵月」が現れる。
「事前に精密な設計図を作って書いた作品もあるんですが、この作品はまったく違いました。書いている時には伏線になるなんて思ってもいなかったところが、のちに伏線になることが多かったですし、次に何を書くかは、その前に書いたものによって実は決められていたということを、読み返すことで気付いていった。因果律というこの作品のテーマと、書き方が完全に一致していたんです」
基本は一話完結でありながらも、前章で描かれた嘘が、次章以降の物語に意外なかたちで作用していく。全編にわたって因果律が細かく張り巡らされ、連作ミステリーとしての完成度を追求している。その一方で、作家はこの物語の出口に、すべてを揺るがすようなメッセージを込めた。それは何故なのだろう?
「その世界の中では、小説には書かれていないこともいっぱい起きているはず。そこを無視して"全ては繋がっている"って言ったら、嘘をつくことになってしまいますよね。もちろん、これは創作ですし、言ってしまえば全部嘘です。でも、嘘を書きながらも、本当のことを書きたかったんですよ」
ミステリーと人間ドラマのかつてない配合に挑戦した本作は、嘘を通じて本当のことを描く試みでもあったのだ。
「この小説がミステリーなのか何なのか、というラベルを自分で貼ることはしたくないんです。ただ、面白いものを書こうとするとどうしても、ミステリーにはなりますよね(笑)。初めて読んだ時に十分面白かったものが、もう一回読むと別の面白さや深さが出てくる。そのやり方って、ミステリーという形式にぴったりなんです。読んだ人が実人生の中に、何かを持って帰れるような作品にしたいという気持ちは今回、明確にありました。それができたんじゃないかな、と思っています」