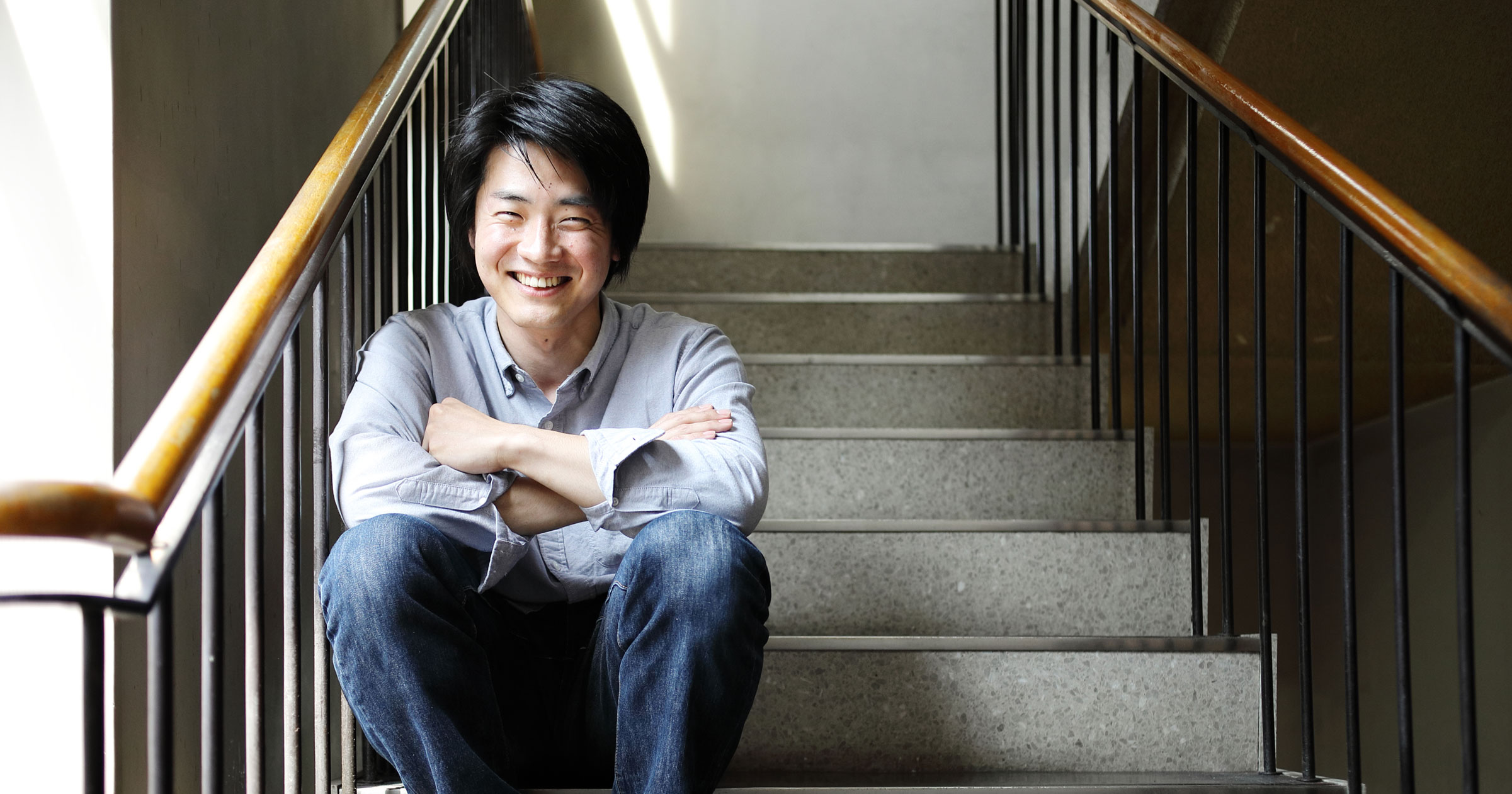柿村将彦さん 『隣のずこずこ』
恩田陸や森見登美彦らを輩出してきた「日本ファンタジーノベル大賞」が四年にわたる休止期間を経て、昨年復活を果たした。再始動一発目の受賞作に選ばれたのが、柿村将彦の『隣のずこずこ』だ。ポップで間の抜けたタイトルの響きに騙されると痛い目をみる、ぞわぞわさせられっぱなしの終末ファンタジーだ。
山の麓にある集落で暮らす中学三年生の少女・住谷はじめは、ゴールデンウィーク終盤に同級生から衝撃のニュースを知らされる。この地で古から語り継がれてきた昔話「権三郎狸」の狸が、村唯一の旅館に滞在しているというのだ。会いに行ってみると、見た目は信楽焼の狸そっくりだが、ズコズコと足音を立ててその狸は動く。一緒に村へやって来た謎の美女・あかりさんは、もの言わぬ狸のスポークスマンとして宣言する。一ヶ月後に狸が、この地での昔話で語られてきた通り、「村を壊します。あなたたちは丸呑みです。ごめんね」。
日本ファンタジーノベル大賞2017受賞作『隣のずこずこ』は、物語の序盤で「世界の終わり」の時限装置が作動する。そこから流れる時間を、リアルタイムで追いかけていく構成だ。
「僕の母親が、信楽焼の狸の置物が怖いって話をしていたんです。そういえば怖いなあ、と。なんであんなふうに、目の前にいる相手を呑み込んでやろうみたいな顔をしてるんやろうな、と。そのイメージが、この話を書いてみようと思ったきっかけです。話の作り自体は単純で、終わりが誰の目にもはっきり見えていて、そこに向かって登場人物達が動いていく。昔からある"物語のタイプ"を使わせてもらいました」
最初のきっかけがそれだったとしても、「世界の終わり」をもたらす存在に信楽焼の狸をそのまま採用したのはなぜ?
「他にもいろいろ試してみたんですけど、誰も見たことがないような突飛な存在にしてしまうと、それを前にして"ぎょっとした"や"なんと!"など、いちいち周りのリアクションを入れなきゃいけない。そのたびにちょっと醒めるし、演出している感じがして面白くなかったんです。書きたかったのは、こういう存在が現れたらどうなるかというところだったので、存在自体は当たり前のように受け入れて欲しかった。"昔話でずっと語られてきた"という設定を加えたのも、そのためでした」
綺麗さを目指さないもっちゃりした文章
物語の前半は、一ヶ月後の「世界の終わり」は逃れ難い運命であると知った、集落の人々の日常が丹念に描かれる。みんなさほど切羽詰まることなく、作中の表現を借りれば「年末の過ごし方と変わらない」様子が面白い。ある人はお金を全部使ってやれと高級な肉で毎晩バーベキューを行い、主人公のはじめは、どうせ村が滅ぶのなら宿題をやらなくていいし、受験もせずに済むからラクだ、くらいのノリでいる。
「この日はこのことを書くというメモを五月の三一日間分、最初に作ったんです。例えばゴールデンウィーク明けの五月七日は、"はじめが学校に行ったら、狸の話題でみんな慌ててた"ぐらいでメモは終わっていたんですよ。実際に書いてみたら、原稿用紙四〇枚ぐらいの長さになってしまった。本当は、前半はもっとさくさく進むはずだったんです。あんなに書く必要は、ないといえばないじゃないですか。完全に自分の趣味ですね」
「世界の終わり」程度ではびくともしない人々の日常を、楽しく読み進めることができるのは、筆力の賜物だ。一読すれば明らかだが、この作家の文章には独特のグルーブ感がある。憧れの作家の名前を聞いて納得した。舞城王太郎だ。
「基本意味が分からないのに、なぜか読まされてしまうところが好きですね。舞城さんが書くものだったら、内容とか関係なく、何を書いても僕は読むと思います」
作品世界で起こる出来事を記述するだけであれば、もっとシンプルな文体もあり得たのだ。しかし、作家は「文章」それ自体がエンターテインメントでありたい、と望んだ。
「この小説を読んでくれた友達から、"お前の文章はもっちゃりしてる"と言われました。なんとなく分かるんですよ。仕入れた言葉をすぐ使いたい中学生的な文章のこねくり回し方をしてる、ということだと思うんです(笑)。綺麗な文章を書こうとは思わなかったんですよね。それがこの物語にとっては、しっくりくるものになったのかなと思うんです」
ミステリーのつもりが ファンタジーになった
前半で日常シーンを大事に書き継いでいったからこそ、後半でがらっと空気が変わった際のシリアスなムードが映える。そもそも、残酷で不条理な運命を、村人達が不思議なほど受け入れ反抗を諦めてしまうのはなぜだ? 主人公が抱く違和感は、物語の終盤で意外な回答へ辿り着く。
「最初はミステリーを書こうとしていたので、その名残ですね。なんとなくのあらすじを決めた時点では、ちゃんとしたミステリーにするはずだったんですよ。それを舞城さんがデビューしたメフィスト賞に送ろうと思っていたんですが、謎の出し方とか推理とか、ミステリー的な部分がぜんぜんうまく書けなかった(苦笑)。途中からミステリーにすることは諦めて、好きなように書こうと思ったんです」
原稿ができ上がった頃、書店で偶然「小説新潮」を手に取り、「日本ファンタジーノベル大賞」が復活するという記事を見つけた。
「賞については名前を知っているぐらいだったんですけど、選考委員の方(※恩田陸、萩尾望都、森見登美彦の三氏)のコメントに"何を送って来てもいいよ"みたいなことが書いてあったんです。森見さんの『有頂天家族』を昔読んでいたので、"狸の話を森見さんに送っていいのか"という葛藤はあったんですが(笑)」
自分の書いているものが「ファンタジー」である意識はなかったというが、「ファンタジー」の回路を利用しなければ得られなかったものが、この小説の中にはたくさん詰まっている。物語終盤、ある出来事によって引き出された"昨日まで覚えていたこと"が思い出せなくなってしまうことへの恐怖や葛藤、"忘れていた大切なこと"を思い出したときの感情は、この世界観、この設定を採用したからこそ発見できたものだ。
「書きながらなんとなく思い出していたのは、大学の校舎でした。数年前に建て替え工事が始まって、僕が勉強していた校舎がほとんどなくなっちゃったんです。ひとつだけ残った校舎には中国語の授業を受けていた教室があったので、卒業してから久しぶりに観に行ってみました。そうしたら、部屋の改変があって、僕の勉強した教室が便所になっていた。教室がなくなっていたのもショックだったし、便所にすることないでしょ、と(笑)。そういった自分の中にあるものすごく小さな悲しさを、小説の中でどんどん広げていきながら書いていったのかもしれないです」
三年やってダメだったら一生ダメだと思っていた
一九九四年、兵庫県尼崎市生まれの柿村将彦は、地元の工業高校を経て、京都にある大谷大学へ進学。卒業後は就職せず、牛丼屋で週二回深夜アルバイトをしながら、小説の投稿をする日々を送った。
「兄と弟が二人とも、高校を出てすぐに仕事をしているんです。僕は親の金を使って私立の大学に行って、仕事もしていない。"自分は何をしているんだ?"という負い目はありました。小説に本腰を入れ始めたのは二二歳からなんですけど、二五歳までやって全くダメだったらやめちまおうと思っていたんですよ。三年間、本気でやってもダメならたぶん、僕は一生やってもダメだろうと」
そして、「それまでで一番自分の好きなように書いた」作品で見事大賞を受賞し、作家デビューの夢を掴んだのだ。
「偶然書けたという感覚が強いんですよ。賞金をもらって気が大きくなって、東京に出てきたのは失敗だったんじゃないかと最近後悔しつつあります(笑)。次は何を書こうかなと頭の中で考えても、なんにも浮かばないんです。とにかく文章を書いてみて、書いたものから想像を膨らましていくと、それまで考えもしていなかったことを思い付いたり、なんとなく次の文章が見えてくる。自分にはそのやり方しかないんだろうなと思っています。だから……とにかく書くしかないんですよね」