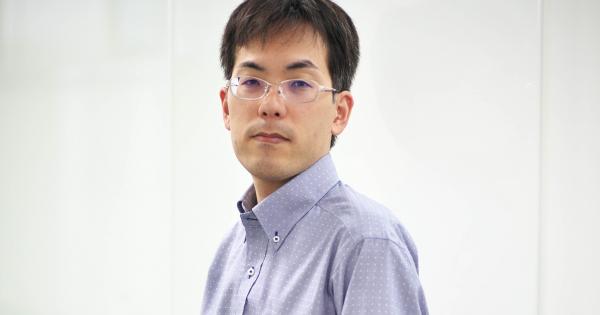詠坂雄二さん『君待秋ラは透きとおる』
綾辻行人や米澤穂信など名だたるミステリー作家たちが偏愛する書き手が、詠坂雄二だ。かつて「今、もっともひねくれた新鋭作家」と帯に銘打たれた過去からも明らかなように、本格ミステリーの定型を逸脱する作品群ばかりを世に問うてきた。
その道のりを知る読者にとっても最新長編『君待秋ラは透きとおる』は度肝を抜かれるものだったろう。本作は純然たる「異能バトルもの」なのだ。
人智を超えた特殊能力を、運命的に手にした者同士が覇権を巡って争い合い、時に手を組んで大いなる敵に立ち向かっていく──。いわゆる「異能バトルもの」は、山田風太郎の小説『甲賀忍法帖』を起源に持ち、現在はマンガやアニメ、ライトノベルのシーンで一大ジャンルとなっている。このジャンルに、気鋭の本格ミステリー作家が初挑戦した。
「次はまっすぐなエンターテインメントを書きたい、という気持ちがあったんです。一つ前の『T島事件 絶海の孤島でなぜ六人は死亡したのか』(二〇一七年七月刊、光文社)を書きあげた時に、反省したんですよ。あの作品は自分としては珍しく、冒頭に幻想的な謎がありその解決に向けて物語が展開する、ミステリーらしいミステリーでした。ただ、ミステリーとしての構造を意識しすぎた結果、トリックに説得力を与えるためにはここでこういう説明が必要で……という手続きが増えて、読みこなすのが難しいものになってしまったんです」
その反省から、ジャンルを大きく変えてみようと考えたのだ。
「エンターテインメントの中でもこのジャンルを選んだことに関しては、長編の依頼をいただいたのが、角川書店さんだったことが大きいんです。角川といえばいろいろなライトノベルのレーベルを持っている出版社だ、ライトノベルといえば異能バトルものだろう、だったら自分も異能バトルものにしようと、半ば自動的に決まったんですよね。長編のネタのストックがなかったため、その連想に飛びついたというのが本音でもあります(笑)」
〝読者としての自分〟が読んだことのないものを
本を開くといきなり、白熱のバトルが幕を開ける。都内で一人暮らしをする一九歳の女子大学生・君待秋ラが、自宅マンションの通路で襲撃される。襲撃者は、手から任意の長さと太さの鉄筋を取り出す、「鉄筋生成」という匿技(=異能力)を持つ青年・麻楠均だ。対する君待は、実は「透明化」という匿技の持ち主だった──。
「まっすぐなエンターテインメントを目指すならば、最初から面白くなければいけないと思い、バトルから始めました。戦況を描く過程で異能の種類や世界観の設定をある程度説明できる、という利点もあったんです」
バトルに意外な決着がもたらされた先で、麻楠均が所属する独立行政法人「日本特別技能振興会」に、君待秋ラが加入する。その組織は終戦直後に、匿技士を保護するために作られたものだった。
「異能バトルものをやると決めた段階で、能力者の人生をしっかり描かなければいけないと思っていました。ただ、能力者が世間から差別にあい、それが理由で人間の敵に回るというお話は、今まで無数に語られてきた定番です。これはどの作品を書いている時も意識していることなんですが、どうせ書くならば、少なくとも〝読者としての自分〟が読んだことのないものにしたい。そう考えた時に、人権保護の名目で能力者を集めて管理する、『振興会』という組織の存在が思い浮かびました。ここでならば能力者同士も自然に出会えるし、友情を築くこともできて、孤独が原因で力を暴走させるような展開も回避できる。唯一の問題は、この組織はそもそも対立をなくすために作られているので、戦う理由が弱くなるんですよ」

それでも匿技士たちの間でバトルが起こるとしたら、どんな状況設定が考えられるか? ファーストバトルは新人の「勧誘」と称して、拳を交えた話し合いが描かれた。第四章で登場するセカンドバトルは、「模擬戦」だ。アメリカ合衆国から二人の匿技士が送り込まれ、「匿技の応用可能性の模索および親交を深めるため」という名目で、君待&麻楠と直接攻撃禁止のタッグ戦が敢行される。
「匿技士の組み合わせによって、いろいろな戦い方が可能になっていく。現実にはない能力の持ち主同士が戦うからこそ、現実にはない景色が見られるというのは、異能バトルものならではの醍醐味だなと感じました。バトルを描く上で一番意識していたのは、できるだけコンパクトに叙述することです。短ければそのぶん構成が際立ち、展開の濃度も高まりますよね」
二度のバトルが繰り広げられた先で、物語の空気がガラッと変わる。ひとつの死体が現れると共に、巨大な「謎」が急浮上して、本格ミステリーとしてのギアが一気に上がる。
指針となったのは、幼少期から読み継いでいる「週刊少年ジャンプ」の異能バトルマンガの記憶だった。中でも荒木飛呂彦の『ジョジョの奇妙な冒険』は、本作に直接的な影響を与えている。
「『ジョジョ』の第四部には、物語を引っ張る謎として〝透明の赤ちゃん〟が出てきます。自分を含め、周りのものを透明にするスタンド能力者です。主人公の君待秋ラは、あの赤ん坊が大きくなったイメージなんですよ。赤ん坊は女の子だったよね、じゃあこちらも女の子にして、透明化の能力を持たせることにしよう、というふうに設定を固めていきました」
先行作品へのリスペクトは抱きつつ、競争心を失わないのがこの人らしさだ。
「『ジョジョ』の魅力って、やっぱり絵が強いんです。例えばネーム(文字)だけを追っていったら、意味が通らない場面は多々あると思うんですね。荒木飛呂彦の独特な絵があるからこそ、話の展開に理屈を超えた納得が宿っていく。でも、小説には絵がありません。であるならば自分がやるべきことは、言葉を追うだけできちんと納得できるような、論理性を重視したバトルであり世界観の記述だと思いました。論理を展開する面白さって、ミステリーが得意とするところでもあるんですよ」
目が見える透明人間はどうしたら作れるか?
異能バトルものの牙城として知られる少年ジャンプの作品群や、異能バトルもの最大のヒットとなったハリウッド映画『アベンジャーズ』も研究対象に取り入れ、当該ジャンルの王道を目指したと言うが、そこで終わりとする書き手ではない。本作は古今東西の物語作家たちが描いてきた「透明人間」に、新たな光を当てるプロジェクトでもある。
「そもそも透明になれる能力って、憧れはするけれどそんなにいいものじゃないよな、と思うんです。世界で最初に透明人間を描いたH・G・ウェルズの『透明人間』を読んでみても、服が着られないとか、食べ物が宙に浮いて見えるからイヤだとか、主人公が愚痴ばっかり言っているんですよ」
そんな能力を持って生まれたことを、本作の主人公もまた悲しみ、悔やんでいる。かつて大切な人を、自分の能力のせいで傷つけてしまったこともある。けれど、終盤に現れる「謎」を前にして、彼女はこう思う。〈わたしの匿技はいざという時どう使えるのか。/今考えるべきは、それだ〉。
「能力を忌み嫌っていた少女が、透明化に関する科学的な理屈を学び力の使い道に気づくことによって、一歩前へと進めるようになる。まっすぐなエンターテインメントにしようと志した以上は、そこは必ず書かなければいけない展開だと思っていました」
その展開と重ね合わされる形でもう一つ、ゴールが設定されている。
「透明人間に関して〝頭が透明になったら目が見えなくなるよね?〟というツッコミは、昔からずっとあるものです。科学的に考えても、水晶体が不可視になってしまったら、光を集めることができないから何も見えないはず。そのツッコミをただ取り上げるだけなら、わざわざ今の時代に透明人間を書く必要は感じません。ツッコミを〝お題〟と捉えることで、自分なりの新しい透明人間像を作ることができるんじゃないか。つまり、〝目が見える透明人間は、どのような理屈を立てれば、ある程度の説得力を持って存在させることができるか?〟。それを書くことが、作家としての面白味でもあるし、他では読めない価値に繋がるんじゃないかと思ったんです」
物語の中で「謎」として明示されてはいないが、透明人間を巡るその「謎」と解決こそが、本作にとって最大のオリジナリティなのだ。

角川書店
唯一無二の力「匿技」(異能力)の持ち主たちを集める「日本特別技能振興会」。透明化の匿技を持つも組織に背を向けて生きようとする君待秋ラは、終わりなき戦いに巻き込まれてゆく。ミステリー界の異能が贈るバトル&リドル!