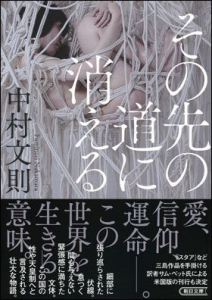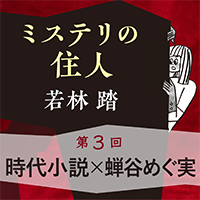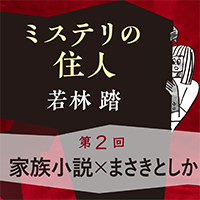ミステリの住人 第5回『犯罪小説 × 中村文則』

若林 踏(ミステリ書評家)
中村文則を考えることで見えてくるもの
2013年に刊行した『去年の冬、きみと別れ』(幻冬舎文庫)で年末ミステリランキング上位になり、翌年に「デイヴィッド・グーディス賞」を受賞した頃からミステリの分野における中村への注目が一挙に上がった印象がある。だが、犯罪小説としての側面はデビュー作を含めた初期作から既に色濃かった。『銃』は河原で偶然、拳銃を拾った大学生がその存在に心を奪われていく物語だ。本作では若者の内奥にある破壊衝動が武器を手にしたことで外部へと漏れていく過程が描かれている。何らかのトリガーによって内なる暴力性が放たれていく様を犯罪小説寄りの展開で書いた初期作としては『最後の命』(講談社文庫)も挙げることが出来るだろう。斎藤美奈子は『日本の同時代小説』(岩波新書)において、2000年代の文学トレンドを「テロと殺人」としつつ、中村文則や吉田修一といった純文学作家たちが社会から見捨てられた若者たちの衝動を描く殺人小説を多く手掛けていたことを指摘する。
ちなみに同書には「神戸連続児童殺傷事件(1997年)や佐世保小六女児同級生殺害事件(2004年)など、90年代後半から00年代前半の日本が『少年の凶悪犯罪』を前に呆然としていたのは事実」と書かれているが、同時期にミステリの分野では家族を題材にした犯罪小説が台頭してきたのは連載第2回で触れた通りだ。家族ミステリの発展と、斎藤が言うところの「純文学作家による殺人小説」が同時多発的に書かれたことについては、別の機会に掘り下げてみたい。
話を戻そう。初期の中村作品が若者の凶悪犯罪が多発する時代の空気にも通ずる暴力の衝動を描いた物語だとすれば、2009年に発表された『掏摸』 は犯罪小説という観点から見れば毛色の違う作品だと捉えることが出来る。同作はそれこそデイヴィッド・グーディスのような、硬質で研ぎ澄まされた古典的な犯罪小説の香りが漂うのだ。
同作に登場する掏摸の“僕”は物悲しい。インタビューで中村が「掏摸は行為そのものが存在である」と語っているように、“僕”の存在は他人から物を盗るという行いによって支えられている。小説の序盤で、“僕”が痴漢の被害に遭っている学生から男を引き離しながら、その男から財布をしっかり抜き取る場面が淡々と描かれている。“僕”が善悪の境界をうろつくちっぽけな存在であることが、動作の描写のみで提示されるのだ。さらに“僕”は強烈な諦観を持って生きている事が、“僕”自身の口から語られる。佐江子という女性から「あなたは、何か望みとかある?」と問われた時、“僕”は下記のように答える。
「最後かな」
僕は、不意に口を開いていた。
「最後?」
「自分の最後がどうなるのか。……こういう風に生きてきた人間の最後が、どうなるのか。それが知りたい」
ここには“僕”があらかじめ決められた破滅にしか向かって生きていないことが表れている。いわば“僕”は必然的な悲劇を背負った人間なのだ。
本文の冒頭でデイヴィッド・グーディスを紹介した際、犯罪小説の一つの類型を指す言葉として“ノワール”を使った。諏訪部浩一『ノワール文学講義』(研究社)はアメリカ大恐慌時代の影響からノワール小説の勃興を語った論考だが、そこで諏訪部は大恐慌という社会状況が、「暴力」や「犯罪」という真っ当ではない手段による閉塞からの脱出を試みて失敗するという物語構造を持つノワール作品を生み出した旨を語っている。米国の古典的なノワールと『掏摸』では書かれた国も社会状況も全く異なるものではあるが、それでも『掏摸』の“僕”にはかつてのノワール小説の主人公たちと重なる部分が多い。
『掏摸』には木崎という得体の知れない人物が存在し、“僕”をはじめ主人公たちの人生を徹底的に支配しようとする。本作以外にも『悪と仮面のルール』など、中村作品には他者の運命を握る絶対的な悪がしばしば登場する。初読の際は、木崎というキャラクターを、善悪の彼岸を完全に越えてしまった、ある意味で普遍的な存在として、筆者は捉えていた。しかし今回のインタビューを機に再読すると、やや異なる印象を受けた。
特に第12章において木崎が“僕”に向けて放つ言葉には、『掏摸』刊行時より狭量な社会になった感のある現在、極めて現実味を持った恐怖として受け取れる部分がある。そうした身近で現実的な社会の圧迫を具現化したものとして木崎を捉え直すとするならば、“僕”が感じる諦観や脱却への足掻きは、大恐慌以後に米国で書かれたノワールの主人公達にも通ずるところがあるのではないか。1990年代から2000年代にかけてミステリではジャンルの細分化が進み、日常の閉じた世界へ関心を寄せた小説が多く書かれていったことは本連載で繰り返し述べた。そうした2000年代以降の流れの中で、古典的なノワールの構造を感じさせながら現代日本の抑圧的な側面も射程に入れた犯罪小説が、純文学の領域で活躍する作家の手によって生み出されたことは改めて注目すべきことだろう。
インタビューにもある通り、中村は先に挙げたようなノワール小説をそれほど多く読んでいるわけではなく、『掏摸』については明確なジャンル意識をもとに書かれたものではないようだ。古典文学の中にもカミュやドストエフスキーのように、犯罪を題材としたものはたくさんある。それら名作から、中村の言葉を借りれば「ミステリ史で言うところの古典犯罪小説をすっ飛ばして、純文学に内在していた犯罪小説的な側面を受け取った」という方が正鵠を得ているのだろう。その意味においては無自覚にミステリというジャンルに辿り着いたとも言える。
いっぽうで中村は謎解きや警察小説といったミステリの技巧や趣向を積極的に取り入れ、ジャンルの読者も十分に納得し楽しませることに取り組んでいる。最新作『列』 (講談社)でも第二部で非常に奇抜なフーダニットが盛り込まれていて驚いたが、近年の収穫でいえば『あなたが消えた夜に 』(毎日文庫)と『その先の道に消える 』(朝日文庫)の2作が必読だろう。
『あなたが消えた夜に』は連続通り魔殺人事件を追う2人の刑事を描いた、正統的な警察捜査小説の趣きで最初は始まる。ついに中村文則もこのようなストレートな捜査小説を書くようになったのか、と感心していると思わぬ展開が待ち受けていて唖然とする。捜査小説としてのプロットが途中から奇妙な屈折を始め、底なしの不気味さが増していくのだ。
今回のインタビューで中村は、本作は「フランツ・カフカの『城』の構造を警察組織に重ね合わせて書いてみたらどうだろうか」といった発想から生まれたと語っている。『城』は測量師の主人公が目当ての城へ一向に入れない様を描いた小説で、絶対的にあるはずのものの全容が分からない不条理が示されている。『あなたが消えた夜に』では警察機構をカフカの小説における“城”に準え、霧に包まれたように茫洋とした組織の姿を描き出そうとしているのだ。この辺りの掴みどころのなさが、通常の警察捜査ものとは異なった味わいを持つ小説になっている。『その先の道に消える』もインタビューの通り、警察捜査小説の定型を崩すような試みがなされており、アウトローな行動を取る警官を主人公にした小説としても風変わりな趣向が施されている。これも『あなたが消えた夜に』同様、第一部の終わり方に唖然としてしまう読者は多いはずだ。
「純文学の作家がミステリの手法を取り入れる際、曖昧さが残るような書き方をすることが多い。しかし、自分はミステリのジャンルにおける“約束事”は守り、曖昧さは排する」というインタビュー内の言葉にあるように、中村はミステリというジャンルが蓄積した技巧を取り入れることに自覚的な書き手であり、それが純文学とジャンル小説、双方の読者にも開けた作品を書くことに繋がっている。他方、ノワールと形容できるような犯罪小説の要素はジャンル小説を意識せずに書いている。このミステリというジャンルに対する意識的な部分と無意識的な部分が組み合わさったところに、中村文則の書く小説の面白さがある。
今回のインタビューにおける中村の言葉を聞くと、そもそも無意識的に表れる犯罪小説の要素とは、果たしてミステリというジャンルの範疇で捉えるべきものだろうか、という問いが生まれるだろう。犯罪小説をミステリの一類型として捉えるのではなく、それとは切り離して眺めた時にジャンル内外の作家を含めた発展史を描く必要があるように思う。中村文則という作家を考えることは、犯罪小説の輪郭を考えることに等しい。
※本シリーズは、小学館の文芸ポッドキャスト「本の窓」と連動して展開します。音声版はコチラから。
若林 踏(わかばやし・ふみ)
1986年生まれ。書評家。ミステリ小説のレビューを中心に活動。「みんなのつぶやき文学賞」発起人代表。話題の作家たちの本音が光る著者の対談集『新世代ミステリ作家探訪 旋風編』が好評発売中。