横山秀夫、警察小説を語る

「捜査一課長の抱えるジレンマ」
──デビューしてから数年の間は、短編を週一本のペースで書かれています。膨大なストーリーは、どのようにして生まれたのでしょうか?
短編は出たとこ勝負でやっていました。よく聞かれるんですが、ネタ帳のようなものは作ったことがありません。マンガの原作を書いていた時代の苦い経験で、手元にプロットやアイディアのストックがあると右肩下がりに作品のクオリティーが落ちる。「持っている」という安心感が生まれて、本気で次の新しいストーリーを考えなくなってしまうんですね。で、締切とかで追い詰められた時に、一番ではない、何番目かのクオリティーのプロットに縋ってしまう。寝床や食事中の閃きもメモしなくなりました。たいていは次の日には忘れてしまうし、大切な閃きならあとで何度でも思い出しますから。メモを取らないことは、面白い、面白くないを篩にかけるだけでなく、自分が本当に書きたいものを見極めるフィルターでもあるんですよ。

そんなわけで、短編をハイペースで書いていたころは、一本仕上がると、二時間ほど眠ってから、「よーい、どん」で次のプロットを一から考え始めていました。自分の脳みそを掻き回し、いま一番自分が面白いと思える話をアウトプットする作業ですね。何も思いつかないかもしれないというリスクがあるわけですが、その恐怖感が能力以上のものを引き出す秘訣のような気もします。
カテゴリーの話をすると、これまで私が書いてきた短編はすべてミステリーです。ミステリーと人間ドラマを高い次元で融合させたいというのが、デビュー以来、今も変わらぬ目標ですね。ミステリーの定義は人それぞれでしょうが、私のは「自分以外の人生が存在することに気づくまでの話を書く」かな。何をいまさらかもしれませんが、そもそも自分以外の人間なんて想像の産物のようなものですし、人は自分の環境と経験でこしらえた物差しでしか他者を推し量れないので、繰り返し見誤るんですね。で、見誤った絵が別の絵に見えた瞬間が「どんでん返し」というわけです。ただ、どんなミステリーでも仕掛けが必要なので、その構造に物語そのものが呑み込まれてしまったり、リアリティー部分との間に段差が生じたりします。それを解消できるのは技巧ではなく、主人公をはじめとする登場人物たちの確かな心の動線だと思っています。
──推理小説であり、警察小説であり、刑事小説でもある『第三の時効』は、覇権を争うように競い合う、三人の強行犯刑事(班長)の人物像が魅力的でした。
実は、最初に思いついた人物像は、その三人の班長を統括する捜査一課長の田畑でした。版元から刑事小説の依頼が来たのだけど、直球で刑事を主人公にした小説を書くことにためらいがあったんですよ。で、何を考えたかというと、管理部門小説のフレームに刑事小説を落とし込む方法です。畏敬の対象である捜査一課長が、部下の班長たちが有能すぎるがために苦悩するという設定を思いついた。三人の独善的な捜査を制御できず、けれど彼らの実績のお蔭で「常勝監督」の名をほしいままにしているというジレンマですね。「俺は事件で食ってきたが、連中は事件を食って生きてきた」。この田畑の独白が、刑事小説と管理部門小説のハイブリッドを生み出すための触媒であり、連作全体のモチベーションを支配してもいます。
人物造形の方法はいろいろですが、「第三の時効」シリーズに限って言うなら、書こうとする作品の要請で人物が生み出された感がありますね。たとえば二班の楠見は「冷血」で「謀略型」ですが、かなりハードに設定した作品の筋立てを成立させるために、その種の刑事が必要だったということです。それと、人物造形を考えるときは、主役わき役の別なく、登場人物の子供時代のエピソードを時間をかけて想像することにしています。捨て犬を放っておけずにパンをあげようとしたら牙を剥かれたとか、担任教諭の一瞬の保身に気づいた時の心象風景とか、それらは作品には出てきませんが、人物造形の一部として組み込まれています。時には作品の重要なファクターに昇格することもあります。幼いころ、妹に殺意を抱いた主人公の体験が、事件の真相を喝破するきっかけになったりとかね。

警察官を書く時は、その人が組織から受けている影響の深度をまず考えますね。たいていは「平均的な人」を主人公に据えます。ただ警察の中の「平均的な人」と県庁の中にいる「平均的な人」は同じではありません。どこがどう違うのかを突き詰めて考えてみることが、一つの組織なり業界・団体のイメージをつかむヒントになります。そのあたりを怠ると、警察が舞台なのにちっとも警察小説らしい作品になりません。知識や情報に寄り掛かりすぎるのも考えものですね。いまどきはネットなどで警察に関する情報などいくらでも手に入るのでしょうが、知識や情報は書こうとしている物語に真に必要ならば使い、そうでなければ捨ててしまう潔さというか、さじ加減が大切です。必要な例としては、「地の声」(『陰の季節』所収)という作品があります。警視に昇進できない古参警部の悲哀を書いたのですが、その悲哀を伝えるためには、多くの読者が刷り込まれているであろう「警部信奉」のようなものを壊す必要がありました。警部にまで出世しても小鳥のように震えている警察官がいる。その背景なり根拠なりを書かずして、この短編は成立しえないということです。
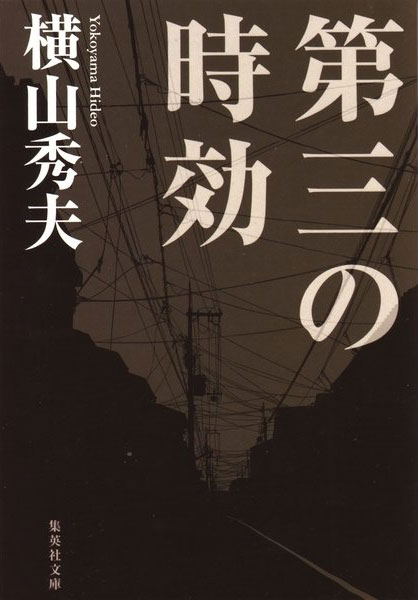
容疑者の海外滞在により発生した時効の7日間のタイムラグ。この間に容疑者を追い詰め逮捕、起訴まで持っていかねばならない。捜査一課長・田畑と「青鬼」「冷血」「天才」と称される三人の班長の葛藤、刑事の執念を描く「F県警強行犯」シリーズ。
http://www.shosetsu-maru.com/pr/keisatsu-shosetsu/



