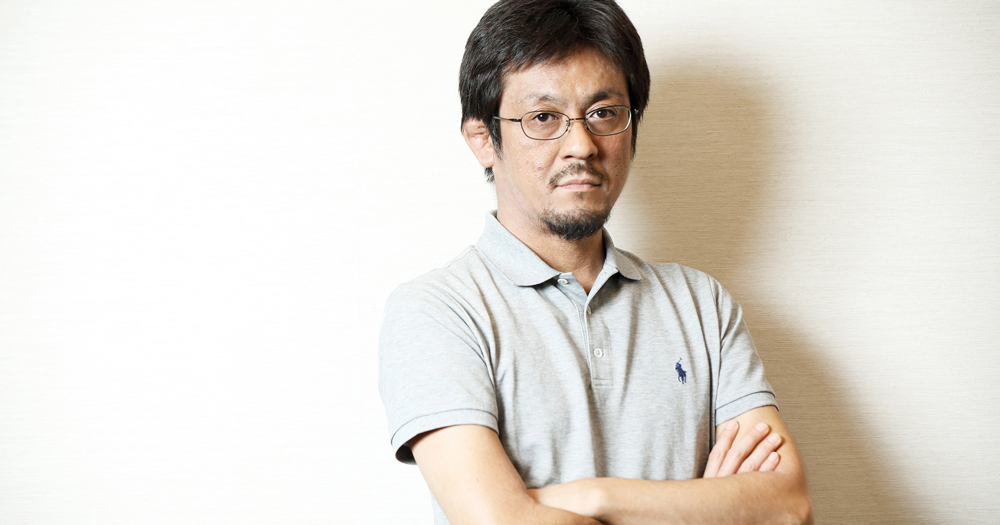川越宗一さん『熱源』
豊臣秀吉の朝鮮出兵を島津藩・朝鮮国・琉球国の三人の男たちの視点から綴る「天地に燦たり」で川越宗一は昨年、第二五回松本清張賞を受賞した。
待望の第二長編『熱源』の舞台は、北海道の北に位置する樺太(サハリン)だ。極寒の島で命を燃やす人々の姿とともに、明治から第二次大戦に至る近代史を活写した。
九州にルーツを持ち大阪で生まれ育った著者が、北海道の先住民族たちの物語を書くことになったきっかけは、夫婦旅行だった。妻のリクエストで二〇一五年夏に北海道へと足を運んだところ、知られざる歴史と出合った。
「たまたま室蘭から足を延ばして、白老町のアイヌ民族博物館へ立ち寄ったんです。そこに、ブロニスワフ・ピウスツキという人物の銅像があったんですよ。説明書きには、一九世紀末から二〇世紀前半にかけて活躍したポーランド人の民族学者で、アイヌを研究していたと記されていました。彼はわざわざ地球を約半周してきて、北海道の少数民族研究の先駆者になった。その歴史的事実に不思議さというか違和感を覚え、ピウスツキについて調べ始めたんです。その過程で樺太出身のアイヌ、いわゆる〝樺太アイヌ〟であり、日本初の南極探検隊に参加した山辺安之助という人物の存在を知りました。ピウスツキと山辺安之助が出会い、二つの人生が交差したポイントを軸に、物語を生み出せないだろうかという構想が生まれたんです」
新人賞受賞後第一作は、プロとなって初めて執筆する作品だ。実力が見定められ、書き手の個性や方向性をくっきりと示すことにもなるこの機会に、温めていた幾つかの着想の中でもっとも史料が少なく難易度の高い題材に挑戦しようと決めたのだ。
懸命に生きた人々の人生の集積が、歴史
まず物語に登場するのは、樺太が日本領からロシア領となったため、九歳の時に故郷から北海道へと集団移住してきた樺太アイヌのヤヨマネクフだ。北海道の対雁村で暮らすこの少年は明治一四年(一八八一年)、一五歳になっていた。和人からは「野蛮」「未開人」という差別的な視線を浴び、学校の教師から「諸君らは、立派な日本人にならねばなりません」と指導を受ける。こうしたアイヌとしての生き方を奪われる現実に反発した、ヤヨマネクフのとある勇敢な行動が、村一番の美人であるキサラスイの心を動かす。後に彼女と結婚し息子をもうけるが、疫病で妻が若くして死んでしまう。彼女の「故郷へ帰りたい」という遺言を胸に、ヤヨマネクフは息子とともに樺太へ渡る。パスポートを得るために手に入れた日本名が、「山辺安之助」だ。
身を切るような冬の寒さ、アイヌの集落の様子や独自の伝統文化など、書き込まれた細部のディテールが圧巻だが、
「時代背景の説明も必要ですしどうしても手厚くなってしまうんですが、地の文を書くのはあんまり好きじゃないんです。地の文って作者の自意識が出がちですし、歴史の知識自慢にもなりかねない。僕は物語が書きたいし、キャラクターたちの会話や行動が書きたいんですよ。歴史とは、ある時代を自分なりに懸命に生きた人々の、人生の集積だと思っているんです」
何より重要なことは、登場人物たちの人生をいきいきと描き出すことなのだ。特にヤヨマネクフ=山辺安之助の前半生は、この時代にアイヌという少数民族の人々が被った苦悶を示すためにも、手厚く記述する必要があった。
「ヤヨマネクフの前半生に関しては史料があまりにも少なく、想像で膨らませる必要がありました。指針となったのは、彼が歴史に名を残す要因となった、南極探検隊にまつわる言動です。アイヌを和人に認めさせる、アイヌの地位向上のために自分は南極へ行く、という理由で参加を決めたそうなんです。そんな決断ができる人間は、人生の過程で何かしらの大きな経験を介して成長し、強固な自己を獲得してきたはずだろう。そう考えた結果、史実からフィクションへと一歩踏み込み、対雁村時代に厳しい現実を経験してもらうことにしました」

続く「第二章 サハリン島」で描かれるのは、リトアニア生まれのポーランド人、ブロニスワフ・ピウスツキの人生だ。サンクトペテルブルグで大学生活を送っていた彼は一八八七年、皇帝暗殺計画に連座して逮捕された。懲役一五年の刑でサハリン(樺太)の刑務所に送られ、開拓労働に従事する絶望の日々を過ごす。だが、その地で少数民族のギリヤークと出会い、彼らの生活を学びたいと思ったことから、民族学者として歩み出すこととなる。
「サハリンは北海道よりさらに寒い気候ですし、第三者からすれば、もっと住みやすい場所もあるのではないかとつい感じてしまうような土地です。でも、生まれ育ったその土地で、少数民族の人々は暮らしているんですよね。住まざるを得ないという現実もあるにせよ、自らの選択で住んでいると思うんです。ピウスツキの故郷であるポーランドは、彼が生まれる直前にロシア領となり国名も消えました。あらかじめ故郷を奪われた、帰るべき場所のない欠落を抱えた人物が、極寒の島を故郷とする少数民族たちと出会った。そこで生じたであろう熱は、消えかけた彼の命の火を灯すものだったんじゃないかと思います」
現代の人々が読んだ時に心震えるものになるよう
のちにアイヌ研究も手がけるようになったピウスツキは、樺太アイヌの女性と結婚し、集落に学校を作り子供たちの教育に携わったという史実がある。
「自分の人生を振り返ってみても、学校で文字を教えてもらったからこそ本が読めるようになり、流れ流れて今小説家になっている。教育によって偏った思考に教化される危険性も孕んではいますが、知る世界の広さは人生の可能性の広さにつながっていると思うんです。僕自身の教育というものに対する信頼感というか願いが、ピウスツキの人生に共鳴したところはあるかもしれません」
やがてピウスツキは、極寒の島で山辺安之助と出会う。その感動的な場面が描かれた後も……物語は終わらない。二葉亭四迷や大隈重信、金田一京助やポーランド共和国の初代国家元首となるユゼフ・ピウスツキら実在の人物が多数登場し、世界大戦の開幕とともに歴史のうねりが高まり出す。
「最初の構想ではピウスツキと山辺安之助の人生を面白かっこよく描きたい、ぐらいのノリだったんです(笑)。史料を読み込んでいくうちに構想が膨らんで、二人が生きた近代という時代そのものを描きたいと思うようになりました」
近代には、この時代ならではの生きづらさがあった。それを象徴する存在が、樺太アイヌだったのだ。
「第一章でアイヌの集落の村長が文明とは何かという問いに対し、『馬鹿で弱い奴は死んじまうっていう、思い込みだろうな』と言っています。その当時、はっきりとそう言葉にした人はいなかったかもしれませんが、心の中でそんなふうに感じている人はいただろうと思って書いたセリフでした。当時はダーウィンの進化論が受け入れられて一巡した時代で、適者生存の原理が弱肉強食に誤解されつつ、その原理が社会にも適応されると広く信じられていました。遺伝形質によって社会発展を図ろうとする優生学が生まれ、ナチスのような極端な集団が現れたりします。日本でも少数民族への抑圧が起こり、彼らは強引に自分たちの生き方を変えられた。自由に生きる権利が認められている現代に比べると、あまりにも生きづらい、矛盾と理不尽に満ちた世界なんですよ。でも、それでも懸命に生きた人々の熱を伝えたかったんです」
この物語をどう終わらせるか、この物語にどんなタイトルを付けるかは、最終稿まで悩み抜いたと言う。読者は最後の一文に触れれば必ず、この小説に「熱源」というタイトルが付けられた意味を理解し、胸を熱くすることだろう。
「デビュー作との大きな違いは、登場人物のほとんどに実在のモデルがいることでした。実在した人物の人生を、フィクションであるとはいえ、好き勝手に加工していいものなのか。この小説を書きながら、歴史小説家とは罪深い職業なのかもしれないと感じましたね。勇気も要りましたし、執筆中は常に不安に駆られていたんです。でも、当時の歴史を正しく記述しようとするのであれば、それは小説じゃなくてもいいんですよ。小説がすべきことがもしあるのだとすれば、現代の人々が読んだ時に、心が震えるものになるよう脚色を交えてでも恐れず描写することなんじゃないか。そうすることで結果的に、歴史や時代を伝えられるんだと信じられるようになったんです」

文藝春秋
明治期に樺太で生まれたアイヌ、ヤヨマネクフと、リトアニア生まれのブロニスワフ・ピウスツキ。文明を押し付けられ、同化政策によりアイデンティティを揺るがされた二人が、樺太で出会い、「熱」を追い求めて生きていく──。